幻の「東京ビーフ」に密着!島で育ち東京で仕上がる黒毛和牛の秘密|2025年4月6日放送
2025年4月6日(日)放送のNHK総合『うまいッ!』では、「島育ち!絶品の黒毛和牛〜東京〜」と題して、東京都青ヶ島で生まれ、都内で育てられる黒毛和牛が特集されました。限られた頭数しか出荷されないことから“幻の黒毛和牛”と呼ばれ、シェフや肉の専門家たちからも高い評価を受けるこの牛。その誕生から出荷までの長い旅や、育てる人々の思い、そして有名シェフによるレシピまでが紹介されました。
青ヶ島でのびのび育つ子牛たちの物語
東京ビーフの原点ともいえるのが、伊豆諸島に位置する青ヶ島です。東京都心から約358kmも離れたこの小さな島は、火山に囲まれた地形と、澄んだ空気、豊富な水に恵まれています。人口約160人のこの島で、黒毛和牛の子牛たちは生後8か月までの時間を過ごします。
子牛を育てているのは、島の畜産農家・山田さんです。一般的に黒毛和牛は屋根付きの牛舎で一日中過ごすことが多い中、山田さんはあえて毎日1回、牛を散歩に連れ出しています。これは筋肉と骨格の発達を促すためで、将来的にしっかりとした体つきの健康な牛に育てることが目的です。運動の習慣があることで、肥育の仕上がりにも大きな違いが出るとされています。
牛の健康を支える環境づくりにも、島ならではの工夫があります。
-
畑ではさつまいもを栽培し、一部は牛の飼料にも活用されています。
-
畑のまわりには「ハチジョウススキ」という植物が植えられており、これは昔から牛のえさとして使われてきました。
-
ハチジョウススキは繊維質が多く、反すうに時間がかかるため、牛の胃が鍛えられるのが特徴です。
こうした環境に育まれながら、子牛たちは人の目が届く距離で自然と調和した生活を送ります。静かな島の暮らしと、農家の手間ひまが一体となって、丈夫で健やかな牛の基礎が築かれていきます。
青ヶ島で過ごすこの8か月間が、後の東京ビーフとしての品質を支える大切な時間であり、他の黒毛和牛にはない個性と味わいの土台となっています。島の風、土、植物、そして人の手。すべてが合わさった環境の中で、未来の高級和牛が着実に育っていきます。
400kmの旅を経て町田市や西多摩郡へ
青ヶ島で生まれ育った子牛たちは、生後8か月になると東京都本土の牧場へと旅立ちます。その距離は約400kmにもおよび、船とトラックを使って丁寧に移送されます。目的地は、町田市や西多摩郡にある肥育農家です。ここでさらに約22か月、大切に育てられていきます。
町田市では、萩生田さんが黒毛和牛の肥育を担っています。島からやってきた牛たちは、人見知りで繊細な性格を持っており、環境の変化にも敏感です。そのため、萩生田さんは日々のケアに力を入れています。
-
牛たちのストレスを和らげるために、毎日丁寧にブラッシングを行う
-
牛舎の環境を清潔に保ち、落ち着いた空間づくりに努めている
-
地元の豆腐店から譲り受けたおからをおやつとして与え、栄養面と嗜好性のバランスも意識している
このような取り組みの一つひとつが、牛たちの健康や食欲に直接影響し、結果として肉質の向上につながるのです。
島の自然に育まれた牛たちは、本土の静かな牧場で穏やかに成長していきます。萩生田さんのように、牛の個性を理解しながら接することで、牛自身も安心して暮らせるようになります。人と牛との信頼関係が、長い肥育期間を支える大切な要素となっているのです。
約30か月齢を迎えるころには、しっかりと脂がのり、赤身とのバランスが絶妙な肉質に仕上がります。こうして東京産の黒毛和牛「東京ビーフ」として出荷される準備が整うのです。東京の離島から本土へと受け継がれる命のリレーが、1頭1頭の牛に込められています。
東京ビーフとして認定される条件とは?
青ヶ島で育ち、東京都内で大切に仕上げられた黒毛和牛がすべて「東京ビーフ」と名乗れるわけではありません。東京都が定めた厳しい基準を満たした牛のみが、その称号を得ることができます。つまり、「東京ビーフ」はただの産地名ではなく、品質と育成過程の証明でもあります。
東京ビーフとして認定されるための主な条件は次の通りです。
-
黒毛和種であり、血統が明確であること
→ 血統がしっかりと管理されていることで、安定した品質と味が保証されます。 -
最も長く育てられた場所(最長肥育地)が東京都内であること
→ 途中で他県に移動されていないかを確認し、東京都内でじっくりと肥育された実績が求められます。 -
生産者や出荷ルートがきちんと追跡できる体制があること
→ 牛がどこでどのように育てられたかを証明できることで、安全性と信頼性が高まります。
これらの条件をクリアした黒毛和牛だけが、「東京ビーフ」の名で市場に出荷されます。つまり、東京ビーフという名前は、厳選されたルールのもとで育った牛の証しなのです。
また、東京ビーフは年間の出荷頭数が非常に限られており、希少性も高いブランドです。一頭ごとの育成背景がしっかりと記録されていることもあり、レストランのシェフや精肉の専門家たちからも高い信頼を得ています。
このように、東京ビーフというブランドはただの名前ではなく、生産地・育て方・安全管理・血統すべてにおいて東京都が責任を持って認定した証です。その一頭に込められた努力と物語が、食卓に並ぶとき、特別な味わいを生み出しています。
有名シェフが教える極上のレシピ
番組では、東京ビーフを最大限においしく味わえる2つの特別なレシピが紹介されました。どちらも一流シェフが考案したもので、自宅でも無理なく挑戦できるのがポイントです。赤身と脂のバランスが絶妙な東京ビーフの特長を活かした調理法であり、素材の良さを引き出すプロの技が光っていました。
まず紹介されたのは、浅草の人気店シェフ・家亀智裕さんによる煮込み料理です。手順はシンプルながらも、長時間じっくり火を入れることで赤身のうまみがぎゅっと濃縮された一品に仕上がります。
【東京ビーフのトマト煮込み】
材料(2〜3人分)
-
東京ビーフ(もも肉)…300g
-
オリーブ油…大さじ1
-
にんじん・玉ねぎ・セロリなどの野菜…各適量(粗みじん切り)
-
赤ワイン…100ml
-
トマトソース(市販のものでOK)…200ml
-
水…100ml
-
塩・こしょう…適量
作り方
-
牛肉は食べやすい大きさに切り、塩・こしょうをふる。
-
フライパンにオリーブ油を熱し、牛肉の表面を軽く焼いて取り出す。
-
同じフライパンで野菜を炒め、しんなりしたら赤ワインを加えて煮立たせる。
-
トマトソースと水を加え、焼いた牛肉を戻し、ふたをして弱火で約2時間煮込む。
-
味を見て塩・こしょうで調えたら完成。
時間はかかりますが、火にかけておくだけなので意外と手間は少なく、柔らかくて深みのある煮込みが楽しめます。
続いては、銀座の肉の巨匠・和知徹さんによる、シンプルで香ばしいバター焼きのレシピです。希少部位のカタサンカクを使ったこの料理は、素材の力をストレートに味わう一皿となっていました。
【東京ビーフのバター焼きと赤ワインソース】
材料(2人分)
-
東京ビーフ(カタサンカク)…2枚(各150g程度)
-
塩…少々
-
黒こしょう…少々
-
オリーブ油…大さじ1
-
無塩バター…10g
〈ソース〉
-
赤ワイン…50ml
-
しょうゆ…小さじ1
-
はちみつ…小さじ1
-
無塩バター…5g
作り方
-
肉の両面に塩を、片面だけに黒こしょうをふる。
-
フライパンにオリーブ油とバターを熱し、強火で表面をカリッと焼く。
-
火を弱めて中までじっくり火を通す。焼き上がったら取り出して休ませる。
-
同じフライパンでソースの材料を加えて煮詰め、最後にバターを加えてとろみをつける。
-
肉にソースをかけて盛りつけて完成。
シンプルな調理法ながら、赤身の濃厚なうまみと脂のまろやかさが一体となった贅沢な味わいが広がります。東京ビーフならではの肉質を活かすには、火加減や焼き時間が大切なポイントです。
どちらのレシピも、プロの技を家庭で再現できるように考えられた内容であり、特別な日やごちそうにぴったりです。手に入れる機会があれば、ぜひ東京ビーフで試してみてください。
スタジオでも大絶賛されたその味
スタジオでは、天野ひろゆきさんと塚原愛さんが実際にバター焼きと煮込み料理を試食しました。天野さんは「熟成された旨みがスゴい」とコメント。番組を通して、その深い味わいと品質の高さがしっかりと伝えられました。
まとめ
青ヶ島の自然と人々の愛情、そして町田や西多摩の肥育技術が一体となって生まれる東京ビーフ。その誕生には島と都市をまたいだ400kmの旅があり、“幻の黒毛和牛”と呼ばれるにふさわしい背景と味わいがありました。
生産者の工夫や、島での暮らし、プロの調理法まで、幅広い視点で描かれた今回の『うまいッ!』。東京都内で育てられた和牛の魅力を、改めて感じることができる放送内容でした。
放送を見逃した方も、ぜひ「東京ビーフ」に注目してみてください。特別な日のお祝い料理にもぴったりの逸品です。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


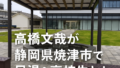
コメント