伊勢神宮への旅・第二夜|2025年4月12日放送
2025年4月12日(土)放送の『ブラタモリ』は、伊勢神宮を目指す新シリーズの第二夜として、三重県鈴鹿市を舞台に展開されます。江戸時代に大ブームとなった「お伊勢参り」の面影をたどりながら、宿場町の魅力や街道グルメ、歴史の痕跡を紹介する内容となっています。今回は、江戸から伊勢神宮を目指した人々のメインルート「伊勢路」を旅する中で、鈴鹿市に残る貴重な歴史資源や名物料理にも焦点が当てられます。
江戸時代に憧れられた「伊勢路」の旅の魅力
伊勢路は、三重県桑名市から伊勢神宮までをつなぐ約90kmの街道で、江戸時代には「お伊勢参り」のメインルートとして知られていました。庶民にとって一生に一度の大きな夢だった伊勢参りは、この道を通って実現されていたのです。
伊勢路の旅は、ただ目的地を目指すだけではありませんでした。途中にある宿場町が、旅人たちにとって休息と交流の場となっていたことが大きな魅力のひとつです。
-
桑名宿は東海道と伊勢路の分岐点であり、伊勢路の玄関口として重要な場所でした。海路との接続点でもあり、渡し船で旅を始める人も多くいました。
-
四日市宿は商業都市として栄え、旅人だけでなく荷物の中継点としても活躍しました。市が開かれる日には町が賑わいを見せ、多くの茶屋や屋台が立ち並びました。
-
鈴鹿宿は、鈴鹿峠を越える手前の要衝で、街道旅の疲れを癒すための宿が集中していました。鈴鹿市には今も、江戸時代の街道の名残を感じさせる町並みや石畳、古い家屋が点在しています。
-
津宿では、城下町ならではの文化と、参詣者へのもてなしが融合した賑わいがありました。多くの宿屋や料理茶屋が整備され、参拝前の身支度を整える場所でもありました。
-
松阪宿は伊勢商人の故郷として栄え、上質な衣食を提供することでも知られていました。松阪牛のルーツとも関わる地域で、食の記憶も旅の楽しみのひとつだったといえます。
旅人たちは、このような宿場をひとつひとつ辿りながら、伊勢神宮という大きな目的地に向かいました。街道沿いには、石標や地蔵、道標などの史跡が今も数多く残っており、当時の人々の足跡をたどることができます。
また、各地の宿場には伊勢音頭や俳句などの文化的記録も残されており、人々が旅の中で感じた風景や感動が、言葉としても伝わっています。
鈴鹿市の旧街道「札の辻」などには、江戸時代から続く建物や道筋がそのまま残されており、まるで当時の旅人になったかのような感覚で歩くことができます。こうした町並みは、今でも観光や地域学習の場として活用されています。
伊勢路は、単なる通り道ではなく、地域の暮らしと文化、信仰が交差する物語の道だったことが、今もその風景から伝わってきます。
タモリさんも大興奮!三差路に建つ老舗旅館の魅力
今回のブラタモリでは、三重県鈴鹿市の旧伊勢街道「札の辻」交差点に建つ歴史ある旅館『油伊旅館』が登場します。この場所は、江戸時代から続く宿場町・神戸(かんべ)の中心にあたり、今もその面影を色濃く残す貴重なエリアです。
旅館が建つ「三差路」は、旅の分岐点として多くの旅人が行き交った重要な場所でした。そこに佇む油伊旅館は、明治35年(1902年)創業で、築約150年の木造建築が今も使われています。
-
外観は落ち着いた黒い瓦屋根と格子窓が特徴で、江戸時代の旅籠のような雰囲気を感じさせます
-
室内には畳敷きの和室や障子、木製の天井梁などが残されており、時代の流れを体感できる空間です
-
徒歩3分ほどの距離に近鉄鈴鹿市駅があり、アクセスも非常に便利です
旅館が位置する神戸の町は、旧城下町としての歴史を持ち、街道沿いには今も石畳や蔵造りの建物が点在しています。旅館の周囲を歩くだけでも、まるでタイムスリップしたような感覚が味わえます。
また、この宿は伊勢参りの中継地として多くの旅人が宿泊した歴史を持つとされ、当時の記録や品々が残されていることも知られています。そうした背景もあって、タモリさんが番組内で訪れるにふさわしい場所として取り上げられたのでしょう。
静かな町並みに溶け込むように建つ油伊旅館は、現代に残る数少ない“旅人気分”を体験できる場所として、地元の人々にも親しまれています。テレビを通してその魅力がどのように描かれるのか、今から注目が集まっています。
鈴鹿サーキットで発見!宿場町生まれの名物グルメ「とんてき」
鈴鹿市で生まれた名物料理「とんてき」は、江戸時代から続く宿場町文化の中で育まれたご当地グルメです。今では市内の多くの飲食店やご家庭でも親しまれており、鈴鹿を訪れる人々にとっても大きな楽しみのひとつです。
とんてきの魅力は、なんといっても厚切りの豚肩ロース肉を豪快に焼き上げるそのインパクトです。見た目のボリューム感もさることながら、味もガツンと濃いめで、食べ応えがあります。
-
厚さは1.5cm以上ともいわれ、ナイフを入れた瞬間にじゅわっと肉汁が広がります
-
味付けにはにんにくと濃口しょうゆベースの特製ソースが使われており、香りからすでに食欲をそそります
-
皿にはたっぷりの千切りキャベツが添えられ、こってりした肉とのバランスも考えられた構成です
このとんてきを味わえる注目スポットのひとつが、鈴鹿サーキット内の「鈴鹿トンテキ本舗」です。サーキット内という特別な空間で、ご当地の味を楽しめることもあり、観戦の合間や家族連れの食事にも大人気となっています。
鈴鹿サーキットはモータースポーツの聖地として知られていますが、こうした地域色豊かなグルメとの融合があるからこそ、観光客にとっても特別な体験が生まれるのです。
とんてきという料理には、旅人をもてなし、力をつけてもらおうとする宿場町の思いが込められています。江戸の昔、鈴鹿の町で旅人たちが立ち寄り、活力を取り戻して再び伊勢へ向かって歩き出したように、現代の私たちにも元気をくれる存在です。
伝統と現代が交差する鈴鹿サーキットのグルメ体験は、伊勢路の魅力を味わうもうひとつの旅の形として、ますます注目されそうです。
「お伊勢参り」ブームの痕跡を探る旅
江戸時代、多くの人が一度は訪れたいと願ったのが「お伊勢参り」でした。そんな歴史的ブームの名残は、現代にも確かに残されています。今回の旅では、そうしたお伊勢参りの痕跡をたどることが大きなテーマになっています。
出発地点として知られるのが、三重県桑名市にある「一の鳥居」です。ここは伊勢神宮への道の入り口とされ、式年遷宮のたびに鳥居が建て替えられてきました。木曽三川を渡る渡し船の場でもあり、全国からの参拝者が最初に伊勢の空気を感じる場所でした。
-
一の鳥居は現在も存在し、石造りのものが立っています
-
桑名宿としても栄えたこの地は、参拝前の準備を整える場所としても大切にされていました
参拝を終えた後、多くの人が立ち寄ったのが「古市遊郭」です。ここは、伊勢参りの“精進落とし”の場所として知られ、参拝の緊張から解放された旅人たちが、食事や酒、遊びを楽しむために訪れました。吉原や島原と並ぶほどの規模を誇り、当時の風俗文化の一端を担っていた重要な場所でもあります。
-
最盛期には約1,000人以上の遊女と数十軒の妓楼が存在
-
遊郭の中には、詩や俳句が残されているものもあり、文化の中心地としても機能していました
また、参拝そのものにも一定の順序と習慣がありました。特に有名なのが以下のようなルートです。
-
二見浦で海水に入って身を清める「禊(みそぎ)」を行う
-
外宮を先に参拝し、次に内宮へ向かう「外宮先祭」
-
最後に朝熊岳(金剛證寺)へ登る「お伊勢まいりの締めくくり」としての習わし
この流れは現在も伊勢参拝の正式な順序とされており、多くの人がその形を大切にしています。
鈴鹿市をはじめとする旧街道沿いの町並みには、こうした歴史の名残が今も数多く残っています。道沿いの石碑やお地蔵様、古い木造の商家、格子窓のある町屋などは、当時の旅人たちの足跡を今に伝えるものです。
また、食文化においても、お伊勢参りと関わりの深い郷土料理や名物が各地に受け継がれています。とんてきや伊勢うどん、てこね寿司なども、元をたどれば参詣者をもてなすための工夫から生まれた食べ物と考えられます。
こうした街道沿いに今も息づく文化や景観が、「お伊勢参り」という庶民の旅の記憶を静かに語りかけてくれるのです。番組では、それぞれの遺構や地域の空気をタモリさんが歩いて感じ取り、どのように伝えてくれるのか、見どころとなるでしょう。
まとめ
今回の『ブラタモリ』伊勢神宮への旅・第二夜では、「伊勢路」の宿場町・鈴鹿市を舞台に、旅人たちが辿った歴史とその名残を丁寧にたどっていきます。旅情あふれる老舗旅館や、宿場町生まれの名物グルメ「とんてき」、江戸時代の参詣ブームの痕跡など、鈴鹿に秘められた魅力が存分に紹介される内容となるでしょう。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

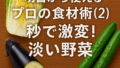

コメント