高橋文哉が焼津市で足湯&水産高校へ!感動の出会いと地域の魅力満載の旅
2025年4月7日放送のNHK総合「鶴瓶の家族に乾杯」では、朝ドラ「あんぱん」で注目を集める高橋文哉さんが静岡県焼津市を訪れ、ぶっつけ本番の出会い旅に出ました。今回の旅では、市役所の足湯を目指して歩く中で出会った人々とのふれあいや、地元の名物「ツナ専門店」、さらに焼津水産高校の生徒たちとの交流など、焼津の魅力がたっぷり詰まった内容となりました。一方、笑福亭鶴瓶さんは商店街や住宅街を訪ね、地域に根差した人々との出会いを通じて、焼津の温かな日常を紹介しました。
高橋文哉さん、焼津市の旅は食堂からスタート

旅の始まりは、焼津市内にある地元の食堂。高橋文哉さんはここで、焼津名物のカツオのお刺身を注文しました。新鮮なカツオはしっとりとして弾力があり、厚めに切られた身からは漁港の町ならではの豪快さが感じられました。食堂には地元の人々が集い、ゆったりとした時間が流れていました。
食事を終えた高橋さんに、店の方が教えてくれたのが「市役所に足湯がある」という情報です。高橋さんはその足湯を目指して歩き始めました。
道を進む途中で、彼の目にとまったのが特徴的なデザインの看板。それが、ツナ専門店の入口でした。気になった高橋さんは自然とその店に足を向け、中へ入っていきます。
ツナ専門店では、さまざまなフレーバーのツナ缶が棚に並んでいました。
-
プレーンタイプは、ビンチョウマグロ本来の風味が生きたシンプルな味わい
-
ガーリック&オレガノは、香ばしさとスパイスの風味が食欲をそそる一品
-
ドライトマト&バジルは、イタリアン風でパンにも合う味付け
スタッフにすすめられて、いくつかのツナをその場で試食。使われているマグロはすべて地元焼津港で水揚げされた新鮮なもの。オイルや調味料にもこだわっており、すべて手作業で製造されているとの説明もありました。
缶詰とは思えないほどしっとりとした食感と、口いっぱいに広がる旨味は印象的で、高橋さんはその品質に驚いた様子でした。焼津のツナ缶が全国的に評価されている理由を、体感を通して理解する場面となりました。
食堂での温かい接客、ツナ専門店での丁寧な紹介と試食、どちらも焼津の人々のやさしさや地元愛が感じられるひとときでした。高橋さんの旅は、この時点ですでにたくさんの魅力に出会い始めています。
鶴瓶さんは焼津駅前通り商店街で老舗のお茶屋さんへ
鶴瓶さんが向かったのは、焼津駅前通り商店街の一角にある昔ながらのお茶屋さんです。この店は代々続く地域密着型の老舗で、現在は3代目の店主が中心となって店を運営しています。店構えは落ち着きがあり、どこか懐かしさを感じさせるたたずまいでした。
注目すべきは、70代の先代店主の姿勢です。息子に店を任せるにあたって、「自分がいない方がやりやすいだろう」と考え、自身は別の場所で薬剤師として現役で働いているというエピソードが紹介されました。その潔さと息子への信頼は、まさに家業を継ぐ家族ならではの思いやりがにじんでいました。
店内ではお茶の販売はもちろんのこと、お菓子類も取り扱っており、お茶と合わせた地元ならではの楽しみ方ができる品ぞろえになっています。地元の常連客が多く、観光客にも焼津の味を伝える役割を果たしています。
さらに印象的だったのは、営業本部長として活躍する人物の存在です。この本部長は、なんと店主の同級生の父親。商売の場に家族ぐるみの関係性があることで、店の運営に安心感と温かみが加わっています。
-
3代目店主が中心に運営
-
先代は薬剤師として別の道へ
-
お茶とお菓子の取り扱いあり
-
営業本部長は店主の同級生の父親
このように、お茶屋さんはただの販売の場ではなく、家族の絆と地域の信頼が交差する場所であることが伝わってきました。鶴瓶さんの訪問を通じて、店の歴史や人と人とのつながりの深さが静かに浮かび上がる時間となりました。
足湯「ととゆ」に到着!温かいつながりが生まれる

高橋さんが向かったのは、焼津市役所本庁舎の北側にある芝生広場。ここに設置された足湯施設「ととゆ」は、地元の温泉資源を活用した無料の足湯スポットとして知られています。この日は16時の営業時間終了目前、わずか3分前の到着でしたが、運良く利用することができました。
施設は清潔に整えられており、10名ほどが同時に入れる造りとなっています。屋外で開放的な雰囲気の中、焼津温泉の湯がじんわりと足元を温めてくれます。お湯は無色透明で、少しとろみを感じるような肌ざわり。しばらく座っていると、冷えていた身体の芯がぽかぽかと温まってきます。
この足湯の魅力は、お湯の質だけではありません。ふらりと訪れた人々が自然と集まり、世代を超えた会話が生まれる交流の場でもあります。この日も、ベンチでお湯に浸かっていた町の人が、高橋さんに「水産高校がいいよ」と話しかけてきました。焼津のことをもっと知るなら、ぜひ訪ねてみてはという地元ならではの温かい助言です。
-
施設名:「ととゆ」
-
営業時間:9:00~16:00(夏季は17:00まで)
-
利用料:無料(タオルは持参)
-
定員:約10名
-
設置場所:焼津市役所北側の芝生広場
「ととゆ」の名前は、焼津で「魚(とと)」と呼ぶことに由来しています。観光地としての側面だけでなく、地元住民にとっても憩いの場となっているこの足湯は、焼津ならではの文化や人のつながりを実感できる場所です。短い滞在時間ながら、高橋さんの旅に新たな目的地をつなげる大きな出会いとなりました。
鶴瓶さん、住宅街で映画看板に注目
鶴瓶さんは商店街をあとにして、焼津市内の静かな住宅街をゆっくり歩いていました。穏やかな道沿いを進んでいると、ひときわ目を引く映画の看板が、個人宅の前に掲げられているのを見つけました。看板にはタイトルのほか、上映情報や連絡先の電話番号が丁寧に書かれており、手作りながらもしっかりとした内容でした。
看板の雰囲気からは、地域の誰かが本気で映画上映に取り組んでいることが伝わってきました。鶴瓶さんはその場で看板に記載された電話番号に連絡。応対したのは「太田さん」という人物で、すぐに訪問の約束を取りつけることになりました。
この看板が掲げられていた場所は、住宅街の中でも特に落ち着いたエリアで、車通りも少なく、のんびりとした空気が流れています。映画のチラシなどは見かけても、個人宅で映画上映の告知を堂々と行っているのは珍しく、地域に根差した文化活動であることがうかがえました。
-
看板には「吉永小百合」主演作品の名もあり、昭和の名作映画を思わせるラインナップ
-
ペンキで丁寧に描かれたタイトルと日付が並び、住民の目にも親しみやすいデザイン
-
表札の横に設置されており、家の人が訪問者を受け入れる意志を感じさせる配置
この出会いは、地域で活動する人との縁をつなぐきっかけとなりました。映画上映という文化活動が、静かな住宅街の一角で続けられている事実に、焼津の人々の豊かな暮らしぶりが垣間見えます。看板を見つけた偶然が、やがてこの旅にとって大きな意味を持つ出会いへとつながっていきます。
焼津の地域活動と人の想い
鶴瓶さんは住宅街を歩きながら、地域の人々と自然にふれ合い、写真撮影を求められる場面にも気さくに応じていました。そんな中、先ほど電話で約束をした太田さんと再び合流します。太田さんの表情には、地域活動への強い意志とやさしさがにじんでいました。
話を聞くと、太田さんは静岡福祉大学の元学長で、現在は地域のために完全ボランティアで活動しているとのこと。高齢者から子どもまで楽しめるようなイベントを定期的に開催し、地域全体に元気を届けているそうです。その一環として、自宅で映画の自主上映会も実施しています。
-
上映作品には「吉永小百合」主演の名作映画など、世代を問わず楽しめる作品を選定
-
会場は太田さんの自宅で、リビングの壁にスクリーンを設置
-
上映にかかる費用はすべて太田さんの自己負担
-
入場は無料で、近隣住民が集う場として親しまれている
さらに太田さんは、同じく75歳の望月さんとともに、地元の自然素材を使った竹あかりの制作活動にも取り組んでいます。使われるのは地元で採れる竹で、穴を開けた部分に灯りをともすことで、まるで灯篭のような柔らかい光を放ちます。
-
作品のモチーフには、カツオや花火の形が取り入れられており、焼津らしさが表現されている
-
竹の内側から漏れる光が夜の町に幻想的な空間をつくり出す
-
夏祭りや地域イベントで展示されることもあり、来場者の目を引いている
-
すべて手作業で制作されており、ひとつひとつに丁寧な想いが込められている
こうした活動は「高齢者が地域の未来を照らす」象徴でもあり、太田さんと望月さんの取り組みは、多くの人に影響を与えています。映画と竹あかりというふたつの文化を通じて、地域にやさしい光を灯し続けるその姿勢に、焼津というまちの静かで強い力を感じることができました。
高橋文哉さん、いよいよ焼津水産高校へ
足湯で出会った人に勧められた静岡県立焼津水産高等学校へ向かった高橋さん。到着後、まずは学校側に撮影の許可を交渉。許可が得られると、校内を案内してもらいながら、生徒たちの学びの現場を訪れました。この高校は、焼津市に根ざした特色ある教育を行っており、水産業や食品加工、流通など多様な分野を学ぶことができます。
校内には専門的な学びの場が整っていて、以下のような学科があります。
-
海洋科学科:航海、機関、工学、開発など、実際の船に関わる分野を細かく分けて学習
-
食品科学科:水産物の加工や保存方法を学び、ツナ缶や佃煮などを自分たちで製造
-
栽培漁業科:魚の育て方や繁殖方法について、実習を通じて理解を深める
-
流通情報科:商品開発や販売の仕組みを学び、模擬会社で販売や経営も体験
実習施設では、実際に使われている船舶用機械や加工場も見学できるようになっており、地元産業と直結した学びが行われています。
この日の高橋さんは、吹奏楽部とカッター部の生徒たちの活動を見学しました。吹奏楽部では、部員たちが明るく元気に挨拶しながら、楽器を手に一生懸命練習している姿がありました。
そして特に注目されたのが、カッター部の練習風景です。
-
カッターは全長9mのボートに14人が乗り、1000mの距離を漕ぐ競技
-
全国大会で3回の優勝実績を持つ強豪校
-
練習では、タイミングを合わせるための号令や、力強い漕ぎの音が校内に響いていた
-
チームワークと集中力が求められ、互いを支え合う姿勢が自然と育まれている
高橋さんは、真剣な表情でボートを漕ぐ生徒たちの姿に心を打たれた様子でした。このような実践的な学びの場で生徒たちが日々努力している姿を知ることで、焼津の未来を担う若者たちのたくましさと情熱が感じられる時間となりました。教室の中だけでなく、地域の資源や文化を生かした教育がしっかりと根づいていることが、焼津水産高校の大きな魅力です。
焼津名物「魚河岸シャツ」と地域の誇り
鶴瓶さんが太田さんとともに訪れたのは、焼津で長く親しまれてきた魚河岸シャツの専門店です。このシャツは、昭和の初めごろ、焼津の漁業関係者たちが手ぬぐいを再利用して仕立てたのが始まりとされています。風通しがよく、濡れても乾きやすく、作業着としても快適なことから、地元の漁師たちに重宝されてきました。
店内にはさまざまな柄や色の魚河岸シャツが並び、目を引く鮮やかなデザインが特徴です。中にはカツオや波模様、花火など焼津を象徴するモチーフをあしらった柄もあり、着るだけで地域の文化や季節感を表現できるようになっています。
-
現在では日常着や贈答品としても人気
-
夏の時期には焼津市役所の職員も着用している
-
地元のお祭りやイベントでは市民が一斉に魚河岸シャツを着ることもある
-
生地は綿素材で、軽くて動きやすい仕様
この魚河岸シャツは、ただの衣類ではなく、地域文化の象徴です。長年にわたり焼津の人々に愛されてきた背景には、実用性だけでなく「誇り」があります。太田さんと望月さんのように、竹あかりなどで地域を明るく照らす活動と同じく、このシャツもまた地域の歴史と今をつなぐ大切な存在となっています。
焼津の人々が夏になると自然にこのシャツを身につける姿は、観光客にとっても印象的で、焼津らしさを体感できる一場面です。鶴瓶さんの訪問を通じて、見た目以上に深い意味を持つ一着のシャツが紹介され、地域文化の奥深さを伝える締めくくりとなりました。
まとめ
今回の「鶴瓶の家族に乾杯」では、高橋文哉さんが足湯や水産高校、ツナ専門店を訪ね、焼津の人情と魅力に触れる旅を展開しました。一方で鶴瓶さんは商店街や住宅街を歩きながら、家族や文化を大切に守る人たちと出会い、心温まるエピソードを届けてくれました。焼津という町の奥深さが感じられる、見どころ満載の回となりました。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


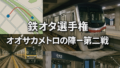
コメント