かしわ飯からお米が消えた!?“米騒動”の真相とは
2025年7月19日放送の「所さん!事件ですよ」では、私たちの食卓に欠かせない“お米”をめぐる思いがけない騒動が特集されました。番組では、佐賀の駅弁から始まり、味噌や日本酒、そして農業の最前線まで、お米を取り巻く現状とこれからの課題が幅広く紹介されました。なぜかしわ飯からお米が消えたのか?そして、ビールがカギとなる新農法とは?さまざまな視点から、“米騒動”の真相に迫ります。
駅弁のかしわ飯が「トースト」に変わった背景とは
米価格の高騰が駅弁に与えた影響
佐賀県鳥栖市にある老舗の駅弁メーカーでは、長年愛されてきた「かしわ飯弁当」に代わる新しいメニューとして、「かしわトースト」を生み出しました。この一見ユニークな変化の背景には、主食用米の価格が急激に上がったことがあります。とくに最近では、米の仕入れ価格が約2倍にまで跳ね上がり、原材料費が大きく圧迫されていました。
弁当として販売するには価格を一定に保つ必要がありますが、米の高騰によってその維持が難しくなったため、やむなくごはんをパンに置き換えるという大胆な発想が求められました。そして誕生したのが「かしわトースト」です。
新メニュー「かしわトースト」に込められた工夫
このかしわトーストは、駅弁としての食べやすさを意識しながらも、かしわ飯の風味をしっかりと感じられるように設計されています。パンには香ばしく焼いた鶏肉や甘辛く味付けされた具材がはさまれていて、どこか懐かしさも残る味わいになっています。
伝統ある駅弁が形を変えるのは非常に珍しいことですが、それだけ今のお米事情が深刻であることがうかがえます。これまで当たり前だったごはんが使えなくなるという事態は、駅弁に限らずさまざまな食品業界にも影響を与え始めているのです。
今後、こうした“代替メニュー”の登場はさらに増える可能性があり、米を中心とした日本の食文化が新しい方向へ動き出している様子が感じられます。駅弁の世界でも、価格と品質のバランスをとりながら工夫する現場の努力が続いていることが伝わってきます。
米だけじゃない!?みそや酒にも広がる影響
加工用米の供給不足が味噌メーカーを直撃
長野市にある老舗の味噌メーカーでは、これまで毎年安定して仕入れていた加工用米の量が、突然3割も削減されるという通知を受けました。味噌づくりには米麹が欠かせず、米はその原料となります。原料米の確保が難しくなると、仕込みの量を減らさざるをえず、年間の生産量も落ち込みます。結果として、売上が大幅に減ることになり、企業の経営そのものに大きな影響を与える事態になっているのです。
味噌は毎日の食卓で欠かせない調味料ですが、その裏では、米の供給状況が商品の安定供給に直結しています。もしこの状況が続けば、値上げや品薄も避けられないとみられています。
酒蔵も苦境に 原料米の高騰が続く
また、同じ長野県の佐久穂町にある酒造メーカーでも、日本酒の仕込みに使う原料米の価格が上がり続けていることが紹介されました。高品質の酒を作るには、一定の等級と条件を満たした米が必要ですが、その確保が難しくなってきており、コストの増加を吸収しきれず、商品の価格を段階的に上げることも検討されています。
お酒は季節ごとの楽しみとしても人気がありますが、裏では米の価格がじわじわと負担になっており、消費者にもその影響が広がる兆しがあります。
なぜ加工用米が不足しているのか?
こうした状況の背景には、加工用米と主食用米の価格差が大きくなっていることがあります。近年、主食用米のほうが高く売れるため、多くの農家が加工用米から主食用米の生産に切り替える傾向にあります。結果として、加工用米の供給量が年々減少しており、その余波が味噌や酒のような発酵食品業界にも広がっているのです。
今後もこの傾向が続けば、私たちの食卓に並ぶ定番品が手に入りにくくなったり、値段が上がったりすることも考えられます。米の使い道の違いが、さまざまな食品に与える影響は想像以上に広がっているといえるでしょう。
お米の代わりに「ふりかけ」が人気に
節約志向が広げた“ふりかけごはん”ブーム
お米の価格が上がっている中で、意外な形で注目されているのがふりかけの売れ行きの好調さです。番組では、ある食品メーカーが過去最高の売上を記録したという事実も紹介されました。この背景には、家計の負担を少しでも減らしたいという消費者の節約意識があるとされています。
今では、たくさんのご飯を食べるのではなく、少量のごはんにふりかけをかけて満足感を得るという食べ方が広まりつつあります。味がしっかりしているふりかけを使えば、少ない量でも満足できるうえ、冷蔵保存もいらず手軽です。これが忙しい家庭や一人暮らしの人たちの生活スタイルにもマッチし、人気を集めている理由のひとつとなっています。
また、最近のふりかけは種類も豊富で、定番のたまごや鮭だけでなく、野菜ミックス、カレー風味、韓国風などの変わり種も登場しています。なかには栄養強化された商品や、大人向けに辛みやだしを効かせたものもあり、手軽さと多様性の両方を備えているのが大きな魅力です。
ふりかけの人気は、単なる“おかずの一部”を越え、今や生活を助ける工夫のひとつとして再評価されています。お米が高くなっても、こうしたアイデアで乗り切る家庭の工夫が、これからの食卓を支えていくかもしれません。
新農法で未来を変える?畑で育てるお米
水を使わない「乾田直播」とはどんな農法?
埼玉県北葛飾郡で実践されている「乾田直播(かんでんちょくはん)」という農法が、これからの米づくりのあり方を大きく変える可能性として注目されています。これは、田んぼに水を張ることなく、畑のような乾いた土地に種籾を直接まいて育てる方法です。通常の田植えに必要な育苗・田植え・水管理といった工程が省かれるため、労力や時間を大きく削減することができます。
乾田直播で特徴的なのは、ビールの製造工程で出る副産物を活用した液体肥料を種に吹きかける技術です。この液体には、植物にとって「病気かもしれない」と感じさせる成分が含まれており、種籾は危機を感じて早く芽を出そうとするのです。この“勘違い”の働きが、芽出しをそろえて安定させるポイントになっています。
環境にもやさしく、省力化にも貢献
この新しい農法は、水をまったく使わないため水資源を守ることができ、同時に作業時間を約7割も短縮できるというメリットがあります。特に高齢化が進む農業の現場にとっては、作業の負担を軽くできる点で非常に魅力的な方法といえます。また、農薬や化学肥料の使用を減らす取り組みとも相性がよく、持続可能な農業を目指すうえで重要な選択肢となりつつあります。
ただし、乾田直播はすべての土地に適しているわけではありません。たとえば、湿度の高い地域や、水はけの悪い土壌ではうまく育たない場合があります。さらに、収穫量は通常の水田よりやや少なくなるという課題もあり、導入には適した条件を見極める必要があります。
これからの農業は、こうした新しい技術を地域ごとの特性に合わせて活用していくことが求められます。乾田直播はその一つの答えとして、多様な栽培法の可能性を広げているのです。お米の未来を支える新しい選択肢として、これからも注目されていきそうです。
農業の未来に必要なのは「多様性」
番組では、農法の多様性に注目する声も紹介されていました。新しい方法だけを推すのではなく、それぞれの土地や農家に合った方法があってよいという考え方です。農業の魅力は、いろんなやり方があって、それぞれの現場が工夫しながら成り立っているところにあると紹介されました。
今回の特集を通して、お米の問題は単に価格の話ではなく、生活・産業・環境に深く関わっていることが分かります。おいしいお米を食べ続けるためには、生産現場への理解や応援も大切になってきそうです。
出典:NHK「所さん!事件ですよ」2025年7月19日放送
https://www.nhk.jp/p/jiken/ts/X8R36PY6R3/
米の等級と加工用途のちがい

ここからは、私からの提案です。お米には、見た目のきれいさや形のそろい方によって等級がつけられています。1等米、2等米、3等米、そして規格外という4つの区分があり、それぞれの特長に合わせた使い道があります。ここでは、そのちがいを表にしてわかりやすくまとめ、その内容を少しくわしく解説します。
等級ごとの特徴と主な用途
| 等級 | 整粒歩合(玄米) | 外観の特徴 | 主な使い道 |
|---|---|---|---|
| 1等米 | 70%以上 | 粒がそろっていてつやがあり、割れや着色がほとんどない | 百貨店や贈答用、レストランなどで使われる食卓米として流通 |
| 2等米 | 60%以上 | やや割れた粒や色のついた粒があるが、味に問題はない | 一般家庭や飲食店などでのご飯用、コスパ重視のお米として販売される |
| 3等米 | 45%以上 | 割れや変色の粒が多く見た目にばらつきがある | ふりかけ、せんべい、米菓、加工食品などの材料として利用される |
| 規格外 | 45%未満または異物混入が多い | 粒の大きさがそろっておらず、混ざりものがあることも | 飼料用や工業用の原料、あるいは一部の輸出向け米などに使われる |
等級による味や価格の差
等級は見た目や粒のそろい方で決まりますが、味そのものに大きな差はないこともあります。たとえば2等米や3等米でも、炊き方や料理によっては十分おいしく食べられます。ただし、等級が下がるほど見た目が不ぞろいになり、市場での評価が下がるため、価格は安くなります。
加工用と主食用のちがいとは?
加工用米は、おにぎりやお弁当、総菜などに使われたり、せんべいやふりかけの原料になったりします。また、みそや日本酒の原料となる米も「加工用米」に含まれます。これに対して、主食用米はそのまま炊飯して食べることを前提としたお米です。
最近では、加工用米にまわす分が足りなくなってきており、その結果ふりかけや酒、みその値段にまで影響が出ています。農家の人たちは、価格が安定している主食用米に生産を切り替える動きもあり、等級と用途の関係がますます注目されてきています。
このように、等級ごとのちがいを知ることで、お米を選ぶときのヒントになったり、なぜ価格が上がっているのかを理解したりする手がかりになります。お店で「2等米」と表示されていても、品質的に問題のないお米が多いので、目的や予算に合わせて選ぶことが大切です。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


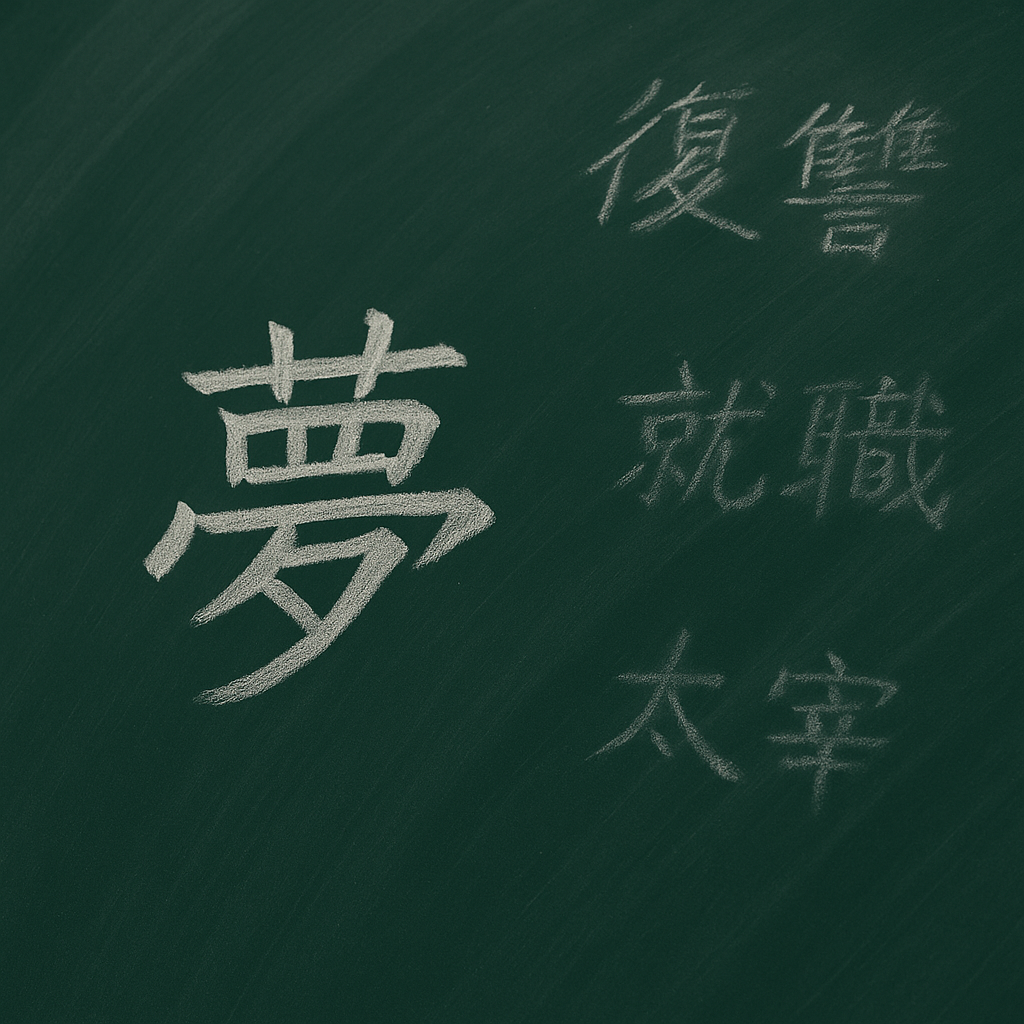
コメント