大阪・関西万博を支える技とは?開会式直前の現場に潜入
2025年4月12日(土)放送のNHK総合「探検ファクトリー」では、開幕直前の大阪・関西万博会場を訪れ、華やかなイベントの裏側で奮闘する人々の姿が特集されました。出演は中川家(剛さん・礼二さん)とすっちーさん。今回は、日本の伝統と最先端の技術が融合した建築や展示の数々を通じて、世界に誇る“ものづくり”の力を楽しく、そして深く伝える内容でした。
世界最大の木造建築“大屋根リング”の技術力を支える匠の技
2025年大阪・関西万博の会場にそびえる「大屋根リング」は、直径約600メートルという圧倒的なスケールを誇る、世界最大級の木造建築物です。その存在はまさに万博の象徴であり、広大な敷地を包み込むように設計されています。リングの下は、万博を訪れる人々が行き交うメイン動線となっており、直射日光や雨から守る巨大な日よけの役割も担っています。
この前例のない巨大構造に挑戦したのは、日本の建築技術をけん引する3つの企業。それぞれの技術が一体となり、困難な課題に立ち向かいました。中心となる建材には、「集成材」と呼ばれる特殊な木材が使われています。これは、薄い木の板を何枚も重ねて接着し、一体化させたもので、以下のような特徴があります。
・高い強度と曲げにくさを実現しており、大きな荷重にも耐えられる
・乾燥による収縮や反りが少なく、寸法の安定性が高い
・天然木のような温もりを持ちながらも、品質が均一に保たれる
このように優れた素材を用いながらも、設計に採用されたのは、日本古来の木造建築技法「貫工法(ぬきこうほう)」です。柱に穴をあけて横木を通し、くさびで固定するという方法で、かつては清水寺や寺社仏閣でも使われてきた伝統的な工法です。この技法の特徴としては、
・釘やボルトを使わず、木材同士のかみ合わせで強度を持たせる
・地震などの揺れに強く、柔軟に力を逃がす構造を実現
・見た目も美しく、建物全体に自然な一体感が生まれる
しかし、今回のように屋外で、しかも巨大なリング状の建造物に応用するには、課題も少なくありませんでした。現代の建築基準法に照らすと、伝統工法だけでは安全性を確保できない部分もあるため、金属部材を一部に取り入れて構造を補強。木と金属を適材適所で組み合わせることで、現代の安全基準を満たしつつ、伝統の風合いを損なわないバランスのとれた構造となっています。
・構造体のつなぎ目には鋼製の補強プレートを内蔵
・くさびの部分には現代的な素材で耐久性を強化
・全体の施工には3Dモデルを用いたシミュレーションも併用
また、素材となる木材は全国の林業地から集められたもので、日本各地の森と職人たちの力が結集したプロジェクトであることも番組で伝えられました。こうした工夫と努力の積み重ねによって、かつてない規模の木造建築が現実のものとして形になったのです。
大屋根リングは、ただのシェルターや構造物ではありません。技術の粋と文化の継承が重なった、日本が世界に誇る建築作品として、訪れる人々の記憶に強く残る存在となるでしょう。
海外パビリオンが続々登場!先進技術とアートの融合
大阪・関西万博では、国内パビリオンの内側を囲むようにして、各国のパビリオンがずらりと並んでいます。会場の外側に広がるこのエリアは、まるで世界を旅するような体験ができる場所で、オランダ・オーストラリア・オーストリア・カナダ・スイス・チェコなど、多彩な国々が参加し、それぞれの文化や価値観を反映した展示を準備しています。これらのパビリオンは、建築や展示においても強いこだわりがあり、デザイン性と技術力が融合した見応えのある空間となっています。
中でも目を引いたのが、「null2(ヌルツー)」と名付けられたパビリオンです。この建物の外装には、金属と樹脂を組み合わせた特殊な膜が使用されており、ただの装飾ではなく、音や振動を感知して形や動きを変えるという驚きの機能が備えられています。まるで生き物のように動く外壁は、見る人に強い印象を与え、建築そのものが“展示”として成立している点が注目されています。
・特殊膜は金属の強さと樹脂の柔軟性を融合させたハイブリッド構造
・音や振動に反応して、見る角度や環境によって印象が変化する外装
・まるで動く彫刻のように、来場者を包み込む不思議な存在感
内部の構造も非常にユニークで、天井と床一面にLEDディスプレイを敷き詰め、視界を360度で映像が取り囲むように構成されています。さらに四方の壁は全面鏡で、映像と自分の姿が何重にも重なり合う“仮想空間”のような世界が広がります。そこでは、ただ見るだけではなく、自分が空間の一部になったような没入体験ができるようになっており、今までの展示とはまったく異なる発想が込められています。
また、「null2」と並んで話題となっているのが、「Mirrored Body(ミラード・ボディ)」という未来型の展示空間です。このパビリオンでは、来場前に専用アプリを使って、自分の顔や声などの情報を事前登録することができます。会場に足を踏み入れると、その情報をもとに生成された“自分の分身”が登場し、あたかも本当に会話をしているかのようなやりとりが体験できます。
・AIと音声認識技術を活用して、リアルな対話が可能
・来場者の姿や表情を映し出すことで、「未来の自分」や「もう一人の自分」と出会う感覚を演出
・人とテクノロジーの境界を考えさせる、哲学的なテーマも内包した展示構成
これらの海外パビリオンは、単に国を紹介する場ではなく、その国がどんな未来を描いているのか、どのような価値観を持っているのかを体験的に感じられる空間となっています。先進的な技術と芸術的な表現が重なり合うことで、人の心を動かす“体験型アート”の場が生まれており、万博の新しい可能性を感じさせます。
日本の技術とのコラボレーションも多く、これらの構造物を支える製造技術や素材開発にも、国内の企業や職人たちが多く関わっています。国際的なプロジェクトでありながら、日本のものづくりがしっかりと根を張っている点も、番組内でしっかり紹介されていました。
海外パビリオンのひとつひとつが、まるで未来からやってきた建物のよう。技術・芸術・文化が融合した万博らしい空間が、世界中からの来場者を出迎える準備を着々と進めています。
伝統が息づく西陣織の外装と、手作業のこだわり
今回の大阪・関西万博では、先端技術だけでなく、日本の伝統工芸の美しさを体現したパビリオンも登場しました。そのひとつが、住宅メーカーが手がけたパビリオンで、外装にはなんと全面に京都の伝統織物「西陣織」が使用されています。この大胆な取り組みは、世界に向けて日本の美意識と技術力を伝える象徴的な試みです。
建設にあたっては、まず本番会場に設置する前に、別の場所で仮組みを行い、各部材が正確に組み合うか、デザインに問題がないかを細かくチェック。その上で慎重に現地搬入・設置が行われました。この工程は、効率と正確さを重視する万博会場ならではの重要な作業であり、完成度の高さを支えています。
設営には最新の建築機械だけでなく、手作業による調整や仕上げも多く含まれており、昔ながらの道具も使用されていました。
・ロープで丈夫な膜材をぴんと張り、下地をきれいに整える工程
・その上から丁寧に西陣織の布を貼り合わせていく作業
・微妙なズレやシワを職人の手で細かく修正しながら貼る技術
このように、一見するとシンプルに見える布張りの作業も、実際には高い集中力と長年の経験が求められる繊細な工程でした。機械では対応できない部分だからこそ、人の手が生きているのです。
使用された西陣織は、風雨に耐えるために特別に加工されたもので、伝統的な織りの美しさを保ちながらも、屋外での展示に耐える機能性も兼ね備えた新素材となっています。これは、伝統技術と現代の素材開発が手を取り合った成果といえます。
・色彩や織り模様は、光の当たり方によって表情を変える構造
・生地の裁断から貼り込みまで一貫して手作業で行われた
・西陣の職人と建築スタッフが密に連携して仕上げたチームワーク
このパビリオンは、遠くから見てもその存在感が際立ち、「手仕事の美」が建築の中に息づいていることを強く感じさせてくれます。来場者にとっては、日本の伝統がいかに現代の空間デザインと共存できるかを体験できる、非常に貴重な機会になるはずです。
こうした展示は、単に技術の進化だけでなく、「人の手の温かさ」「文化の継承」といった、未来の社会にとって本当に大切な価値を再確認させてくれる存在でもあります。日本が大切にしてきたものを、世界へ届ける役割を果たす素晴らしいパビリオンとなっています。
館内展示では未来の都市を体験
住宅メーカーのパビリオン内では、来場者が2050年の未来都市を体感できるジオラマ展示が行われていました。このジオラマは、大阪公立大学が中心となって企画・制作を担当し、科学的根拠とビジョンに基づいて構築されたものです。会場では子どもから大人までが足を止め、未来の暮らしや都市の姿を立体的に見られる空間となっていました。
展示の内容はとても精密で、建物ひとつひとつの形や高さ、街の構成、交通の流れなどが実際の都市のように再現されていました。特に印象的だったのは、都市全体が人や自然、技術と調和して構成されていることです。
・建物は環境に優しい素材で作られ、屋上には緑化スペースが広がっていた
・道路には自動運転車が走り、電気や水素を使うクリーンエネルギー車両も再現
・ドローンによる配達や空中移動システムも取り入れられていた
ジオラマの中には、AIと連動したスマート信号や、災害時に安全なルートを表示する案内装置など、人の安全と快適を守るための最新技術も多数組み込まれていました。こうした未来技術が、目に見える形で並べられているため、来場者は自然と“こんな暮らしになるのか”と想像を膨らませることができます。
さらに注目すべきは、インフラ設備の再現度の高さです。地中には上下水道・電力・通信などのインフラ網が配置され、普段見えない部分までしっかりと再現されていました。
・地下には災害に強い設備が整備されていた
・再生可能エネルギーを利用する発電設備も設置
・街全体がネットワークでつながり、情報がリアルタイムで共有される仕組み
こうした構成は、未来を抽象的に語るのではなく、「どうすればそれが実現できるのか」をリアルに伝える工夫が感じられます。ジオラマの横には解説パネルもあり、誰でも理解できるように図や言葉で丁寧に説明されていました。
この展示の魅力は、子どもたちにとっては未来への夢や好奇心を刺激する学びの場であり、大人にとっては社会や環境について考えるきっかけをくれるヒントの場になっていたことです。
未来の都市は決して遠い話ではなく、今の技術や考え方が一歩ずつ積み重なることで生まれると、展示を通して実感できました。このジオラマは、“未来”を身近に感じさせてくれる素晴らしいコンテンツとして、万博の中でも特に注目すべきポイントのひとつになっています。
裏方がつなぐ万博の未来
今回の番組では、目立つステージの裏側で動いている多くの人々の努力と工夫が丁寧に紹介されました。建築・技術・伝統工芸・デジタル表現、それぞれの分野のプロフェッショナルたちが連携し、“未来の日本”を世界に向けて発信する大舞台を築いている姿に強く心を打たれます。
イベントが無事に始まるまでには、見えない部分での努力と試行錯誤が積み重ねられているという事実を、この番組は丁寧に伝えてくれました。すべての人の仕事に光を当てる「探検ファクトリー」らしい視点で、万博の“支える技”がしっかりと描かれていました。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


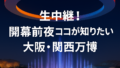
コメント