金色に輝く警察の紋章工場を探検!高度な技と芸術センスに迫る
2025年6月21日放送の「探検ファクトリー」では、福井県福井市にある警察の紋章をつくる工場を訪問。番組のテーマは「金色に輝く警察の紋章」。出演者のすっちーさん、中川家の礼二さんと剛さんが現地を訪れ、工場の歴史や、警察の紋章がどのようにしてつくられているのか、その工程を丁寧に紹介しました。金色に光る美しい紋章は、実は緻密な技術と芸術的な感覚が詰まった一品であることが明かされました。今回はその工場の秘密に迫ります。
創業は1956年 警察・消防・学校の紋章を製作する老舗工場
福井県福井市にある紋章製作の工場は、1956年に創業され、長い歴史を持つ老舗のものづくり現場です。創業者は現社長の父親で、時代とともに需要のある製品を丁寧につくり続けてきました。工場では、全国の警察署に設置される「警察紋章」をはじめ、消防署の紋章、そして小学校や中学校などの校章など、公共施設のシンボルとなる製品を幅広く手がけています。
以前の警察紋章は木製で、表面に金色の塗装を施したものでした。しかし、木材は雨や紫外線に弱く、屋外に設置すると数年で劣化してしまうという大きな課題がありました。この問題を解決するために、工場ではセラミックス製の紋章を開発しました。
セラミックスを使うことで以下のような利点が生まれました:
-
屋外でも長期間使用できる高い耐久性
-
金色の輝きが変色しにくい
-
雨風・直射日光にも強く、メンテナンスの頻度が減る
こうした改良によって、現在では多くの警察署でセラミックス製の警察紋章が採用されています。特に注目すべきは、そのセラミック製法に陶芸の技術が活かされている点です。焼き物としての伝統的な技術を活用しながらも、現代的なニーズに対応した工業製品を作る姿勢が、この工場の強みでもあります。
また、この工場では次のような地域に根ざした取り組みも行われています:
-
地元の職人技術を活かした製品開発
-
福井県内の公共施設や学校とのつながり
-
地元の工業技術センターとも連携し、新たな素材や加工技術を取り入れる努力
こうした背景には、単なる工業製品としてではなく、人々の記憶や誇りを形にするものづくりへの深い思いが感じられます。長年にわたって築き上げた技術と信頼、そして未来を見据えた素材の選択が、金色に輝く美しい紋章に込められているのです。
粘土から始まる紋章づくりの工程
紋章づくりは、まず粘土を使って原型をつくるところからスタートします。最初に使うのは、設計図の役割を果たす平面図。これをもとに、職人が手作業で粘土をこねて立体的な原型をつくりあげます。形や線の細部にまで注意を払いながら、紋章の元になる形が丁寧に作られていきます。
原型が完成したら、それをもとに石膏型を作成します。これは同じ形の紋章を何度もつくるために必要な工程で、大量生産の土台ともいえます。石膏型を作る際には、隙間や気泡が入らないように細心の注意を払います。
完成した石膏型には、水で溶かした粘土――いわゆる**泥漿(でいしょう)**を流し込みます。
-
泥漿はとろみのある液体で、石膏型の内側に沿って自然と広がります
-
時間をおいて一定の厚みができたら、余分な泥漿は排出します
-
このときの流し込み時間が短すぎると薄く、長すぎると厚くなってしまうため、熟練の感覚が求められます
形が定まったら、金具の取り付けに使う土台や支えを手作業で取り付けていきます。これにより、最終的な設置時にしっかりと壁に固定できるようになります。
そして、型から慎重に取り外された素地は、まず自然乾燥させて水分を飛ばします。
-
自然乾燥は時間がかかりますが、内部からじっくり水分を抜くことで形が崩れにくくなります
-
その後、遠赤外線乾燥機を使ってさらに内部の水分をしっかり取り除きます
-
遠赤外線での乾燥により、ムラなく乾かすことができ、焼くときにひび割れたりゆがんだりするのを防ぎます
乾燥後の素地は、まだ粘土の状態なので、失敗した場合や余った場合でも水を加えれば再利用が可能です。
-
工場では無駄を出さないように、再利用のルートがしっかりと整っています
-
使えなくなった粘土はすぐに廃棄せず、また別の紋章づくりに活かされます
このように、紋章づくりはただの型抜き作業ではなく、すべての工程に繊細な調整と職人の経験が必要です。粘土の性質、乾燥の時間、泥漿の粘度など、どれか一つでもバランスを欠くと、美しい紋章は完成しません。そうした細やかな工程を経て、強くて美しい紋章の土台がつくられているのです。
焼成と金色の輝きを生み出す技術
乾燥が終わった素地は、まだ仕上げ前の状態です。ここから、表面を滑らかに磨き、形を整える作業に入ります。小さな凹凸や不要なバリを取り除くことで、焼き上がったときに美しく、かつ安全に仕上がるようにします。作業は一つ一つ手作業で行われ、職人の目と手が重要な役割を果たします。
その後、紋章の表面には釉薬(ゆうやく)がかけられます。釉薬とは、焼き物に使う透明または色のついた液体で、焼くとガラスのような膜を作り出す性質を持っています。
-
この膜ができることで、紋章の表面にツヤと滑らかさが生まれます
-
さらに、水や汚れが染み込みにくくなり、屋外に設置されても美しさを保ちやすくなります
-
釉薬は全体にムラなくかける必要があり、均一な塗りが重要です
釉薬をかけた紋章は、窯に入れて5日間かけて本焼きされます。長時間の焼成により、粘土がしっかりと焼き締まり、強度も増します。
-
窯の温度は高温に保たれ、一気に焼かずに徐々に加熱していくことで、割れを防ぎます
-
この焼成によって、紋章は陶器としての強さと耐久性を得るのです
さらに、紋章に金色の輝きを与える工程も行われます。これには純金を使った「金がけ」という技術が使われています。あらかじめ焼き上げた紋章に、金を塗ってから再度焼くことで、金がしっかりと表面に定着します。
-
使用されるのは本物の純金で、色味に品があり、見る角度によって柔らかな輝きを見せます
-
金がけされた紋章は、専用の窯で6日かけて焼成されます
-
焼く温度や時間を正しく管理しないと、金がムラになったり、色がくすんでしまうため、ここでも職人の技術が求められます
焼成後には、金が表面にしっかりと焼き付いて、雨や風にも強い、美しい金色の紋章が完成します。こうしてできた紋章は、光を受けて上品に輝き、公共の場で人々の目を引く存在となります。
この一連の工程には、長い時間と手間、そして繊細な手作業が込められており、一つひとつが大切に仕上げられていることがわかります。表面のツヤ、金の輝き、形の美しさは、どれも簡単には真似できない職人技の結晶です。
警察紋章以外の製品開発も進む
この工場では、紋章以外にも、焼き物の技術を活かした製品づくりを行っています。福井県工業技術センターと連携しながら、伝統技術と現代のニーズを組み合わせた新しい製品の開発にも力を入れており、地元産業の未来を担う役割も果たしています。
番組では、こうした工場の取り組みや、ものづくりに携わる人々の姿も紹介されていました。特に、警察署で使用されている紋章の設置事例として「廣部耕佑福井警察署」の名前が取り上げられ、現場での使用例が紹介されていました。
福井の小さな町工場で、金色に輝く警察の紋章が一つ一つ丁寧に、そして誇りを持って作られていることが伝わる内容でした。今回の探検は、見た目の華やかさの裏にある職人の技術と情熱を知る良い機会となりました。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

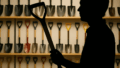

コメント