信楽焼の“今”がすごい!伝統と新しい風が生まれる町へ
「焼き物の町」と聞くと、どこか職人だけの世界のように感じるかもしれません。でも、滋賀県信楽町はちょっと違います。この町には、誰でもふらりと訪れて“手のぬくもり”を感じられる温かい空気が流れています。信楽焼は、見た目の美しさだけでなく、暮らしの中に自然と溶け込む器。毎日使うことで、その魅力が少しずつわかってくる不思議な存在です。
今回の探検ファクトリー(2025年10月4日放送)では、お笑いコンビの中川家(礼二・剛)とすっちーが、そんな信楽焼の魅力を探る旅に出ました。伝統を守る老舗の工場から、若手が挑む革新的な作品づくりまで――土と炎、そして人が紡ぐ物語を覗いてみましょう。
古琵琶湖の土が生み出す“強くて優しい”器
信楽焼を語るうえで欠かせないのが、古琵琶湖層と呼ばれる土です。およそ400万年前、琵琶湖が今よりも広かった時代の堆積物から採れる土で、粘りが強く、耐火性に優れています。焼くと独特の赤褐色になり、表面には「焦げ」や「ビードロ」と呼ばれる自然な模様が浮かび上がります。これこそが信楽焼の“素朴な味わい”を生み出す秘密です。
番組では、土を手で触りながら「この土はコシがある」「粘りがちょうどいい」と語る職人の姿も。ろくろの上で回る土はまるで生きているようで、指先のわずかな圧力や呼吸のリズムで形が変わります。職人は、「土を触りすぎない」ことが美しい器づくりのコツだと語ります。余計な手を加えず、素材の力を信じて形にしていく――そこには自然と共に生きる知恵が息づいています。
タヌキの置物が生まれた“奇跡の瞬間”

信楽焼の代名詞ともいえるタヌキの置物。どこか愛嬌のある表情で、店先や玄関で出迎えてくれるあの姿は、日本中でおなじみです。
そのきっかけは、昭和26年(1951年)に昭和天皇が信楽を行幸された際、地元の人々が手作りのタヌキ像を並べてお出迎えしたこと。昭和天皇がそれをたいへん喜ばれたことから、一気に信楽焼の名が全国に広まりました。
番組では、その制作現場も紹介されました。薄く延ばした土を型に押し込み、前後2枚の型を丁寧に合わせます。乾燥させたあと、耳や尻尾、腹の膨らみなど細かな部分は手作業で仕上げられます。職人の指が動くたびに、土がまるで笑っているような表情に変わるのが印象的でした。
仕上げには、筆で“目”を入れる工程があります。「少し角度を変えるだけで、表情がまるで違う」と職人。タヌキが持つ柔らかいユーモアと温かみは、まさに人の手から生まれる芸術です。
登り窯が語る、火と人の関係
信楽には、現在ほとんど姿を消した登り窯が唯一残されています。番組の中で中川家とすっちーが訪ねたこの窯は、山の傾斜を利用して造られ、複数の「間(ま)」と呼ばれる部屋が縦に連なっています。
下の部屋から火を入れると、炎と熱気が上へと伝わり、順に器を焼き上げていきます。炎の勢いをコントロールするため、職人は15分おきに24時間体制で薪をくべ続け、4日間をかけて窯の温度を1400℃まで上げます。その後も1日以上かけて余熱で仕上げるという、気の遠くなるような工程です。
この窯は今、カフェとして再生され、訪れる人がその空間でゆっくりと過ごせる場所になっています。かつて火の粉が舞っていた場所で、今は香ばしいコーヒーの香りが漂う――そんな「再生の物語」こそ、信楽焼の魅力のひとつです。古いものを壊すのではなく、次の形で生かすという発想が、町全体に息づいています。
若手職人が挑む“ファンタスティックフェスティバル”
信楽の若手たちは、伝統にとらわれず自由な発想で新しい作品を生み出しています。その一つが、ファンタスティックフェスティバル。
番組では、ユニークな作品が次々と登場しました。たとえば、古いティーポットの型を再利用して作られたスマートフォン用の音響器。陶器の中にスマホを置くと、音がやわらかく響く――まるで“自然のスピーカー”です。
また、チョコレート専用の皿という発想も話題に。焼き物の質感がチョコの艶を引き立て、スイーツの見た目をワンランク上にしてくれます。まさに、暮らしをデザインする信楽焼の新しい形。若手職人たちは「使う人の笑顔を思い浮かべながら作る」と語り、伝統を“続ける”のではなく、“更新する”姿勢を見せていました。
町に息づく文化と人の絆
信楽は、単なる陶器の町ではありません。てんびんばかりが使われていた商家の町並みや、ミュージシャン河島英五が愛した風景など、文化と人の記憶が今も残る町です。
町を歩けば、登り窯の煙突がのぞく古い工房や、新しいデザインのカフェ、ギャラリーが点在しています。それぞれが違う形で“焼き物の精神”を受け継いでいるのです。地元の人たちは、「信楽焼は単なる器ではなく、人と人をつなぐもの」と口をそろえます。まさに、土と炎、そして人の心がつくり出した“生きた文化”が、今も信楽には息づいているのです。
まとめ:信楽焼がつなぐ「過去」と「未来」
この記事のポイントは以下の3つです。
・古琵琶湖の土が生み出す、強くて優しい信楽焼の質感
・昭和天皇の行幸が生んだ“タヌキの置物”の全国的な広まり
・若手職人による“新しい信楽焼”と登り窯カフェの再生物語
信楽焼は、過去から未来へと受け継がれる日本の知恵そのもの。
それは単なる器ではなく、「人と自然が調和して生きること」を教えてくれる象徴です。
もし次に信楽を訪れる機会があれば、ぜひ登り窯カフェで一杯のコーヒーを。器のぬくもりと共に、この町が持つ“つなぐ力”を感じてみてください。
出典:NHK総合「探検ファクトリー」2025年10月4日放送
公式サイト:https://www.nhk.jp/p/ts/7QYVW9Z1X7/
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

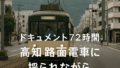
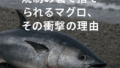
コメント