高級マグロが捨てられている現実を追う
青森・深浦町で“海のダイヤ”と呼ばれるクロマグロが次々と放流されている――。高級食材の代名詞であるマグロが、なぜ捨てられなければならないのか。この疑問から始まった今回の取材は、国際的な漁獲規制の仕組み、各国の思惑、漁師たちの本音、世界のマグロ文化、そして若者が集まる遠洋漁業の新しい姿までつながっていきます。
NHK【鶴瓶の家族に乾杯】高橋文哉が焼津でマグロ漁とぶっつけ本番旅に挑戦!朝ドラ「あんぱん」出演俳優が漁港で出会った人情ドラマ|2025年3月31日
高級クロマグロを「捨てる」現場の衝撃
番組の冒頭、取材班が向かったのは青森県 深浦町。ここではクロマグロが穫れても、そのまま海へ放流しなければならない状況が続いています。
背景には、2014年に国際自然保護連合(IUCN)がクロマグロを絶滅危惧種に指定したこと。そして2015年、中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)が各国の年間漁獲量上限を設定したことがあります。
その結果、クロマグロの資源は回復傾向にありますが、既定の年間漁獲枠を超えてしまうと、どれほど価値の高いマグロでも“持ち帰れない”。
漁師たちは日々の生活がかかっているにも関わらず、国際ルールを守り、黙々と放流作業を続けています。
深浦町の漁港では、「目の前にいるクロマグロを売ることができないのは正直つらい」といった漁師たちの声も紹介されました。
漁獲枠が増えない理由と複雑に絡む国際情勢
では、資源が戻ってきているのになぜ漁獲枠は増えないのでしょうか。番組で紹介された理由は予想以上に複雑なものでした。
まず、マグロは世界中で人気が高まっています。特にイタリアなど地中海沿岸の国では、新しい料理文化が広がり、輸出のチャンスが増えている状況です。
そのため、各国には「日本に漁獲枠を増やさせず、自国のマグロを売りたい」という思惑があるといいます。
こうした利害関係が絡む中、漁獲枠がなかなか増えないまま、資源管理と漁師の生活がせめぎ合う状態が続いているのです。
深刻化する“闇マグロ”の問題
番組がもう一つ取り上げたのが、未報告の“闇マグロ”の存在です。
本来、クロマグロが穫れた場合、漁業者は 水産庁 に漁獲量を報告する義務があります。しかし、報告せずに市場へ流れてしまうケースがあり、取材では「今の法律では未報告の売買を罪に問えない」という問題点も浮かび上がりました。
正直者が損をする状況は、現場の不満を生み、漁獲管理にも影響が出てしまいます。資源を守るためにも、ルールの整備が急がれていることが伝わります。
遠洋マグロ漁船に若者が集まる理由
番組の雰囲気を変えたのが、若者に人気が高まる“遠洋マグロ漁船”の話題です。
紹介されたのは、21歳の 鬼束遼空 さん。
大分大学 を中退し、遠洋漁業の道へ飛び込んだ青年です。1年目の年収は500万円。さらに船の機関士の国家資格を取れば、20代で1000万円も夢ではありません。
鬼束さんは給料の中から 両親に150万円のヨーロッパ旅行をプレゼント したと語り、スタジオは驚きに包まれました。
所ジョージさんは「やりがいのある仕事だね」とコメント。
海の過酷さだけでなく、それを越える魅力が若者を引きつけている現状が伝わってきました。
さかなクンが語る「冷凍マグロの実力」
マグロの知識が豊富な さかなクン は、冷凍マグロについて興味深い事実を紹介しました。
「冷凍したほうがおいしくなることもある」
新鮮なうちに急速冷凍することで、身の締まりや風味が安定し、解凍するとむしろおいしさが際立つことがあるといいます。冷凍技術が進んだ現代ならではの話です。
マグロ文化が根付く シチリア島 の映像も紹介され、丸ごと吊るして熟成させながら使い切る、日本とは違う食文化がとても印象的でした。名物の『マグロのパニーノ』の紹介では、スタジオの反応も大きく、日本での新たなマグロ需要が生まれる可能性を感じました。
“サバキ女子”の姿に観客が熱狂
番組の後半では、マグロ解体ショーで人気の“サバキ女子”が登場しました。
彼女は自分の体重より重いクロマグロを、たった30分で見事に解体します。
年間40回以上のショーをこなし、昨年は JAPAN FOOD FESTIVAL in HAWAII にも参加するほどの実力。
包丁の入れ方、身の切り出し方、スピード感――そのすべてに観客が見とれてしまうほどで、マグロの魅力を広げる存在として注目を集めています。
木村佳乃が感じた「マグロの繊細さ」
スタジオでは 木村佳乃 さんが、「マグロは大きくてたくましいイメージだったけど、小さく産まれて繊細なんだって知って驚いた」と感想を述べました。
クロマグロは幼魚の時期がとてもデリケートで、環境の変化に弱い特徴があります。
資源管理が難しい理由は、こうした生態にも関わっていることが改めて分かりました。
種類で違う“旬”があり、味わいも変わる
番組では、マグロの種類ごとに旬が違うことも詳しく紹介されました。
・キハダ
・ビンナガ
・メバチ
・コシナガ
それぞれの特徴とおいしさのピークが異なるため、市場でも季節によって入荷状況が大きく変わります。
豊洲市場 ではプロの目利きが旬を見極めながら取引を行っている様子が映され、マグロの奥深さを感じる内容でした。
まとめ
マグロをめぐる今回の特集は、海の資源を守るための国際ルールの必要性と、それによって生まれる現場の苦悩を丁寧に映し出した回でした。
捨てられるマグロという衝撃的な現実の裏には、資源保護への努力や世界的な需要の高まり、そして漁師たちの複雑な思いがあります。一方で、若い世代が遠洋漁業へ飛び込み、新しいキャリアを築く姿も紹介され、マグロを取り巻く世界が大きく変化していることを感じられました。
今後もマグロをおいしく食べ続けるために、ただ消費するだけでなく、資源管理や漁業の現実への理解がますます求められると感じさせる内容でした。
【カズレーザーと学ぶ】サバがマグロを育てる!?世界初の技術と野菜が変える“未来の食卓”完全ガイド|2025年7月15日放送
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

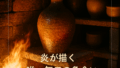
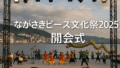
コメント