文化財を守るということは、未来をつなぐということ
「文化財の修理費って、国が全部出してくれるんじゃないの?」と思ったことはありませんか?実はそうではありません。10月11日放送の『所さん!事件ですよ』では、滋賀県の常楽寺が重要文化財「絹本著色浄土曼荼羅図」を2億800万円で文化庁に売却したニュースが紹介されました。理由は、国宝である本堂と三重塔の修繕費の一部を自ら負担する必要があったから。今回は、番組で取り上げられた「文化財を守る現場の現実」を通して、日本の“宝”を次世代に残す難しさを考えます。
修繕費を捻出するために「宝」を手放す現実
滋賀県にある常楽寺は、平安時代からの歴史を誇る古刹です。境内に建つ本堂と三重塔はいずれも国宝に指定されており、建築史的にも極めて貴重な存在です。木造建築の美しさをそのままに残し、地域の信仰と文化を支えてきました。しかし、長い年月を経て老朽化が進み、屋根や柱、内部の装飾にまで傷みが見られるようになりました。専門家による調査の結果、修理には約9,300万円という膨大な費用が必要だとわかりました。
国の補助金制度はありますが、全額ではなく、所有者も1割以上を自己負担する仕組みです。つまり、国宝を持つことは名誉である一方で、大きな経済的責任を伴うという現実があります。寺院の収入は主に檀家や参拝者からの寄進で成り立っており、日々の維持だけでも苦労が絶えません。そんな中で、数千万円単位の修繕費を捻出することは容易ではありませんでした。
苦渋の末、住職は寺に代々伝わる絹本著色浄土曼荼羅図(重要文化財)を手放す決断をしました。売却先は文化庁で、価格は2億800万円。信仰の象徴とも言える貴重な仏画を手放してまで、寺を守ろうとしたその選択には、地域の人々も深い衝撃を受けました。曼荼羅図はもともと浄土信仰の象徴で、極楽浄土の世界を絹に精緻に描いたもので、平安末期から鎌倉期の仏教美術の傑作とされています。
番組の中で所ジョージさんは、「指定って言うなら全部出しなさいよ」と率直にコメントしました。その言葉は、国が“守るべき文化財”と指定したにもかかわらず、維持費の負担を個人や寺院に任せている制度への違和感を多くの視聴者と共有するものでした。文化財を守ることは日本の誇りであるはずなのに、その重荷が現場の人々にのしかかっている――それが、この問題の根の深さを物語っています。
日本全国で進む“文化財の消滅”
実は、常楽寺のように文化財の維持が難しくなるケースは全国で増え続けています。登録有形文化財(建造物)は、国の制度によって保護の対象とされていますが、老朽化や自然災害、管理者の高齢化などによって、維持が困難になり登録が抹消された件数は314件にも上ります。さらに、そのうち233件が過去10年以内に発生しているというデータが示されています。つまり、ここ10年で日本各地の文化財が次々と姿を消しているのです。
文化財の登録は「守るための第一歩」ではありますが、それを長く維持するための仕組みはまだ十分ではありません。修繕にかかる費用、専門技術者の確保、後継者の不在といった問題が積み重なり、所有者が手放さざるを得ない状況が増えています。特に地方では、過疎化や人口減少によって地域全体の維持力そのものが落ちており、「残したくても残せない」現実が浮き彫りになっています。
岡山県にある備前長船刀剣博物館も、その象徴的な例の一つです。日本刀の名産地として知られる長船地区では、伝統的な刀剣作りの技術を後世に伝えるために、貴重な刀剣や資料を展示・保存しています。しかし、温湿度管理や展示ケースの更新、建物の老朽化対策などには莫大な費用がかかり、運営側は常に資金不足と人材不足に悩まされています。それでも、備前長船の職人たちは「文化財を守ることは、技を守ること」との信念で日々取り組み続けています。
文化財とは、過去の遺産であると同時に、未来への約束でもあります。しかし現実には、その“約束”を支える仕組みが追いついていないのです。登録や指定の制度を超え、地域の力と国の支援がどう共に働けるのか――今まさに問われています。
山村に眠る“未指定の宝物”
番組は次に、奈良県山添村にある小さな寺院を訪ねました。奈良県の東端に位置するこの村は、かつては信仰と農業で栄えた地域ですが、いまでは人口の半数が60歳を超える高齢化地域となっています。村人たちは力を合わせて寺や神社を守ってきましたが、世代交代が進まず、文化財の維持管理が年々厳しくなっています。
この寺には、木造不動明王像や観音菩薩像など、歴史的にも美術的にも高い価値を持つ仏像が複数安置されていました。中には、平安時代後期から鎌倉期にかけての特徴を残す造形もあり、仏像研究者が見ても「国指定レベル」と評するほどの出来栄えです。しかし、これらの仏像は未指定文化財のままで、国や県の保護制度の対象には入っていません。そのため、修理や防犯にかかる費用はすべて地域の負担となっており、結果的に手が回らなくなっているのが現状です。
取材中、関係者が庫裏を確認した際、安置されていたはずの仏像の一体が盗難に遭っていたことが判明しました。村の人たちは愕然とし、静まり返った本堂には長年の信仰の重みと無念さが漂っていました。地方の寺院では、管理体制の緩さを狙った盗難事件が全国的に相次いでおり、文化庁によると年間で100件を超える文化財被害が報告されています。
番組では、東大寺の関係者や文化庁の職員が現地を訪れ、現状の課題を確認しました。専門家たちは「指定文化財でなくても、地域の信仰と文化を支える貴重な遺産」として、保護の枠組みを広げる必要性を訴えていました。文化財は国の誇りであると同時に、地域の人々にとっては“心の拠りどころ”。その重みを、山添村の小さな寺が静かに語っていました。
博物館も“パンク寸前”
次に番組が焦点を当てたのは、文化財を保管・展示する博物館や美術館の現状でした。文化財を守る最後の砦ともいえる施設ですが、今その“受け皿”が限界に達しています。
取材で訪れた奈良県立民俗博物館では、長年にわたり県民から寄贈された古い農具や生活道具、民俗資料が収蔵庫にぎっしりと詰まっていました。かつては「地域の歴史を未来へ残す場所」として多くの寄贈を受け入れてきましたが、現在は収蔵庫が満杯で、新たな資料を受け入れることがほとんどできない状況になっています。収蔵品の一部は通路や簡易棚にも積み上げられ、職員たちは限られた空間の中でどうにか整理と保管を両立させようと奮闘しています。
この問題は奈良県だけではなく、全国の公立博物館・資料館でも深刻化しています。文化財や民俗資料は一度引き取ると簡単に処分できないため、「引き取っても保管できない」という新たなジレンマが生まれています。特に寄贈されたものの中には、修繕や防虫、防カビのための維持管理費がかかるものも多く、地方自治体の財政を圧迫しています。
番組には、なら歴史芸術文化村で学芸員として活動する大河内智之さんが登場しました。彼は「捨てるしかなかった仏像に出会ったことがある」と、現場での衝撃的な体験を語りました。文化財としての価値は十分にあっても、保管場所も修繕費も確保できず、最終的に廃棄を選ばざるを得なかったというのです。その言葉には、現場で文化財を守り続けてきた人々のやるせなさと無力感がにじんでいました。
今、多くの博物館や美術館は、文化財を“守る場所”であると同時に、“守れなくなる現場”にもなりつつあります。収蔵庫の中で眠る無数の遺産たちは、静かに次の居場所を求めているのです。
災害に襲われた“紙の文化財”を救え
番組では、令和6年能登半島地震や令和6年奥能登豪雨で被災した地域の文化財を救うための取り組みも紹介されました。地震や水害で多くの建物が倒壊・浸水し、貴重な古文書や仏像、絵画などが泥水にまみれたまま放置される危険な状況に陥りました。こうした中で、文化財を守るために動いたのが、文化財防災センターの職員と、地元の学芸員たちです。
被災地の現場では、まず文化財を救出する“文化財レスキュー”が行われました。濡れた古文書は放置するとわずか数日でカビが発生し、紙が貼りついて文字が読めなくなってしまいます。そのため、彼らは一つひとつの資料を丁寧にビニール袋に密封し、冷凍保存するという応急処置を施しました。これにより、劣化の進行を一時的に止めることができます。
その後、資料は奈良市の文化財防災センターに運ばれ、真空凍結乾燥機による修復作業が始まります。まずマイナス温度で凍結させたのち、真空状態にすることで氷を水蒸気として昇華させ、紙に残る水分を徐々に除去していきます。この工程を経ることで、泥水に浸かって文字が消えかけた文書でも、再び文字を判読できる状態にまで復元することができます。
作業を担当する職員たちは、わずかなインクの跡や筆跡を頼りに、一枚一枚の古文書を息を止めるように扱っていました。復元には時間と根気が必要で、1枚の資料を完全に乾燥させるのに数週間から数か月かかることもあります。それでも、失われたら二度と取り戻せない“地域の記憶”を残すため、現場の努力は続いています。
こうした文化財レスキューの取り組みは、過去の災害での教訓を生かしたものです。東日本大震災や熊本地震でも同様の活動が行われており、全国各地の専門機関が連携して技術と経験を積み重ねてきました。文化財を守るということは、単に物を修復することではなく、人々の暮らしと歴史を未来へつなぐ行為。泥にまみれた一枚の古文書が、再び光を取り戻すその瞬間こそが、日本の記録を支える希望の証といえます。
まとめ:文化財を守るのは「誰か」ではなく「私たち」
この記事のポイントは以下の3つです。
・国宝や重要文化財でも、維持費の一部は所有者負担である
・人口減少や過疎化により、地域で文化財を守る仕組みが崩れつつある
・博物館・美術館の保管能力や災害対応にも限界がある
文化財を守ることは、単に“古いものを残す”ことではありません。それは、日本の記憶を未来へとつなぐ行為。国や自治体だけでなく、私たち一人ひとりが文化財の価値を理解し、支える意識を持つことが、これからの時代に求められているのかもしれません。
出典:NHK『所さん!事件ですよ 文化財はつらいよ!?ニッポンの宝の危機』(2025年10月11日放送)
https://www.nhk.jp/p/jiken/
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

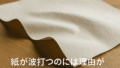
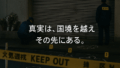
コメント