砂糖の結晶ができるまでを探検!甘さの裏にある“職人技”とは?
「砂糖って、どうやって作られているんだろう?」そんな素朴な疑問を持ったことはありませんか。スーパーで当たり前に手に入る上白糖やグラニュー糖ですが、その透明で美しい結晶の裏には、緻密な技術と人の目による“職人の感覚”が息づいています。今回の『探検ファクトリー』(2025年10月11日放送・NHK総合)では、すっちーさんと中川家の礼二さん・剛さんが、千葉市の砂糖工場を訪ねました。和食を支える砂糖の秘密を、実際の製造現場でたっぷり探ります。
日本の砂糖はこんなに多彩!用途で変わる味と姿

番組冒頭では、日本の砂糖文化の奥深さが紹介されました。私たちの暮らしに欠かせない砂糖には、見た目や味、香りにそれぞれ個性があります。家庭で最もよく使われるのが上白糖。しっとりとした質感とやさしい甘さが特徴で、煮物やお菓子づくりなど、どんな料理にも合う万能選手です。水分を保つ性質があるため、ケーキやクッキーをしっとり仕上げたいときにも重宝されます。
一方で、グラニュー糖はサラサラとした粒状で、クセのないすっきりとした甘さが持ち味。コーヒーや紅茶などの飲み物によく使われ、世界的にも標準的な砂糖として親しまれています。料理に使うと素材の色や風味を邪魔しないため、プリンやカステラなどのデザートにもぴったりです。
そして、三温糖は茶色みを帯びたコクのある甘さが魅力。精製の過程で加熱を繰り返すことで、独特の風味と香ばしさが生まれます。すき焼きや照り焼きなど、味に深みを出したい料理には欠かせない存在です。この三温糖の“深い甘み”が、和食の伝統的な味わいを引き立てています。
番組で訪れた千葉市の砂糖工場では、これらの砂糖を用途やメーカーの要望に応じて製造しています。注文ごとにザラメの大きさや結晶の形を微調整することで、同じ甘さでも口どけや香りに違いを生み出しています。その緻密な調整こそが、日本の砂糖が「ただ甘いだけではない」と言われる理由です。甘さの中に“上品さ”や“奥行き”を感じるのは、この細やかな技術のおかげなのです。
また、日本の砂糖づくりは湿度や気温の変化に敏感な環境との戦いでもあります。季節や天候によって結晶の仕上がりが微妙に変わるため、職人たちは日々のデータと経験を頼りに調整を重ねています。機械では再現できない「人の感覚」が、どの家庭でも変わらない甘さを支えているのです。
グラニュー糖づくりの工程を探検!3つのステップとは
今回の探検の舞台となったのは、千葉市・京葉線千葉みなと駅のほど近くにある大規模な精製糖工場。ここでは、私たちが日常で使うグラニュー糖がどのように作られているのか、その全工程を3つのステップで見ることができました。工場内は常に白い湯気と甘い香りに包まれ、巨大な機械がリズミカルに動く様子はまるで生きているよう。そこに働く人々の真剣なまなざしが、甘さの裏にある技と情熱を物語っていました。
最初の工程は「清浄(せいじょう)」。ここでは、原料となる原料糖に含まれる不純物を徹底的に取り除きます。原料糖は海外から輸入されたサトウキビ由来の粗糖で、見た目はうす茶色。これを溶かして糖蜜と混ぜ合わせるのですが、温度が低いと分離してしまうため、工場内では冷房を一切使わず、一定の温度と湿度を保つよう管理されています。夏でも汗だくで作業を続けるのは、品質を守るためのこだわりです。マグマミングラーと呼ばれる巨大な機械で原料糖を練り、遠心分離機にかけると、内側に黄金色の糖蜜が、外側に白い砂糖の結晶が現れます。この瞬間こそ、砂糖が“生まれる”第一歩です。
次の工程は「結晶化」。ここでは砂糖の粒そのものを形づくります。濃度73%の糖液を大きな釜でじっくりと煮詰めていき、液体の中に少しずつ結晶が育っていきます。温度や圧力を保つために、工場では中央制御室からコンピューターで細かく操作していますが、最終判断はやはり人の目。熟練の技術者が結晶の光の反射や粒のそろい具合を見て、「もう少し水を足す」「少し煮詰める」と微調整を重ねます。わずかな違いが仕上がりの透明度や口どけに影響するため、この“見極め”が最も重要なポイントです。砂糖がきらめく瞬間には、職人たちの経験と感覚が息づいています。
最後の工程が「分離乾燥」。結晶と液体を再び機械で分離し、巨大なドラム型のドライヤーでゆっくり乾燥させます。水分をほどよく飛ばすことで、粒がサラサラになり、グラニュー糖特有の軽やかな口当たりが生まれます。同じ原料から作られる上白糖は、糖液でコーティングすることでしっとりとした甘さに仕上がり、三温糖は分離後に残る液体を煮詰めて再利用することで、コクのある味と色合いを生み出します。つまり、一つの原料から透明で上品なグラニュー糖、しっとりした上白糖、深みのある三温糖という、全く異なる3つの個性が生まれるのです。
工場の中はまるで“砂糖の実験室”のようで、温度、湿度、濃度、結晶の大きさ――そのすべてが計算し尽くされています。自動化が進んでも、最後の決め手は人の手と目。日本の砂糖づくりが世界でも高く評価される理由が、この現場には確かにありました。
品質管理室での最終チェック!“安心”のための努力
出荷を目前にした砂糖は、最後に品質管理室で最終検査を受けます。ここはまさに“砂糖の番人”ともいえる場所で、どんなに生産ラインが自動化されていても、人の感覚と判断が欠かせません。検査員たちは、砂糖の純度・透明度・結晶の大きさを一つひとつ確認し、わずかな異物や色の濁りも見逃しません。白い照明の下で光を当てながら結晶の輝きを確かめるその姿は、まるで宝石職人のようです。
ここでは見た目だけでなく、微生物検査や水分量の測定など、科学的なデータに基づいた厳密なチェックも行われています。砂糖は一見すると“保存のきく食品”ですが、湿度や異物混入によって品質が変わることもあります。そのため、出荷までのわずかな時間も油断はできません。工場の空気や機械設備も定期的に点検され、清潔な環境を保つ努力が続けられています。
また、砂糖は法律上、「賞味期限の表示が不要な食品」とされています。これは、きちんと密閉して保管すれば、長期間にわたって品質がほとんど変化しないほど安定しているためです。つまり、砂糖の“長持ちする甘さ”には、科学的根拠と長年の品質管理の積み重ねがあるのです。
最終検査をクリアした砂糖は、袋詰めされて全国のスーパーや食品メーカーへと出荷されます。家庭の台所で使うスティックシュガーも、洋菓子店で使われる粉糖も、すべてこの厳しい基準をくぐり抜けた結晶たち。透明で美しい甘さの裏側には、見えないところで働く人々の丁寧な手仕事と、「安心して食べられる甘さを届けたい」という確かな使命感が息づいています。
甘さの裏にある「冷房禁止」の職人魂
番組の中でも特に印象的だったのが、「工場内では冷房を使わない」という現場のルールでした。普通の工場なら作業効率を優先して空調を整えるのが一般的ですが、この精製糖工場ではあえてそれをしません。理由は、砂糖のもとになる原料糖と糖蜜が温度に敏感だからです。わずかな温度差でも混ざり方が変わり、結晶の透明度や粒のそろい方に影響が出てしまうため、室温を一定に保つことが最も重要とされています。まさに“品質のための環境づくり”が徹底されていました。
真夏でも機械の熱と湿気に包まれた工場内で、スタッフたちは汗をぬぐいながら作業を続けます。巨大な釜の前で温度計をにらみ、遠心分離機の音を確かめながら、ひとつひとつの工程を丁寧に進めていく姿。その表情には「おいしい砂糖を届けたい」という真剣な思いがにじんでいました。暑さや労力を惜しまず、甘さの理想を追い求める――そこには、日本の味を支える職人たちの誇りがあります。
近年は自動制御やAI技術の導入が進み、機械が多くの作業を担うようになりました。しかし、砂糖づくりの最終工程では、今でも人の目と感覚が欠かせません。結晶の輝き、粘度、香り――それらを瞬時に判断できるのは、長年現場に立ってきた熟練の職人たちだけです。機械がどれほど進化しても、最後の「仕上げ」を決めるのは人の手。この信念こそが、日本の砂糖の品質を世界トップレベルに押し上げているのです。
番組のラストで、すっちーさんや中川家の礼二さん・剛さんが見学を終えて語った表情にも、自然と尊敬の色が浮かんでいました。甘さの裏にある努力、そして“人が支える日本の技術力”。それを肌で感じられる、まさに「甘さをつくる職人たちの探検ファクトリー」でした。
まとめ:この記事のポイント
・日本の砂糖は上白糖・グラニュー糖・三温糖など、用途に合わせて多彩に作られている
・グラニュー糖の製造は「清浄」「結晶化」「分離乾燥」の3段階で進む
・温度管理や結晶チェックには、人の経験と感覚が欠かせない
・品質管理室での最終検査により、安心で安全な砂糖が私たちの食卓へ届く
毎日の料理に欠かせない砂糖。その一粒の中には、技術と情熱、そして“おいしさを届けたい”という人の思いが詰まっています。和食の味の決め手となるこの甘さを、これからも大切に味わっていきたいですね。
ソース:NHK総合『探検ファクトリー 和食の強い味方!徹底的に透明な結晶を作る 千葉・砂糖工場』(2025年10月11日放送)
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


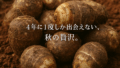
コメント