家庭菜園から建築現場まで大活躍!日本一のショベル・スコップ工場を探検
2025年6月20日放送の「探検ファクトリー」では、大阪府堺市にあるショベル・スコップの生産量日本一を誇る工場を紹介。すっちーさんと中川家の礼二さん、剛さんが出演し、年間80万本を生産する巨大な工場の製造工程や技術の数々を探検しました。家庭菜園など身近な場面から建築現場まで、幅広く使われているショベル・スコップがどのように作られているのか、その舞台裏をたっぷり紹介しました。
呼び方も作り方も奥深い!ショベルとスコップの違い
番組の冒頭では、まず「スコップ」と「ショベル」の呼び方の違いについて紹介されました。ふだんはあまり気にせず使っているかもしれませんが、日本産業規格(JIS)では明確な違いが定められています。
-
踏み板が付いていて足で押し込める道具は「ショベル」
-
踏み板がなく、手で使う小型のものが「スコップ」
地域によっても呼び方が異なり、西日本では「ショベル」、東日本では「スコップ」と呼ぶ傾向があります。今回の舞台となった堺市の工場は、日本で最初にショベルとスコップの国産化に成功し、年間約80万本の製造数を誇る大規模工場です。
工場には、家庭用から業務用まで150種類以上のショベル・スコップがそろっており、形や長さ、素材もさまざまです。たとえば、植物の根を切りやすいように刃のついたタイプや、水を含んだ泥を効率よく取り除ける穴あきタイプなど、用途に応じた工夫が詰まっています。
製造の要は「さじ部」から!スチール板がスコップの形に変身
製造工程は「さじ部」と呼ばれる、土をすくう部分の成形から始まります。まず、スチール製の板をプレス機で型抜きします。その後、土に刺さりやすくするために先端を削って刃付け加工が行われます。
-
150トンの圧力で一気にプレスして成形
-
高温で熱し、急冷する「焼き入れ」工程で強度を上げる
-
**粘り(しなやかさ)を出すために「焼き戻し」**という再加熱を行う
この「焼き戻し」がとても重要で、これを行うことで、叩いても割れないしなやかで丈夫なスコップが完成します。中川家の2人は、流れてくるさじ部を運ぶ作業にも挑戦しましたが、5枚運ぼうとして1枚しか成功せず、その作業の難しさと正確さが必要な現場の空気を体感していました。
柄の加工はスピードと正確さが命!金属と木の2種類
スコップやショベルには「柄(え)」が欠かせません。この柄には金属製のパイプ柄と、木製の木柄の2種類があります。
-
金属製のパイプ柄は、機械で取っ手部分を自動で溶接
-
1日で約3000本の溶接が可能という高い生産力
-
溶接後は機械で塗料を均一に吹き付け、乾燥へ
-
仕上げは品質検査。合格した製品だけが出荷される
作業はスピーディーでありながら、一つ一つの工程で確認が行われていて、安全性と品質を保つための努力が感じられました。
江戸時代から続く伝統と挑戦の歴史
この工場の歴史は、江戸時代にたばこ包丁の製造から始まったと紹介されました。その後、**明治時代に6代目社長が外国からの輸入に頼っていたショベル・スコップを、国産で作ることを決意。**これが日本のショベル・スコップ製造の出発点になりました。
現在では、多種多様な製品を作っており、番組では以下のような特別な用途に使われるスコップも登場しました。
-
2.5mの長さがあるショベル:電柱を立てるために深い穴を掘る専用道具
-
蒸気機関車の石炭用スコップ:昔ながらの鉄道で活躍したモデル
-
ポールや杭を立てるスコップ:穴の幅や深さを調整しやすい形状
どれも一般の人が使うことは少ないですが、現場で活躍するプロ向けの道具として、信頼され続けていることが伝わってきました。
このように、ただの道具ではなく、使う人や使う場面に応じて設計・製造されているスコップとショベル。その裏には、何世代にもわたる職人たちの技術と工夫、そして挑戦の歴史があることを、今回の番組は教えてくれました。これから家庭で使うスコップを見る目が、少し変わるかもしれません。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

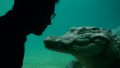

コメント