知らなかった!?朱肉なしハンコの秘密に迫る
NHKの人気番組『探検ファクトリー』では、モノづくりの現場を楽しく学べる内容が毎回放送されています。2025年5月10日の放送回では、「朱肉のいらないハンコ」の製造に迫るべく、愛知県稲沢市にあるシヤチハタ稲沢工場を探訪。漫才コンビ中川家とすっちーが、工場を案内されながらその仕組みや技術の裏側を深掘りしました。便利に使っているハンコに、これほどの工夫が隠されていたことに驚かされる内容でした。
朱肉なしで使えるハンコの技術
番組で注目されたのは、朱肉なしで使える浸透印という画期的なハンコの仕組みです。1968年に登場し、現在までに累計1億9000万本以上が出荷されているという、まさに驚異のロングセラー商品です。押したときにだけインクがにじみ出てくる仕組みは、シンプルに見えて非常に高度な技術に支えられています。
このハンコの中で重要な役割を果たしているのが、インクを通す特殊なゴムです。ゴムにはあらかじめ塩が練り込まれており、それをお湯に長時間浸けて塩を溶かし出すことで、インクの通り道となる微細な穴を多数作り出しています。
・ゴムに練り込まれているのは粒状の塩で、加熱されたお湯の中に約17時間浸けて塩分を抜き取ることで、ゴム全体に無数の小さな穴が形成されます
・この工程を経たゴムは、まるでスポンジのような構造に変わり、インクをしっかりと内部に保持しながら、押したときにだけ出すという性質を持つようになります
・また、塩の粒のサイズが異なるゴムを2種類用意し、それを貼り合わせることで、インクの流れ方をさらに細かく制御できるようになります
塩の混入による空洞形成は非常に繊細な作業で、均一な品質を保つためには、材料の配合や温度管理などにも熟練の技術が求められます。そのため、製造現場ではミキシングロールと呼ばれる工程で、カーボンや薬品とゴムを均等に混ぜる作業が丁寧に行われています。
・この段階では、インクの吸収性と押印時の強度を両立させるために、カーボンを加えて弾力性を補強
・さらに数種類の薬品も加えることで、耐久性と安定性を確保しています
こうした材料の処理を経た後、ゴムはローラーで圧力をかけてシート状に加工され、インクの通り道となる構造が整えられていきます。完成した印面は、均一にインクが染み出るように設計された緻密な構造を持ち、日常で使ってもムラなく鮮明に押すことができるのです。
見た目には単純なスタンプに見えるこの浸透印ですが、その裏には塩の作用を利用した画期的な製法と、ゴムという素材への徹底したこだわりがありました。押したときにだけインクが出るという便利さを支えているのは、こうした地道で緻密な工程の積み重ねだったのです。普段使っているハンコの中に、ここまで複雑で洗練された技術が隠れているとは、驚かされた人も多いのではないでしょうか。
印面作りにも最新技術
シヤチハタのハンコ製造で欠かせないのが、印面に名前や文字を彫る工程です。まずはパソコンで専用ソフトを使い、印面のデザインデータを作成します。このデータには、使う書体や文字の配置が正確に記録されています。作られたデータはそのままレーザー加工機へと送られ、ゴムの印面に高精度で文字を彫刻していきます。レーザーは非常に細かく動くため、とめ・はね・はらいなどの微細な部分までしっかりと再現できるのです。
・使用される書体はシヤチハタ独自開発の基本書体が9種類あり、フォントの見やすさと印影の美しさが両立されています
・管理されている文字数は約1万3000文字にのぼり、漢字・ひらがな・カタカナのほか、会社のロゴやマークなども対応可能
・実際の彫刻は、最大8文字までの印面に対し、1文字ずつ丁寧に加工されます
加工された印面のゴムは、切断・整形されたのち金属の枠に装着されます。その後、印面と本体をつなぐバネ機構やインクカートリッジを内蔵したボディに組み込まれ、ハンコとして完成します。これらの工程は全て工場内で一貫して行われており、年間でおよそ230万本のハンコがこの工場で製造されているとのことです。
番組内では、「探検ファクトリー」の特製ハンコがその場で作られる様子も紹介されました。パソコン上で文字を選び、レーザーでゴムに彫り込み、部品を組み立てるという一連の流れがわずかな時間で進んでいきました。完成したハンコは押印してもにじみがなく、印影がくっきりしていて高品質。見た目には小さな製品ですが、設計から加工、組み立てにいたるまで、すべての工程に最新の技術と職人のこだわりが詰まっていることが伝わってきました。
こうして仕上げられた朱肉不要のハンコは、ただの事務用品ではなく、日本のものづくりの精度と情熱が集約された製品だと感じられます。文字ひとつひとつに込められた工夫と技術が、日常の「押す」という行為を支えているのです。
ハンコの歴史と進化も紹介
番組では、現在の便利なハンコに至るまでの長い歴史と進化の過程についても紹介されました。日本最古のハンコとされるのは、西暦57年に中国から倭の国に贈られた「漢委奴国王印」です。これは福岡市の志賀島で発見された金印で、当時の国際的な交流を物語る貴重な証拠として有名です。こうした印章文化は、その後も脈々と受け継がれ、日本では重要な文書や契約に押す文化が定着しました。
・江戸時代には武将たちが使用した「朱印状」も登場し、権威を示すために使われていました
・明治6年には印鑑登録制度が法制度として定められ、個人の身分証明や公的文書の証明手段としての地位を確立しました
このように、ハンコは個人や組織の「証明の道具」として発展し、日本人の生活やビジネスに深く根付いてきたのです。
さらに番組では、近代以降の技術革新によるハンコの進化にも注目が集まりました。
・1965年には、朱肉が不要なスタンプ台付きスタンプが登場し、事務作業の効率化に大きく貢献
・1968年には、名前入りの朱肉いらずハンコ(現在のシヤチハタ式)が発売され、押すだけでくっきりと印影が出る便利さで大ヒット
・1995年には電子印鑑システムが導入され、企業などで使われる印鑑情報をデジタルで一元管理。なりすましや偽造のリスクを防ぐ仕組みが整備されました
また、産業向けの製品としては、ボルトの締め具合を目視で確認できるスタンプ技術も開発されています。これは、本締めした際に印がズレていなければしっかり締まっていることが確認できるというもので、インフラや建築現場での安全確認に活用されています。
このように、ハンコは単なる事務用品の枠を超えて、現代社会のあらゆる場面で活躍できるよう進化してきました。デジタル化や脱ハンコの動きが加速する中でも、新たな技術や用途で存在価値を保ち続けていることが印象的です。日常的に目にするハンコの背後には、何世紀にもわたる歴史と、時代に応じた革新の積み重ねがあるのです。
エンディングで伝えられた想い
番組の最後では、今やデジタル化が進む中でハンコの存在価値が見直されていること、そして「押す」という行為の安心感や確かさが、今もなお多くの人に支持されている理由が語られました。見た目以上に奥深く、改めてハンコの魅力を実感できる25分でした。
番組を通して、普段何気なく使っているハンコに込められた匠の技術と工夫、そして長年の開発努力が見えてきました。朱肉のいらないハンコ一つにも、材料の工夫、歴史、使いやすさへの配慮が詰まっていることに気づかされる貴重な回でした。
読者の皆さんも、もしハンコを使う機会があれば、その小さな道具の背後にある大きな物語を思い出してみてください。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


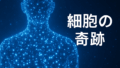
コメント