「“ヤバい・エぐい”は危険!?注目される感情リテラシー」
2025年4月16日放送のNHK『クローズアップ現代』では、「“ヤバい・エグい”は危険!?」というタイトルのもと、現代社会における感情リテラシーの重要性が取り上げられました。特殊詐欺や校内暴力など、深刻な問題の背景には、感情をうまく言葉にできない若者たちの現実がありました。番組では、刑務所の取り組みから小学校での実践、さらに専門家による分析まで幅広く紹介されており、「言葉で感情を伝える力」の大切さが浮き彫りになりました。
特殊詐欺の実行犯に共通する「感情を表現できない」若者たち
佐賀少年刑務所の取材では、闇バイトに関わり刑に服している若者たちの多くが、感情をうまく表に出せないことが明らかになりました。例えば、ある受刑者は罪の意識がほとんどなかったと語り、複雑な家庭環境で感情を抑え込む生活を続けてきたことを明かします。
番組では刑務所・少年院の収容者287人にアンケートを実施。
・「闇バイトに関わった」と答えたのは78人
・「自分の気持ちがわからない」と“いつもそう・だいたいそう”と答えたのは35.6%
・「悩みを相談しない」と答えたのは57%
この数字から、気持ちを言葉にできない状態が、犯罪に巻き込まれるリスクを高めていることが読み取れます。
また、実行犯を集めるリクルーターの証言では、「感情を言語化できない子ほど扱いやすい」とされ、感情表現の未熟さが悪意ある大人たちに利用されている実態も浮かび上がりました。
刑務所内での新しい教育「言葉のバブル」
こうした課題に対応するため、佐賀少年刑務所では「言葉のバブル」と呼ばれる教材を使った感情表現トレーニングを行っています。怒りの感情についても、「イライラ」「腹が立つ」「激怒」といった複数の言葉を用いて、感情の強さの違いや表現の幅を学びます。
この教材を開発したのはヒューマンハーバーそのとく塾。この教育プログラムは刑期を終えた人にも提供され、6年間で再犯率はゼロという驚くべき成果をあげています。また企業研修にも活用されるなど、感情リテラシー教育は社会全体に広がり始めています。
・怒りには強さの段階があることを学べる
・他人と感じ方が違うことを理解できる
・表現する力が育ち、衝動的な行動が減る
このような教育を通じて、感情を正しく理解し伝える力が犯罪の予防につながることが実証されつつあります。
感情と言葉の関係を阻むデジタル社会の影響
感情心理学の専門家、渡辺弥生さん(法政大学教授)は、現代の若者が感情を表現できなくなってきている背景に、スマートフォンやデジタル機器との過剰な接触があると説明しました。
調査によると、
・高校生で1日2時間以上スマホに接触する生徒は語彙力が低下する傾向
・スマホは受け身の情報取得が多く、自分で言葉を生み出す機会が少ない
・LINEやSNSでは短文・スタンプが主流で、感情を深く伝える言葉を使わなくなる
渡辺さんは、語彙が不足すると自分の気持ちを的確に表現できなくなり、他人の感情にも共感しにくくなると話しており、この傾向が人間関係の希薄化や衝動的行動に影響していると警鐘を鳴らしています。
小学校の授業で感情トラブルを減らす工夫
感情リテラシーを育てる取り組みは、大阪市立南市岡小学校でも実践されています。ここでは、色分けされた「きもちことばマップ」を活用し、授業で登場人物の感情を言葉にする練習をしています。
導入のきっかけは、年間100件以上の校内暴力によるケガでした。学校では次のような工夫がされています。
・「命令」に聞こえてしまう言い方を見直す
・自分の気持ちを言葉で説明する練習を重ねる
・泣いている友達に気づいて声をかける力を育む
取り組みの成果として、子どもたちが自分の感情を伝えられるようになり、トラブルが減少しています。また、感情に向き合う経験が、思いやりのある行動につながっていることも紹介されました。
家庭でも求められる感情リテラシー教育
子どもたちの感情リテラシーを育てるには、家庭での関わり方も大切です。番組では、親が子どものケンカやトラブルにどう対応するかが問われました。
・子どもがけんかして帰ってきたとき、「なんでやったの!」と叱るだけでは逆効果
・まずは「どんな気持ちだったの?」と聞き、感情に寄り添うことが大切
・親自身がイライラや不安をぶつけると、情動感染してしまうこともある
渡辺さんは、大人が感情と向き合う姿勢を見せることが、子どもにとっての手本になると話しており、家庭内でも感情を言葉にする練習が必要だと強調しました。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

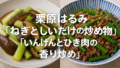

コメント
[…] 【クローズアップ現代】ヤバイ、エグいの危険性とは […]