桃山の革命 織部焼|2025年7月6日放送
2025年7月6日(日)の夜11時から、NHK・Eテレで「美の壺 選『桃山の革命 織部焼』」が放送されます。今回は、桃山時代に誕生した大胆で個性的な陶芸、織部焼の魅力に迫ります。織部焼は、普通の焼き物とはちょっと違い、自由な形や色、そして不思議な模様で有名です。どうやって生まれたのか、どんな意味があるのかをわかりやすく紹介してくれる番組です。
織部焼とは?桃山時代の芸術革命

織部焼は16世紀末から17世紀初めの桃山時代に、美濃(現在の岐阜県)で誕生した焼き物です。特徴は、深い緑色の釉薬や歪んだ自由な形、個性的な模様で、当時の焼き物の中でも特に目立つ存在です。大名茶人だった古田織部の美意識が反映され、伝統にとらわれず、自由な発想で作られました。そのため、茶道の道具としてだけでなく、日常使いの器としても広まり、今でも多くの人に親しまれています。
表:織部焼の特徴
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 色彩 | 緑・黒・白・赤などの鮮やかな釉薬が使われる |
| 形状 | 歪んだ形や非対称なデザインが多い |
| 文様 | 幾何学模様や自然・動物をモチーフにした抽象的な絵柄 |
| 製法 | 型打ち技法や手作業で一点ずつ個性を出す |
当時、美濃の陶工たちは連房式登窯(のぼりがま)という大きな窯を使い、一度にたくさんの器を焼くことができるようになりました。この登窯は、いくつもの焼成室が階段状につながっている構造で、上と下で温度の違いを生かしながら、効率よく大量生産を実現しました。
その一方で、織部焼の魅力は、同じ釉薬や型を使っていても、一点ずつ表情が違うところです。たとえば、
・焼き加減や釉薬の流れ方が器ごとに異なる
・わざと形を歪ませて個性的なフォルムを生み出す
・絵柄も、職人の手描きによって一点ずつ違いが出る
このように、一つひとつが世界に一つだけの作品になるのが織部焼の面白さです。大量生産が進む中でも、個性や遊び心を忘れず、見る人・使う人を楽しませる器として愛され続けています。桃山時代の美意識と職人たちの技術が詰まった織部焼は、まさに日本の芸術革命と呼ばれる存在なのです。
織部焼と料理の美しい組み合わせ

番組には、日本料理店「銀座 小十」の店主・奥田透さんが登場します。奥田さんは、織部焼の器と料理を組み合わせて、見た目と味の両方を楽しめる盛り付けを工夫しています。織部焼は、その独特の緑色や歪んだ形が特徴で、普通の器とはひと味違う魅力があります。器自体が芸術作品のようなので、そこに料理を盛りつけるだけで、まるで一枚の絵のような演出ができるのです。
特に注目なのが「鳴海織部(なるみおりべ)」という器です。鳴海織部は、白土と赤土を貼り合わせた土台に、鮮やかな緑釉がかけられているのが特徴で、緑・赤・白のコントラストがとても美しい器です。奥田さんは、この器にハモ料理を盛りつけます。そこに梅肉の赤や、ミニオクラの緑が加わることで、色とりどりの美しい料理が完成します。
さらに、織部焼はその歪んだ形や不規則なデザインが、料理に自然なリズムや動きを与えます。
・盛りつけが決まりすぎず、どこか遊び心を感じさせる
・器の形の歪みが、料理全体に立体感や奥行きを生み出す
・釉薬の濃淡や模様が、料理の彩りをより鮮やかに見せてくれる
このように、織部焼は単なる食器ではなく、料理を引き立て、食卓をより豊かに演出してくれる大切な道具です。見た目の美しさだけでなく、使う人や食べる人が自然と楽しくなる、それが織部焼と料理の一番の魅力です。奥田透さんは、そんな織部焼の魅力を料理で最大限に生かし、器と料理が一体となる楽しさを伝えてくれています。
ゆがんだ「沓茶碗」の不思議な魅力
番組で古美術商の梶高明さんが紹介するのが、「沓茶碗(くつちゃわん)」です。沓茶碗とは、伏せたときに昔の履物「沓(くつ)」に似ていることから名付けられた、独特な形の茶碗です。この茶碗の最大の特徴は、あえてわざと歪ませたその形です。丸くない、左右対称でもない、不思議なフォルムが見る人を引きつけます。
桃山時代の人々は、このような歪んだ形の器に、遊び心や個性、そして自由な美意識をたっぷり詰め込みました。それまでの茶碗は、できるだけきれいな丸い形や安定感が重視されていましたが、沓茶碗はそれをあえて崩しています。この「わざと歪ませる」という発想こそが、織部焼らしい大胆さの象徴なのです。
また、沓茶碗には実用的な工夫もあります。たとえば、
・どこからお茶を飲めばよいか、自然と手に取る向きが決まりやすい
・歪んだ縁が、持ちやすく、口当たりにも変化を生む
・見る角度によって、全く違う表情を楽しめる
こうした工夫が、茶道の中で使われたときに、新しい発見や楽しさを生み出してくれます。普通の茶碗とは違い、沓茶碗は見る人、使う人の感覚やセンスによって、その魅力が何通りにも広がるのです。
桃山時代の茶人たちは、決まりきった形にとらわれず、器を使う楽しさや美しさをもっと自由に表現したいという思いから、このような個性的な沓茶碗を生み出しました。今でもその精神は、茶道具や美術品として高く評価され続けています。番組では、そんな沓茶碗の魅力を、実物とともにわかりやすく紹介してくれます。
200種類以上の型を追求する陶芸家・小山智徳さん
陶芸家の小山智徳さんは、200種類以上の織部焼の型を写し取り、長年にわたって研究と制作を続けています。織部焼といえば自由な形や個性的なデザインが特徴ですが、その背景には、こうした型を使った職人たちの技術が隠れています。
小山さんが使うのは「型打ち技法」という方法です。この技法では、あらかじめ作られた型に粘土を押し当てて形を作るため、ろくろでは難しい複雑な形や、大胆で安定感のある造形ができるのです。ただし、型を使うといっても全てが同じにはなりません。小山さんは、
・同じ型でも高さを変えたり、口の広さを変えたりすることで、多彩な作品を生み出す
・型のあとに手作業で細かく形をなぶり、柔らかい口当たりや、自然な歪みを加える
・土や釉薬の違いで、一つひとつの作品に異なる表情を持たせる
このように、型を使いながらも、それぞれの器が世界に一つだけの個性を持つように工夫されています。
たとえば、同じ型を使っても、
・高さを出せば花器に
・平らに広げればお皿に
・深さを出せば鉢やボウルに
というふうに、用途によって形や雰囲気を自在に変えることができます。これが織部焼の面白さであり、実用性と芸術性の両方を楽しめる理由です。
小山さんは、こうした伝統的な技法を生かしつつ、現代の暮らしや感覚にも合う新しい織部焼を作り続けています。昔の良さを大事にしながら、新しい工夫を取り入れることで、織部焼は今も進化を続けているのです。番組では、小山さんの工房の様子や、制作のこだわりも紹介される予定です。どんな作品が登場するのか、楽しみにしたいですね。
不思議な文様に込められた願い
織部焼の魅力のひとつが、見る人の心を引きつける不思議な文様です。織部焼には、耳の長いウサギや、籠目(かごめ)模様、藤の花など、個性的で意味深い模様がたくさん描かれています。これらの模様は、単なる飾りではなく、すべてに意味が込められています。
たとえば、籠目模様は六角形を組み合わせたようなデザインで、古くから魔除けの意味があるとされています。この模様を器に描くことで、災いや悪いものから身を守りたいという願いが込められているのです。
また、藤の花は、しなやかに垂れ下がるその姿から、長寿や子孫繁栄の象徴とされています。藤は日本の風景や文化に深く根づいている植物で、織部焼にもよく描かれ、見る人に安らぎと希望を与えてくれます。
さらに、耳の長いウサギと垣根の模様もよく見られます。ウサギは生命力や繁栄の象徴、垣根は家や家族を守る結界の意味を持っています。こうした組み合わせの模様には、家族の安全や平和を願う気持ちが込められています。
桃山時代は、戦乱や社会の変化が多い不安定な時代でした。そのため、人々は身の回りのものに、安全や幸福、家族の無事を願う思いを込めていたのです。織部焼の器に描かれた模様も、そうした時代背景と人々の願いを映し出しています。
番組には、学習院大学の荒川正明教授が登場し、これらの文様がどのような意味を持ち、どんな背景から生まれたのかを詳しく教えてくれます。普段何気なく見ている器の模様にも、深い願いや物語が隠されていることを知ると、よりいっそう織部焼を身近に感じられるはずです。
現代にも続く織部焼の精神
織部焼は、桃山時代に誕生してから400年以上たった今も、自由な発想や大胆なデザインという精神を受け継ぎ、多くの陶芸家たちの手によって進化を続けています。番組には、現代を代表する陶芸家のひとり、玉置保夫さんが登場し、伝統的な技法を大切にしつつも、現代の感覚を取り入れた迫力ある作品を紹介してくれます。
織部焼といえば、深い緑色や歪んだ形、不思議な文様が特徴ですが、現代の作品にはさらに新しい素材や表現が加わり、昔の焼き物とはまた違った魅力を持っています。それでも、根本にあるのは、決まった形にとらわれず、楽しく自由な発想で器を作るという精神です。
現代の織部焼は、
・普段の食卓で使われるお皿やカップ
・インテリアのアクセントになる花器や置物
・美術館やギャラリーで展示されるアート作品
として、私たちの生活に溶け込み、今も多くの人に愛されています。昔の美意識を大切にしながら、時代に合わせて変わり続けるからこそ、織部焼は今でも新鮮で魅力的なのです。
織部焼は、形や色に決まりがないからこそ、見る人、使う人の想像力を刺激し、楽しませてくれる器です。桃山時代から現代に至るまで、その精神は変わらず、多くの人を魅了し続けています。番組では、そうした現代作家たちの作品や取り組みも紹介される予定です。昔と今をつなぐ織部焼の魅力を、ぜひ番組でじっくり楽しんでください。
まとめ
織部焼は、桃山時代の自由な発想と大胆なデザインを今に伝える、日本を代表する焼き物です。歴史や文化、職人たちの思いが詰まった器は、見る人や使う人の心を豊かにしてくれます。番組「美の壺 桃山の革命 織部焼」で、その奥深い世界をぜひ感じてみてください。
まとめ
「美の壺 桃山の革命 織部焼」は、織部焼の歴史や魅力、現代の作家たちの挑戦をたっぷり紹介してくれる番組です。
【ソース】
https://www.nhk.jp/p/tsubo/ts/XK5VJNN92Q/episode/te/LQKRZQY2X2/
https://omotedana.hatenablog.com/entry/bi-563/Oribe
https://ja.wikipedia.org/wiki/織部焼
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


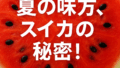
コメント