池上彰 世紀を刻んだ歌「イマジン」再び
2025年6月13日にNHK総合で放送された『時をかけるテレビ』では、池上彰さんと又吉直樹さんが、2002年にBSで放送された特集番組「世紀を刻んだ歌 イマジン」を振り返りました。ジョン・レノンの名曲「イマジン」に込められた平和への願いが、アメリカ同時多発テロの記憶とともに再び語られました。放送では、当時の記録映像や関係者の証言、学校での教育実践、そして現在に続く子どもたちの想像力までが丁寧に紹介されました。
「イマジン」に込められた平和のメッセージ
番組の冒頭では、2002年に放送されたBS特集「世紀を刻んだ歌 イマジン」が紹介されました。この番組はアメリカ同時多発テロの出来事をきっかけに制作され、ジョン・レノンの名曲「イマジン」が世界中でどのように平和の象徴として受け止められてきたかを深く掘り下げた内容でした。
出演者の一人であるサー・アイバンさんは、アウシュビッツ強制収容所を生き延びた人の子どもとして登場しました。彼は「イマジン」という曲が持つ平和の力を伝えることが自分の使命だと語りました。また、当時の出来事を振り返ったデニスさんは、時代が進む中で「イマジン」の意味も変わってきたと述べていました。
日本ではこの曲が教育の現場でも使われるようになり、東京都杉並区の西宮中学校では、4年前から英語の授業に「イマジン」を取り入れています。担当する藤原孝弘先生は、オノ・ヨーコさんが新聞広告に掲載した「イマジン」の一節に感動し、生徒たちにもその想いを共有したいと考えて教材にしたのが始まりでした。
授業では、生徒たちが歌詞を理解し、自分の考えを手紙にまとめてオノ・ヨーコさんに宛てて書く取り組みが行われました。実際に生徒たちが書いた手紙には、それぞれが「イマジン」から受け取った気持ちがまっすぐに表れていました。
-
石倉志織さんは、「テロなどの悲しい出来事があるときこそ必要な曲だと思う」と書きました。
-
藤田良さんは、「ジョン・レノンは死んでしまっているけれど、心の中に生き続けている」と綴りました。
-
斉藤潤さんは、以前はテロへの報復に賛成していたと正直に振り返り、「でも、イマジンの歌詞にふれることで、本当に正しいのか疑問に思うようになった」と記しました。
-
船越七菜子さんは、「この曲を聴いて悲しくなった。けれど、平和は一人ひとりが心がければ実現できるはず。だから、私はもっと優しくなりたい」と述べています。
こうした生徒たちの手紙からは、「イマジン」が単なる音楽ではなく、人の考え方を変える力を持っていることが伝わってきます。平和の大切さを、個人の言葉で考え、表現する経験が、教育の中で実現されていることがよくわかるエピソードでした。また、それぞれの生徒が自分自身の過去の気持ちや変化と向き合いながら、「イマジン」を通して社会の出来事と自分とのつながりを実感している様子も印象的でした。
ジョン・レノンとオノ・ヨーコの平和活動
「イマジン」が生まれた1970年代初頭、アメリカではベトナム戦争が激化しており、国民の間では戦争に対する反発が広がっていました。そんな中、ジョン・レノンとオノ・ヨーコは、平和を訴える活動の象徴的存在として注目されるようになります。二人は「ベッド・イン」と呼ばれる取り組みを行い、ホテルのベッドに横たわったままメディアを通じて平和について語るというユニークな手法でメッセージを世界に発信しました。
この活動の中で生まれたのが「Give Peace A Chance(平和にチャンスを)」という曲です。その後、2人は「君が望めば戦争は終わる(War is Over if You Want It)」という言葉を使い、主要都市の屋外広告や新聞などを通じて大規模な反戦キャンペーンを展開しました。
「イマジン」は、その流れの中で誕生した曲です。この歌には、オノ・ヨーコが1964年に出版した詩集『グレープフルーツ・ジュース』からの強い影響が見られます。この詩集には「想像してごらん(Imagine)」というフレーズが何度も登場し、ジョン・レノンも大きなインスピレーションを受けました。実際に残されている直筆の歌詞原稿には、彼が最後まで自分の理想を貫こうとする思いが込められていたことが読み取れます。
レコーディングはロンドン郊外の自宅で行われ、オノ・ヨーコもプロデュース面などで積極的に関わっていました。アットホームで自由な雰囲気の中で制作された「イマジン」は、家庭からでも世界に向けた強いメッセージを発信できるという新しい形の音楽表現を示したとも言えます。
当時のアメリカは、公民権運動やカウンターカルチャーの影響で大きな社会変動期にありました。その中で「イマジン」は、国境や宗教、所有といった概念を超えて、人々がひとつになる世界を想像することの大切さを問いかけました。だからこそ、この曲は一過性の反戦ソングにとどまらず、今もなお世界中の人々の心に響き続ける普遍的なメッセージソングとして生き続けているのです。
日本の家庭にも広がる「イマジン」の輪
番組の中では、東京都杉並区の西宮中学校で「イマジン」にふれた生徒のひとり、柴田真里さんの家庭の様子も紹介されました。彼女の父である柴田義一さんは、いわゆるビートルズ世代にあたります。学生時代にはバンドを組み、音楽に没頭していた経験を持っており、当時からジョン・レノンのファンだったことが語られました。
社会人になった柴田さんは、仕事に追われる日々の中で音楽から離れる時間も増えていきましたが、ある日ふと耳にした「イマジン」に心を動かされ、それ以来、仕事帰りには必ずこの曲を聴くという習慣が続いているそうです。彼にとって「イマジン」は、現実と理想の間に立ち返る場所になっているといえます。
柴田真里さんが授業を通して「イマジン」に触れたことで、親子でジョン・レノンについて語る機会が生まれたというエピソードも印象的でした。学校で学んだことが家庭に持ち帰られ、世代を超えて一つの曲について話すという体験は、音楽が持つ本来の力を感じさせるものでした。
また、番組では「イマジン」がイギリスの人気楽曲アンケートで1位に選ばれたことも紹介されました。この結果は、ただの懐メロとしてではなく、「イマジン」が今を生きる人々にも必要とされている曲であることを裏づけるものでした。
この曲の魅力として、番組では次のような点が挙げられていました。
-
歌詞がとてもシンプルでわかりやすい
-
宗教や国境、所有などを超えて、すべての人がひとつになれる可能性を描いている
-
世代や文化を問わず、多くの人に届く普遍性がある
こうした特徴が、「イマジン」が国や時代を越えて人の心に届く曲として評価されている理由につながっています。そしてそれは、家庭というもっとも身近な場所で共有される瞬間にも現れており、番組を通して「イマジン」が日本の家庭にも静かに広がっている様子が伝えられました。
世界中で続く「イマジン」の実践
番組では、「イマジン」が音楽としてだけでなく、行動としての平和活動にも活かされている実例が紹介されました。アメリカ・ボストンで展開されている『イマジン・プロジェクト』はその代表的な取り組みのひとつです。このプロジェクトでは、街のさまざまな場所に「Imagine」と描かれたカラフルな壁画が制作されており、その内容には子どもたち自身が考えた理想の世界のイメージが反映されています。
この活動は単なるアートにとどまらず、ボストン市全体が協力して進めている教育プロジェクトです。幼稚園児から高校生までの子どもたちがそれぞれのクラスで詩を考え、その詩をもとに壁画のテーマが決まります。子どもたちは絵を描く作業にも参加し、クラス全体で1つの作品を完成させるという流れになっており、「想像する力」が形になった例として紹介されました。
番組に登場したゴードン・スキナーさんは、生徒たちに向けて「イマジンの歌詞は読むだけではなく、実際に行動に移してこそ意味がある」と語りました。授業を受けた生徒の中には、「考え方が違っても、その人の中身を見ることが大切」と話す子どももおり、歌のメッセージが日常の人間関係にもつながる考え方へと広がっている様子が伝わりました。
また、日本でも「イマジン」を題材とした授業は現在も続いています。番組には再び杉並区立西宮中学校の藤原孝弘先生が登場し、2025年現在も歌詞を通して平和について考える授業を行っていることが紹介されました。この日の授業では、イスラエルとガザの紛争問題をテーマに、戦争が続く地域でこの歌がどう伝わるかを話し合いました。
授業では次のような意見が生まれました。
-
「この曲を、戦争が続いている地域に伝えたい」
-
「武器よりも想像力があれば、人は争わずに生きていけるかもしれない」
-
「どんな状況にあっても、想像することをやめてはいけない」
こうした声は、「イマジン」が今も世界のさまざまな場所で人々の心に響き続け、未来への道しるべとなっていることを証明していました。争いが絶えない現実の中にあっても、この曲は子どもたちに想像する力と行動する勇気を与え続けています。音楽は終わっても、そのメッセージは続いていく――それが「イマジン」の本当の力なのだと番組は伝えていました。

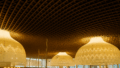

コメント