“神の手を持つ老兄弟”の整備工場の記録
2025年4月18日(金)よる10時30分からNHK総合で放送の『時をかけるテレビ』では、池上彰さんが案内役となり、2015年に話題を呼んだ『プロフェッショナル 仕事の流儀』の1本を振り返ります。取り上げられるのは、広島県福山市にある「小山自動車」。兄の小山明さんと弟の小山博久さんが営むこの小さな整備工場は、「神の手を持つ兄弟」として全国に知られるようになりました。今回の放送では、その技術と人間味あふれる仕事ぶりを、池上さんが時代を超えて紹介していきます。
廃車寸前の車が息を吹き返す瞬間

番組の冒頭で登場したのは、ほとんど動かなくなった三菱ミニカでした。見た目にも傷みが目立ち、エンジンはかからず、まさに「廃車寸前」という状態でした。しかし、小山兄弟にとってはこうした車こそが腕の見せどころ。工場に持ち込まれたその日から、弟の博久さんは黙々と原因の調査を始めました。
・まずはエンジンルーム全体を点検し、ホースの脱落を発見
・ホースをつけ直すとエンジンはかかるようになったが、それだけでは終わらなかった
・ホースがなぜ外れたのか、その根本原因を探る姿勢が際立ちました
外れたホースだけを修理して返してしまえば、次に同じことが起こる可能性があります。博久さんはそこを見逃しませんでした。さらに調べると、点火プラグに劣化があり、スパークの不調が結果的にホースの脱落を引き起こしていたことを突き止めました。このように、一つの故障の奥にある真の原因まで掘り下げて対処する姿勢こそが「神の手」と呼ばれる理由なのです。
・整備後にはエンジンの振動や音も確認し、異常がないことを入念にチェック
・テスト走行を行い、走行中の感触やレスポンスにも違和感がないかを判断
・わずか3日で、エンジンが完全に蘇り、走れる状態にまで整備
工場に入った当初は誰もが「もう無理だろう」と思っていた一台が、まるで生まれ変わったように力強く走り出す様子は圧巻でした。この一連の工程には、経験・知識・観察力・そして車への愛情すべてが詰まっているといえます。
小山兄弟の整備は、表面的な処置では終わらせません。「なぜ壊れたのか」「次に壊れないためにはどうすればいいか」までを考えて直す姿勢が、見ている人の心に響く整備を生み出しています。そしてそれが、全国から依頼が絶えない理由でもあるのです。
兄・明さんのこだわりと誇りある仕事

兄・小山明さんの担当は車検整備ですが、その仕事ぶりは一般的な「点検整備」とはまったく違います。整備のはじまりは洗車から。単に車をきれいにするためではなく、洗いながら車全体の状態を見極める重要な工程となっています。
・洗車をしながら、タイヤの摩耗具合やホイールの汚れ方に注目し、異常な減りや片減りを見逃さない
・ドアの開閉音や力のかかり具合、窓のすき間の風の通り方までチェックし、経年によるズレや歪みを把握
・細かなひび割れや小さなサビなども、洗車中に目視と触感で確認
今回の点検では、車検の基準は満たしていたにもかかわらず、ブレーキパッドの交換を即決。その理由は「2年後の状態を見越して、今のうちに交換しておくべき」という先を読む判断でした。お客さんには見えない部分こそ、今後の安全に大きく関わると明さんは考えています。
・法的には合格でも、2年後には確実に交換が必要になる部品は先に対応
・「ハンドルの微妙な揺れ」が走行中に感じられれば、それがわずかでも異常のサインと捉えて原因を突き止める
その後、すべての項目を確認し、車は問題なく仕上がったかに見えましたが、明さんは試運転を実施。走行中、ハンドルに伝わるごくわずかな振動に気づき、再度工場に戻って点検を続行。部品交換を提案し、完了後に改めて試乗しました。
こうした作業のすべてに共通しているのが、「お客さんが安心して運転できるかどうか」という明確な基準です。単なる合否の判定ではなく、これから先の2年間、車が安全に快適に走れることまでを含めて整備をする。それが小山明さんの整備士としての誇りです。
このような姿勢が、何十年も地元で信頼され続け、さらには全国から車が持ち込まれる理由につながっています。整備とはただ直すことではなく、車の未来をつくることだという考えが、日々の仕事にしっかりと表れているのです。
“どんな車でも直す”という信念

小山兄弟の整備工場には、さまざまなタイプの車が持ち込まれます。その幅広さは、一般的な整備工場とは一線を画します。軽自動車やトラックはもちろん、外車やクラシックカー、さらには高級スポーツカーまで対応可能という対応力は、まさに“どんな車でも直す”という信念の表れです。
・国産車ではプリンススカイラインや三菱ミニカ、トヨタのセダン
・外車ではアルファロメオ・スパイダー、ジャガーXJ、ダッジチャレンジャーなどの希少モデル
・そしてフェラーリ308 GTの整備まで手がける
このフェラーリの修理では、わずか2日で部品交換を済ませたにもかかわらず、博久さんは音に納得がいかず、3日目に試走を実施しました。表面上は問題がないように見えても、“音が気になる”というわずかな違和感を放置しないのがプロとしての矜持です。
・お客が「これで大丈夫」と感じていても、自分が納得できなければ整備を終えない
・「音の響き方」「エンジンの微妙な振動」「足回りの沈み方」など、五感を総動員して車の状態を感じ取る
また、スポーツカーのような繊細なハンドリングやレスポンスが求められる車種においては、ミリ単位の調整や、部品同士のわずかなかみ合わせのズレを丁寧に修正する作業も日常的に行っています。こうした手間を惜しまない姿勢が、「遠方からでもお願いしたい」という信頼につながっています。
その結果、工場には月に150件以上もの依頼が寄せられるようになり、現在は3人で運営しているにもかかわらず、全国から車が集まる人気工場に。整備士という枠を超えた、“車の声を聞く職人”としての信頼が築かれているのです。どんなメーカーでも、どんな年式でも、どんな状態でも、“車である限り直す”という姿勢が、小山兄弟の仕事の核にあります。
兄弟で続ける50年の歴史と家族の支え

小山兄弟の整備工場の歴史は、昭和34年に父・小山稔さんが創業したことに始まります。当時は家庭に車が普及しはじめたばかりの時代。兄・明さんは高校を卒業してすぐに工場に入り、父の背中を見ながら技術を身につけました。弟の博久さんは8歳年下で、少し遅れて工場に加わることになります。
・最初の頃、博久さんは作業に時間がかかり、不器用な一面もあった
・それでも明さんは一度も叱ることなく、背中で教える姿勢を貫いた
・黙って支える兄の姿勢が、兄弟の信頼関係の土台を築いていきました
時代の流れとともに整備の内容も変化していきます。ある時期、法人車両の整備契約をやめるという決断を明さんが下したことをきっかけに、工場の経営は厳しくなりました。従業員がすべて退職し、残ったのは兄弟だけという状況にまで追い込まれました。
・そのとき、博久さんは兄のために自らスポーツカー整備の道を切り開きます
・厳しい要望に応え続けるうちに、遠方からも依頼が来るようになり、工場に活気が戻る
・スポーツカーという難易度の高い分野で結果を出すことで、新たな信頼と顧客を獲得しました
しかし再起の矢先、今度は兄・明さんが倒れてしまいます。その間、博久さんは一人で工場を切り盛りしながら、あらゆる整備依頼に対応しました。そして彼が手がけた車両が、全日本選手権で1位から4位までを独占するという偉業を達成。整備士としての努力が、見事な形で証明された瞬間でした。
・明さんはその快挙に対し「すごいな」と一言だけ口にした
・しかしその後、「本当は嬉しくて、心の中で万歳した」と明かされたことからも、兄弟の深い絆がうかがえます
50年という長い歴史のなかで、苦しい時期も、困難な判断もありましたが、支え合う兄弟の力がそれを乗り越えてきました。この工場には、単なる整備技術だけでなく、家族の絆と誇りが詰まっているのです。その積み重ねこそが、全国から依頼が集まる工場を生み出し、今なお“神の手”と呼ばれる理由につながっています。
人を想う整備。障害のある方への対応

番組の後半では、脳性麻痺の藤井剛さんが使用する軽自動車を、小山兄弟が整備する場面が紹介されました。藤井さんは長期入院しており、その間に車は野ざらしの状態となってしまい、エンジンもかからない状況になっていました。小山兄弟はこの車を再び安全に走らせるため、通常の整備に加えて特別な改造と調整を施しました。
・まずは弟・博久さんがエンジンを点検し、さびて劣化した部品を交換しながら、内部を丁寧に洗浄
・兄・明さんは洗車を担当しながら、全体の状態を確認して次の整備の準備を整える
・ブレーキやタイヤなどの基本的な整備だけでなく、コーティング加工などの処理で耐久性も回復
その後、小山兄弟は藤井さんの身体状況に配慮して、サイドブレーキの角度や位置を調整。腕の力が弱くなっていた藤井さんでも、少ない力で確実に操作できるようにカスタマイズしました。
・操作レバーの位置をミリ単位で調整
・角度を工夫して、手の動きが自然に伝わる設計に変更
こうした工夫によって、半年ぶりに車の運転を再開できた藤井さんは、試運転で競技時と同じターン操作を再現することにも成功。かつてのように走れる喜びを全身で感じている様子が映し出され、視聴者にも強く印象を残しました。
・納車前には再度兄・明さんが点検と洗車を行い、最終チェックを抜かりなく実施
・整備は“完了”で終わりではなく、“安心して運転できる”ところまでやり抜くという姿勢が表れていました
そして何より、整備が終わったあとも、藤井さんの車は毎月欠かさず点検され、9年間にわたり故障ゼロという成果を維持していることが紹介されました。この事実が、小山兄弟の整備の“確かさ”を静かに物語っています。
このエピソードの中で語られた「ただ直すだけでは整備ではない」という博久さんの言葉は、まさに兄弟の仕事観を象徴しています。彼らにとって整備とは、人の暮らしと希望に寄り添う仕事であり、車を通じてその人の人生を支えることでもあるのです。その思いが、ひとつひとつの作業ににじみ出ているからこそ、多くの人が彼らの工場に信頼を寄せているのです。
それでも現役で挑み続ける兄弟
2024年11月現在、兄・明さんは81歳、弟・博久さんは74歳。9年間で工場の設備を一新し、今も最先端の車にも対応可能です。VTRに登場した藤井さんの車も、9年間故障ゼロを記録しており、整備の精度と丁寧さが裏付けられています。
兄弟それぞれが愛犬(ハチとナナ)とともに暮らし、整備の合間の癒しを見つけながら、変わらぬ情熱でハンドルを握る人のために車と向き合い続けています。
――――
番組で描かれた内容は、機械を直す職人ではなく、「命を支える人間」そのものとしての姿でした。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

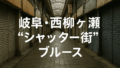
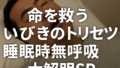
コメント