人間の毛が少ない理由・食器を持つ理由・赤みそと白みその違いとは?
2025年4月11日(金)放送のNHK総合『チコちゃんに叱られる!』(19:57〜20:42)では、毎回驚きと発見があるチコちゃんの質問が、今回も生活の中でふと気になるテーマを深掘りしていきました。ゲストには榊原郁恵さんとカンニング竹山さんが登場。番組で紹介された3つの問い「なぜ人間には毛が少ないの?」「なぜ日本人は食器を持ち上げるの?」「赤みそと白みその違いは?」を中心に、それぞれの内容をわかりやすくご紹介します。
人間に毛が生えていないのはなぜ?

人間に毛が少ない理由は、長い進化の過程の中で「生き延びるための工夫」が積み重なった結果です。番組では、「ヒトが狩りをするようになったから」という理由が紹介されましたが、その背景には複数の出来事が関係しています。
まず、約440万年前にいたとされる猿人「ラミダス」は、体毛に覆われて森林で暮らしていたと考えられています。ラミダスは果物や木の実を食べ、木の上で生活するスタイルでした。ところが、気候の変化によって森林が減少し、食べ物も少なくなってしまいます。
-
食糧を求めて森林を出た祖先は、開けた場所での生活を余儀なくされた
-
新たな環境は、アフリカの暑く乾燥したサバンナだった
-
サバンナでの暮らしには「狩り」が欠かせなくなった
このように、森林からサバンナへ移動した人類の祖先は、動物を追いかけて長距離を走る必要が出てきました。その中で問題となったのが体温の上昇です。毛に覆われたままだと、熱が体にこもってしまい、脳や筋肉の働きが鈍って狩りに不利になることがわかってきました。
-
毛があると、汗をかいても蒸発しにくく、熱が逃げにくい
-
脳は熱に弱いため、過熱すると命に関わる
-
発汗による冷却を効率化するために体毛を減らした
そして、人類は体毛を減らし、汗を全身から効率よくかけるように進化していきました。これにより、長時間走っても体温を下げやすくなり、暑い気候でも活発に行動できるようになったのです。
さらに、体毛の減少は別の利点ももたらしました。毛が減ることで寄生虫がつきにくくなり、病気のリスクも軽減されました。清潔に保ちやすくなったことも、毛を減らす進化を後押ししたと考えられています。
このようにして人間は、過酷な環境に対応するため、少しずつ体毛を減らしていきました。進化は一瞬で起こるものではなく、長い年月をかけて「必要なものを残し、不要なものを捨てていく」過程です。体毛が少なくなったのも、狩りに強くなるための“選ばれた特徴”のひとつだったのです。
なぜ日本人は食事のときに食器を持ち上げるのか

日本では、茶碗や汁椀を手に持って食事をするのが自然なマナーとなっていますが、これは世界的に見ると少し特別な習慣です。番組ではこの疑問に対して、正解は「日本の家が狭かったから」と紹介されました。この理由には、日本の住まいと生活の工夫が深く関係しています。
昔の日本では、最初に建てられた住居が竪穴式住居でした。この住まいは広さが約12畳ほどで、家族全員が同じ空間で生活を送っていました。やがて時代が進むと、長屋のような狭い住宅が登場し、一般庶民は4畳半や6畳の部屋に家族全員で暮らすのが当たり前になっていきます。
-
限られた空間の中で、食事・睡眠・仕事をすべてこなす必要があった
-
テーブルのような大型家具を置く余裕はなかった
-
床に直接置く「御膳」や「ちゃぶ台」を使うのが主流になった
そのような環境で使われた御膳は、床に直接置く低い台です。椅子ではなく座って食べる日本のスタイルでは、器を持たないと食べ物を口に運びにくい高さになります。この「食べにくさ」を解決するために、自然と器を持って食べる習慣が根づいていったのです。
また、日本の食器にはこの習慣に合わせた工夫がされてきました。茶碗や汁椀は、小ぶりで軽く、手にフィットしやすい形をしています。特に汁椀は漆器が多く、熱が伝わりにくいため持ちやすいという特徴があります。
-
和食器は「持って使う」ことを想定してデザインされている
-
素材や大きさも「手のひらで使いやすい」ことを基準に作られている
-
器のかたちや作りそのものが、文化を支えている
さらに、日本人の生活文化には、食べ物を大切にするという価値観があります。「いただきます」「ごちそうさま」の挨拶に表れるように、食事は感謝の気持ちをもって行うものという考えがあり、器を丁寧に扱う所作が礼儀とされてきました。
-
食器を手に持つことで「丁寧に食べている」という印象を与える
-
食べ物や作ってくれた人への敬意を表す行為でもある
-
持つことで「大切にしている」姿勢を見せることができる
このように、日本で食器を持って食べる文化は、住まいの狭さから生まれた生活の工夫であり、道具の形や礼儀作法、そして心のあり方と密接につながっているのです。今では当たり前になっているこの行動にも、長い歴史と日本人の暮らしの知恵が詰まっています。
赤みそと白みその違いとは?

番組の最後に登場したテーマは「赤みそと白みその違い」。出演者の岡村隆史さんは「発酵時間の違い」と答えましたが、正解は「赤みそは蒸した大豆、白みそはゆでた大豆」という、調理法そのものに注目したものでした。
この違いについて、東京農業大学の前橋健二教授が詳しく説明していました。味噌は、大豆に麹と塩を加えて発酵させることで作られますが、その大豆を蒸すか、ゆでるかで、仕上がる味噌の色・味・香りが大きく変わるのです。
-
赤みそは蒸した大豆を使用
蒸すことで大豆の糖分とアミノ酸が濃く残り、熟成中に「メイラード反応」が活発に進みます。これにより色が濃くなり、香りやコクが深まるため、赤みそ特有の力強い味わいが生まれます。 -
白みそはゆでた大豆を使用
ゆでることで大豆の一部が湯に溶け出し、メイラード反応が起こりにくくなります。そのため、色が淡く、やさしい甘みとまろやかさが特徴の白みそが出来上がるのです。
また、発酵期間の違いも補足として語られていました。赤みそは長期間熟成されることが多く、より深い風味になりますが、白みそは短期間で熟成されるため、すっきりした味わいが残ります。関西地方では、お正月の雑煮に白みそが使われることが多く、地域の食文化にも深く根付いています。
-
赤みそは塩味と旨みが強く、味噌汁や煮込み料理に最適
-
白みそは甘くてまろやか、白和えや酢みそ和えにぴったり
さらに、栄養面にも違いがあると紹介されました。赤みそは熟成が長いため、抗酸化作用のあるメラノイジンを多く含んでおり、老化や生活習慣病の予防に期待できるといいます。一方で白みそは、発酵によって生まれるGABA(ギャバ)を含み、リラックス効果や安眠効果があるとされています。
スタジオでは「紅白みそ合戦」が開催され、赤みそ・白みそそれぞれを使った料理が次々と登場。みそマーボーなす、ビーフシチュー、サバの白みそ煮など、和洋を超えたアレンジ料理が紹介され、出演者たちも思わず驚く内容となっていました。
-
赤みそ:濃厚なコク、長期熟成、蒸し大豆使用、抗酸化作用あり
-
白みそ:まろやかな甘み、短期熟成、ゆで大豆使用、GABAによるリラックス効果
また、番組では郷ひろみさんやTHE ALFEEにまつわる味噌エピソード、愛知や京都の味噌文化、さらには歴史資料『和名類聚抄』に登場する古い味噌の記述なども紹介され、味噌の文化的側面にも触れていました。
このように、赤みそと白みそは、見た目も味も作り方もまったく異なるもの。どちらが上というわけではなく、料理や季節、体調に合わせて使い分けることで、食卓がより豊かになるということを教えてくれる内容でした。日本の発酵文化の奥深さを感じられる、学びの多い一幕でした。
今回の『チコちゃんに叱られる!』では、人間の進化、住まいの構造、発酵食品の文化という異なる3つのテーマが、身近な生活と結びついていることを楽しく学ぶことができました。何気ない疑問の背景に、これだけ深い歴史や工夫があることに驚かされる45分間でした。次回の放送も楽しみです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


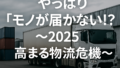
コメント