熱中人と探る!ナナフシの“もはや植物”な七不思議|2025年4月20日放送
2025年4月20日(日)のNHK『ダーウィンが来た!』では、「シリーズ熱中人 もはや植物!?ナナフシの七不思議」が放送されました。今回のテーマは、昆虫でありながらまるで植物のような姿や生き方を持つ“ナナフシ”。個性豊かなナナフシマニア=熱中人たちとともに、その不思議な生態に迫ります。放送では、長年の観察者から140匹を飼育する若き研究者、さらには鳥とナナフシの意外な関係まで、多角的にナナフシを掘り下げました。
熱中人と一緒にナナフシワールドへ

番組の最初に登場したのは、ナナフシ探し歴20年の舟木翔一さんです。20年の経験を持つ彼は、ロケ当日もナナフシ探しを始めてすぐに発見。スタッフが驚くほどの手際で、ナナフシを木の枝の中から見つけ出しました。探すポイントとして、クリ・サクラ・バラ・エノキなど、ナナフシが好む植物を目印にすることが重要と紹介されました。実際、日本には20種以上のナナフシが分布しており、それぞれ好みの植物があります。
ナナフシの体は枝のように細く、前脚のつけ根はわずかに曲がっていて、頭を自然に枝に沿わせる構造になっています。これにより、まるで本物の小枝のように擬態し、敵から身を守っています。羽を持っていても飛べない種類が多いため、ナナフシは飛ぶ代わりに“隠れる力”を極めた昆虫です。危険を感じると、木から身を投げるようにして地面に落下し、そのままじっとして捕食を避けるという行動も観察されました。
さらに、舟木さんがスタッフにふるまったのは「ナナフシ糞茶」という珍しいお茶でした。これは、ナナフシが食べたサクラの葉の成分が残る糞を乾燥させ、ティーバッグにしてお湯で抽出したものです。糞はフライパンで弱火でじっくり水分を飛ばしてから使い、仕上がりはほんのり桜の香りが漂う、見た目からは想像できない風味とのことでした。
・使用する葉によって風味が変わるため、育てる植物にこだわる必要がある
・糞は新鮮なものを使い、弱火で乾燥させるのがポイント
・サクラ風味以外に、タイではグァバの葉で育てたナナフシ糞茶も存在し、異なる香りが楽しめる
このように、ナナフシの生態にとことん向き合ってきた舟木さんだからこそ紹介できる、“糞からお茶”というユニークな世界が広がっていました。昆虫観察の域を超えて、食と結びついたナナフシ文化としても注目すべき内容でした。
卵に秘められた“種のような”秘密
続いて登場したのは、140匹以上のナナフシを飼育する大学生・轟木沙椰子さんです。彼女は中学生の頃からナナフシに魅了され、特に繁殖行動に強い興味を持って研究を重ねてきました。現在ではその研究成果がコンテストで表彰されるほどで、海外での発表経験もあるとのことです。
ナナフシの産卵方法は非常に特徴的で、お腹を細かく揺らしながら卵を1つずつ地面にばらまくというものです。この動きは一見すると地味ですが、進化の過程で選ばれた重要な生存戦略でもあります。
・葉の裏などにまとめて産む昆虫は、天敵に見つかった際に卵が全滅するリスクがある
・ナナフシはばらまくことで、1か所で全滅する可能性を避け、生存率を高めている
この“ばらまき戦略”により、ナナフシの卵は自然の中に散らばり、目立たず、守られた状態でふ化の時を待つことができます。
卵そのものも非常にユニークな構造です。硬くて丸みのある形状は、まるで植物の種のような外観で、茶色がかった色味に斑点模様が加わることで、落ち葉や土の中に紛れても見分けがつきにくくなっています。
特に興味深いのが、卵の先端にある「蓋帽(がいぼう)」と呼ばれる突起部分です。
・この部分には栄養が含まれており、アリが餌と勘違いして巣に運び込む
・アリは突起部分だけを食べ、卵本体はそのまま巣の中に残される
・結果として、天敵の少ない安全な場所で卵が守られる
この仕組みは、まさに植物の種がアリに運ばれる「ミルメココリー」と呼ばれる自然現象に近いもので、ナナフシは植物と同じように“分布と保護”の仕組みを動物に委ねているといえます。
・卵の色や質感も自然物にそっくりで、捕食者の目を欺く
・アリとの共生関係によって、安全なふ化環境を確保
・ばらまき式の産卵+擬態+輸送=三重の防御戦略
ナナフシは昆虫でありながら、植物のような戦略を使って命を次世代へとつないでいることが、轟木さんの観察と研究からも明らかになりました。ナナフシの卵は、見た目の可愛らしさとは裏腹に、驚くほど複雑で巧妙な生存システムを備えているのです。
鳥によって運ばれる卵!?自然の輸送システム
番組の後半では、神戸大学の末次健司博士が登場し、ナナフシと鳥との間にある驚きの関係を紹介しました。ナナフシは飛ぶことができず、自力で遠くへ移動することが難しい昆虫ですが、実は鳥を“輸送手段”として利用している可能性があることがわかってきました。
その仕組みはこうです。ナナフシの中には、体内に卵を抱えたまま鳥に捕食されてしまう個体もいます。通常であれば、捕食されれば命は尽き、卵も失われてしまうはずですが、ナナフシの卵は非常に硬く、鳥の体内でも消化されずにそのまま排出されるのです。
・実際に、ヒヨドリの糞からナナフシの卵が発見された例もあり、糞の中から無事にふ化した個体も確認されている
・この仕組みは、植物の種子が動物に食べられ、排泄によって別の場所に広がっていく「種子散布戦略」と同じ原理
・ナナフシは、自らの移動力を持たない代わりに、鳥の体を“自然界の乗り物”として活用していると考えられる
このように、鳥に食べられるという一見不利な状況も、ナナフシにとっては子孫をより広く拡散させるための重要なチャンスとなっているのです。自然の仕組みの中で、捕食という行動までもが進化の武器になっていることに驚かされます。
そして、春になると、排出された卵の中からふ化したナナフシの子どもたちが姿を現します。体長はおよそ1cmほどですが、その小さな体にはすでに大人と同じ形状が備わっており、生まれた瞬間から枝のように静かに擬態しています。
・ふ化直後のナナフシも、天敵から身を守るためにじっと動かず、周囲に溶け込んで行動を開始
・すでに“かくれんぼ名人”としての素質を持ち、生まれてすぐに高い擬態能力を発揮
この章では、ナナフシが植物のように“まかれ”“運ばれ”そして“芽吹く”かのような生命の流れを持つことが紹介されました。鳥に食べられても、子孫を未来へつなぐ――まさに自然の驚異そのものでした。
まとめ
今回の『ダーウィンが来た!』では、ナナフシの外見の不思議さだけでなく、その卵・繁殖・移動の戦略まで“植物そっくり”な進化の数々が紹介されました。自然の中で生き抜くための工夫が、ここまで洗練されていることに驚かされます。
ナナフシという小さな昆虫に、こんなにも壮大なドラマが秘められていたことに気づかせてくれる、学びの多い30分でした。放送の内容と異なる場合があります。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


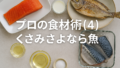
コメント