文化か虐待か 動物行事で刑事告発相次ぐ
2025年5月27日にNHK総合で放送された『クローズアップ現代』では、「文化か虐待か」をテーマに、動物行事に対する刑事告発が相次いでいる現状と、その背景にある社会の価値観の変化に迫りました。東北・岩手県遠野市や宮城県涌谷町で行われる馬の行事、そしてメキシコの闘牛や三重県の神事まで、国内外の事例を通じて、伝統行事と動物福祉の両立について深く掘り下げる内容でした。
遠野の「馬力大会」が中止に
岩手県遠野市で約70年続いてきた伝統行事「馬力大会」が、2025年は中止となりました。この大会は、馬が重りを引いて力や手綱さばきを競うもので、遠野の人々にとって大切な文化のひとつでした。農業や物資の運搬に馬が欠かせなかった時代の名残として、地域の誇りとして親しまれてきた行事です。
しかし今年、動物愛護団体からの刑事告発を受けて、市は開催を見送りました。問題視されたのは、馬を走らせる際に手綱で叩くような動作があったこと。SNS上でその様子を収めた動画が拡散され、市役所には抗議の電話やメールが殺到しました。
・市によれば、通常業務に支障が出るほどの抗議が連日寄せられた
・大会を告発したのは、保護動物を育て新たな飼い主へとつなぐ活動を続けているヤブキ氏
・ヤブキ氏は自身が撮影した映像をSNSに投稿し、遠野市への意見送付を呼びかけた
遠野市は、馬の産地として長い歴史を持ち、馬は生活の一部として地域と共にありました。「馬力大会」は、馬と人との信頼関係を示す場でもあり、後継者への技術継承の目的もありました。大会では、馬を操る技術だけでなく、扱い方や手入れの仕方も重要視されていたといいます。
・地域の学校では馬の学習も取り入れられ、馬文化を学ぶ機会が設けられていた
・大会には観光客も多く訪れ、物産販売なども行われ地域経済にも貢献していた
そうした中での中止決定は、市民や関係者にとって衝撃でした。一方で、時代が求める動物福祉の視点にどう対応するかという課題も突きつけられました。遠野市の多田市長は、再発防止策を含めた大会の見直しを進めたうえで、来年の再開を検討しているとしています。
文化を守ることと、動物への配慮をどう両立させるか。遠野の馬力大会は今、その分岐点に立っています。
宮城・涌谷町では大会継続も告発に
東北地方の宮城県涌谷町では、伝統行事として馬の力比べ大会が現在も続けられています。この大会では、馬が重りを引きながら力や動きの正確さを競い合います。地元では長年親しまれてきたイベントであり、農耕文化の継承という意味でも大きな役割を担ってきました。
近年では、動物への配慮を意識して重りの軽量化やムチの使用の禁止など、改善の取り組みが行われてきました。馬の負担を減らすための措置として町も一定の工夫を重ねてきたことがうかがえます。
しかし、それでもなお動物愛護団体からの告発は止まりませんでした。ヤブキ氏は、たとえ形式が変わったとしても「大会そのものが動物虐待にあたる」として、強く批判。馬を競技に使う行為そのものに対して、見直すべきだと主張しています。
この大会の様子を撮影して告発のきっかけを作ったのは、千葉氏という男性です。もともと野生のイルカの捕獲方法に疑問を抱き、そこから動物愛護の活動に共感するようになったといいます。彼はその後、涌谷町での大会に注目し、自ら映像を記録して訴えに活用しました。
・撮影された映像はSNSなどでも広まり、世間の注目を集めた
・刑事告発を受けた大会関係者は最終的に不起訴処分となった
・それでも地域には大きな波紋が広がり、行事のあり方が再び問われることとなった
町としては、伝統行事を守りながらも時代に合った形を模索し続けています。改善策を講じたにもかかわらず批判が続く現実は、動物福祉に対する社会の基準が急速に変わっていることを示しているともいえます。
このように、涌谷町の事例もまた、人と動物の関係性の見直しが求められる時代の流れを象徴しています。文化と倫理のバランスをどのようにとっていくか、これからの課題として残されています。
海外でも起きている変化:メキシコの闘牛

メキシコでは、およそ500年もの歴史を持つ闘牛文化が、近年大きな転換点を迎えています。従来の闘牛では、牛をじわじわと弱らせて最後に屠るという流れが一般的でした。しかし、この方法は動物愛護の観点から激しい批判を受けてきました。
そうした声を受け、新たに条例が制定され、伝統的な闘牛の内容が見直されることとなりました。
・牛への刃物の使用を禁止
・1頭あたりの出場時間を15分以内に制限
・出血を伴う攻撃行為を廃止
この改革によって、「暴力のない闘牛」という新たな形が誕生しつつあります。従来の形式を完全に否定するのではなく、文化的側面と倫理的配慮のバランスを取る方向へと動いています。
改革の過程では、アルバレス議員をはじめとする政治家、獣医師や動物保護団体の代表、畜産関係者など多様な立場の人々が意見を交わしました。協議の様子はインターネット上で公開され、市民に向けて透明性を確保したかたちで進められたのも特徴です。
一方で、闘牛の廃止を求める声は依然として根強く、観客数の減少や経済的損失を懸念する声もあります。議論の中では、文化の継続と経済効果の維持を理由に、完全な廃止ではなく形式の見直しが妥協点として選ばれました。
メキシコの事例は、伝統を守ることと、現代の価値観に合わせた改善を両立させようとする試みとして、世界的にも注目を集めています。文化の本質を失わずに進化させる方法を模索するこの動きは、動物行事をめぐる他国や地域にとっても大きな示唆となるものです。
三重の上げ馬神事でも見直し進む
日本国内でも、動物を扱う伝統行事の見直しが進められています。三重県で長年行われてきた「上げ馬神事」では、馬が急な坂を一気に駆け上がる迫力ある場面が見どころの一つとされてきました。しかし過去に馬が足を骨折し、殺処分される事故が起きたことをきっかけに、行事の在り方が問われるようになりました。
こうした事態を受け、神社側は行政に相談。その後、獣医師、動物愛護団体、専門家らを交えた検討会が設けられ、行事の安全性を高めるための改善策が協議されました。
・急勾配だった坂の傾斜を緩やかに調整
・馬の体調管理や安全性への配慮を強化
・運営側の行動に対する基準の見直しも議題に
これらの取り組みにより、安全性を重視した形での継続が可能となりました。ただし、すべての関係者が納得しているわけではありません。
愛好家からは「迫力が失われた」とする声が上がる一方で、動物愛護団体からは「改善では不十分、中止すべき」との意見が続いています。伝統を守りたい立場と、動物福祉を優先すべきと考える立場の間で、議論の溝は深いままです。
それでも、地域が行政や第三者と協力しながら継続と改善の両立を模索している点は注目すべき動きです。行事の価値や意義を保ちつつ、時代に合った在り方を模索する姿勢が、今後の伝統行事のあり方を考えるうえで重要なモデルとなるかもしれません。
専門家の視点と今後の課題
番組には、獣医師であり帝京科学大学の教授である佐伯潤氏が出演し、動物と人との関わりについて専門的な立場から意見を述べました。佐伯氏はまず、犬や牛、豚、鶏といった動物は、人間社会が作り出した存在であり、食や医療、日々の暮らしを支えてきた重要な存在であると指摘しました。
そのうえで、「動物を一切使わないという極端な考え方は、社会構造を考えると現実的ではない」とし、現実に即した視点で動物との共生を見直す必要性を語りました。
ただし、伝統行事などで動物を扱う際には、その安全を守る体制がまだ不十分であることにも触れました。
・行事現場に獣医師が常駐していないケースが多い
・事故や負傷が起きた際の対応体制が整っていないことも問題
・専門家の積極的な関与が今後の信頼回復につながる可能性がある
また佐伯氏は、動物と人との距離を完全に隔てるような考え方には慎重な姿勢を示しました。動物と関わる機会を減らすことが、かえって無関心や虐待の助長につながることもあるとし、「触れ合いを通じて生まれる愛情こそが、動物愛護の心につながる」と語りました。
つまり、動物との関わりを「なくす」のではなく、どうすれば互いに安心して共存できるかを考える視点が重要だということです。行事を支える地域の人々、保護を訴える団体、そして科学的知見を持つ専門家が連携することで、文化の継承と動物福祉の両立を図る道筋が見えてくるといえます。
まとめ
『クローズアップ現代』の今回の放送は、伝統と動物福祉のはざまで揺れる地域社会の今を映し出すものでした。伝統行事を守りたい人、動物を守りたい人、それぞれの立場には信念があり、一方的に否定するのではなく対話が必要であることがよくわかりました。
伝統文化をただ守るだけでなく、時代に合わせた形へと見直すことの重要性も、国内外の事例から見えてきました。今後も「人と動物の共生」が真に実現される社会を目指すためには、多様な立場の声を聴き合う柔軟な姿勢が求められます。

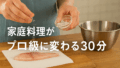

コメント
この様な伝統文化より、お金儲けの為の競馬などは告発しないのかな?
大勢の人間を敵に回すのは怖いのですねキット。
動物愛護も理解できるのですが 告訴したあとこの主役の動物はどうする 365日大切に育て晴れの舞台でみんなに見てほしいと 育ての家族の思いも理解出来ないのかな 祭り中止でこの子達の活躍する場が無くなると 子孫もいらないから この子達の子孫は 未来も考えられたいいのに 動物も虐待可哀想だけど 世界の何処かで生きて行けない人間に興味ないのか それのほうが不思議