外国人労働者“争奪戦”の実態と課題とは
2025年6月17日に放送されたNHK「クローズアップ現代」では、「わが町に来てほしい!」と題して、全国の自治体で広がる外国人労働者の“争奪戦”について特集されました。人手不足が深刻化する中、外国人労働者の確保をめぐる取り組みが加速し、地域ごとの支援策や受け入れの課題が浮き彫りとなりました。番組では実例を交えながら、日本社会がどのように外国人と向き合っていくべきかを探りました。
外国人労働者争奪戦が始まった背景

番組では冒頭から、今や街中の様々な場所で外国人労働者を見かけるようになったという現実が映し出されていました。背景にあるのは、日本社会全体で深刻化する人手不足です。とくに介護や建設、農業、宿泊業など16の主要分野で、今後3年間で約242万人もの労働力が不足する見通しだといわれています。政府はその対策として、高齢者や女性の就業促進、さらにはロボットやAIの導入による業務効率化を進めていますが、これらを組み合わせても160万人分程度の補填しか見込めず、残る82万人分の労働力は未解決のままです。
そこで、注目が集まっているのが外国人労働者です。都市部に限らず、地方の中小企業でも外国人の力が欠かせない状況が広がってきています。特に茨城県では、その傾向が顕著です。
・茨城県の生産年齢人口(15~64歳)は、この20年でおよそ2割も減少しており、県内企業の多くが人手不足に悩まされています。
・ある金属加工会社では、生産ラインの一部を止めるしかない事態にまで追い込まれたケースもありました。
このような状況に対して、茨城県ではいち早く行動を起こしました。
・ベトナムやインドなど5つの国の機関と協定を結び、外国人材の送り出しと受け入れに関する強力な連携体制を築いています。
・企業への支援として、ビザ取得や生活支援、語学面のフォローなどのサポートが実施されています。
実際に、番組で取り上げられた茨城県内の金属加工工場では、現在161人の従業員のうち11人がベトナムからの外国人労働者です。県の支援によって、さらに新たに3人の労働者がベトナムから来日する予定で、工場の生産体制の維持に大きな期待が寄せられていました。
こうした取り組みは、単に人手不足を補うという目的にとどまらず、地域経済や企業の存続にとって不可欠な戦略となっています。特に茨城県のように、地元で人材を確保することが難しいエリアでは、外国人労働者の存在が今後ますます重要になっていくことがうかがえました。
地方ごとの独自支援とその反響
地方自治体では、外国人労働者を受け入れるだけでなく、その生活や家族への支援に取り組む例が増えています。山梨県では、外国人労働者の安心につながる保険制度を導入しました。これはベトナム人労働者の家族が母国で病気やけがをした際、医療費の約9割をカバーできるという制度です。
・この制度は、県が民間保険会社と連携して作られたもので、企業が保険料の約75%を負担し、さらにその企業負担分の半額を県が補助しています。
・労働者が離れた家族の心配を抱えながら働くのではなく、家族の健康が守られることで精神的な安定と職場定着につなげたいという意図があります。
しかし、制度の導入後にはSNSや電話を通じて400件を超える苦情が殺到しました。その多くは「日本人にはない優遇だ」といった誤解に基づいたもので、内容をよく理解していないまま反発する声も目立ちました。このような反応から、制度の背景や仕組みについて、地域住民への丁寧な説明の必要性も浮かび上がっています。
また、宮城県では、宗教的な背景を持つ外国人に配慮した取り組みが行われています。イスラム教徒の間では、亡くなった際に宗教上の理由から土葬を望む文化があります。これに対応するため、県は土葬ができる墓地の整備を検討しています。
・日本の法律では土葬自体は禁止されておらず、すでに国内には土葬に対応している地域も存在しています。
・宮城県はこの施策について、あくまで文化や信仰への理解を深めるものであり、外国人労働者を増やすための政策ではないと明言しています。
しかし、SNSでは否定的な声が目立ち、「日本の風習を変えるのか」といった批判も見られました。これに対して、県内で働くイスラム教徒の一部からは、日本社会はまだ異文化への理解が十分ではないとの声もあがっており、共に暮らすための相互理解の重要性が改めて問われています。
地方ごとのこうした支援策は、外国人労働者にとっての「働きやすさ」や「暮らしやすさ」を高める一方で、地域社会とのすれ違いや、情報不足による混乱も生んでいます。支援の中身だけでなく、それをどのように伝えるか、受け止めてもらうかという点が、これからの課題として浮かび上がっています。
互いの理解を深める地域の取り組み

外国人労働者の受け入れを進める中で、ただ働いてもらうだけではなく、地域住民と外国人がともに暮らしていくための取り組みが各地で始まっています。宮城県大崎市や大阪市では、外国人と地域社会の橋渡しを担う「日本語教育」が中心となっています。
宮城県の大崎市立おおさき日本語学校では、単に日本語を教えるだけでなく、地域の人たちとの交流を積極的に取り入れた授業内容が特徴です。
・登校時には、地域住民が校門に立って生徒たちを出迎える姿が日常となっていて、挨拶を交わすだけでも自然なつながりが生まれています。
・授業の中にも地域とふれあう時間が設けられており、行事への参加や地元の人との会話を通して、文化や習慣の違いを理解し合う機会が広がっています。
・この取り組みにより、地域に住む人々の間で「外国人に対する不安」が徐々にやわらぎ、受け入れの気持ちが育まれていることが番組内で紹介されました。
大阪市でも同様の方向性で、日本語教育と地域活動を組み合わせたプログラムが実施されています。ここでも、外国人が言語だけでなく生活に必要なマナーや文化的背景を学ぶ環境が整えられ、住民との接点を大切にしています。
こうした地域の工夫は、外国人が孤立せずに暮らしていくための「小さなきっかけ」をつくるものです。言葉の壁を越えることはもちろん、日常の中で自然と顔を合わせる機会を増やすことが、お互いを理解し合う第一歩になります。
地域住民にとっても、自分たちの生活の中に異文化があることを知ることで、視野が広がり、共に生きるという実感が持てるようになります。こうした取り組みは、将来的に「多文化共生」が根づく社会を作っていくために欠かせない大切な土台となっていくといえます。
支援が広がる理由と現在の状況
現在、全国の自治体で外国人労働者の受け入れをめぐる支援が広がっている背景には、人手不足がかつてない深刻な水準に達している現実があります。特に介護やバス運転手、清掃、インフラ整備などの分野では、人材確保ができずにサービスの維持が困難となっている地域が増えています。
・昨年度だけで、人手不足を理由に倒産した企業は350件にのぼり、これは2年連続で過去最多の記録です。
・このままでは、地域の交通、医療、介護といった生活の基盤が崩れる可能性が高まり、自治体は企業の存続と住民サービスの維持のために、外国人労働者の確保を支援する動きを強めています。
また、もう一つの大きな理由として、日本が外国人にとって選ばれにくい国になりつつあるという懸念があります。近年では、アジア諸国が競うように外国人労働者を受け入れようとし、国を挙げて魅力づくりに取り組んでいます。
・たとえば韓国では、外国人のための言語教育や生活支援、法整備などが進み、労働者が「選びたい国」と感じられるような環境が整っています。
・台湾やマレーシアなどでも、就労ビザの取得手続きの簡略化や、家族帯同の制度充実が進んでおり、競争が激化しています。
このような状況で、日本が遅れを取らないためには、ただ雇用の場を提供するだけでなく、生活面での支援や文化的な配慮、言語教育の機会など、トータルで「暮らしやすさ」を提供する必要があります。
・言語面では、日本語の学習機会を地域ごとに広げていくこと。
・生活面では、住居探しや医療、教育などでの相談窓口の設置。
・文化面では、宗教や食習慣、祭事への理解と配慮。
これらの対策が揃って初めて、外国人が安心して日本を選び、働き続けられる環境が生まれます。自治体は企業支援の延長としてこれらの支援を行っており、今後は地域ぐるみでの「暮らしの共生」がより重要になっていきます。支援の広がりは、社会全体の持続可能性を守るための選択でもあるということが、番組の中で強く伝えられていました。
海外の事例:韓国の取り組み
番組では、外国人労働者の受け入れに積極的な海外の事例として韓国の取り組みが詳しく紹介されました。韓国では、国全体で支援体制を整える方針を明確にし、外国人労働者が働きやすく暮らしやすい環境づくりが進められています。
まず特徴的なのが、全国に設置された外国人労働者向けの支援センターの存在です。
・このセンターは国の予算によって運営されており、6か国語以上に対応した多言語サービスを常時提供しています。
・韓国語の授業も無料で受けられ、就労に必要な語学力の習得や日常生活の支援が一体となっています。
韓国では2004年に法改正が行われ、労働者の受け入れに関する制度が大きく変わりました。
・国が受け入れ人数を調整し、法令違反のない優良企業を対象に労働者を優先的に配分する制度が整えられました。
・これにより、不適切な労働環境での就労や中間業者による搾取のリスクが抑えられる仕組みができたのです。
さらに、韓国では「社会統合プログラム」という教育制度が設けられています。
・このプログラムは全国384か所で実施されており、韓国語に加えて法律、文化、生活習慣などを学べる場となっています。
・年間予算は14億円以上にのぼり、国を挙げた一貫した受け入れ政策の柱として位置づけられています。
こうした制度によって、外国人労働者は韓国社会への適応がしやすくなり、企業にとっても信頼性のある雇用が実現されています。ただし課題も残っており、在留期限を過ぎても国内に留まる外国人労働者の存在が、社会の一部で不安視されています。
・治安への影響や福祉コストの増加に対する国民の懸念も根強く残っているという現実があり、
・制度と社会の受け止め方にズレが生じている点も指摘されていました。
このように、韓国は国の政策として労働力の確保と共生社会の実現を目指す明確な方向性を持っています。日本にとっても、制度整備や支援体制づくりを考える上で、大いに参考となる取り組みとして紹介されていました。
日本に求められるこれからの姿
番組では、アジアで外国人労働者の確保競争が進む中で、日本も国を挙げた取り組みが求められるとまとめていました。特に、日本語教育の充実、文化・宗教・生活習慣に関する学びの場の提供が大切です。また、企業や地域が個別に対応するのではなく、国が支援する体制を整える必要があります。
地方自治体も、ただ受け入れるだけでなく、住民との関係づくりをサポートすることが求められます。外国人を「労働力」としてだけでなく、地域の一員として迎える姿勢が大切になります。
番組の最後には、社会学者の万城目氏が「真の共生社会とは、国籍や文化の違いを“個性”として認め合える社会である」と語り、今後の日本の方向性として、外国人と共に暮らす未来をどう築いていくかが問われていると締めくくっていました。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

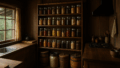

コメント