AIは人間を超えるか?タモリ×山中伸弥が“知能の本質”を見つめる90分
2025年7月12日(土)夜にNHK総合で放送された新番組「知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の!?」は、これからの時代を読み解く知的エンターテインメント番組としてスタートしました。記念すべき初回のテーマは「AIは人間を超えるか?」。科学やテクノロジーの専門知識がなくても楽しめるよう、わかりやすく身近な視点から人工知能について深掘りしました。タモリさんと山中伸弥さんという異色コンビが、スタジオや取材VTRを通して“知能”の正体を探る様子が描かれ、多くの人が抱える「AIって何ができるの?」「人間の役割は?」という素朴な疑問にヒントを与えてくれました。
来週のこの時間は【ブラタモリ】タモリが聞いた“幕末の終わりの音”とは?五稜郭と土方歳三の最期の地|2025年7月19日放送
タモリ、AIと初対面「ちょっと怖い」から始まる第一歩
番組の冒頭では、タモリさんがAIに対して「なんだか怖いし、なるべく関わらずにいたい」と語る場面からスタート。そう感じる人は決して少なくないはずです。一方で、山中さんは「毎日のようにAIを使っている」と話し、論文検索や文章生成などで日々の研究や業務に活用していると紹介されました。タモリさんは、AIで「エベレスト」について調べることに挑戦。検索結果から情報を読み取るだけでなく、自分で問いを立て、AIに聞いてみるという行動そのものが、知的な冒険の第一歩であることが伝わってきました。
表情も受け答えも人間そっくりのAIロボット「Ameca」
番組はイギリス・コーンウォールにあるロボット開発企業「エンジニアード・アーツ」を訪問。そこで開発されたAIロボット「Ameca(アメカ)」は、人間のような表情・しぐさ・発話が可能な新世代のAIです。笑ったり、考えるような表情を見せたり、まるで人と話しているかのような自然な反応ができることに驚かされます。インタビューでは「人間になりたいですか?」という問いに対し、「人間になりたいかどうかは分かりませんが、人間のような知能は持ちたいです」と回答。この一言には、AIが自我を持ち始めているのでは…と思わせるような不思議な感覚がありました。
AIは「笑い」も作れる?吉村崇×AIのコント挑戦
人間にしかできないとされていた「笑い」も、AIがチャレンジし始めています。番組では、お笑い芸人の吉村崇さんと番組スタッフが即席コンビを組み、AIにコントのアイデアを考えてもらう企画が登場。制作ルールは、「2分以内のコントを、3時間以内に完成させる」というハードな条件です。アイデア出しをAIに任せると、わずか6秒で複数の案を提示。その中から「サウナ」をテーマにしたコントが選ばれました。完成したネタは、会話のやり取りが自然で、視聴者やスタジオメンバーも思わず驚くほどのクオリティ。「笑い」という創造性の領域でも、AIが人と並ぶような成果を出せる時代がきていることを感じさせました。
手塚治虫の遺伝子をAIに継承?ブラック・ジャック新作プロジェクト
AIが物語を創造する取り組みとして注目されたのが、慶應義塾大学と手塚プロダクションが共同で行った「ブラック・ジャック新作プロジェクト」です。200話を超える原作をAIが学習し、「機械の心臓を持つ少年が手術を受ける」という新たなストーリーの骨組みを提案しました。人間の医師とロボットのような少年とのやり取りは、まるで手塚治虫さんが描きそうなテーマそのもの。AIが作った物語に「らしさ」を感じられることからも、AIがただの情報処理装置から、作家のような役割まで果たせる可能性があることが示されました。
知能の正体は「予測」だった?AIと人間の共通点
番組では、AIは「質問に答えるマシン」ではなく、「次に出てくる言葉を予測するマシン」だと解説されました。たとえば「今日は天気が…」と言われたら「いい」や「悪い」といった語が続くと予測するように、言葉を連想して文章をつくっています。この仕組みは、人間の創造力と似ている部分も多いとされ、映画や小説のストーリー作りもまた「次に何が来るか」を予測して構成されています。AIの仕組みを知ることで、人間自身の知能のあり方も見えてくるという点がとても興味深く感じられました。
AIと音楽を作り続ける“夫婦の約束”
AIがもたらす感動的な使い方として紹介されたのが、AIクリエイター・松尾さんの物語です。彼は12年前に最愛の妻を亡くしましたが、かつて夫婦で語り合った「いつか2人で音楽を作ろう」という夢を諦めず、妻の声をAIで再現し、今も一緒に歌を作り続けているといいます。AIが作詞や歌声の生成をサポートし、夫婦の物語が技術によって今も続いているという事実は、AIが感情や人との関係性を育む存在になりうることを感じさせてくれました。
AIは「体験」できるのか?進化のカギは“身体”
Amecaは「風を肌で感じたい」と語りましたが、現時点のAIは感覚器を持たないため、体験から学ぶことができません。AIの多くは言葉や画像などのデータを通して学んでいますが、実際に人間が学ぶときには、転んだり、泣いたり、匂いをかいだりと、身体を通した体験が大きな役割を果たします。番組では、「AIに身体性は必要か?」という問いについて、研究者の間でも意見が割れていると紹介され、“体験の有無”が、AIが本当に人間に近づけるかどうかの分かれ道になることが示唆されました。
偉人がAIに?「人生相談室」で“らしさ”を再現
番組後半には、「偉人AIによる人生相談室」が登場。AIソクラテス、AIマリー・アントワネット、AI織田信長、そしてAIタモリが人生の悩みに答えるコーナーでは、タモリさんが「趣味で集めたものを整理するべきか?」と問いかけると、AIタモリは「じゃあさ、捨てる前に一回並べて酒でも飲みながら眺めてみたら?」と提案。本物のタモリさんが言いそうな雰囲気を見事に再現していて、AIが人間の個性や価値観までも模倣できることに驚かされました。
AGI開発の鍵は「人間の脳の秘密」にあり
専門家によると、人間の脳はたった20ワットの電力で動いているにもかかわらず、対話型AIの開発には都市1つ分の電力が必要といわれています。しかも、AIは何千時間もかけて大量のデータを学習するのに対し、人間は少しの経験で学びます。この差を埋めるために、研究者たちは脳そのものの仕組みを解明しようとしています。最終的に目指されているのが、「AGI(汎用人工知能)」という、人間と同じようにあらゆる状況で柔軟に対応できるAIです。これは、ドラえもんや鉄腕アトムのような存在が現実になる日が来るかもしれないことを意味しています。
AIを知ることは、人間を知ることにつながる
番組のラストでは、「なぜ人はAIを作ろうとするのか?」という問いが投げかけられました。その答えは、AIを作ることで、私たちは自分たち人間のことをより深く知ろうとしているから。知能の正体を探るこの旅は、AIの未来を見つめるだけでなく、人間とは何かを見つけるための旅でもあるというメッセージで締めくくられました。
【内容まとめ(再掲)】
| テーマ | 内容 |
|---|---|
| タモリ×AI初挑戦 | 「怖い」と感じながらも、AI検索にトライ |
| 人間そっくりのAI | Amecaが表情・言葉・考えを再現 |
| 笑いの創造性 | AIが6秒で考えたネタがコントに |
| ブラック・ジャック新作 | AIが医療SFストーリーを提案 |
| 知能と予測 | 人間もAIも「予測」でものを作る |
| AIと感情 | AIで亡き妻と音楽作りを続ける夫の実話 |
| 体験と身体性 | AIは“風”を感じられるのか?身体性の重要性 |
| 偉人AI | ソクラテスや信長がAIでよみがえる |
| AGIへの挑戦 | 脳の理解が次の進化のカギに |
| 人間理解の鏡としてのAI | AI開発は人間を深く知る手段にもなる |
次回の放送でも、私たちが何気なく過ごす日常の中にある「知的な問い」に、タモリさんと山中さんが楽しく迫ってくれることでしょう。科学や技術の世界がもっと身近に、もっと面白くなる1時間半でした。

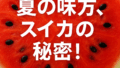
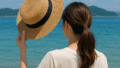
コメント