家庭料理は自動調理器が作ってくれるはずだった?
2025年6月5日放送のNHK総合「未来予測反省会」では、「家庭料理はなんでも自動調理器が作ってくれる」という過去の未来予測をテーマに、当時描かれた理想と現在の現実とのギャップを振り返りました。出演者はシソンヌの長谷川忍さんと影山優佳さん。さらに専門家ゲストとして、和食文化研究者・山下満智子さん、ミシュランシェフ・米田肇さん、ロボット学者・石黒浩さんが参加しました。
1960年代に描かれた“夢のキッチン”とは

今からおよそ60年前、1960年代のアメリカでは「料理は完全に自動化される未来が来る」と多くの人が信じていました。その中でも特に注目されたのが、SF作家で生化学者のアイザック・アシモフが1964年に発表した未来予測です。彼は「2014年には全自動のキッチンユニットが登場するだろう」と語っていました。
アシモフが描いたその未来のキッチンは、ただの調理家電ではありませんでした。ボタンを押すと、お気に入りの料理を選ぶだけで、架空のスーパーシェフが登場。シェフは料理に合わせて、巨大な冷蔵庫から必要な食材を自動的に選び出し、そのまま赤外線などのハイテク技術で加熱。数秒以内にコンベアで料理が運ばれてくるという、今見ても驚くほどのシステムでした。
そのキッチンユニットのイメージは、まさに“未来のレストラン”を家庭に持ち込むものでした。さらに、もう一つの発明として構想されていたのが、貯蔵庫と連動する調理装置です。
-
食材はすべて巨大な貯蔵庫の中に保管されている
-
使用者が一度レシピやスケジュールを設定すると、
-
そのスケジュールに従って機械が自動的に食品を取り出し、
-
それに合わせて加熱・調理・盛り付けまでをこなす
というものでした。
つまり、「朝7時にスクランブルエッグとトースト、12時にチキンサンドとサラダ、夜はシチューとパン」といった1日分のメニューをすべて自動で出してくれるロボット調理人のような存在が想定されていたのです。
このような構想には、当時の技術ではまだ実現できない要素が多く含まれていましたが、それでも人々は未来の家庭が完全に機械化されると本気で期待していたことがわかります。当時の雑誌や見本市などでは、こうした“夢のキッチン”がたびたび紹介され、主婦の負担がゼロになる未来を多くの家庭が思い描いていたのです。
なぜ“夢のキッチン”は現実にならなかったのか

誰もが一度は憧れた「料理がすべて自動でできる未来」。しかし、それはなぜ実現しなかったのでしょうか。番組では、まず技術の限界があったことを大きな反省点として取り上げていました。
1960年代当時は、今ほどロボット技術が発達しておらず、食材を切る・焼く・盛りつけるといった複雑な動作を正確にこなす機械は存在していませんでした。材料の状態や分量、火加減の調整など、人間が感覚で判断するような部分を機械が代わりに行うには、細かな制御技術やセンシング技術が不足していたのです。たとえば、野菜のかたさを見分けて火加減を変えるような技術は、まだ開発途中でした。
-
当時の家電技術は、せいぜい温めや加熱の段階にとどまっていた
-
ロボットアームや人工知能の研究は始まったばかりで家庭用に応用するには遠かった
-
一般家庭に導入できるコスト面でも現実味がなかった
さらにもう一つ大きな要因として挙げられたのが、社会の変化を見誤っていたことです。
1960年代から70年代にかけて、世界中で女性の社会進出が急速に進みました。女性が働くのが当たり前になると、家庭での家事の時間を短縮したいというニーズが高まりました。このとき、理想として期待されたのは全自動のキッチンではありましたが、実際には別の形でニーズが満たされていったのです。
-
スーパーではすぐに使えるカット野菜や下ごしらえ済みの材料が販売されるようになった
-
冷凍食品は年々品質が向上し、レンジで温めるだけで本格的な味が楽しめるようになった
-
レトルト食品の登場により、煮込み料理なども数分で完成するようになった
-
外食チェーンの拡大によって、安くて手早く、一定の味が楽しめる食事が広く普及した
このように、「家庭内での完全自動化」という方向ではなく、外部のサービスや食品技術の進化によって家事の負担が軽減されるという形にシフトしていったのです。
結果として、自動調理器は「夢の家電」としては残りつつも、現実の生活では他の便利な手段に置き換えられていきました。そして現在も、全自動の料理ロボットが当たり前に家庭にあるとは言えない状況が続いています。実現しなかったのは、技術だけでなく、社会の進み方が予想とは違っていたことが大きかったのです。
技術は進んだが「全部自動」はまだ遠い現実
番組では、「特定の料理に限れば、自動調理はすでに可能になっている」と紹介されました。実際、日本では1970年代から、餅つき機や寿司ロボット、パン焼き機などが登場し、家庭や業務用として一定の役割を果たしています。これらの機械は、限られた工程の中であれば人の手を借りずに作業を完了できるという点で、当時の未来予測が一部は現実になっているともいえます。
たとえば、パン焼き機では材料を入れてボタンを押すだけで、こね・発酵・焼き上げまでを1台で行ってくれます。寿司ロボットも、シャリを一定の形に整えて海苔を巻くまでを正確にこなします。こうした機器の登場によって、作業の効率化や品質の安定が実現してきました。
-
餅つき機:もち米を入れれば、蒸す・つくまでを自動で処理
-
パン焼き機:材料を入れるだけで焼きたてのパンが完成
-
寿司ロボット:均一なシャリ玉を高速で成形し、大量調理が可能
ただし、これらの機器に共通しているのは、あらかじめ決まった材料・工程にしか対応できないという点です。たとえば冷蔵庫にある余り物を自由に組み合わせて新しい料理を作るような柔軟性はありません。しかも、下ごしらえや食材の仕分け、盛りつけなどの細かな作業は、いまだに人の手に頼っているのが現実です。
2025年現在、多機能調理家電はさらに進化を遂げています。たとえば、温度管理や蒸気制御、遠隔操作が可能な調理器具も登場しており、レシピ通りに調理してくれる「スマートクッカー」も話題になっています。しかし、それでもすべての工程を自動で行うにはまだ限界があります。
-
食材の皮むきやカットは別の機械が必要
-
盛りつけや配膳は手作業に依存
-
家族の好みや味の調整などは、柔軟に対応しにくい
このように、技術は確実に進歩してきましたが、「家庭料理をなんでも自動で作れる機械」という未来像にはまだ遠いのが現状です。人の手の繊細さや判断力を再現するには、さらなる開発と時間が必要とされています。
技術の進化と、今できること

2025年現在、家庭用の調理家電は大きく進化しており、「全自動」とまではいかないものの、日常の調理を大幅に楽にする家電が次々と登場しています。調理初心者でも失敗しにくく、家族分の料理を簡単に作れる機能が搭載された製品が増えています。
たとえば、アイリスオーヤマの「シェフドラム」は、ドラム型の内釜が自動で回転しながら加熱してくれるため、炒め物や煮込み料理を“放っておいても”作ることができます。火加減の調整やかき混ぜ作業も不要で、材料を入れてスタートボタンを押すだけで済むのが特徴です。
・加熱ムラを防ぎ、均一に仕上げられる回転加熱構造
・炒め物・煮込み・無水料理など幅広い調理モード
・食材を入れるだけで調理が始まる“ほったらかし”調理
また、パナソニックのオーブンレンジ「ビストロ」は、スマートフォン専用アプリ「キッチンポケット」と連動して、その日の食材に合った献立をAIが提案してくれます。アプリで操作すれば、火加減も時間も自動で設定され、段取りも一目でわかります。
・冷蔵庫の中にある食材からレシピを提案
・専用アプリと連動し、献立管理や調理サポートが可能
・レンジ内のセンサーで加熱具合を自動調整
さらに、BOTINKITが開発した「Omni」は、13種類の液体調味料をあらかじめセットしておけば、AIがレシピに応じて自動で分量を調整しながら投入し、調理まで行う本格ロボットです。特に中華料理のような高温・短時間調理を安定して再現できる点が注目されています。
・調味料の自動投入機能で味の安定性を実現
・プロの味を初心者でも再現できる点が評価されている
・本格的な炒めや煮込みにも対応する加熱性能
このように、最新の調理家電は、技術によって「時短」「省力」「失敗しにくい」料理を実現しつつあります。以前のように、すべてを自分の手でやらなければいけなかった時代と比べると、確実に“手間は減っている”といえます。
ただし、完全な自動調理にはまだ距離があります。人の手による味見や盛りつけ、そして「今日は何を作ろうかな」と考える楽しみは、今も私たちの暮らしに残されています。技術が支える“半分自動”の時代が、今なのかもしれません。
家庭より「外」で進んだ調理の自動化
番組では、「家庭内よりもむしろ“外”の世界で自動化が進んだ」という事実にも注目が集まりました。とくに大きな変化が見られたのが、ファストフードや外食産業の自動化です。
現在、多くのファストフード店では調理の一部がすでにロボット化・機械化されており、同じ品質の料理を短時間で安定的に提供できるようになっています。注文から提供までの流れを効率化するため、自動フライヤーや自動盛りつけ装置、食材搬送コンベアなどが導入され、スタッフの負担も大きく軽減されています。
-
ハンバーガーの調理では、パティの焼き加減やタイミングを機械が管理
-
ポテトは自動的に揚げられ、時間や油温も一貫して制御されている
-
ドリンクやソースの分量もマシンが正確に測定・提供
こうした取り組みにより、家庭で料理するよりも「外食の方が手軽でおいしい」という状況が当たり前になりつつあります。特に都市部では、安価で栄養バランスのとれた食事が短時間で手に入ることから、家で1から料理する機会そのものが減ってきているという現実があります。
また、無人店舗やセルフレジ、モバイルオーダーなど、食事の提供プロセス全体が自動化・省人化されていることで、より早く、便利に食べ物を手に入れられる環境が整ってきました。こうした外食の進化に対し、家庭内のキッチンはそこまでの自動化には至っておらず、調理の自由度は高くても、手間や時間はかかるままです。
このように、食の自動化は家庭内ではなく、外食や業務用現場で先に実現したという構図が浮かび上がります。結果として、「家庭料理がなんでも自動で作れるようになる」という未来像は、現実とは違う方向にズレていったといえます。自動化がもたらした便利さは今も進化中ですが、その中心は家庭ではなかったという事実が、当時の予測とは異なる道を示しているのです。
一部の人には“未来のキッチン”がもうすぐそこに
完全自動の家庭料理ロボットは、まだ一般的ではありませんが、それでも希望は確かに残されています。番組に登場したロボット学者・石黒浩さんは、「一部の人が使えるレベルの自動調理ロボットは、それほど遠くない未来に登場する」と語っていました。これは、現実としてすぐに全家庭に普及するわけではないものの、特定の環境や条件に限れば実用化の段階に近づいていることを示しています。
その具体例として紹介されたのが、介護や医療の現場での活用です。高齢者や障がいのある方にとって、毎日の食事作りは大きな負担となることがあります。こうしたニーズに対応するため、限定されたメニューや工程に特化した自動調理機が導入されつつあります。
-
あらかじめ登録された数種類の献立を選ぶと、自動で加熱や盛りつけを行う
-
食材は専用の容器にセットされ、機械が時間管理しながら調理を進める
-
温度や栄養バランスも事前に設定でき、介護食ややわらか食などにも対応
こうした装置はすでに一部の介護施設や個人宅で使われ始めており、“食事の自立支援”としての役割を担っているのです。もちろん、価格や導入のハードル、食材の準備など課題は多くありますが、必要とする人にとっては、手の届く技術になりつつあると言えるでしょう。
また、これまでの未来予測とは違い、「なんでも自由に作れる万能ロボット」ではなく、「必要な人に、必要なメニューだけを、確実に提供する機械」という現実的な方向へと進化している点も注目です。こうした形から始まり、将来的には徐々に応用範囲が広がっていく可能性もあります。
つまり、今の自動調理技術は理想の未来に向けて小さな一歩を着実に踏み出している段階にあるのです。家庭全体が未来型キッチンになるのはまだ先かもしれませんが、一部の人にとってはすでに“未来”が身近な現実になりつつあるのです。
終わりに
「未来予測反省会」は、ただのノスタルジー番組ではなく、夢を描いた過去と今の現実を照らし合わせることで、次の一歩を考えるヒントを与えてくれます。今回のテーマ「家庭料理はなんでも自動調理器が作ってくれる」は、完全実現には至っていないものの、今後の技術と社会の変化次第では、また違った形で夢が叶う可能性もあります。
次回もどんな「外れた未来予測」が登場するのか、期待が高まります。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

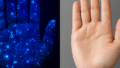

コメント