参院選まで1週間 各党が語るコメ・政治とカネ・外交・家族制度
2025年7月13日放送の「日曜討論」(NHK総合)では、参議院選挙の投開票を1週間後に控え、各党の幹部が政策の違いや争点について語り合いました。注目されたのは「コメ政策」「政治とカネ」「日米関係と関税問題」、そして「選択的夫婦別姓」。候補者の顔ぶれは与野党を代表する幹事長や代表クラスが揃い、選挙前の姿勢が浮き彫りになりました。
コメ政策と農政の転換
今回の討論で最も多くの時間が使われたのが、コメの価格と農業政策のあり方についてでした。現在、全国的にコメの価格が下がっていて、5キロあたり157円の値下がりが報告されています。その原因として、需要よりも生産が追いついていない状況が指摘されており、安定供給の見通しや農家の収入の確保が大きな課題となっています。
自民党は、価格の安定と供給の確保を大事にするとして、棚田や中山間地での米作りに対しても予算を配分し、地域全体の農業を支えていく姿勢を見せました。立憲民主党と共産党は、農家の収入を守るためには所得補償制度の強化が必要だとし、生活が成り立つ農業の再構築を提案しています。
一方、維新の会や参政党は、農業をより自由な形にしていくことが重要とし、株式会社などの民間参入や規制の見直しを強調。新しいプレーヤーを農業に引き込むことで生産性の向上を目指しています。公明党は、機械化や大規模化によって農業を効率化させる必要性を訴え、作況指数に代わる新たな収穫予測制度の導入にも取り組む方針を示しました。
国民民主党は、これまでの農政を「失敗だった」と認めつつ、中間層や農村の再建に向けて政策を見直すと述べました。共産党と社民党は、家族農業や小規模農家を重視し、個別保障制度の復活とともに、農業予算の増額を求めました。特に社民党は「ミサイルよりコメ」というキャッチフレーズを掲げ、農業こそが国の安全保障だと主張しています。
れいわ新選組は、農林関係の予算を倍に増やすとし、農家がつくった作物をすべて国が買い取る制度を提案。高齢化が進む農業の現場で、若者が継ぎたくなる仕組みを作る必要があると訴えました。参政党は、これまで続けられてきた減反政策をやめて生産量を増やし、余ったコメは備蓄や海外支援に活用するという新しい出口戦略を提示しました。
また、日本保守党は、農業法人の制度見直しとともに、外国資本による農地取得に対する規制の強化を求め、農業の主導権を国内にしっかり取り戻すべきだとしました。
以下は、各党の農政に対する基本的な立場をまとめた表です。
| 政党 | 主な主張 |
|---|---|
| 自民党 | 安定的生産と価格を目指し、棚田・中山間地の維持にも予算配分 |
| 立憲民主党 | 所得補償制度を強化、農家の生活を保障 |
| 維新の会 | 株式会社の農業参入を進め、農業の成長産業化 |
| 公明党 | 農業の機械化・大規模化、収穫予想の新制度導入 |
| 国民民主党 | 中間層と農村保護、農政の失敗を認め再建を |
| 共産党 | 減反政策の見直し、家族農業と地域維持を重視 |
| れいわ新選組 | 農家の作物を全量買い上げ、予算倍増 |
| 参政党 | 減反廃止、生産拡大と海外支援活用 |
| 日本保守党 | 外国資本の農地取得を規制、法人農業見直し |
| 社民党 | 「ミサイルよりコメ」を掲げ、個別補償制度を推進 |
政治とカネの透明性をめぐる議論
番組では、政治資金のあり方が大きな争点として取り上げられました。特に注目されたのは、政策活動費の廃止やパーティー券の購入者情報の公開基準についてです。すでに一部の制度改正には各党が合意しているものの、企業・団体献金の扱いについては、政党ごとに大きな温度差があることが浮き彫りになりました。
立憲民主党や共産党、れいわ新選組、参政党などは、企業や団体による献金には問題があるとし、全面禁止を訴える立場をとっています。こうした政党は、お金によって政策が左右される構造を断ち切ることが政治改革の基本だとしています。とくに共産党は、企業献金には賄賂性があり、国民の参政権をゆがめるものだと指摘しています。
一方、自民党や公明党、日本保守党などは、献金そのものを悪と決めつけるのではなく、「透明性の向上」や「金額の制限」を重視すべきだという考え方を示しました。自民党は、企業献金については公開を前提にして透明性を高めることで信頼を回復すべきとしています。公明党も、禁止すればかえって不透明な資金の流れを生む可能性があるとして、一定の規制をかけながらバランスを取る方向性を示しました。
国民民主党は、政党の会計処理に関する独立したルールである「政党法」の制定を提案し、お金の出入りを一元的に管理するべきだとしています。このルールにより、受け手側にも責任を課すことで、政治全体の透明性が高まると主張しました。
また、社民党は、企業や団体からの献金が労働政策をゆがめてきたとし、雇用や賃金のあり方にまで影響を及ぼしてきた歴史を踏まえ、禁止が必要だとしています。れいわ新選組も同様に、自民党の政策の背景にあるのが企業献金であり、これは国民を貧しくしてきた元凶のひとつだと強く批判しました。
参政党は少し異なる視点から、企業・団体献金を廃止したうえで、国民の所得を引き上げてから政党交付金制度でまかなうべきと提案。国民一人ひとりが納得して政党にお金が流れる仕組みをつくることが大事だとしています。
日本保守党は、全面的な禁止には否定的ですが、寄付の総額や受け取り側の上限を縮小していく方向で見直すべきだと述べ、サイズダウンによる健全化を目指す立場です。
以下に、各政党の姿勢をまとめた表を再掲します。
| 政党 | 寄付・献金に対する姿勢 |
|---|---|
| 自民党 | 企業献金は公開性強化が必要 |
| 立憲民主党 | 個人献金化を進める |
| 維新の会 | 団体献金禁止で改革実現 |
| 共産党 | 金で動く政治の転換 |
| れいわ新選組 | 禁止が国民の利益に合致 |
| 国民民主党 | 政党法によるお金の流れ管理 |
| 社民党 | 労働政策ゆがめる要因として禁止主張 |
| 参政党 | 所得アップと政党交付金を財源にすべき |
| 公明党 | 一定の規制は必要だが禁止には慎重 |
| 日本保守党 | サイズダウンを検討するが一律禁止には否定的 |
このように、「禁止か」「公開か」という対立軸に加えて、国民との関係性の再構築や政党の制度設計そのものにまで踏み込む提案が見られたのが、今回の討論の特徴でした。政治資金の透明性をどう確保し、信頼できる政治に近づけるのか――その議論が深まる契機となる内容でした。
選択的夫婦別姓の議論
今回の討論では、家族の形や個人の権利に関わる話題として、「選択的夫婦別姓制度」についても意見が交わされました。これは、結婚後も夫婦が同じ姓を名乗らなくてもよくなる制度で、あくまで「選択的」な導入を目指すものです。
この制度に対して、各党の立場は明確に分かれました。
まず、立憲民主党・共産党・社民党・れいわ新選組は賛成の立場をとり、「選択の自由を尊重し、希望する人が旧姓を使える社会が必要」としています。特に立憲民主党は「選択肢を広げることで個人の権利を守る」ことを強調し、共産党は「現状は強制的な改姓であり、差別にもつながっている」と問題提起しました。社民党やれいわ新選組も、これを時代に合った制度改革だと位置づけ、早期の実現を求めました。
一方で、参政党と日本保守党は明確に反対を表明しました。参政党は「世論調査で現状維持が多数派である」とし、家族制度の分断を招く恐れがあるという考えを示しています。日本保守党も「現状でも不便はない。制度変更の必要性が感じられない」との立場を取りました。
自民党・公明党・日本維新の会は「慎重に議論を続けるべき」とし、明確な賛否を示さずに国民の意見を聞きながら党内議論を深めるとしました。自民党は「党内でも意見が分かれており、引き続き丁寧な議論をしていく」としています。公明党は制度導入には前向きながらも、「現状維持を望む声が多いことも踏まえて慎重に進めたい」とバランスをとる姿勢を見せました。
以下の表に各党の立場をまとめました。
| 賛成 | 反対 | 慎重 |
|---|---|---|
| 立憲民主党・共産党・社民党・れいわ新選組 | 参政党・日本保守党 | 自民党・公明党・維新の会 |
今回の議論では、制度としての導入が国民生活にどう影響するか、また個人の自由と家族の一体感のどちらを重視するかといった価値観の違いが浮かび上がりました。選択的夫婦別姓は、単なる制度改革ではなく、時代に合った家族のあり方や多様性をどう受け入れるかという日本社会全体の課題として、今後も議論が続くテーマとなりそうです。
米国との関税交渉と外交方針
今回の討論では、トランプ大統領による関税引き上げ通告が大きな焦点となりました。もし実施されれば、8月1日から日本製品に25%の追加関税がかかる可能性があり、自動車や鉄鋼業などへの影響が懸念されています。こうした中、各党は日本政府の外交姿勢と今後の対応策について、それぞれの立場を明確にしました。
自民党は、すでに結ばれている日米貿易協定を基盤に、閣僚レベルでの交渉を重ねるべきだとし、「粘り強く交渉を続ける姿勢が重要」としました。国内対策としては、中小企業や資金繰りへの緊急支援なども検討していると述べています。
一方、立憲民主党・共産党・れいわ新選組は、アメリカとの2国間交渉だけでは不利な立場に追い込まれると指摘し、「国際的な枠組みでの多国間交渉が必要」だと主張。特に共産党は、今回の関税通告について「ルールを無視した一方的で無法なやり方」と強く非難し、WTOや国際的ルールに基づいた対応を求めました。
維新の会・国民民主党は、国際協調を重視する姿勢をとりつつも、国内への打撃を最小限にするために、緊急的な内需拡大策や雇用対策が必要だと述べています。国民民主党は特に、自動車業界への影響を最重要課題とし、「消費税5%への引き下げや税制の簡素化」をあわせて提案しました。
公明党は、関税による影響が直撃する中小企業や地域経済を守る対策が最優先だとし、首脳同士の対話の必要性にも言及。選挙後にトランプ大統領との会談を総理が主導すべきだと提案しました。
一方、日本保守党は、今回の交渉に対し、単なる関税だけの問題ではなく「中国との安全保障の構図も背景にある」と指摘し、アメリカとの信頼関係を重視しつつ、資源購入などの対価を用意して交渉を進めるべきとしました。
参政党は、トランプ大統領の行動には背後にある思想的・戦略的な目的があると理解した上で、日本も外交ビジョンを持って対応すべきだと主張。アメリカの関税政策を単なる脅しと見なさず、「世界の再設計の一部としてとらえる視点が必要」としました。
社民党やれいわ新選組は、こうした貿易摩擦が最終的に国内の労働者を直撃することへの危機感を表明。とくに社民党は、かつてのリーマン・ショック時のような「派遣切りや使い捨て労働」が再発しないよう、雇用を守るための対応を政府に強く求めました。
以下に、各党の関税問題への対応方針をまとめた表を再掲します。
| 政党 | 関税問題へのアプローチ |
|---|---|
| 自民党 | 日米協定を土台に閣僚間で交渉 |
| 立憲・共産・れいわ | 米一国依存から国際連携へ |
| 維新・国民民主 | 多国間交渉+国内対策強化 |
| 公明党 | 中小企業・雇用対策が急務 |
| 日本保守党 | 対中戦略との連携を重視 |
| 参政党 | トランプ政権の背景を理解した対応 |
今回の関税交渉は、単なる貿易の問題にとどまらず、日本の経済・外交戦略、さらには安全保障政策にまで関わる大きなテーマです。どの政党の考えが、私たちの生活や仕事にどう影響するのか、注目して見極める必要があります。
選挙戦の残り1週間、各党が訴えるもの
討論の締めくくりとして、各党が残り1週間の選挙戦で国民に伝えたいメッセージと、特に訴えたい政策について語りました。どの政党も共通して言及したのは、物価の高騰にどう対応するか、生活をどう支えるか、そして雇用や社会保障をどう安定させるかといった、日々の暮らしに直結するテーマでした。
自民党は、長期的な視点で将来に責任を持つ政策を掲げ、今後の日本の進むべき道を明確にすることが必要だと主張しました。立憲民主党は、物価高や雇用不安に苦しむ人たちに対し、安心できる社会保障制度の構築と雇用環境の安定化を訴えました。
日本共産党とれいわ新選組は、消費税の廃止とインボイス制度の撤廃を強く求め、手取りの増加と消費の促進を通じて経済の回復を目指す方針を明確にしています。共産党はさらに、多様性の尊重と人権保護にも触れ、包摂的な社会を目指すと述べました。
一方、日本維新の会は、社会保障制度の見直しや地方分権の強化を通じて、構造改革を進める必要があるとしています。公明党は、給付と減税の両方を組み合わせた生活支援策を迅速に実施するとして、暮らしの底上げに注力する姿勢を見せました。
国民民主党は、「年収の壁」を178万円に引き上げる提案や、インボイス廃止、子育て世代への支援など、現役世代を豊かにすることを中心に政策を構成しています。
参政党は、過度な外国人労働力の受け入れの見直しや安全保障の強化を訴え、日本人中心の政治を掲げています。日本保守党は、**消費税の減税とエネルギー政策の転換(再エネ賦課金の廃止・火力発電推進)**を提案し、経済と安全保障の両面からの立て直しを図っています。
社民党は、非正規労働者の問題を重く見ており、安定した雇用と正当な賃金、そして人権の尊重を最も重要なテーマとして打ち出しました。
以下に、各党の主張を簡潔にまとめた表を示します。
| 政党 | 訴えたいこと |
|---|---|
| 自民党 | 将来責任を持つ政策 |
| 立憲民主党 | 物価・雇用・社会保障の安心 |
| 維新の会 | 社会保障改革と地方分権 |
| 公明党 | 減税と給付で暮らし支援 |
| 国民民主党 | 年収壁の引き上げ、現役支援 |
| 共産党 | 消費税廃止と多様性尊重 |
| れいわ新選組 | 消費拡大・経済復興 |
| 参政党 | 移民抑制と安全保障強化 |
| 日本保守党 | 消費税減税・再エネ見直し |
| 社民党 | 雇用安定と人権尊重 |
今回の「日曜討論」では、コメの価格や農業、政治資金の透明性、日米関係から家庭制度まで、幅広いテーマが議論されました。どの話題も私たちの日常生活に深くかかわっており、一票が暮らしを左右する時代であることを改めて感じさせられる内容でした。選挙まで残りわずか。各党の訴えをじっくり見比べながら、自分の未来につながる選択をしていきたいところです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


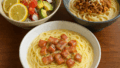
コメント