生きもの子育てスペシャル
2025年7月20日に放送された「ダーウィンが来た!」は、“子育て”をテーマに、世界中のさまざまな生きものたちの暮らしに迫るスペシャル回でした。子どもを守るために工夫をこらしたり、群れで協力したり、人間の影響を受けながらも懸命に命をつないでいたりと、生きものたちの子育ては本当に多彩で奥深いものです。番組では3章に分けて、それぞれの世界を紹介していました。
驚きのテクニック!赤ちゃんを守る子育ての知恵
自然界では、ただ産んで終わりではなく、親が自ら動いて子どもたちを守る姿がたくさんあります。
ヤドクガエルの背中でお引越し
南米・フランス領ギアナの密林に住むアイゾメヤドクガエルは、陸地に卵を産みます。ふ化したオタマジャクシを1匹ずつ父親が背中にのせ、別々の水場へ移動させます。これは、全員が一か所にいると病気や天敵で全滅するリスクがあるため、リスク分散のためと考えられています。木の高い場所にある水たまりにまで運ぶ姿は、とても印象的でした。
しかもその水たまりには、別のカエル(ジュウジメドクアマガエル)のオタマジャクシがおり、ヤドクガエルの子どものえさになるという、自然の厳しさも描かれていました。
口の中で卵を守る魚たち
インドネシア・バンガイ諸島の海では、バンガイカーディナルフィッシュの父親が卵を口の中で守っていました。この間、何も食べずにずっと卵を守るという健気さが際立ちます。ふ化までの約1週間、ひたすら我慢を続けて命をつなぐ姿は、驚きと感動を呼びました。
他の魚に育てさせるナマズの戦略
アフリカの湖では、カッコウナマズという魚が、他の魚(シクリッド)の口内保育に自分の卵を紛れ込ませる托卵をしていました。ナマズの卵は早くふ化し、シクリッドの赤ちゃんを食べてしまいます。この戦略は、鳥のカッコウにも見られるものですが、魚の世界でも同じような方法があることに驚かされます。
撮影の舞台裏も紹介
木に登るヤドクガエルの撮影は、ロープにカメラを吊って追いかけるという工夫で行われました。生きものにストレスをかけず、自然な姿を映すための苦労も伝えられました。
成長を支える仲間と家族の力
子どもを産んだあとも、長く見守りながら成長を手助けする生きものたちの姿が紹介されました。
群れで子育てをするリカオン
アフリカ・ザンビアのリカオンは、複数の家族が集まって群れをつくり、共同で子育てと狩りをしています。若い個体は狩りの経験が少なく、アフリカスイギュウを相手に仕掛けたこの日も、若者の一部が早く飛び出してしまい、うまく連携できず失敗に終わりました。
それでも、こうした失敗から学ぶことが多く、群れで行動することが若者たちの成長の糧になっていることがよく伝わりました。
おばあちゃんシャチが教える狩りの知恵
オーストラリア・ブレマーベイ沖の海では、シャチの家族が一緒に狩りを行い、子どもたちに技を伝えていました。なかでもおばあちゃんシャチは、長年の経験から獲物の動きを予測し、うまく仕留める方法を若い個体に教えていました。
シロナガスクジラのような大型の獲物にも、息継ぎできないように押さえつけて動けなくするという技を見せ、子どもたちはそれを実際に試して成功させていました。
環境の変化で変わる子育ての現場
自然の中だけでなく、人間の活動が影響を及ぼす子育ての現場も取り上げられました。
モンゴルの草原に生きるアネハヅル
モンゴルの広大な草原に暮らすアネハヅルは、夫婦で子育てをしています。しかし近年、家畜のヒツジが急増し、草原に入り込むようになりました。その結果、ヒツジが卵を踏んでしまう事故が起きているとのことです。
それに対してアネハヅルは、自分たちの巣を守るためにキックして追い払う姿も確認されました。人間の影響で、親鳥がより積極的に守る必要が出てきたのです。
ゴミの中で産卵するペールオクトパス
メルボルン近郊の海では、ペールオクトパスが人間の捨てたゴミの中に卵を産んでいました。海底に散らばる瓶や缶の中が、産卵場所になっていたのです。ふ化を見届けたあと、母親はそこで一生を終えます。
本来の環境とは違う場所で命を終える姿に、私たち人間の行動がどれほど自然に影響しているのかを改めて考えさせられました。
日本の絶滅危惧種・アマミノクロウサギの今
番組後半のダーウィンNEWSでは、日本国内の絶滅危惧種についての最新情報が紹介されました。
マングース駆除で復活の兆し
日本には約3500種の絶滅危惧種がいますが、その中の1つであるアマミノクロウサギの個体数が回復していることが取り上げられました。これは、外来種マングースの駆除が成功したことによるものです。
5年かけて大人になる希少な存在
一般的なノウサギが1年で大人になるのに対し、アマミノクロウサギは5年もかかるという特徴があることも明らかになりました。時間がかかるからこそ、安定した環境でじっくり育つことが大切だと感じられます。
今回のスペシャル回は、命をつなぐ努力と工夫のかたちが本当にさまざまであることを教えてくれる内容でした。次回の「ダーウィンが来た!」でも、どんな生きものたちに出会えるのか楽しみです。
世界の意外な子育て戦略を比べてみよう

ここからは、私からの提案です。地球上にはさまざまな生きものが暮らしており、親から子どもへの育て方も本当にバラバラです。哺乳類や鳥だけでなく、魚やカエル、さらにはタコのような無脊椎動物まで、子どもを守り育てる方法はそれぞれの環境に合わせて工夫されています。ここでは、生きものの分類ごとに変わった子育ての方法を紹介します。
哺乳類:野生の犬が子育てを“調整”する
インドネシアにいる野犬たちは、子犬が生まれると母犬が「アクティブケア」と「パッシブケア」を使い分けながら子育てをしています。アクティブケアとは、授乳や毛づくろいのように直接関わるケアのことです。パッシブケアは、そばにいて見守ったり、じっと休ませたりするような接し方です。子犬がまだ小さいころはアクティブケアを多く行い、大きくなるにつれてだんだん減らしていきます。その分パッシブケアを少しずつ増やして、母犬の体への負担を調整していることが研究でわかっています。
鳥類:皇帝ペンギンはみんなで温める
南極の皇帝ペンギンたちは、氷点下の寒さの中で卵を守ります。気温が−17℃を下回るような過酷な環境でも、オスたちは丸く集まって、風を避けながら交代で卵を温め続けます。この集まりを「ハドル」と呼びます。ペンギンたちは身を寄せ合って、自分たちの体温で内側の温度を20℃以上に保ち、卵が凍らないように協力して暖めています。気温や風向きによって位置を変えることもあり、まるで動く壁のように全体で温度をコントロールしています。
魚類:口の中で赤ちゃんを守る魚もいる
バンガイカーディナルフィッシュなど、魚の中には「口内保育」と呼ばれる方法で子育てをする種類がいます。卵をくわえたままの親魚は、ふ化するまでの1〜2週間ほど何も食べずにじっと卵を守り続けます。この期間はストレスや飢えとの戦いでもあります。さらに、一部の魚は長く口に入れている間に、兄弟の中で弱い個体を食べて栄養を得ることもあります。こうすることで、限られた数の子どもがより健康に成長できる可能性が高まるのです。
両生類:母ガエルがえさを与える
ストロベリーポイズンフロッグというカエルは、オタマジャクシに「栄養卵」と呼ばれる未受精の卵を与えて育てます。この栄養卵は、オタマジャクシのえさとなるだけでなく、将来毒を持つ体を作るためにも役立ちます。このカエルはオタマジャクシを1匹ずつ別の水たまりに移動させる習性もあり、母親は定期的に水たまりを巡回しながら各地に栄養卵を運ぶという手間のかかる子育てをしています。
無脊椎動物:タコはゴミの中で命をつなぐ
ペールオクトパスという種類のタコは、人間が捨てた空き瓶や缶の中に卵を産みます。自然の岩場や海藻に代わって、ゴミが産卵場所になっているのです。母ダコは卵がかえるまで一切の食事をせず、外敵から守るために瓶の入り口をふさぎながら何週間もじっとその場にとどまります。子どもたちがふ化すると、自分の命を終えるという一生のサイクルがそこにあります。人間の生活が、思わぬかたちで海の生きものの生態と関わっていることがわかります。
このように、自然界では親が子どもを守るためにそれぞれ違った工夫をしています。生きのびるために進化してきた方法は、私たちが考える“子育て”のイメージを大きく超えるものばかりです。生きものたちの知恵と行動には、まだまだ知られていない発見がたくさんあるのです。


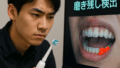
コメント