夏の夜にぞわぞわ!怖い生きもの大集合
2025年8月3日にNHK総合で放送された『ダーウィンが来た!』は、夏の夜にひそむ「ちょっと怖い」生きものたちをテーマにした回でした。世界各地から集められた不思議な姿や驚くべき生態の動物たちが続々と登場し、ぞわぞわするけど目が離せない内容でした。番組では、視覚だけでなく聴覚や嗅覚など、さまざまな感覚を使って生き延びる生きものたちの工夫や、夜の生き残り戦略が紹介されました。
細長い指で虫を探るマダガスカルのアイアイ
マダガスカルに暮らすアイアイは、まるで木の医者のような動きで虫を探します。長くて細い中指を木にトントンと当てて、中の音の違いから虫の居場所を見つけます。穴を見つけるとその細指を差し込み、中の虫を引き出して食べます。その姿はちょっと不気味ですが、木の中にいる虫をピンポイントで捕まえるすごい技術です。
まるで宇宙生物!?エイリアンフィッシュの戦い
アメリカ・カリフォルニア州に生息するエイリアンフィッシュは、口を開くと一気に膜が広がり、その姿がとても不思議です。この大きな口はオスだけにあり、住処となる貝殻を奪い合うために使われます。戦いはまるで異星人のような迫力で、水中のドラマが展開されていました。
サバンナの夜にライオンがゾウを追う
アフリカの夜、サバンナでは30頭ものライオンが1頭のゾウを追いかける場面が紹介されました。狙われたゾウは必死に逃げますが、ライオンたちはしつこく追いかけます。もしゾウを仕留められれば、ライオンの群れ全員が1週間以上食いつなげるほどのごちそうになるのです。自然の中での命がけの攻防が、リアルに映し出されました。
100万匹以上のグンタイアリが見せる連携プレー
エクアドルに登場したのはグンタイアリの大群です。その数は100万匹を超え、役割分担も明確です。獲物を狩る係、道を作る係、仕留めた獲物を運ぶ係、さらに外敵から守る用心棒までいます。この統率の取れた動きは軍隊のようで、まさに「生きた軍団」といえる存在でした。
オオスズメバチとミツバチの壮絶な攻防
日本でもおなじみのオオスズメバチは、巨大なあごで木の皮を食い破るほどの力を持ちます。番組では、たった20匹ほどのスズメバチが6000匹を超えるミツバチの巣を襲撃し、壊滅状態に陥れる様子が映し出されました。女王蜂がたった一匹でスタートさせた巣が、大きな群れになるまでの苦労も描かれ、命の営みの厳しさが伝わりました。
昆虫を操る寄生バチの驚きの生態
テントウムシの体内に卵を産みつけるテントウハラボソコマユバチ。その幼虫はテントウムシの体内で育ち、最終的に外に出て繭を作ります。このとき、テントウムシは動けない状態でも繭の守りとして機能します。番組では、寄生バチが昆虫の行動まで操る例として紹介され、昆虫の世界の深さに驚かされました。
かわいい癒やし系生きものも登場
怖い生きものたちだけでなく、癒やし系の動物たちも紹介されました。雪の妖精とも言われるシマエナガや、空を滑空するエゾモモンガ、吸盤で岩にくっつくダンゴウオなど、小さな体でユニークな姿を見せる生きものたちに心がなごみました。
血を主食とするチスイコウモリの不思議な生活
コスタリカでは、地面を跳ねるように移動するチスイコウモリが紹介されました。ブタの背にそっと乗り、耳の裏の血管を狙って血を吸います。吸う時には痛みを感じにくくする麻酔のような成分を唾液に含んでいるため、ブタは気づきません。仲間に血を分けるという習性もあり、コウモリの社会性の一面が見えました。
おまけコーナー「生きものだもの」でマヌ子ママとツノミンが登場
番組の締めくくりは「マヌールのゆうべ」の定番コーナー、「生きものだもの」。マヌ子ママとツノミンが、今回もゆるく生きものの魅力を紹介してくれました。
今回は「ぞわぞわ」しながらも、思わず引き込まれる不思議な生きものたちが勢ぞろいした回でした。怖いけれど美しく、知らない世界を見せてくれるダーウィンが来た!ならではの内容でした。生きものの多様さと、自然の奥深さを改めて感じさせられる30分でした。
この番組を見て感じたこと
今回の『ダーウィンが来た!』は、まさに夏の夜らしいぞわっとする生きものたちが次々登場し、映像からでもその存在感や迫力が伝わってきました。特に印象に残ったのは、マダガスカルのアイアイの細長い中指の使い方です。木をトントンと叩きながら虫の位置を探し当てる姿は、最初は不気味に見えますが、その精密さに驚かされました。
水中ではエイリアンフィッシュが巨大な口を広げて住処を奪い合う場面が迫力満点で、まるでSF映画を見ているようでした。サバンナでライオンがゾウを追う場面も圧巻で、自然界の食物連鎖の厳しさがリアルに映し出されていました。
エクアドルのグンタイアリの大群が見せた役割分担の連携プレーは、数の多さだけでなく組織的な動きに感心させられます。日本で身近なオオスズメバチとミツバチの攻防も緊張感があり、自然の中で生きることの過酷さを改めて感じました。
寄生バチがテントウムシの行動を操る不思議な生態や、チスイコウモリの巧みな吸血方法も衝撃的で、昆虫や小型哺乳類の世界の奥深さを知ることができました。一方で、シマエナガやエゾモモンガ、ダンゴウオといった癒やし系の生きものが登場し、緊張感のある映像の中にやさしい時間も流れました。
全体を通して、「怖い」だけでなく、自然界の美しさや知恵、そして多様さがしっかり伝わる構成で、夏の夜にぴったりの内容でした。見終わったあとも、生きものの世界の奥深さと、人間が知らない生態の豊かさをずっと考えさせられる回でした。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

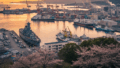
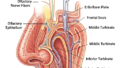
コメント