子ども研究者スペシャル 海の賢者と森の宝石
NHK総合で放送された「ダーウィンが来た!」子ども研究者スペシャルは、自然や生きものを自ら調べる小中学生が登場し、その情熱あふれる研究の様子を紹介しました。今回は、海の賢者・タコと、森の宝石・ルリセンチコガネという、まったく異なる環境に生きる2種類の生きものがテーマです。どちらも見た目の美しさや不思議な能力で知られていますが、研究を通してその奥深さが明らかになりました。この記事では放送内容を詳しく振り返り、研究者たちの挑戦や成果を分かりやすくまとめます。
タコと友達になるための挑戦
最初に登場したのは、静岡県に住む小学4年生の野中風玖さんです。風玖さんが研究しているのは、海の賢者とも呼ばれるマダコ。彼は自宅で「うーちゃん」という名前をつけたマダコを飼育しています。タコは水質に極めて敏感で、一般の家庭はもちろん、プロが管理する水族館でさえ長期飼育が難しいとされる生き物です。
それにもかかわらず、風玖さんは毎日海に通い、新鮮な海水を1日おきに自宅へ運び、見事64日間の長期飼育に成功しました。この並外れた情熱のきっかけとなったのは、ある日の水族館での出来事です。タコの水槽の前で手を振ったところ、まるで返事をするかのようにタコが足を動かしてくれたのです。その不思議で心温まる体験から、「タコとハイタッチしたい」という大きな夢が生まれました。
番組はこの夢を叶えるため、タコ研究の第一人者である琉球大学の池田譲博士を訪ねました。博士は、タコと仲良くなるための重要な条件を2つ提示します。1つ目は「顔を覚えてもらう」こと。タコは「海の霊長類」とも呼ばれるほど知能が高く、形や特徴を正確に記憶できる能力を持っています。2つ目は「一緒に遊ぶ」こと。知能の高い動物は、遊びを通じて相手との信頼関係を深める性質があるのです。
実験で深まるタコとの絆
条件を聞いた風玖さんは、早速行動に移しました。毎日欠かさず水槽の前に立ち、手を振ったり、間近で自分の顔を見せたりして、うーちゃんに存在を覚えてもらう取り組みを始めたのです。根気強く続けた結果、わずか1週間ほどで、うーちゃんが風玖さんを識別できるようになりました。
次の課題は、タコと楽しめる共通の遊びを見つけることです。試行錯誤を重ねた末、ボール遊びがタコの興味を強く引くことに気付きました。水槽越しにお互いボールを押し合うように遊び、二人の距離は一気に縮まりました。
そして迎えた夢のハイタッチの瞬間。通常、タコが直接人間に触れることは命の危険を感じさせるため避けられますが、風玖さんがそっと手を差し出すと、うーちゃんは蛸壺の中から足を伸ばし、自ら手に触れてきたのです。
さらに、タコが持つモノマネ能力を活かし、風玖さんはボールを持って離す動作を実演。すると、うーちゃんも同じ動きをして、まるでキャッチボールをするように遊べるまでになりました。この一連の実験について、池田博士は「タコの知的側面や社会性を引き出す素晴らしい実験」と高く評価しました。
奈良公園の森で宝石を守る
次に登場したのは、奈良県の中学2年生、矢野心乃香さんです。彼女が研究しているのは、奈良公園に生息する美しい昆虫、ルリセンチコガネ。その体は青く輝き、「森の宝石」とも呼ばれています。しかし近年、その数が目に見えて減少しており、心乃香さんは強い危機感を抱きました。
減少の大きな原因のひとつは、観光客の増加です。多くの人が訪れることで、地面に落ちたシカのフンが踏みつぶされてしまい、糞虫たちが利用できなくなっているのです。ここ1〜2年の間に個体数は急激に減り、このままでは姿を消してしまう可能性もあります。そこで彼女は、「減少するルリセンチコガネを増やす」という研究テーマを掲げました。
番組の協力を得て、心乃香さんはルリセンチコガネの地中での暮らしを詳しく観察することにしました。糞虫の仲間は一般的に、フンを丸めて糞球を作り、それを巣穴に運んで卵を産みつけます。ルリセンチコガネの場合、その巣穴は深さ60cmにも達し、これはモグラやアリの巣よりもはるかに深い構造です。
さらに、オスとメスが協力して糞球を運び込み、その中に産みつけられた卵から生まれた幼虫は、約1年間その糞球の中でフンを食べながら成長します。この長い成長過程と独特な生態が、ルリセンチコガネの魅力であり、同時に保護活動の難しさでもあります。
生態観察の難しさと魅力
心乃香さんは、地中深くに隠された糞球を見つける作業に何度も挑みましたが、その深さや位置を正確に予測するのは非常に難しく、簡単には見つかりませんでした。彼女は「虫の気持ちがわからないから、そこが一番難しい」と率直に語ります。
それでも、観察を続ける中で新しい発見や疑問が次々に湧き上がり、その探究心はますます強くなっていきました。未知の世界を知る面白さに引き込まれ、「やめることはできない」と断言します。
この経験を通して、彼女はルリセンチコガネの個体数減少を食い止めるために、環境を守り、観光地での人間活動と生態系保全を両立させる必要性を強く感じるようになりました。研究の一歩一歩が、森の宝石を未来へ残すための確かな道筋となっているのです。
まとめ
今回の放送は、年齢に関係なく自然への興味と行動力があれば、専門家も驚く発見や成果が得られることを示していました。風玖さんのマダコ研究では動物との信頼関係を築く方法が、心乃香さんの糞虫研究では身近な環境の変化が生態系に与える影響がわかりました。どちらも身近に感じられるテーマでありながら、奥の深い内容です。視聴者にとっても、自分の住む地域や興味のある生きものを改めて見つめ直すきっかけになったのではないでしょうか。
番組を見て感じたこと
マダコと人間が心を通わせる瞬間を見て、海の生きものが持つ驚くほどの賢さと、思わず温かい気持ちになる優しさに深く感動しました。水中という異なる世界に暮らす生きものと、人間の間に、こんなにも自然な交流が生まれることに、ただただ驚かされます。
特に印象的だったのは、まだ小学生である彼が、日々の努力と観察を積み重ね、少しずつ信頼関係を築いていく過程です。海に通い、新鮮な海水を運び、タコの習性を理解しようとする姿は、まっすぐで力強いものでした。その情熱と好奇心が、やがて科学的な発見につながっていく様子は、大人にとっても大きな刺激になります。
私たちもまた、身近な自然や生きものにもっと関心を持ち、向き合うことで、予想もしない発見や感動が得られるのではないかと感じました。こうした姿勢こそが、新しい知識や理解を広げる第一歩なのだと思います。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


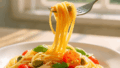
コメント