かわいくて最強!?イモリのひみつに大接近
2025年7月13日放送の「ダーウィンが来た!」では、ちいさくてのんびり屋さんに見えるイモリの驚きの力に注目。東京では絶滅が心配される中、人の手で守られているイモリの暮らしをじっくり観察しました。陸と水のどちらでも生きるイモリの姿、恋の不思議な方法、そして赤ちゃんたちの知られざる生活まで、いままで知らなかったことがたくさん登場しました。
スーパー生物!?イモリのすごい体のひみつ
池と雑木林を行き来する暮らし
イモリは、田んぼや池、そしてその周りの雑木林など、水と陸の両方がある自然の中で暮らしています。水の中では泳ぎながらエサを探し、陸では落ち葉の下や石のすき間に身をひそめて生活します。こうした生活をするため、体はとても柔らかくて動きやすい形をしています。
東京などの都市では自然が減ってしまい、イモリの数も少なくなってきています。そのため、池を新しく作ったり、森を手入れしたりして、イモリが安心して暮らせる環境を整える活動が続けられています。人の手で守られているイモリの住まいは、自然と人とのつながりを感じさせてくれます。
一匹ずつちがうおなかの模様
イモリは、おなかに赤と黒の模様がありますが、よく見ると模様は一匹ずつまったく違います。この模様を見れば、その個体がどのイモリなのかを見分けることができます。まるで人の顔のように、それぞれに個性があるのです。研究者はこの模様を写真に撮って記録し、長いあいだ同じ個体を観察することもあります。
再生能力と長生きのひみつ
イモリは、足やしっぽがちぎれてしまっても、何年かかけて再び生えてくるという、驚きの力を持っています。この再生能力は、ほかの生きものにはなかなか見られない特別な特徴です。研究が進めば、けがや病気の治療にも応用できるかもしれないと期待されています。
さらに、イモリは40年以上も生きることがある長寿の生きものです。自然の中での暮らしは決して楽ではないのに、じょうぶな体で何十年も生き続けられるのは、イモリならではの強さです。
赤いおなかと毒の正体
イモリのおなかは目立つような赤い色をしています。これはただの模様ではなく、敵に向かって「ぼくを食べると危ないよ」と知らせるためのサインです。体には、フグと同じ「テトロドトキシン」という強い毒が含まれていて、敵がうっかり食べると命にかかわることもあります。
この毒は、イモリの体の中に自然にできるもので、自分を守る大切な武器です。はっきりとした赤い色があることで、敵は近づかず、イモリは安全に生きることができるのです。自然界では、見た目の色にも大きな意味があるということがわかります。
田んぼにやってくる!?恋のシーズンのイモリたち
水と一緒に田んぼへ大移動
田植えの時期になると、田んぼには水がはられます。その水を運ぶパイプや水路の中には、イモリの姿もあります。水といっしょに田んぼへ流れ込むようにして移動してくるのです。イモリはきれいな水を好むため、イモリがいる田んぼは「水が清らかである証」として、昔から農家の人たちに親しまれてきました。また、ボウフラなどの害虫を食べてくれるため、お米を育てる上でも頼れる存在とされています。
恋の季節にあらわれる紫のしっぽ
春から夏にかけての繁殖期になると、オスのイモリのしっぽが紫色に変化します。これは「婚姻色」とよばれる特徴で、オスがメスにアピールするためのサインです。オスはこのしっぽをゆらしながら泳ぎ、メスに近づいて自分の存在を知らせます。
冬の田んぼに現れる「イモリ玉」
気温が下がると、イモリたちは田んぼを離れ、周辺の陸地に移動します。落ち葉の下や石のすき間など、あたたかくて静かな場所でじっと冬を過ごします。このとき、たくさんのイモリがかたまりになって越冬する「イモリ玉」と呼ばれる現象が見つかっています。この集まりは、寒さから身を守るための知恵だと考えられています。
精包を使ったふしぎな受精方法
イモリの繁殖はとてもユニークです。オスは「精包(せいほう)」と呼ばれる袋に精子を入れて水中に置きます。それを見たメスが気に入ったオスの精包を自分の体にくっつけて取り込み、体の中で受精させます。この方法は魚やカエルとはちがい、体の中でじっくりと新しい命を育てるスタイルです。繁殖期は秋から初夏までと長く、イモリ玉ができる冬は出会いの場にもなっているのです。
葉っぱを使ったかしこい産卵法
卵を産むとき、メスは産みつける葉っぱを自分で選びます。その葉を器用にくるっと折りたたんで、卵を中に隠すのです。こうすることで、卵が天敵に見つかりにくくなり、安全に成長できるようになります。ひとつひとつの動きには、赤ちゃんを守るための思いやりが感じられます。イモリの恋も子育ても、じつに奥深く、自然の中で静かに続いているのです。
赤ちゃんイモリのふしぎな暮らしと成長
水中生活にぴったりの体
イモリの赤ちゃんは、卵からかえったばかりのとき体の長さがたったの2センチほど。とても小さく、まだ陸では生きられません。体の両側に目立つようなエラがあり、それを使って水の中から酸素を取り入れて呼吸しています。このエラは、魚のようにひらひらとしていて、水の中を自由に泳ぎ回るのにぴったりのつくりです。
成長のようすはまだナゾも多い
イモリの赤ちゃんは、ある程度大きくなるとエラが消えて肺で呼吸できるようになります。そして陸に上がって生活を始めますが、そのあとの暮らしや行動は、まだ研究が少なくナゾが多く残っています。どこで寝ているのか、何を食べて大きくなっているのかなど、自然の中ではなかなか観察がむずかしいのです。
キノコを使ったかしこい狩り
番組では、イモリの子どもがキノコのまわりでエサを探しているようすが紹介されました。ネンドタケというキノコのそばにいると、虫が集まってくるため、それをねらって狩りをしているのではないかと考えられています。キノコを「エサ場」としてうまく使っているところに、イモリの賢さが見られます。
毒や赤い色は食べ物から?
おとなのイモリは、体に毒(テトロドトキシン)を持っていて、おなかにははっきりとした赤い色があります。この毒や色素は、もともと体の中で作られていると思われていましたが、最近の研究では食べ物から取り入れている可能性があることがわかってきました。イモリの赤ちゃんも、自然の中で必要な成分をエサから上手に取り込んでいるようです。
体が小さくても、生きていくために考えながら行動している赤ちゃんイモリたち。自然の中でそっと育っているその姿には、まだまだ知られていないふしぎがたくさんつまっています。
生きものバトルマスターズの予告も放送
番組の最後では、「ダーウィン!生きものバトルマスターズ」の紹介もありました。動物たちの特技やバトルがテーマのシリーズで、今後の放送も楽しみです。
番組情報
| 放送日 | 2025年7月13日(日) |
|---|---|
| 放送時間 | 19:30~20:00 |
| 放送局 | NHK総合 |
| 番組名 | ダーウィンが来た! |
| 放送内容 | イモリの観察(生態・恋・赤ちゃんの成長) |
イモリは、見た目はかわいらしいけれど、実はすごい力を秘めた生きもの。自然の中でたくましく生きる姿に、びっくりと発見がいっぱいの30分でした。身近な田んぼや池にこんなドラマがあることを知ると、自然を見る目が変わってきます。次回の「ダーウィンが来た!」も要チェックです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

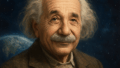

コメント