餅ばあちゃんの物語〜菓子職人・桑田ミサオの93歳の暮らし
2025年8月10日に放送された「プロフェッショナル」では、青森県津軽半島で年間5万個もの笹餅を作り続ける93歳の菓子職人、桑田ミサオさんに密着しました。今も自転車で山へ入り、自分の目で選んだ笹の葉を収穫します。その年は雨不足で質の良い笹が少なかったものの、別の場所で納得のいく葉を見つけ、作業場で大きさを整え清水で丁寧に洗いました。母から教わった「一生懸命やることで仕事が仕事を教えてくれる」という言葉を胸に、経験と直感で動く姿が印象的です。束ねた笹の葉がちょうど30枚と見抜く場面もあり、その正確さに長年の経験が光っていました。
小豆とあんこ作りのこだわり
小豆の状態を見極めた火入れ
取材年は雨不足の影響で小豆が例年より小ぶりでしたが、桑田さんはその状態を受け入れつつ、素材に合わせた火入れを行います。強火で煮立てるのではなく、じんわりと余熱で芯まで火を通す方法を取り入れます。このやり方により、小豆の粒がつぶれすぎず、風味や色も損なわれません。さらに、火を止めた後も時間をかけて水分を吸わせることで、ふっくらとした食感に仕上がります。
皮を活かした独自のなめらかさ
多くの職人は、皮の繊維を取り除くことでなめらかさを追求しますが、桑田さんは皮を多く残したままあんこを作ります。それでも口当たりが滑らかなのは、丁寧な火加減と練りの工程が理由です。皮ごと練り込むことで風味が豊かになり、自然な甘みと香りが増します。これにより、あんこは見た目も味わいも奥行きのあるものになります。
素材を活かす工夫と無駄のない仕込み
桑田さんは素材を余すことなく使い切ることを信条としています。「要するにケチ」という言葉の背景には、無駄を出さず、素材の持ち味を引き出す工夫が詰まっています。皮や煮汁も活用し、色や香りを保ちながら甘みを引き立てます。こうした工程は一つ一つが時間のかかる作業ですが、その積み重ねが独自の味を生み出しています。
作業合間の体操で保つ集中力
長時間の立ち作業が続く餅作りの中で、桑田さんは短時間の体操を日課としています。肩や腕を軽く動かすだけでも血流が良くなり、疲れが和らぎます。こうして体を整えながら作業を続けることで、集中力と手先の繊細な感覚を保ち、常に安定した品質のあんこを作り上げています。
手の感覚で仕上げる餅作り
指先で確かめる生地の状態
餅作りはあんこと米粉を練り混ぜるだけのシンプルな工程ですが、桑田さんは決して手袋を使いません。理由は、手袋越しではわからない微妙な生地のやわらかさや水分の加減を、直接の感触で確かめるためです。指先から伝わる温度やきめの細かさを判断材料にし、その日の気温や湿度に応じて水分量や練る時間を調整します。この積み重ねが、毎回変わらない味と食感を生み出しています。
生きるために磨かれた手の技
「10本指は黄金の山、母からいただいた宝物」という言葉どおり、その手は幼い頃から生活を支えるための技を磨いてきました。父を亡くし、母の手一つで育てられた幼少期は非常に貧しく、学校に通うこともままならない日々でした。その中で裁縫や料理、保存食作りといった実用的な技術を習得し、自分の力で暮らしを立てる術を身につけました。
病と向き合いながら続けた仕事と育児
19歳で嫁ぎ子どもを授かった後、肺病を患いながらも育児と仕事を両立しました。体調が優れない中でも、子どもを守り生活を続けるために、できる仕事を探し、家事や内職をこなしてきました。この厳しい経験が、現在の強靭な体力と精神力、そして細やかな手仕事の支えになっています。
笹餅作りを始めたきっかけと歩み
涙で決意した第二の人生
桑田さんが笹餅作りを本格的に始めたのは60歳のときでした。特別養護老人ホームを訪ね、自分で作った笹餅を入居者に振る舞ったところ、その味に感動して涙を流して喜んでくれた人がいました。この出来事が心に強く残り、「これを一生続けよう」という決意につながりました。
材料づくりからの挑戦
決意後すぐに、桑田さんは材料作りから手をつけました。小豆やもち米を自ら育て、保存や加工の方法を試し続けます。思い描く味に近づくまでには5年の試行錯誤が必要で、さらに納得のいく品質に到達するまで10年の年月を費やしました。手間も時間も惜しまず、納得できる笹餅を完成させた背景には、素材の育成から加工まで一貫して手がける信念があります。
地域に広がる笹餅の魅力
完成した笹餅は評判を呼び、やがて地元観光の象徴ともいえる津軽鉄道「ストーブ列車」での車内販売が始まりました。冬の車内で温かな笹餅を手渡す光景は観光客の楽しみとなり、「餅ばあちゃん」の愛称でも親しまれる存在に。
母との畑作業の記憶
桑田さんは、笹餅作りの原点には母と一緒に畑作業をした記憶があると語ります。土の手触りや作物の育て方を幼い頃から身近に感じてきた経験が、素材を大切に扱う姿勢につながっています。笹餅作りは、ただの仕事ではなく、家族の記憶や地域の暮らしと深く結びついた生き方そのものになっています。
家族を支えながらの仕事
介助と笹餅作りの両立
12月下旬、桑田さんは息子夫婦が共に病と闘う中、日々の生活を支えながら笹餅作りを続けていました。日中は介助のため作業に時間を割けず、笹餅作りは深夜からのスタートになります。静まり返った作業場で、一つ一つの工程を丁寧にこなしながらも、頭の片隅では家族の体調を案じている日々でした。
合間に見せる温かな心配り
作業の合間には、家族や取材スタッフのためにおにぎりを用意しました。炊き立てのごはんを握るその手には、職人としての確かな技と同時に、家族を想う温かさが感じられます。介助の合間に食事を共にし、息子夫婦もそのおにぎりを口にする姿に、桑田さんはわずかな安心を得ていました。
喜びに包まれた節目の日
厳しい冬を越え、2カ月後に93歳の誕生日を迎えた桑田さん。孫たちから祝福を受け、その笑顔には苦労を乗り越えた達成感がにじんでいました。やがて季節は春へと移り変わり、笹の新芽が芽吹く頃、また新たな笹餅作りの日々が始まります。
桑田ミサオさんのプロフェッショナル観
番組の最後、桑田さんは「分からないことは幸せなことよ。そういう気持ちで人生を送っていれば、いいことあるわよ」と語りました。分からないからこそ学びがあり、続けることで喜びや縁が広がるという考え方は、笹餅作りだけでなく生き方そのものに通じています。今回の放送は、手仕事と地域への愛情、家族への思いやりが詰まった温かい物語でした。
番組を見て感じたこと
番組を見ながら、桑田ミサオさんの手の動きに何度も見入ってしまいました。93歳とは思えない軽やかさと正確さ。束ねた笹の葉がちょうど30枚と一目で分かる場面には、半世紀以上積み重ねた経験と感覚のすごみがにじんでいました。手袋をせず、直接の感触で生地のやわらかさや水分量を確かめる姿は、まさに職人の勘そのもの。
印象的だったのは、その技の背景にある人生の物語です。幼いころの貧しさ、父を亡くして母と二人三脚で覚えた生活の知恵、病を抱えながらの子育て。そうした厳しい経験が、素材を無駄にせず、工夫して生かす今の仕事につながっているのだと感じました。
60歳から始めた笹餅作りも、老人ホームでの涙の一言がきっかけだったと知り、胸が熱くなりました。材料を自ら育て、納得のいく味になるまで10年かけて挑戦し続けた粘り強さ。その結果が、地元観光の顔となる「餅ばあちゃん」の笹餅に結実しているのが素晴らしいです。
家族を支えながら深夜に作業を続ける日々や、合間に用意するおにぎりからも、人としての温かさが伝わってきました。最後の「分からないことは幸せなことよ」という言葉は、これまでの人生があるからこそ言える重みのある一言で、聞く側の心をやわらかく包んでくれます。
手仕事の美しさと生き方の強さ、そのどちらも教えてくれる放送で、見終わったあとに静かな感動が長く残りました。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

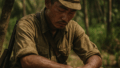

コメント
[…] ・気になるNHK 是非ご覧ください。 […]