美食の国フランスが認めた奇跡の三つ星物語|小林圭の挑戦
「フランス料理に憧れるけれど、日本人が本場で認められるのは無理だろう…」そんな風に思ったことはありませんか。世界の食の中心であるパリで、三つ星を獲得することは夢のまた夢。しかし2020年、その夢を現実にした日本人がいます。それが小林圭シェフです。この記事では、小林シェフが歩んできた挑戦の道のりと、彼の料理哲学がどのように生まれたのかを解説します。読めば、料理人を志す方も、美食を愛する方も、「挑戦し続けること」の意味を深く感じ取れるはずです。
三つ星を獲得した唯一の日本人

(画像元:祝・日本人初 仏ミシュラン三つ星獲得!レストラン ケイ 小林圭シェフ – 料理王国)
小林シェフの店は、芸術と文化の中心であるルーヴル美術館のすぐそばにあります。1日わずか12組しか入れない限定的な空間は、建築家と共に創り上げられた洗練の場。2020年、日本人として初めて三つ星を獲得し、以降6年連続でその星を守り続けています。
フランス全土には17万軒以上のレストランがありますが、その中で三つ星を持つのはわずか31軒。その数字だけでも、この快挙がどれほどの難関だったかが分かります。フランス人からすれば、日本人が三つ星を取るのは「フランス人が寿司で三つ星を取る」ほどの驚き。彼の名前は瞬く間に世界へと広がり、美食の象徴として称賛される存在となりました。
厨房に流れる緊張感と流儀
午後4時、厨房には13人のスタッフが集まります。彼らは「三つ星の厨房で腕を磨きたい」と世界中から集まった逸材ばかり。多くのシェフが仕込みを任せる中で、小林は必ず自らも調理台に立ちます。その姿勢には「料理は日々変化する」という哲学があります。
特に集中するのはフランス料理の要であるソース。コショウひと粒として同じものは存在しないように、レシピも固定するのではなく、その日その時の素材に合わせて調整を繰り返します。ソースを味見しながら、酸味・塩味・香りのバランスを瞬時に判断し、最高の一皿に仕上げていく。そこに小林の職人としての矜持が表れているのです。
午後7時45分、営業が始まると厨房はさらに緊張感に包まれます。魚や肉の担当に分かれたスタッフが持ち場を守り、全体を統率するのは小林。彼はまるでオーケストラの指揮者のように、料理の仕上がりや提供のタイミングを細やかに決めていきます。
提供される料理はどれも五感に響くものばかり。『特製キャビア』、『瞬間燻製したオマールブルー』、『上州和牛フィレ肉の炭火焼き』。そしてスペシャリテである『庭園風季節のサラダ』は旬の野菜40種類を使い、ムース状のドレッシングで彩られた芸術的な一皿。食べ進めるごとに新たな食感や風味が広がり、素材の命をそのまま味わう体験がそこにあります。
孤独と厳しさの中で生まれる革新
営業を終えた深夜0時。シェフたちの多くは休息を取りますが、小林の一日はまだ終わりません。厨房では新しいデザート『ヴァシュラン』の改良作業が続いていました。パティシエ東智子が作り上げたデザートに、小林は細部にわたり確認を加えます。味はもちろん、音やスプーン越しの手触りまで徹底的に吟味する。フランスで戦い続けるということは、それほどまでに完璧を求められる世界なのです。
孤独や重圧に押しつぶされそうな時、彼の唯一の気分転換は深夜のドライブ。パリの街を走ることで心を落ち着かせ、自分自身を取り戻していきます。その姿には、華やかな三つ星の裏にある孤独と戦い続ける料理人の現実が映し出されていました。
長野・茅野で育まれた感性
小林の原点は長野県茅野市。両親が料理人であったことから、幼い頃から料理は身近な存在でした。高校1年の時にテレビで見た三つ星シェフの姿に衝撃を受け、「フレンチシェフになりたい」と強く心に刻みます。そして地元ホテルのレストランに飛び込み修業を始めました。
そこで出会った料理長中村徳宏は、厳しくも温かい指導者でした。徹底的に鍛えながらも「やりたいことは言い続けろ」と常に励まし続け、小林に挑戦する心を植え付けました。この出会いが彼の人生を大きく変えたのです。
フランスでの苦難と突破口
21歳で単身フランスへ渡った小林。ところが到着してみると、約束されていた店に席はなく、寝袋生活を余儀なくされます。食事はフランスパン1本を数日かけてしのぐほど。何十通もの手紙を送っても返事はなく、差別にも苦しみました。それでも「腕だけは負けない」と星付きレストランに飛び込み、休日には精肉店で肉の扱いを学び続けます。
25歳で三つ星シェフアラン・デュカスに弟子入りすると、わずか2年で二番手に昇進。その後、自分の店を持ち、33歳で一つ星を獲得。しかし、二つ星以上にはなかなか届かず、「ホラ吹き日本人」と揶揄されるほど苦しい時期が続きました。
それでも彼は諦めませんでした。「自分を出すのではなく、素材を活かす」という原点に立ち返り、生み出したのが『庭園風季節のサラダ』。シンプルな料理にこそ真実があると気づいたのです。42歳の時、ついに日本人として初めてフランスで三つ星を獲得しました。
三つ星の先へ、終わりなき挑戦
三つ星を取ったからといって、立ち止まることは許されません。世界最高級のガルシア牛を買い付けにスペインへ赴き、生産者と交流しながら新しい可能性を探し続けます。厨房では『カッペリーニ』にオマール海老やトマト、キャビアを組み合わせた新作の試作に挑戦。麺の太さや食材の組み合わせを何度も繰り返し、理想の一皿を追求しています。
三つ星シェフの中には、重圧に耐えきれず命を絶つ人もいます。それほどまでに過酷な世界。しかし小林は「前に進み続けるしかない」と語り、常に挑戦を続けています。
最後に彼が口にした言葉は、すべてを象徴していました。
『プロフェッショナルとは、ブレずに今を超え続けること』
まとめ
この記事のポイントは以下の3つです。
-
小林圭シェフは2020年、日本人で初めてフランス・パリで三つ星を獲得し、6年連続で守り続けている
-
料理哲学は「技巧ではなく素材を最大限に活かすこと」、象徴的な料理が『庭園風季節のサラダ』
-
苦難や孤独を乗り越え、挑戦を続ける姿勢が世界中の料理人に勇気を与えている
料理の世界で頂点を極めてもなお、歩みを止めない小林シェフ。その姿勢は、料理人だけでなく、どんな挑戦をする人にも大きな示唆を与えてくれます。夢を現実に変える力は、決して特別な才能ではなく「諦めずに続ける心」なのだと。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

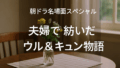
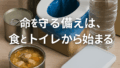
コメント