骨折の治療・リハビリで寝たきりを防ぐ!高齢者の転倒予防と最新対策まとめ
年齢を重ねると、ちょっとした転倒が大きなけがにつながることがあります。特に高齢者が骨折をすると、寝たきりになるリスクがぐんと高まるため、予防と対策がとても大切です。2025年5月18日放送予定の「チョイス@病気になったとき」では、高齢者の骨折に関する最新の治療法やリハビリ、日常生活でできる予防策について詳しく紹介される予定です。これからの自分や家族のために知っておきたい内容がたっぷり詰まった45分間です。放送後、詳しい内容が分かり次第、最新の情報を更新します。
骨折がきっかけで寝たきりに?高齢者に多い骨折の部位とその理由
高齢になると筋力や骨の強さが低下し、わずかなつまずきやバランスの崩れでも転倒しやすくなります。このような転倒によって起こる骨折は、手首・背骨・脚の付け根(大腿骨頸部)などが代表的です。
・手をついて転倒すると起こりやすい手首の骨折
・尻もちや軽い衝撃で起こる背骨の圧迫骨折
・立った状態での転倒によって生じる脚の付け根の骨折
これらの骨折は、痛みや動きにくさで活動量が大きく減少し、筋力もさらに落ちてしまうため、そのまま寝たきりになってしまうこともあります。寝たきりが続くと、食欲の低下や認知機能の低下、さらに別の病気のリスクも高まるため、できるだけ早く動けるようにすることが重要です。
最新の骨折治療法に注目!「ロッキングプレート」や「人工骨頭置換術」とは?

番組では、手首や脚の付け根の骨折に対する最新の治療法が紹介される予定です。
手首の骨折では、「ロッキングプレート」と呼ばれる金属製の固定具を使った手術が広まっています。これは骨をしっかり固定する仕組みで、骨の位置が安定しやすく、リハビリも早く始められるのが特徴です。従来の治療よりも固定力が高く、回復期間の短縮につながると期待されています。
また、脚の付け根の骨折に対しては、「人工骨頭置換術」という手術が一般的に行われています。骨折部分を人工の骨に置き換えることで、術後すぐにリハビリが始められるというメリットがあります。番組ではこの手術の内容や、実際の症例、手術後の過ごし方や注意点についても詳しく説明されると予想されます。
回復のカギは早期リハビリ!無理なく動くための工夫とは
骨折の治療後、どれだけ早くリハビリを始められるかが寝たきりを防ぐポイントです。特に高齢者は体力の回復に時間がかかるため、寝た状態を長く続けないことが大切です。
番組では、リハビリの始め方や、医師や理学療法士がどのように関わっていくか、自宅に戻ってからの生活動作の練習法なども紹介される予定です。
・ベッドからの起き上がり方
・安全な歩行練習の方法
・食事や排泄など日常動作を取り戻す練習
このように、リハビリの内容は一人ひとりの状態に合わせて工夫されており、「動けること」を少しずつ取り戻すことで自信にもつながります。
転倒・骨折を防ぐために今できることとは?

予防こそが最大の対策です。転倒による骨折を防ぐために、日常生活の中でできる運動や住環境の見直しが紹介されると見られます。
・片足立ちでのバランス練習(洗面台や壁に手を添えて)
・かかと上げ運動でふくらはぎの筋肉を鍛える
・椅子から立ち上がる練習で太ももの筋力アップ
また、自宅の転倒リスクを減らす工夫も重要です。
・玄関や廊下にある段差をスロープで調整
・浴室やトイレに手すりを設置
・夜間の足元を照らす足元灯の活用
・カーペットやマットのズレ防止対策
こうした工夫で、安心して暮らせる環境をつくることが骨折予防につながります。
骨を強く保つ食生活と生活習慣も大切
番組では、骨を丈夫に保つための栄養や生活習慣についても取り上げられると考えられます。骨は食べ物や日光、運動によって支えられています。
・カルシウムを多く含む食品(牛乳、小魚、青菜)を日常的に摂る
・ビタミンDを意識してきのこ類や魚類も取り入れる
・日光を浴びて体内でビタミンDを生成
・タバコや過度な飲酒を控えることで骨への負担を減らす
これらの工夫を日常に取り入れることで、将来的な骨折のリスクを減らすことができます。
出演者と講師によるやさしい解説で安心
番組では、俳優の八嶋智人さんと大和田美帆さんがキャスターを務め、骨折について不安に感じている視聴者にもわかりやすく情報を届けてくれます。講師は山陰労災病院 院長の萩野浩先生で、最新の医療知識と現場での経験をもとにした解説が期待されます。
今回の放送は、自分自身や家族の健康寿命を延ばすためのヒントが詰まった内容になることは間違いありません。高齢者の転倒・骨折を防ぐために、日常でどんなことを意識すればいいのか、今からできることを学ぶきっかけとして、多くの方にとって役立つ放送になるでしょう。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

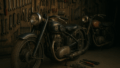

コメント