国会・選挙の舞台裏で見えた本当の姿とは
2025年6月11日放送のNHK「あさイチ」では、「知れば政治の見方が変わる!国会・選挙の舞台裏」と題して、暮らしと深く関わる政治の仕組みや現場の裏側が詳しく紹介されました。かつて国会議員を務めた西川きよしさんを迎え、国会の仕組み、年金改革法案、投票所の現場やこども選挙まで、多角的に政治を掘り下げる内容となりました。
国会と私たちの暮らしのつながりを知る
今回のあさイチでは、政治と私たちの生活がどれほど密接に関わっているかを、具体的な事例をもとにわかりやすく紹介しました。特に、かつて参議院議員として活動した西川きよしさんの語りからは、暮らしの中の政治の存在が丁寧に伝えられました。番組では、実際に国会の内部にカメラが入り、普段見られない場所が紹介されました。
・国会議事堂は1920年に建設が始まり、17年の歳月をかけて完成
・建築材料はすべて国産で、柱には沖縄の珊瑚石灰石が使われている
・中央広間には伊藤博文、大隈重信、板垣退助の銅像が並び、もう1つの台座は「政治に完成はない」という象徴のため空いている
さらに、案内役を務めた衆議院衛視の戸田あゆ美さんの説明により、議員の座席の配置に当選回数が反映される仕組みなども紹介されました。たとえば、議長席から遠いほど当選回数が多い議員が座ることが決まっており、政治の場には見えないルールが存在していることがわかります。また、議員席に使用される金華山織の柄には「ツタ」が描かれていて、これは「議論が枯れないように」という意味が込められています。
続いて、NHK「ニュースウォッチ9」の広内仁アナウンサーが、実際に国会で活動する議員たちに密着しました。
・法案の審議の流れは「衆議院本会議→委員会→衆議院本会議→参議院」と進む
・委員会では細かい点まで議論が行われるため、法律が形になるまで時間がかかる
・現在の衆議院は、与党(自民党・公明党)219議席に対し、野党が246議席と多数を占める「少数与党」の状況
・この構図は約30年ぶりで、政治のバランスが大きく変化している
こうした状況は、政治が変わりつつあることを実感させる大きなポイントです。普段は難しく思われがちな国会の仕組みも、具体的なエピソードを交えた説明によって、視聴者にとってぐっと身近に感じられる内容となりました。政治は遠い世界の話ではなく、生活に直結したものだということが、丁寧に伝えられていました。
年金改革法案の現場に密着
番組では、国会で進行中の年金制度改革関連法案の審議の過程に密着し、法案がどのように扱われ、どのように議論されているのかを具体的に紹介しました。最初に取り上げられたのは、厚生年金と基礎年金の違いについてです。特に注目されたのは、就職氷河期世代や現在の若年層など、将来的に年金額に不安を持つ世代が影響を受けやすい点でした。
・厚生年金は企業などに勤める人が対象で、保険料の一部を事業主が負担
・基礎年金はすべての人が対象で、所得の少ない人ほど負担が重く感じやすい
・政府は基礎年金の底上げを検討したが、財源の問題などで反対意見が多数を占め、盛り込まれなかった
番組では、議員が本会議で質問をするまでの準備の様子にも注目。自民党の三谷英弘議員が同じく自民党の佐々木紀議員に意見を聞きながら、質問内容を精査する場面が映されました。また、立憲民主党の井坂信彦議員は、自身が作成した原稿について先輩議員からアドバイスを受ける様子が紹介され、本会議に向けた入念な準備と確認のプロセスが丁寧に描かれていました。
・議員は法案の主旨だけでなく、反対意見や過去の経緯も踏まえて質問内容を組み立てる
・質問の前には原稿を作成し、先輩議員や政党関係者と内容の整合性を確認
・質問内容には、専門的な知識と生活者目線の両面が求められる
審議の結果、立憲民主党は修正案を提出。この修正案は自民党・公明党・立憲民主党の賛成多数で可決されました。一方で、日本維新の会・国民民主党・共産党・れいわ新選組は反対の姿勢を示しました。
・修正案は与野党の一部が賛成し成立したが、すべての政党が賛成したわけではない
・法案の成立には、議論の末に多くの調整が行われることがわかる
・議会は単なる賛否の場ではなく、意見を擦り合わせながら制度を動かしている
この特集では、法案がどのように形作られていくのか、そしてその過程にどれだけ多くの人の手と時間がかかっているかを実感できる内容となっていました。年金制度という身近な問題が、国会でどのように扱われているかを知る機会として、非常に意義深い放送でした。
国会職員の支えと調整力
番組では、国会の表舞台だけでなく、その運営を裏から支える職員の姿にも密着しました。取り上げられたのは衆議院の議院運営課に所属する畠山利行さんで、日々の調整や運営業務の一部始終が紹介されました。
畠山さんの仕事は多岐にわたり、朝8時には出勤して本会議の準備に取りかかるなど、非常に早い時間から活動しています。特に重要なのが、本会議の内容や日程をめぐる与野党間の調整で、細かなすり合わせを行うことが求められます。
・会派ごとに事前に訪問して、本会議の見通しや協議事項を説明
・会派から出された意見や懸念点を整理し、議長サロンなどで与野党代表に伝達
・本会議の前には「議院運営委員会」「理事会」「与野党の筆頭間協議」など、複数の打ち合わせが並行して行われる
このような業務を通じて、畠山さんは短時間のうちに合意を引き出すための調整役を担っており、その働きによって議会が円滑に進行していることがわかります。さらに、会議中には大臣席のすぐ後ろに控えて不測の事態に備えるなど、職員のサポート体制も整っています。
・登壇のタイミングや質疑の進行にあわせて、必要に応じて声をかける
・議員が使う「発言通告書」の作成も担当し、内容の正確さや時間配分にも配慮
・議会の進行に乱れが出ないよう、常に裏で動いている
表には出ませんが、こうした職員の緻密な段取りと素早い判断力によって、国会は機能しています。今回の特集では、政治家だけでなく、政治の仕組みを支える存在としての国会職員の重要性がよく伝わる内容でした。まさに国会という大きなシステムを動かす「縁の下の力持ち」として、その存在感が際立っていました。
視聴者の疑問にきよし師匠が答える
番組では、かつて参議院議員として活動していた西川きよしさんが、視聴者から寄せられた疑問に対して自身の体験を交えてわかりやすく解説しました。政治に関心を持ちづらい人にも伝わるよう、実際に制度が動いた具体的な事例を紹介しながら、国会議員の役割を丁寧に説明しました。
西川さんは、議員としての活動の中で、委員会での発言をより聞いてもらえるように工夫していたことに触れました。特に、当時の小渕恵三総理大臣に福祉に関する書籍を委員会で取り上げ、「この本をぜひ読んでください」と伝えた結果、実際に読んでもらえたというエピソードを紹介しました。
・委員会では限られた時間の中で伝えたい内容をどう伝えるかが大切
・政治家に対しても直接言葉で伝えるだけでなく、資料や本を使って働きかけることが有効
・一人の行動が、政治の意思決定に影響を与えることがあると証明された事例
さらに、年金の支給日が祝日や休日の影響で前倒しされないことについても、西川さんは繰り返し問題提起し、制度が変更されるきっかけとなったことが語られました。これにより、生活に直結する制度が、国会の中で議論を通じて変わっていく過程が具体的に示されました。
また、視聴者から寄せられた「議員の数が多すぎるのではないか」という疑問には、多様な意見を反映するには一定の人数が必要であると回答しました。政治は多数派だけでなく、少数派の意見も尊重する必要があり、そのバランスを保つために、議員の数には意味があると説明されました。
・政治は多数決で進むが、少数の声も国会で扱うには一定の人数が必要
・地域や立場の違う人たちの声を国に届けるため、さまざまな背景の議員が求められる
・単純に数を減らすことは、意見の偏りにつながるおそれがある
このように、西川さんの言葉からは、国会議員としての責任と現実的な政治の仕組みが伝わり、視聴者の疑問に対しても、感情論ではなく具体的な経験をもとに誠実に答える姿勢が印象に残る内容でした。
投票所の舞台裏とこども選挙
番組では、選挙の現場を支える投票所の準備や運営の裏側にも密着しました。取材先はさいたま市選挙管理委員会で、市の職員たちが一丸となって投票所を整える様子が紹介されました。準備が行われたのは浦和区にある岸町公民館で、ここは市長選挙の際の投票所の一つとなっています。
・投票所の設営は市の職員が協力して実施
・使用する備品は、公職選挙法のルールに則って整備されている
・投票箱が空であることは、一番乗りの有権者2人が確認し、その後封印する
また、投票が無効となってしまう具体例についても紹介されました。名前を書いたあとに応援メッセージや余計な言葉を書き添えてしまうと、その票は無効扱いになることがあります。こうした基本的な注意点は見落とされがちであり、投票所の現場を知ることで初めて分かるルールの存在が明らかにされました。
さらに注目されたのが、同市で行われた「こども選挙」です。これは選挙の仕組みを子どもたちに体験してもらう取り組みで、実際に選挙で使用されている投票台や投票箱を用いて模擬選挙が行われています。
・投票前にはワークショップが開かれ、候補者に聞きたいことを考える
・その質問を子どもたちが動画に撮影し、候補者に送る機会も設けられている
・投票用紙には実際の立候補者が並び、より本番に近い環境を再現
・投票立会人として保護者が運営に協力しており、家庭と地域が一体となって選挙を学ぶ機会となっている
この「こども選挙」は全国ですでに14の自治体に広がっており、今後さらに普及が期待される取り組みです。海外ではスウェーデンが先進的な事例として紹介され、子どもが実際の大臣と討論できる機会が設けられていることや、投票率が80%を超える国民意識の高さが伝えられました。
また、今回の特集では、選挙に行かないことによる損失についても具体的に示されました。村上一真教授の試算によると、参議院選挙に行かないことで、有権者1人あたりおよそ91万5000円分の権利を放棄しているという結果が出ており、投票の重要性を数字で実感できる内容となっていました。
このように、選挙は単なる手続きではなく、自分の意見を社会に反映させるための大切な権利であるということを、多角的に伝える特集でした。投票所の準備からこども選挙、海外の実例までを丁寧に取り上げ、誰もが関心を持つきっかけとなる構成になっていました。
雨に映える京都・楊谷寺のあじさい
いまオシ!LIVEのコーナーでは、京都・長岡京市にある楊谷寺(ようこくじ)が紹介されました。このお寺は平安時代に創建され、1200年もの歴史を誇る由緒ある寺院です。別名「あじさい寺」とも呼ばれ、梅雨の季節には美しく咲くあじさいが境内を彩ります。
楊谷寺は、目のご利益がある観音様を祀っていることで知られています。眼病平癒を祈願する人々が全国から訪れ、古くから信仰を集めてきました。現在では、初夏になると約5000株のあじさいが咲き誇り、写真映えするスポットとしても人気です。
・境内には参道沿いや石段、手水舎のまわりにも色とりどりのあじさいが咲く
・雨に濡れたあじさいの花がいっそう鮮やかに映え、訪れる人の目を楽しませる
・花手水(はなちょうず)やあじさいのハート型飾りなど、季節限定の演出もあり
楊谷寺では25年前からあじさいを植栽し始め、春の長岡天満宮や乙訓寺、秋の光明寺に続く「夏の名所」として整備されました。季節を通して訪れたくなるお寺として、地域の魅力を引き出す存在となっています。
また、阿弥陀堂では「眼力ヨガ」というユニークな体験も提供されており、視力回復や目の疲れを癒やすことを目的としたプログラムが行われています。
歴史、信仰、自然美が融合する楊谷寺は、梅雨の京都を楽しむにはぴったりのスポットです。あじさいがしっとりと雨に映える光景は、訪れる人に穏やかな時間を届けてくれる場所となっています。
あじの干物とポテトのミルク煮を紹介
「みんな!ゴハンだよ」では、家庭的で優しい味わいの「あじの干物とポテトのミルク煮」が紹介されました。干物を焼いてほぐし、じゃがいもと合わせて牛乳や生クリームで煮込む料理です。アレンジでグラタンにしても美味しいと紹介されました。
【あさイチ】あじの開きとじゃがいもで!渡辺雄一郎流“ブランダード”レシピ|2025年6月11日放送
佐賀の練り上げ陶芸の魅力
いまオシ!REPORTのコーナーでは、佐賀市で活動する陶芸家・西岡孝子さんの作品と、彼女が用いる「練り上げ技法」が紹介されました。練り上げとは、色の異なる粘土を緻密に組み合わせて模様を作り出す技法であり、完成までに半年以上を要する繊細で高度な作業です。
・複数の色の粘土を重ね合わせ、削ったり伸ばしたりして模様をつくる
・絵付けではないため、模様は器の内部まで一体化している
・焼成しても色や模様がずれることなく残るのが特徴
番組内では、西岡さんの代表作のひとつである金魚模様の器が登場。金魚が水の中で泳いでいるような動きのあるデザインは、粘土の性質と手作業の精度が生み出す繊細な造形です。さらに、「華丸・大吉」の名前をもとにした模様も披露され、番組へのオリジナル作品としての遊び心も感じられる仕上がりとなっていました。
・練り上げは寸分のズレも許されない作業の連続
・完成するまでに数ヶ月かかるため、集中力と根気が必要
・型にはめるのではなく、一つひとつの模様を手で構成していく
こうした陶芸は、見た目の美しさだけでなく、触れたときの温もりや重みにも職人の技が感じられるものです。大量生産では味わえない、一点物としての価値と存在感を持っており、長く使い続けたいと思わせる魅力があります。
西岡さんの取り組みを通して、日本の伝統工芸の技術力と創造力が改めて示されました。あさイチでは、政治や選挙といった社会的なテーマに加え、こうした地域の職人の技にも光を当てることで、番組全体の幅広さと奥行きがより印象に残る内容となっていました。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


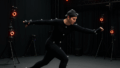
コメント