「べらぼう」コラボ!歌麿と蔦屋重三郎が起こした“美人画革命”と幕府への“抵抗”とは?
2025年6月8日にNHK総合で放送された『浮世絵ミステリー』では、現在放送中の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』と連動し、浮世絵界に革新をもたらした喜多川歌麿と版元・蔦屋重三郎の関係に迫りました。彼らが手がけた美人画の革新、幕府の規制との闘い、その裏にあった江戸の文化と政治の変化が描かれました。
歌麿と蔦屋重三郎が挑んだ“美人画革命”
喜多川歌麿は、江戸時代後期の浮世絵師として知られていますが、その人物像には多くの謎が残っています。生年月日や出生地、親の名前、妻がいたかどうかなど、基本的な情報の多くが不明で、研究者の間でも諸説があります。そのため、彼の人生の輪郭は、作品から推測するしかありません。
そんな謎多き歌麿が名を上げたきっかけが、版元・蔦屋重三郎との出会いでした。蔦屋は出版の分野で新しい試みを次々と形にした人物で、歌麿の才能を見抜き、浮世絵の新境地を切り拓くパートナーとなります。
2人が手がけたのが「大首絵(おおくびえ)」と呼ばれる、顔を大きくクローズアップした美人画の形式です。それまでの浮世絵では、八等身のようにスラリと全身を描いた美人画が主流でしたが、歌麿は顔の表情や手元の仕草を拡大して描くことで、人物の内面や性格までも浮かび上がらせる表現に挑みました。
代表作の一つ『深く忍恋(ふかくしのぶこい)』では、キセルを持った既婚女性が描かれており、髪型の丸髷(まるまげ)やお歯黒といった細かい描写から、結婚した女性であることがわかります。この絵は、2016年にパリのオークションで約8800万円という高値で落札され、現在でも高い評価を受けています。
歌麿の美人画が革新的だった理由は、次のような点にあります。
-
表情の一瞬を切り取ったような描写(例:ふと振り返る、微笑む、目を伏せる)
-
しぐさから感情や思考が伝わる構図(例:手ぬぐいを握る指先の緊張感)
-
背景や装飾を極力排除し、人物の存在感を強調
-
既存の理想像にとらわれず、リアルな江戸の女性像を描いたこと
これにより、美人画は単なる美の表現を超えて、江戸の人々が日々感じていた感情や暮らしの一部までも描き出す手段となりました。絵を見る人は「この人はどんな気持ちでこの場面にいるのか」と考え、感情移入するようになったのです。
こうした表現は、庶民にとって身近な“アート”であり、娯楽でもあり、心の鏡のような存在となりました。歌麿と蔦屋が作り上げたこの新たな表現スタイルは、単なる技術革新にとどまらず、当時の文化や価値観に大きな影響を与えた革命的な出来事といえます。
蔦屋重三郎の才覚と人脈
蔦屋重三郎は、江戸時代の出版文化をけん引した人物であり、新しい価値を生み出す力と人を動かす力を持った版元でした。彼は単なる商売人ではなく、文化の担い手として、多くの絵師や文人と交流しながら時代の流れを読む力を発揮しました。
その象徴的な仕事の一つが、喜多川歌麿との出会いと育成です。歌麿をただの弟子や職人として扱うのではなく、表現者としての可能性を見抜き、大きな仕事を任せました。その中でも特に知られているのが、狂歌をテーマにした絵本『画本虫撰(えほんむしえらみ)』です。
-
この本は、江戸の洒落や風刺を盛り込んだ「狂歌」を題材に、歌麿が虫の絵を添えて構成したもの
-
歌麿が描いた虫は、外観だけでなく、動きや生き生きとした生命感まで描かれていた
-
歌麿の師・鳥山石燕も、この絵本を「心の絵」と高く評価した
蔦屋はこの本を成功させるため、吉原の人脈を活かして宴会を開き、文化人たちと交流を深めました。例えば、
-
狂歌を詠む文化人たち(大田南畝など)を招待
-
原稿料の代わりに宴席でもてなすという方法で協力を得る
-
結果的に、内容の質が高く、書籍としても高い評価を受けた
このような人とのつながりと感謝の形が、蔦屋の成功を支えた要因でした。当時、作者に原稿料を出すことは一般的でなく、宴で礼を尽くすという姿勢が蔦屋の人間性を表していたのです。
また、台東区の誠向山正法寺にある蔦屋重三郎の墓石には「信義を尊び、器が大きく、細かいことにこだわらない性格であった」と刻まれていることからも、彼が人から深く慕われていたことがうかがえます。
歌麿の才能を見抜いた目、作品を育てる企画力、文化人との信頼関係を築く人柄――それらが組み合わさって、蔦屋重三郎は江戸の出版界に大きな足跡を残すことになりました。
政治の動きと出版の自由への圧力
18世紀後半の日本は、大きな社会的変動にさらされていました。田沼意次が老中として政権を握っていた時期は、経済政策により町に活気が生まれ、商人文化が発展していました。しかし、1783年の浅間山大噴火をきっかけに天候不順が続き、天明の大飢饉が全国を襲います。これにより、庶民の暮らしは一変し、暴動や打ち壊しも相次ぎました。こうした混乱の中で、田沼は失脚し、次に政治を担ったのが松平定信です。
松平定信は「寛政の改革」と呼ばれる一連の政策を進め、倹約・道徳重視・風俗の取り締まりを徹底し、出版にも厳しい規制をかけました。この流れの中で、蔦屋重三郎の出版活動も制限されることになります。
蔦屋は当初、「黄表紙(きびょうし)」と呼ばれる、風刺や洒落を交えた大人向けの絵入り読み物を出版していました。
-
黄表紙は町人文化を背景に、江戸庶民の感覚や日常をユーモアで描いた人気のジャンル
-
内容には幕府や支配階層を風刺するものも含まれており、規制対象になりやすかった
-
結果として、蔦屋は絶版処分を受け、さらに財産の半分を没収されるという重い処分を受けました
それでも蔦屋は出版を諦めず、新たな表現の場を浮世絵に見いだしました。当時の浮世絵は、カラー印刷の技術が進み、庶民でも手が届く価格で販売できる媒体として人気が出始めていたのです。
彼が目をつけたのは、町中で話題になっていた「看板娘ブーム」でした。
-
茶屋や観光地の店先で働く美しい町娘たちが評判になっていた
-
蔦屋と歌麿は、そうした町娘たちをモデルにした浮世絵を制作
-
絵には直接名前を描かず、匿名の魅力を活かして庶民の関心を集めた
この時期、歌麿の表現力はさらに高まり、町娘を生き生きと描く作品群が大人気になります。庶民は身近な場所で見かけるような女性たちの姿に親しみを覚え、それが作品への共感と人気を生みました。
政治による規制が強まる中でも、蔦屋はその状況を逆手に取り、風俗や流行を描く浮世絵の力で新しい文化を生み出したのです。歌麿とのコンビはここでも健在で、時代の空気を鋭くとらえた絵が次々と世に出されました。
出版の自由が失われようとしていた時代に、蔦屋重三郎は浮世絵という手段を通して、庶民の笑いや共感を守り、芸術としての表現を模索し続けたのでした。
歌麿の表現の進化と幕府との対立
歌麿は蔦屋重三郎の死後も創作を続け、他の版元からも依頼を受けながら自分の表現を深めていきました。その過程で、幕府の厳しい風俗統制に直面しつつも、独自の工夫を凝らした作品を次々に発表していきます。
そのひとつが「判じ絵(はんじえ)」です。これは絵を用いたなぞなぞで、描かれた人物や場面が何を意味するかを読み解く形式の作品でした。当時、幕府は浮世絵に実在の茶屋娘の名前を明記することを禁止していたため、歌麿はそれを避ける方法として、絵に隠された言葉や文字を使い、見る者が想像で補うスタイルを採用しました。
-
判じ絵は庶民の間でも人気を集めたが、表現としての曖昧さゆえに幕府の目にもとまりやすくなっていきました
-
やがて幕府は「名前を描かない判じ絵」でさえも禁止し、絵の中に含まれる暗示的な表現すら取り締まる方針に変わっていきました
その後、歌麿はさらに表現の幅を広げていきます。有名な茶屋娘に代わって、名前のない働く女性たちを描くようになり、生活感や感情がにじみ出るようなリアルな人物像を描写しました。また、妖怪や伝説の登場人物を題材とした作品にも挑戦し、規制の網をかいくぐりながら新しい創作を展開していきました。
-
例えば「山姥と金太郎がたわむれる図」は、男女のたわむれを直接描くことが禁止されていた中で、民話の世界を借りて人間関係を表現した作品です
-
これにより、歌麿は時代の制約の中でも物語性と感情表現を両立させる方法を模索しました
しかし、1804年に描いた『太功記』に基づく武将の絵が問題視され、幕府の規制に違反したとして処罰を受けることになります。当時、天正年間以降の実在する武将を描くことも禁じられていたためです。このとき歌麿は、「手錠の刑」すなわち50日間にわたる自宅謹慎を命じられました。
この処罰を受けた2年後、歌麿は亡くなります。最晩年に描かれたとされる『杭打ち図』は、逆境にあっても信念を貫く姿勢が感じられる作品とされ、現在でも高い評価を受けています。杭を打つという動作には、地面にしっかりと自分の場所を刻むような意味合いが込められているとも解釈されており、幕府の規制と闘いながらも、自らの芸術を信じてやまなかった歌麿の強い意志がにじむ作品とされています。
幕府の圧力に屈することなく、あらゆる手法を駆使して表現の自由を追い求めた歌麿の姿は、今もなお多くの人々に感銘を与えています。
革命と抵抗の果てに残されたもの
この番組は、浮世絵の枠を超えて表現を追い求めた歌麿と、それを支えた蔦屋重三郎の信念と情熱に満ちた人生を描いていました。2人の挑戦は、厳しい時代の中で庶民の心を捉える芸術を生み出し、後世に残る文化の礎となりました。
彼らが残した美人画、役者絵、妖怪絵など多様な作品群は、江戸という時代を映す鏡でありながら、今を生きる私たちにも問いかけるものを含んでいます。どんな時代にも自由な表現を求める心があり、それを形にした2人の歩みが、今改めて注目されています。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

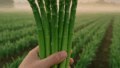

コメント