肩こり改善のカギは“肩のリズム”!3分ワザでラクになるSP
2025年7月17日放送の「あしたが変わるトリセツショー」では、「肩の不調を改善する新しいヒント」が特集されました。肩こりや肩が重い、動かしにくいなどの悩みに対して、わかりやすいチェック方法や、わずか3分でできる簡単なエクササイズが紹介され、すぐにでも取り入れたくなる内容でした。市村正親さんやロッチの中岡さん・コカドさん、たんぽぽの川村さんが出演し、楽しく真剣に肩の健康を考える時間となりました。
肩こりの原因は「肩のリズムの乱れ」
番組の最初に取り上げられたのは、肩こりの意外な原因として注目されている“肩のリズムの乱れ”についてでした。肩の違和感や重だるさを感じている人の多くは、実はこのリズムがうまく働いていない可能性があるのです。
番組では、街で肩の不調を訴えた33人を対象に調査を行いました。その結果、なんと32人に肩のリズムの乱れが見られたというデータが紹介され、驚きの声があがっていました。
正しい肩のリズムとはどんなもの?
「肩のリズム」とは、腕の骨(上腕骨)と肩甲骨が一緒に連動して動く動き方のことです。健康な肩の場合、たとえば腕を横から90度の高さまで上げたとき、腕の骨は60度、肩甲骨は30度動きます。このバランスが1:2であることが、肩の動きにおける理想的な比率です。
さらに、腕を耳の横まで真上に上げるときには、腕の骨が120度、肩甲骨が60度動きます。この時も同じく1:2のバランスになります。このように、肩甲骨がしっかりと動いていることで、腕の骨が無理なく上がるようになっているのです。
リズムの乱れが引き起こす体の不調
この動きのバランスが崩れると、本来肩甲骨がサポートすべき部分まで腕の骨だけで動かそうとしてしまい、筋肉に無理な負担がかかります。その結果、肩が重く感じたり、腕が上がりにくくなったり、こりや痛みが出る原因となってしまいます。
つまり、肩こりの根本的な原因は、筋肉の疲労や姿勢だけでなく、「肩のリズム」が崩れてしまっていることにあるという視点が大事なのです。
番組では、この肩のリズムに着目することで、これまで改善しづらかった肩の不調に新しいアプローチができると紹介されていました。肩を無理に動かすのではなく、正しいリズムに戻すことこそが改善の第一歩になるという考え方です。
自分の肩をチェックする簡単な方法
番組では、自分の肩の状態をその場でチェックできる2つの簡単な方法が紹介されました。どちらも鏡の前やテレビを見ながらでもできる内容で、肩のリズムが崩れていないかを手軽に確かめられます。
肩のリズムを確認するセルフチェック法
| チェック法 | やり方 | 注意ポイント |
|---|---|---|
| 手を胸に当てて肘を上げる | 手のひらを胸にぴったりつけたまま、無理せず肘を持ち上げる | 首の付け根あたりから肩が一緒に上がってしまっていたら、肩のリズムが崩れているサイン |
| 前へならえの姿勢 | 両腕を肩の高さまでまっすぐ前に出す | 左右の肩の高さに差がある場合は、筋肉のバランスが乱れている可能性あり |
どちらの動きもわずか数秒でチェック可能で、特別な道具も必要ありません。日常生活の中で、ふとしたタイミングに取り入れることで、肩の不調のサインに早めに気づけるようになります。
もしどちらかのチェックで「おかしいな」と思った場合は、肩のリズムが乱れている可能性があるため、次に紹介されるストレッチやエクササイズを試して整えていくのが効果的です。肩の不調を感じていない人でも、予防としてこのチェックを習慣にすると安心です。
肩が軽くなる!1回3分の簡単ストレッチと運動
肩の動きをスムーズにするには、筋肉のバランスを整えることがとても大切です。番組では、肩のリズムを取り戻すために、特に働きかけるべき4つの筋肉が紹介されました。それぞれの筋肉に合ったストレッチやエクササイズを行うことで、肩周りの可動域が広がり、こりや重さがやわらぎます。
肩のリズムを整える4つの筋肉とエクササイズ
| 筋肉名 | 体の場所と役割 | エクササイズのやり方 |
|---|---|---|
| 広背筋・肩甲挙筋 | 背中から肩甲骨にかけて。肩を下に引きおろしたり、持ち上げる動きを支える | 手を肩の後ろ側に回し、肩甲骨を反対の手で下に押さえる。もう片方の手で肘をつかみ、首を斜め前に倒して体を傾けた状態で20秒キープ(左右) |
| 前鋸筋 | 脇の下の奥にある筋肉で、肩甲骨の動きを支える | 両肘を胸の前で合わせ、そのまま肘をつけたまま上がるところまで上げる。脇の下の筋肉を感じながら、力を入れずに10回行う |
| 僧帽筋下部 | 肩甲骨の下の方にある背中の筋肉で、肩甲骨を安定させる | 両手を頭の後ろで組み、肘を開きながら胸を張る。息を吸いながら肩甲骨を背骨に寄せるイメージで、吐きながら力を抜く(10回) |
どの動きも特別な道具を使わずに、そのままの姿勢でできるのが特徴です。イスに座ったままや、テレビを見ている合間にも行えるので、生活の中に無理なく取り入れられます。
特に広背筋や肩甲挙筋のストレッチは、日常的に肩をすくめがちな姿勢が多い人にぴったりです。また、前鋸筋の動きは普段あまり意識しにくい部分なので、筋肉を目覚めさせる感覚で取り組むと効果的です。
全て合わせても3分程度で終わるため、毎日の習慣にしやすく、続けることで肩の軽さやスムーズな動きを実感しやすくなると紹介されていました。肩の不調が気になる方だけでなく、予防としても役立つ内容です。
腕の動きまで変わる!肩こり対策に+αのワザ
肩こりの改善だけでなく、腕がスムーズに動くようになる効果も期待できる追加エクササイズも番組で紹介されました。特に、「前へならえ」の姿勢で左右の腕の高さに差が出た人にはぴったりの内容です。
このエクササイズでは、肩の奥深くにある小さな筋肉「腱板(けんばん)」を鍛えることがポイント。腱板は、肩関節を安定させるために重要な働きをしていて、年齢や使いすぎによって弱りやすい場所です。
腱板を目覚めさせるシンプルな動き
やり方はとても簡単で、特別な器具は必要ありません。
-
タオルを小さくたたんで、脇の下にしっかりはさむ
-
肘を体につけたまま固定し、肩が動かないようにする
-
手にうちわを持ち、手首を動かさずに腕の力だけで外側に扇ぐ
この動きを左右それぞれ10回ずつ、1日3セット行います。時間にすれば数分でできるため、仕事の合間やテレビを見ながらでも続けやすいのが特長です。
うちわがない場合は、丸めたタオルや軽めのハンカチなどでも代用可能。大事なのは、肩の奥にある筋肉をしっかり意識しながら、丁寧に動かすことです。
このエクササイズを続けることで、腕が上げやすくなったり、動きがスムーズになったと感じる人が多いそうです。肩こりや肩の違和感だけでなく、腕の動かしにくさにも悩んでいる方にとって、取り入れやすく効果的な“+αのワザ”となっています。
肩がつらい人は“黄金リズム”を取り戻して
今回の特集では、肩の健康を守るには「肩甲骨と腕の骨の連動=黄金リズム」が大切であると伝えていました。日々の生活の中で気づかないうちに乱れているこのリズムを、自分で気づき、整えるための方法がたくさん紹介されました。
少しの意識と数分のエクササイズで、肩の重さがスッと軽くなるかもしれません。体操やストレッチが苦手な方でも、毎日続けやすい内容ばかりです。肩こりや腕の上がりづらさに悩んでいる方は、ぜひ試してみてください。
番組名:あしたが変わるトリセツショー
放送日:2025年7月17日(木)
放送時間:19:30〜20:15(NHK総合)
出演:市村正親、中岡創一(ロッチ)、川村エミコ(たんぽぽ)、コカドケンタロウ(ロッチ)
出典:NHK番組情報より
https://www.nhk.jp/p/torisetsu-show/ts/5V52Z3Q4YL/
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

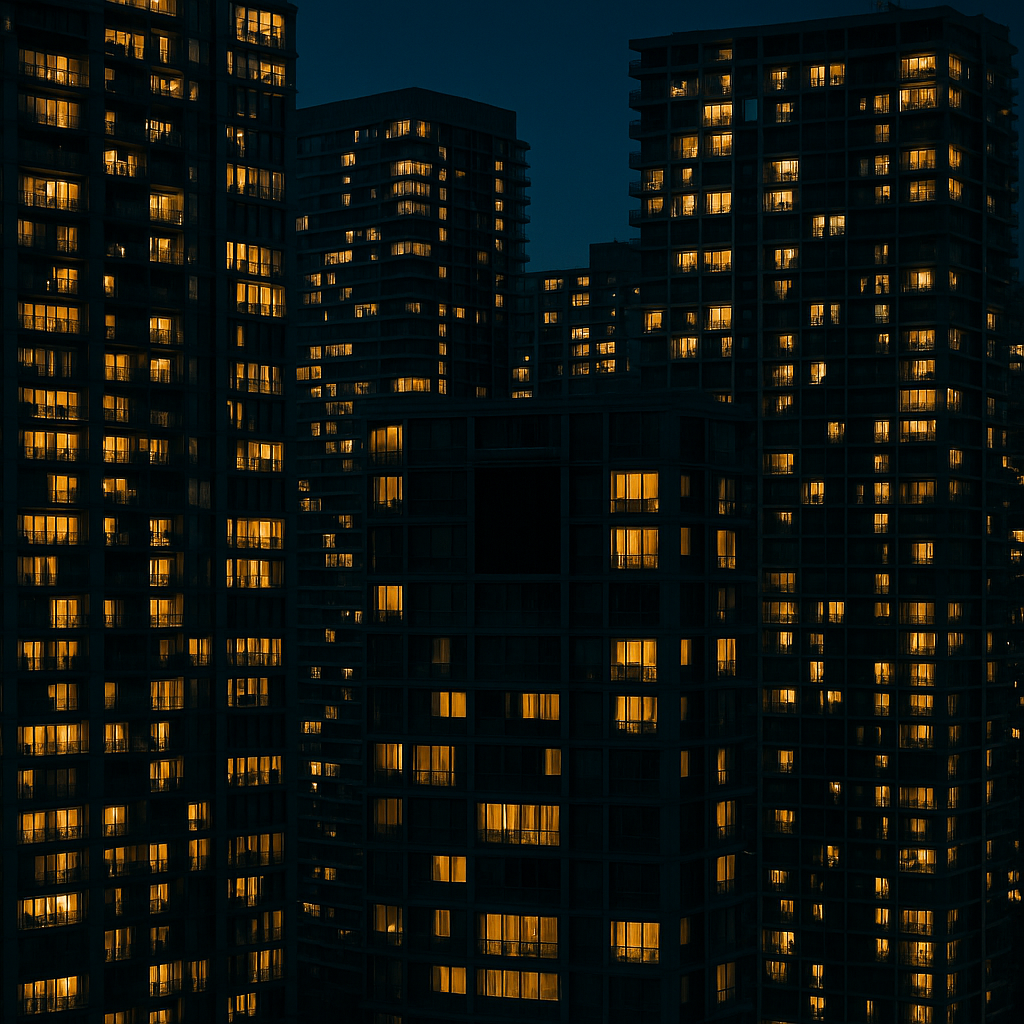

コメント