ライオンの若き挑戦者マヒリに試練の時が…!
2025年7月27日に放送された「ダーウィンが来た!」では、東アフリカ・セレンゲティ国立公園を舞台に、若きオスライオン・マヒリの生きざまを追ったシリーズ第5弾が放送されました。王者を目指す彼の姿に加え、ブサーラやスージャといった他のライオンたちの動きも描かれ、自然の厳しさとライオンの知恵が見える回となりました。
マヒリ、どん底からの再スタート
仲間を持てず孤立した若きライオンの過去
東アフリカ・セレンゲティ国立公園で追跡されているオスライオン・マヒリは、密着取材が始まった2年前、まだ3歳の若さでした。当時のマヒリは、まだ体も小さく、他のオスライオンとの関係もうまく築けずにいました。縄張りを持つこともできず、単独で行動することが多かったため、ライオン社会のルールを学ぶ機会にも恵まれませんでした。おしっこを使って優位性を示そうとしても、他のライオンに受け入れられず、思うようにいかない日々が続いていたのです。
成長とともに増える苦しみ、体に刻まれた傷
今回の放送では、マヒリが5歳となり、見た目にはたくましい大人のライオンへと成長していました。しかしその体には、無数の傷が残されていました。特に肩や背中には大きなひっかき傷があり、最近の争いの激しさを物語っていました。ちょうど雨季の時期で、草原には草食動物たちが多く集まっていたにもかかわらず、狩りができないマヒリは、ただ遠くから眺めるしかないという状況でした。ライオンは1週間ほどなら食べずに過ごすことができますが、それが続けば体力も衰え、次の機会にも動けなくなってしまいます。
獲物の横取りで生き延びる日々
空腹に耐えかねたマヒリは、ある日、自分の近くで狩りに成功した若い放浪オスのところへ向かい、その獲物を力づくで横取りしました。5歳という年齢になり、体格でも若いオスを圧倒できるようになったことで、こうした行動が可能になったのです。けれど、そうした優位は長くは続きませんでした。その後、複数の放浪オスが現れ、マヒリの奪った獲物をさらに横取りしようとします。マヒリは囲まれてしまい、逃げる間もなく激しい争いに巻き込まれていきました。
ライオン社会の「マナー」を学ばずに育った影響
このような衝突の原因には、マヒリの成長過程も大きく関係しています。通常、若いオスライオンは群れの中で同年代の仲間と過ごしながら、オス同士の距離感や上下関係を少しずつ学んでいきます。しかしマヒリの場合、同じ年頃のオスと出会うことが少なく、群れの中でも孤立したままでした。そのため、他のオスとどう接すればよいかを学ぶ機会がなかったのです。自分を大きく見せようと威張ったり、必要以上に攻撃的になってしまうことが、衝突を招く原因となっていました。
こうして、マヒリは強くなると同時に、孤独や不器用さとも戦いながら、王者への道を少しずつ歩き続けています。今回の放送では、その一歩一歩の重さが伝わってくるような場面が続きました。今後、彼がどのように周囲と関係を築いていくのか、次回の展開にも注目が集まります。
ブサーラ、頼りの兄を失う試練
突然の長距離移動と兄の不在
ブサーラは、これまで兄と一緒にセレンゲティの山間部に縄張りを持ち、協力して生き抜いてきたオスライオンです。取材が始まった2年前から、兄弟は抜群のコンビネーションで狩りや縄張りの防衛をこなし、安定した暮らしを築いていました。しかし今回、ブサーラのGPSに異変が現れました。なんと、自らの縄張りから約60kmも離れた場所に移動していたのです。
それは、通常の縄張り行動からは大きく外れる距離でした。その理由は明らかではありませんが、外敵からの圧力や、兄との別れに関係していると見られています。やがてブサーラは再び元の縄張り付近に戻りましたが、そこに兄の姿はありませんでした。周囲の様子や行動から判断し、兄はすでに命を落とした可能性が高いと考えられています。
兄の喪失と新たな仲間との歩み
長年連れ添ってきた兄の不在は、ブサーラにとって非常に大きな喪失でした。ライオン社会において兄弟は、ともに獲物を狩り、敵から身を守り、縄張りを維持するかけがえのない存在です。それを突然失ったことで、ブサーラは精神的にも孤立し、これまでと違う行動を取らざるを得なくなっていきました。
そんな中、ブサーラは一頭の若い放浪オスと一緒にいる姿が確認されました。このオスは、自分の群れや縄張りを持たず、常に新たな居場所を探し続けている個体です。ブサーラは、年齢も性格も異なるこの新しい仲間との関係に戸惑いながらも、かつての兄との日々を思い返しつつ、また一から信頼関係を築こうとしています。
群れの中心的な存在としての役割を果たしてきたブサーラにとって、この変化は決して小さなものではありません。しかし、新しい環境に身を置き、異なる個体と関わることで、彼の中にこれまでにない成長や進化が生まれるかもしれません。今後、ブサーラがどのように再起していくのか、その姿に注目が集まっています。
マヒリ、痛みを知りマナーを学ぶ
勝てない戦いから学んだこと
マヒリは、ある日、自分よりも力のある複数の放浪オスライオンたちと対峙する場面に出くわしました。獲物をめぐる争いは激しく、逃げ場のない状況での戦いを余儀なくされます。数で圧倒されたマヒリは、力では敵わず獲物を失い、体にも大きなダメージを受ける結果となりました。しかし、この敗北がマヒリにとって無駄ではありませんでした。こうした実戦の中で、他のライオンとの力関係や距離の取り方など、自然の中でしか学べない“オス同士のマナー”を少しずつ理解しはじめたのです。
マヒリは若い頃、同世代のオスと過ごす機会がほとんどなく、群れでの社会性を学ばないまま成長してしまいました。そのため、相手との関係をどう築くべきかがわからず、無用な衝突を招くこともありました。今回の経験は、そんなマヒリにとって大きな転機となったようです。
分け合うことで築いた“対等な関係”
この後、マヒリはまた別の場面で狩りのチャンスを得ます。ハイエナがしとめた獲物を見つけたマヒリは、迷わずその場に突進し、獲物を奪い取ります。そこに、もう一頭の放浪オスが現れ、一気に空気が緊迫します。これまでのマヒリであれば、強引に押し切ろうとしてさらに争いを引き起こしていたかもしれません。しかしこの日は違いました。お互いに一瞬立ち止まり、相手の出方を冷静に見ながら、最終的には争うことなく獲物を分け合うという展開に落ち着きました。
これはマヒリにとって、とても大きな進歩でした。相手を「敵」ではなく「仲間になれる存在」として認識し、無用な戦いを避けるという行動ができたのです。自然界では、無駄な争いは命取りになります。だからこそ、相手の実力を見極め、必要以上に戦わずに済ませる判断力は、生き抜く上でとても大切です。
きょうだいとの再会、新たな希望の兆し
さらには、マヒリがかつてのきょうだいのメスと再び一緒に行動しはじめたことも報告されました。孤独だったマヒリにとって、家族との再会は心強い支えになります。きょうだいの存在は、単に安心感をもたらすだけでなく、今後群れを作るための基盤にもなり得ます。
こうした変化の連続が、マヒリを次のステージへと導いています。試練を経て学びを得た今のマヒリには、これまでとは違う未来が見えはじめているようでした。王者の座に近づくために必要な“他者との関わり方”を身につけはじめた彼のこれからに、ますます注目が集まります。
次回は王者候補・スージャに注目
エンディングでは、次回の放送につながるスージャの近況も紹介されました。スージャは放浪オス2頭と手を組み、協力して狩りを行うなど順調な様子。3頭の絆が深まる中、王者の座に一番近い存在として今後の展開に期待が高まります。
ライオンたちの生き様を通して、「強さとは何か」「仲間との関係がいかに大切か」が自然の中でくっきりと描かれた今回の放送。厳しい環境の中で少しずつ成長していく姿が心に残る回となりました。
次回「王者への道(6)」も放送予定です。見逃し配信や再放送のチェックもおすすめです。
動物たちの“生きる知恵”をもっと知りたい人へ

ここからは、私からの提案です。番組を見て、「どうしてライオンはおこぼれをもらうの?」「仲間をつくるってどういうこと?」といった疑問を持った方には、NHK関連の図鑑や本がとても役立ちます。特に「ダーウィンが来た!」をもとにした図鑑やマンガは、子どもから大人まで楽しく読めて、動物たちのサバイバル戦略をわかりやすく学べます。
発見!マンガ図鑑 NHKダーウィンが来た!サバイバル大作戦編
この本は、「ダーウィンが来た!」のエピソードをマンガ形式で再現した図鑑です。グンタイアリの行進や、仲間で協力して生き延びるチーター兄弟など、さまざまな動物の生き方を紹介しています。マヒリのように、けがをしてもあきらめずに行動する姿と重なる話も多く、読みながら自然と野生の知恵を学べる構成になっています。絵が多くて文章もわかりやすいので、小学生のお子さんにもおすすめです。
ダーウィンが来た!DVDブックシリーズ
こちらは、番組の映像と解説がセットになった書籍シリーズです。DVDには番組で実際に放送された映像が収録されていて、ページにはその背景となる知識や動物の特徴がくわしく書かれています。映像を見ながら学べるので、まるで現地にいるような臨場感があります。マヒリのように“見えない戦い”をしている動物たちが、どうやって生き延びてきたのかがよくわかります。
特におすすめなのは、『発見!マンガ図鑑 NHKダーウィンが来た!サバイバル大作戦編』です。この本では、動物が置かれた環境にどう適応しているかを、失敗と成功の連続で描いているので、マヒリのような「弱くても諦めない動物」に共感した人にはぴったりです。書店やオンラインショップで取り扱いがあり、親子で読む“学びの入門書”としても人気があります。
このような関連図鑑を読むことで、番組で感じた「どうして?」をより深く理解することができ、動物たちの世界にぐっと近づくことができます。記事の最後に購入リンクや紹介文を加えることで、読者の関心をそのまま行動につなげることも可能です。観察だけでなく、知識としても動物の世界を楽しむための導線として、こうした書籍の紹介はとても効果的です。


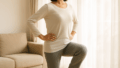
コメント