日本のヨーグルト文化を探る旅
ヨーグルトといえばブルガリアを思い浮かべる人が多いですが、実は日本も独自に発展した“ヨーグルト大国”です。この回の「最深日本研究」では、ブルガリア出身の経営人類学者 ヨトヴァ・マリア が、日本でのヨーグルト文化の深まりを研究する姿が紹介されました。ヨトヴァは日本に20年以上住み、これまで食べたヨーグルトは1000種類以上。パッケージを保存し、20本以上の論文も執筆してきたほどです。この記事では、番組で描かれた日本のヨーグルトの歴史と未来を振り返ります。
日本独自の乳酸菌文化
ヨーグルトは、牛などの乳を乳酸菌によって発酵させて作られる発酵乳です。乳酸菌が乳糖を分解し、乳酸を生み出すことで、あの独特の酸味が生まれます。発酵の過程でたんぱく質の構造も変化し、消化吸収が良くなるのも特徴です。世界中で愛される理由のひとつは、このシンプルな仕組みに隠されています。
ヨーグルトの本場であるブルガリアでは、ヨーグルトと名乗るために厳しい基準があります。必ず『ブルガリア菌』と『サーモフィルス菌』という二種類の菌を含んでいなければならず、これが国によって法律で定められているのです。つまりブルガリアでは、ヨーグルトの味や香りはある程度共通しており、“国民食”として安定した品質が守られています。
一方で日本にはそのような制限がありません。そのため、メーカーや地域ごとに自由な発想で乳酸菌を使うことができ、現在では数十種類以上、菌株レベルでは数百から数千にものぼる多様な乳酸菌が活用されています。この自由さこそが、日本独自のヨーグルト文化を育んできました。スーパーに並ぶヨーグルトを見比べると、酸味の強いものから甘みを感じるもの、さらには機能性を前面に出したものまで、実に幅広い商品があるのはこの背景によるものです。
その中で、ブルガリア出身の研究者ヨトヴァ・マリアが特に注目しているのが『ロイテリ菌』です。これは南米アンデス山中に暮らすペルー人女性の母乳から発見された特別な乳酸菌で、口の中の細菌バランス、いわゆる口内フローラを整える働きが期待されています。腸だけでなく口内環境まで考えるヨーグルトは、これまでになかった新しい健康アプローチとして注目を集めています。
このロイテリ菌を商品化するにあたり、日本のある企業はスウェーデンの会社と独占契約を結びました。世界でも限られた場所でしか取り扱えない菌を使えるという点で、大きな価値が生まれています。こうして開発されたヨーグルトは、日本市場で“口内フローラを意識したヨーグルト”という新たなカテゴリーを築きつつあります。健康志向が高まる今、こうした研究と商品化の流れは、さらに広がっていくことが期待されています。
日本に根づいたヨーグルトの歴史
ヨーグルトの歴史はとても古く、その起源は7000年以上前にさかのぼるといわれています。あるとき偶然、牛乳に乳酸菌が入り込み、自然に発酵してできたのが始まりでした。冷蔵技術のない時代に、保存性を高める知恵として発酵乳が受け継がれ、やがてヨーグルトとして食文化の中に定着していきました。
20世紀の初めになると、ヨーグルトは単なる保存食を超え、健康食品として大きな注目を集めます。きっかけは、ブルガリアに長寿の人が多いことに目をつけたロシアの免疫学者でした。彼は「ブルガリアの人々が日常的に食べているヨーグルトこそ、腸内環境を整え、長寿を支えているのではないか」と発表しました。この研究によって、ヨーグルトは初めて科学的に健康効果が証明された食品として世界に広まっていったのです。
日本にヨーグルトが登場したのは明治時代。当時は「凝乳」と呼ばれ、整腸剤のように健康目的で販売されていました。その後、戦後の食文化の変化とともに“甘いヨーグルト”が登場し、子どもたちのおやつとして親しまれるようになります。
大きな転機となったのは1970年の『大阪万博』です。ブルガリアから持ち込まれた“酸っぱいヨーグルト”を食べた日本の乳業会社の関係者が、その味に大きな衝撃を受けました。当時の日本では甘いヨーグルトが常識でしたが、この酸味こそ本場の味であると知り、粘り強い交渉の末に『ブルガリアヨーグルト』が誕生します。
最初は酸味が強くて受け入れられにくかったものの、次第にその味が浸透し、「プレーンヨーグルト」という新しい選択肢が定着しました。この出来事をきっかけに、日本のヨーグルト文化は大きく広がり、機能性や風味にこだわった多彩な商品が次々と誕生していったのです。
和菓子店が作る新しいヨーグルト
番組では、創業70年以上を誇る老舗の和菓子店が紹介されました。どら焼きや地元産のマスカット菓子で知られるこの店が、実は4年前からヨーグルト作りに挑戦していたのです。和菓子店らしい視点で生み出されたヨーグルトは、単なるデザートではなく、ひとつの“作品”のように丁寧に仕上げられていました。
この店の大きな特徴は、効率よりも素材を大切にする姿勢です。地元でとれる旬の果物を贅沢に加えることで、ヨーグルトに四季折々の味わいが生まれます。春にはベリー、夏にはマスカット、秋には柿や栗、冬には柚子など、季節ごとに異なる表情を見せるヨーグルトは、訪れるたびに新しい楽しみを提供してくれます。こうした“季節感を映すヨーグルト”こそ、日本ならではの独自性だとヨトヴァ・マリアは高く評価しました。
さらに、羽田空港のお土産コーナーにも多彩なご当地ヨーグルトが並び、観光客の注目を集めていました。地方ごとに異なる乳や果物を生かした個性豊かなヨーグルトは、旅の思い出としても人気が高く、日本の食文化を象徴する新しい“おみやげ”になりつつあります。
岡山・建部町のご当地ヨーグルト
さらに番組では、岡山市建部町にある小さなヨーグルト工房を訪れました。ここは従業員がわずか4人という規模ながら、地元でとれた牛乳を100%使用することにこだわり続けています。工房を率いるのは、かつて酪農家だった社長。自分たちが育ててきた牛の恵みを無駄にせず活かしたいという思いから、ヨーグルト作りを始めたといいます。
背景には、1980年代に起きた牛乳の供給過剰問題がありました。当時は余った牛乳が廃棄されることもあり、その状況を何とか打開するために、この地域では新しい活用法を模索しました。その結果生まれたのが、ご当地ヨーグルトという形での取り組みだったのです。
また、工房では牛乳の質を左右するものとして、牛の餌にまで目を向けています。どんな飼料を与えるかによって牛乳の風味が変わり、その違いが最終的にはヨーグルトの味わいに直結します。つまり一杯のヨーグルトには、地域の自然や農業の歴史が色濃く反映されているのです。
こうした取り組みを通じて、ご当地ヨーグルトは単なる食品ではなく、地域の自然・文化・人々の暮らしを伝える存在となっていることが改めて示されました。
ヨーグルトが映す日本の未来
ヨトヴァ・マリアの研究は、単にヨーグルトという食品を分析するだけにとどまりません。彼女は比較文明学や経営人類学の視点を交えて、日本におけるヨーグルト文化の広がりを社会全体の姿として読み解いています。どのように企業が商品を開発し、地域が特色を生かし、消費者がそれを受け入れていくのか。その過程を追うことで、日本の多様性や企業文化までもが浮かび上がってくるのです。
今の日本でヨーグルトは、単なる整腸効果や健康食品の枠を超えています。ご当地の素材を活かしたり、旬の果物を加えたりすることで、ヨーグルトは地域性や四季感を映し出す食品へと進化しました。かつては「日本人に馴染みのない乳製品」とされていたヨーグルトが、今では「地元の味」「ふるさとの味」として親しまれ、暮らしの中にしっかり根づいています。
ヨトヴァの目を通して見れば、日本のヨーグルトは単なる発酵食品ではなく、人々の生活・文化・歴史を語る象徴的な存在になっているのです。
まとめ
この記事のポイントは以下の通りです。
-
ヨトヴァ・マリアが1000種類以上のヨーグルトを研究し、日本独自の文化を解明
-
『大阪万博』を契機に酸っぱいヨーグルトが定着、日本市場が拡大
-
和菓子店やご当地工房が作る“日本らしいヨーグルト”が新しい潮流に
-
『ロイテリ菌』など健康効果を追求した研究が進展中
ヨーグルトは単なる食品を超え、日本文化や地域性を映す存在になっています。次にスーパーや空港で見かけたときは、その背景にある物語を思い出してみてください。きっと新しい発見があるはずです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

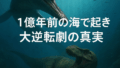

コメント