政局の分岐点に立つ日本――日曜討論
2025年秋、日本の政治は新たな転換点を迎えました。おととい、公明党が自民党との長年の連立を解消するという決断を下したのです。政権運営を支えてきた26年の関係に終止符を打つ——その報せは政界に衝撃を与えました。
今週の『日曜討論』では、公明党代表・斉藤鉄夫氏が生出演し、連立離脱の真相と今後の方針を率直に語りました。また番組後半では、内政の混乱が外交にどのような影響を及ぼすのか、4人の専門家が深く掘り下げて討論。政治と外交の両面から、「新しい日本の進路」が問われる1時間となりました。
斉藤代表が語る「決断の真意」
番組冒頭、司会の太田真嗣アナウンサーがまず問うたのは、「なぜ今、離脱なのか」。
斉藤代表は静かに、しかし明確に答えました。「理由は単純です。国民の信頼を失ってしまっては、政治は成り立たない。」
問題の根底には、自民党の政治資金不記載問題があります。昨年の参院選で公明党が苦戦した背景には、この“政治とカネ”をめぐる不信がありました。それ以来、公明党の議員たちは地方の支持者から「自民党の説明は納得できない」「なぜ公明党が庇うのか」といった声を聞き続けてきたといいます。
「自民党の代わりに説明して回るような状況は限界だった」と斉藤氏。新総裁に就任した高市早苗氏に対しても、「信頼を回復する改革の姿勢を見せてほしい」と伝えたものの、明確な回答は得られなかったと明かしました。
とくに焦点となったのが「企業・団体献金の規制強化」です。これは、かつて立憲民主党・国民民主党・自民党の3党首が話し合いを行った重要テーマで、公明党は「全面禁止ではなく、透明性を高めた規制強化」を提案していました。しかし、交渉の中で自民党から具体的な姿勢が示されず、「このままでは国民の信頼を得られない」との結論に達したといいます。
斉藤代表は、「タイミングは、まさに連立政権を再構築する話し合いの場だったからこそ」と語り、「連立を一度白紙に戻す」という決断に至った理由を明確にしました。
公明党の今後と自民党との関係
番組では、連立解消後の公明党の立ち位置にも注目が集まりました。
斉藤代表は、「自民党と敵対関係になるわけではない」としながらも、「26年間積み上げた信頼を壊すことはないが、同じ関係には戻れない」と強調しました。
「今後も、これまで一緒に準備してきた予算案や法案は協力して成立を目指すが、政治的な枠組みとしての連立は終わりを迎えた」と明言。その姿勢は、与野党どちらにも偏らない“中道政党”としての自負を示すものでした。
さらに「首相指名選挙」への対応を問われると、「長年連携してきた自民党の名前を書かないというのは現実的に考えにくい」と本音をのぞかせ、公明党が単なる野党化ではなく、“建設的距離感”を保つ意向を示しました。
企業・団体献金問題の核心
政治資金の扱いをめぐる改革案について、公明党は国民民主党と協力して法案化を模索しています。司会の上原光紀アナウンサーが「野党側から法案提出を目指すのか」と問うと、斉藤代表は「政治活動のルールは全党で議論し、合意していくのが本来の姿だ」と答えました。
また、選挙協力についても「党同士の推薦は行わないが、人物本位で支援を考える」と説明し、政党間よりも「人間として信頼できる候補者」を軸に判断する考えを示しました。
この発言は、今後の選挙戦における「無所属・個人重視」の流れを予感させるものであり、政界全体に波紋を広げています。
日本外交の課題――“内政の不安定さ”がもたらす影響
番組後半では、連立離脱によって揺れる政局が日本の外交にどのような影響を与えるのかがテーマになりました。
登壇したのは、国分良成(防衛大学校)、中西寛(京都大学)、小谷哲男(明海大学)、大庭三枝(神奈川大学)の4名。
国分氏は「外交の本質は継続性にある。政権交代が続けば、国際社会での信頼は失われる」と指摘。
中西氏も「戦後80年の節目に、内政の混乱が日本外交の安定を脅かしている」と述べました。
特に小谷氏は「トランプ大統領が再び求める“防衛費の負担増”にどう対応するかが日本の課題」と分析。
大庭氏は「アジア情勢が不安定化する中で、ASEAN諸国やグローバルサウスとの関係を強化することが、日本の生き残り戦略だ」と語りました。
ASEAN・日米首脳会談に注目が集まる
今後の外交スケジュールで注目されるのがASEAN首脳会議と日米首脳会談です。
国分氏は「アジア太平洋地域は米中対立の最前線。日本は“自由で開かれたインド太平洋”という理念を現実の外交でどう示すかが問われている」と述べました。
中西氏は「アジア太平洋経済協力会議(APEC)など国際会議を通じて、米印関係の修復にも関心を持つべき」と強調。
一方で大庭氏は「トランプ大統領がASEAN会議に直接出席することで、東南アジア各国の反応を首相自らが感じ取ることが重要」と語り、現場主義の外交を求めました。
トランプ政権のもとで、防衛・貿易・関税の再交渉が行われる可能性も高く、日本の外交姿勢は大きく問われることになりそうです。
中国と北朝鮮、そして地域の緊張
次に議論が及んだのは中国と北朝鮮の動きです。
中国は上海協力機構を主導し、「冷戦思考に反対」「多極化の推進」を訴える一方で、レアアースの輸出規制を強化し、**アメリカの追加関税100%**に対抗する構えを見せています。
国分氏は「中国は内政重視の体制に傾いており、外交は閉鎖的になっている」と指摘。研究者や民間人の往来も減り、「中国の真意が見えにくくなっている」と懸念しました。
北朝鮮については、朝鮮労働党創立80周年の軍事パレードで新型ICBM『火星20型』を公開し、中国・ロシアの要人が出席。キム・ジョンウン、李強、メドベージェフが並ぶ光景は、3国の連携強化を象徴するものでした。
小谷氏は「トランプ大統領が再び金正恩氏と会談する可能性がある。北朝鮮を“核保有国”として容認する流れには警戒が必要」と述べ、地域安全保障への影響を指摘しました。
中西氏は「アメリカ頼みではなく、日韓連携を軸に地域の安定を守る時期に来ている」と語り、これまでの日本外交の成果を踏まえて「歴史を越えた協力が必要」と訴えました。
新政権が描くべき外交ビジョンとは
討論の最後に、4人の専門家がそれぞれの視点から「これからの日本外交」に提言しました。
大庭氏は「国際秩序の維持に日本がどう貢献するかが問われている。他国と連携しながら、ミドルパワーとしての存在感を高めるべき」と語りました。
小谷氏は「『自由で開かれたインド太平洋』の理念を堅持し、トランプ大統領に第一列島線の重要性を理解してもらうことが必要」と発言。
中西氏は「アメリカ依存の外交は限界にきている。より多面的で奥行きのある外交が求められる」と指摘。
国分氏は「日米同盟の本質は太平洋にある。アメリカの影響力が低下する中で、日本がどのように役割を担うかが最大のテーマ」と締めくくりました。
まとめ
この記事のポイントは以下の3つです。
・公明党の連立離脱は「政治とカネ」への不信が頂点に達した結果である。
・新政権の外交課題は、トランプ政権との再交渉と中国・北朝鮮への対応。
・日本がアジアと世界の間でどんな役割を果たすのかが、今後の試金石となる。
政治の安定が外交の信頼を生み、外交の信頼が国の未来を形づくる。いま、政権も国民も、改めて「信頼」という言葉の重さを問われているのかもしれません。
出典:NHK『日曜討論』(2025年10月12日放送)
https://www.nhk.jp/p/touron/
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

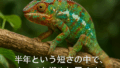
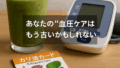
コメント