ナスとオクラが虫を呼ぶ?有機栽培の知恵が満載の里山菜園
2025年5月20日放送のNHK「やさいの時間」では、「里山菜園 有機のチカラ」と題して、虫との関係に注目した有機栽培の知恵が紹介されました。出演は宮崎慶太さん、トラウデン直美さん、そして農学博士の牧田習さん。番組は体調不良で休演した有機栽培研究家・佐倉朗夫さんの代わりに、宮崎アナが進行を担当。今回は「ムシできない関係」と題し、ナスとオクラ、そしてソルゴーの不思議な関係に迫りました。
春キャベツの収穫と観察ミッション
番組の冒頭では、田植えの時期を迎える水田の様子が紹介され、ハクセキレイやアオサギが水面の上を歩いたり、飛んだりする姿が映し出されました。田んぼの水と空の色が映えるなか、鳥たちが自然の中で自由に動く姿は、まさに人と自然が共に生きる里山の風景でした。
舞台は有機栽培の菜園へと移り、ここでは昨年の11月に植えた春キャベツが大きく育ち、いよいよ収穫のタイミングを迎えています。キャベツの収穫は見た目だけでなく、球を手のひらで押してみて、硬く締まっているかどうかを確認することで収穫時期を見極めます。畑ではキャベツの葉にアオムシがついており、農薬を使わない有機栽培ならではの光景がありました。虫を排除するのではなく、自然の営みの中で野菜と虫が共存していることが、この畑の特徴でもあります。
トラウデン直美さんは収穫したばかりのキャベツを調理場へ運び、料理づくりを担当しました。新鮮なキャベツの香りや葉のシャキッとした音が、春の味覚を連想させます。キャベツの水分や甘みを活かしたレシピが紹介される流れとなりました。
一方、農学博士の牧田習さんには「捕食の瞬間を観察せよ!」というミッションが与えられました。畑の中に目を凝らし、小さな昆虫たちの動きを丁寧に追いかけながら、捕食の現場に出会うことが目的です。
-
牧田さんが観察対象としたのは、ナナホシテントウやアブラムシなど畑に多く見られる昆虫たち
-
特にナナホシテントウはアブラムシを捕食する益虫として知られており、1日に約100匹ものアブラムシを食べる力を持っています
-
畑では虫たちの生態系が循環しており、食べる側と食べられる側の関係が自然に成り立っていることが確認できました
このように、春キャベツの収穫をきっかけに、畑では野菜・虫・人の営みが一体となっていることが番組を通じて伝えられました。有機栽培の現場は、ただ野菜を育てるだけでなく、命のつながりを理解する場でもあることが、具体的なシーンから丁寧に描かれていました。
春キャベツとしらすのペペロンチーノ風
トラウデン直美さんが手がけた料理は、春の旬食材を活かした「春キャベツとしらすのペペロンチーノ風」です。使われたのは、収穫されたばかりの春キャベツと、旨みたっぷりのしらす。シンプルながら素材の味が際立つレシピでした。
調理の手順は、まずニンニクをオリーブオイルでじっくり炒めて香りを出し、そこに食べやすい大きさに切ったキャベツを投入。赤トウガラシも加えて、ピリッとしたアクセントを加えます。キャベツの緑色が鮮やかになったころに、たっぷりのしらすを加え、さっと火を通して完成です。
-
春キャベツは火を通すと甘みが増し、葉が柔らかくなる
-
しらすは最後に加えることで、ふんわりとした食感と塩気をそのまま活かせる
-
ニンニクと赤トウガラシが香りと刺激をプラスし、春キャベツのやさしい味を引き立てる
試食した牧田習さんは、「キャベツのうまみが出ている」と感想を述べていました。料理の様子からは、春キャベツの甘みとしらすの塩味がちょうどよく調和していることが伝わってきました。
この一皿は、春の旬食材を無駄なく活用でき、手軽に作れて栄養もたっぷりな家庭向けメニューです。有機栽培で育てた野菜だからこそ感じられる、やさしい味わいが詰まった料理でした。
ナナホシテントウの捕食行動を観察
牧田習さんに与えられたミッションは、「捕食の瞬間を観察せよ!」。その対象は、畑で見かける身近な昆虫たちでした。今回は、特にナナホシテントウに注目。黒地に7つの赤い斑点を持つ小さなテントウムシが、アブラムシを捕らえる瞬間をじっくりと観察しました。
ナナホシテントウは、野菜を守る「益虫」として知られています。観察の中では、キャベツの葉や草の茎につくアブラムシを、ナナホシテントウが器用に動き回りながら、次々と口に運ぶ様子が映し出されていました。その捕食スピードは意外に速く、アブラムシを次々と飲み込むように処理していく姿が印象的でした。
-
ナナホシテントウは1日に最大100匹のアブラムシを捕食するとされており、被害を受けやすい農作物の強い味方
-
観察中は、葉の裏や茎の分かれ目など、虫が潜みやすい場所を丹念にチェックする姿も映されていた
-
捕食によってアブラムシの数が減ると、化学農薬を使わずとも作物の被害が抑えられることにつながる
また、他にも畑に見られた昆虫として、コアオハナムグリの姿も紹介されました。光沢のある緑色の甲虫で、花の蜜や花粉を好む性質があります。畑にはこのようにさまざまな昆虫が共存しており、それぞれが独自の役割を担っていることがわかります。
畑の中では、人の目には見えにくい世界で、虫たちの営みが静かに続いています。今回の観察を通じて、**野菜作りの裏には、虫と虫とのせめぎ合いという「小さな生き物のドラマ」**があることが実感できました。これは、有機栽培ならではのリアルな自然の姿でした。
ナス・オクラ・ソルゴーのムシできない関係
番組の後半では、ナス・オクラ・ソルゴーがつくる自然の連携プレーに注目した特集が展開されました。テーマは「ムシできない関係」。これは単なる言葉遊びではなく、野菜と虫、そして植物同士が影響し合う有機栽培の知恵を象徴する言葉です。
登場したのは、筋状の傷がついたナス。この傷は、アザミウマという非常に小さな害虫の被害によって生じたものでした。アザミウマは新芽などの柔らかい部分を吸汁し、植物全体を弱らせてしまうため、放っておくと株が衰えて収穫量も減るという深刻な問題を引き起こします。
そこで救世主として紹介されたのが「ヒメハナカメムシ」。この小さな昆虫は、アザミウマをはじめ、ハダニやアブラムシなど複数の害虫を捕食する益虫です。農薬に頼らずに害虫を減らすには、こうした天敵を味方につけることがとても重要になります。
ヒメハナカメムシを畑に呼び寄せる方法として登場したのが、ソルゴーとオクラの存在です。
-
ソルゴーはイネ科の植物で、畑の周囲に帯状に種をまくことで、益虫がすみやすい環境をつくることができます
-
ソルゴーの茎や葉がヒメハナカメムシの隠れ家となり、自然と畑に定着するようになる
-
オクラもまた、花や茎の構造が益虫にとって過ごしやすく、同じように呼び寄せる効果がある
このように、ナスが被害を受けやすいアザミウマから守られるためには、別の植物や昆虫との関係をつくることが有効であることが、番組で詳しく紹介されました。
-
ソルゴーは日よけにもなり、風よけとしても活躍するため、畑にとっては一石二鳥の存在
-
オクラはアフリカ原産のため、乾燥や暑さに強く、育てやすい野菜としても親しまれている
-
畑の設計段階から、どこに何を植えるかを考えることで、虫との関係を味方につけることができる
この「ムシできない関係」は、単なる害虫対策ではなく、生態系全体を活用した自然との共生の仕組みです。農薬を使わず、自然の循環を利用して畑を守る工夫は、家庭菜園にも応用できる知恵として紹介されていました。人の手を最小限にしつつ、自然の力を最大限に引き出す仕組みが、ナス・オクラ・ソルゴーのトライアングルから見えてきました。
トラウデンさんがソルゴーの仕組みを解説
番組内でトラウデン直美さんに課されたのは、「ソルゴーが益虫を呼ぶ仕組みを説明せよ!」というミッションでした。トラウデンさんは、畑の中で実際にソルゴーに触れながら、その役割を丁寧に解説していきました。
ソルゴーはイネ科の植物で、成長が非常に早いことが特徴です。この特性により、短期間で背の高い植物群を形成し、畑の中に虫たちが過ごしやすい環境をつくることができるのです。葉の裏や茎の隙間が、ヒメハナカメムシをはじめとする益虫の隠れ場所や移動経路となり、結果として畑全体に自然な虫の循環が生まれると紹介されました。
-
ソルゴーは直射日光や風を和らげる効果もあり、畑の周囲に植えることで作物全体を守る壁の役割にもなる
-
葉の茂り方や密度がちょうどよく、小さな昆虫たちにとって最適な生活空間になる
-
畑の一部ではなく、外周に沿って種をまくことが推奨され、畑全体を囲むように配置することで効果が高まる
さらに、オクラの苗の植え付け作業にも触れられました。オクラはアフリカ原産で乾燥に強く、浅く植えるのが適していると解説されました。これは、根が広がりやすくするためであり、日本の土壌でも比較的育てやすい野菜です。オクラにも益虫を呼び寄せる効果があり、花の部分や葉の構造が虫たちの居場所となることが紹介されました。
-
オクラの浅植えは水はけと通気性を良くし、根腐れを防ぐための工夫
-
花が咲く時期になると、ハナカメムシやアブラムシの天敵となる虫が自然に集まる傾向がある
-
ソルゴーとオクラの組み合わせにより、多様な益虫が畑に滞在しやすくなる
このように、植物の特性を活かして虫との関係をコントロールする方法は、有機栽培の基本とも言える発想です。ソルゴーやオクラの育て方や植え方の工夫は、家庭菜園にもそのまま取り入れやすく、無農薬で野菜を育てたい人にとっても大きなヒントとなるものでした。トラウデンさんの説明は、自然と人が協力して畑を守る仕組みをわかりやすく伝えるものでした。
放送を通じて伝わったメッセージ
今回の放送では、有機栽培が虫たちと密接につながっていること、そして「害虫=悪」ではなく、「自然とのバランスを取ること」が大切であることが強調されました。ナスやオクラの栽培においても、虫との関係を知ることが豊かな収穫につながるというメッセージが伝わってきました。
春キャベツのレシピ紹介から、虫の生態の観察、そして有機栽培の知恵まで、今回の「やさいの時間」は盛りだくさんの内容でした。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

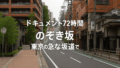
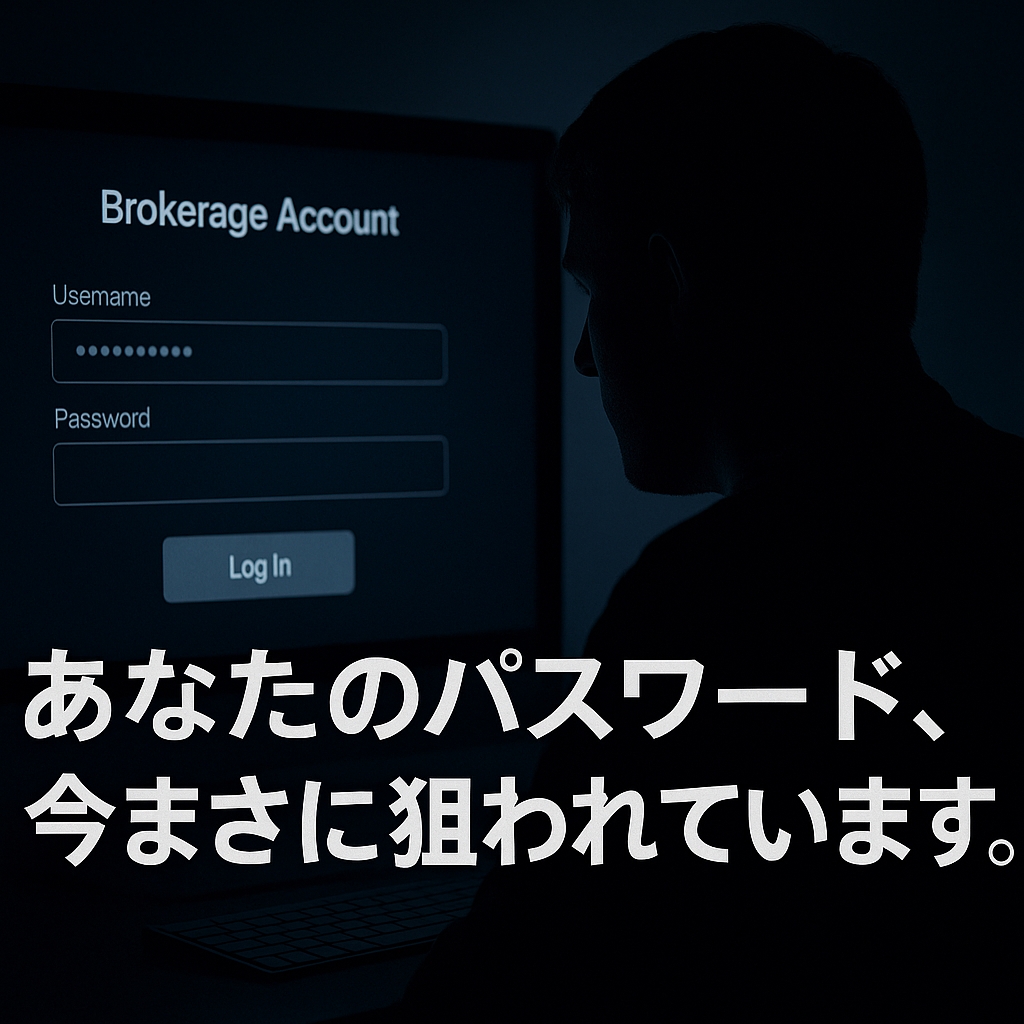
コメント