インカ帝国のふしぎがぐっと近くなる話
インカ帝国と聞くと、なんだか遠い国の昔話のように感じるかもしれません。でも、500年前に南米で生きていた人たちは、とても知恵があって、工夫いっぱいの暮らしをしていました。石で作られた町や、山の上の都市、そして今も解き明かされていない『キプー』のひみつまで、インカ帝国にはワクワクする話がたくさんあります。
Eテレ【地球ドラマチック】UFOの正体 〜科学者たちが迫る最前線〜|米軍映像・AI解析・市民報告で迫る未確認現象の真実(2025年8月2日放送)
500年前のインカの人たちはどんな世界で生活していたの?
インカ帝国があった南米アンデス山脈は、標高がとても高く、天気も厳しい場所が多い地域です。気温の差が大きく、昼は暑くても夜はとても寒くなるような、自然の変化が激しい土地でした。
そんな環境でも、インカの人たちは自然と向き合いながら工夫を続けていました。たとえば、山の斜面には石を積み上げて段々畑を作り、作物が育ちやすいようにしていました。これは『テラス農法』と呼ばれる方法で、トウモロコシやジャガイモなど、アンデスで育つ作物を効率よく作るための知恵です。
帝国の中心となった町はクスコです。クスコは石をていねいに組み合わせて作られた建物が多く、皇帝が暮らした場所としても知られています。ここから北へ南へと領土が広がり、エクアドル、ボリビア、チリ、アルゼンチンなど、今の国の地域まで支配が広がっていました。
インカ帝国がまとめていた距離は約4000キロ。これは日本列島の長さのおよそ10倍にもなる巨大な広さです。
これだけ広い国で暮らしていた人たちは、民族も言葉も文化も違いました。それでもひとつの国としてまとまっていたのは、インカが持つ独自の工夫や制度が大きく関わっていたのです。
なぜ「インカ帝国は文字がなかった」と言われているの?
インカ帝国が“文字を持たなかった文明”と言われるのには理由があります。
インカの石碑や建物には、マヤ文明のような『文字の刻まれた記録』がほとんど残っていません。スペイン人が南米にやってきた時も、インカの人々が「紙に書いた文書」を使っている様子が記録されていなかったため、長い間「文字がなかった」とされてきました。
しかし、文字がなかったとしても、インカの人たちは決して“何も記録していなかった”わけではありません。
ここで登場するのが、インカの代表的な記録道具 キプー です。
キプーは、糸の束に色のついたひもをぶら下げ、そこに結び目を作ることで情報を記録する道具です。ひもの結び目は、数や量、順番などを表していました。たとえば、「村に何人住んでいる」「どれだけトウモロコシを収穫した」「どれだけ働いた」といった情報が記録されたと考えられています。
最近では、キプーのひもには数字だけでなく、もっと深い意味――『物語や歴史に関わる情報』が含まれていた可能性も研究されています。
まだすべてが分かったわけではないので、キプーには今もたくさんの謎が残っています。
こうした“解き明かされていない部分”が、インカ文明の魅力を大きくしていると言えます。
なぜマチュピチュはあんな高い山の上に作られたの?
インカ帝国の象徴とも言える有名な遺跡がマチュピチュです。
標高2430メートルという高い山の尾根に建てられ、雲が足元に広がるような景色の中にあります。
では、なぜそんな場所に都市を作ったのでしょうか?
番組でも紹介されていた主な理由は次のとおりです。
-
皇帝が静かに過ごすための別の住まいだった
-
太陽神『インティ』をまつる儀式のための神聖な場所だった
-
山の形や川の流れなど、自然そのものが神聖とされ、その地形に意味があった
マチュピチュの建物は石をきれいに切り出し、すきまなく積み上げる技術が使われています。この石積みは地震にも強いと言われ、実際に長い年月がたった今でも崩れずに残っています。
また、マチュピチュがある場所は、山々の形や太陽の動きと深い関係があるといわれています。これは、インカの人たちが自然を神聖な存在として大切にしていたからこそ生まれた都市の形だと考えられています。
マチュピチュは、ただの町ではなく、“自然と一体となった都市”であり、皇帝と神々がつながる特別な場所だったのです。
どうやって4000キロもの広い領土をまとめたの?
インカ帝国が本当にすごいのは、「山ばかりの地形」「遠くまで続く領土」という厳しい条件の中で、4000キロもの広い土地をまとめたところです。
まず、インカ帝国では国を4つの大きな地域に分けていました。これを『スユ』と呼び、それぞれを中心地のクスコがしっかりと管理していました。こうすることで、離れた地域も目が行き届くようになっていました。
さらに、インカ帝国を支えたのが、広い道路網 カパック・ニャン です。
この道は南北4000キロにもおよび、石畳の道路や吊り橋が連なり、人が歩きやすいように工夫されています。山道も多いアンデス地域で、これだけの道路を作るのは大きな挑戦だったはずです。
道路の途中には、使者や兵士が休むための施設 タンボ が点々と作られていました。こうすることで、誰でも長い距離を移動でき、国の中で情報や物資がすばやく行き来できるようになっていました。
また、インカの人々は ケチュア語 を帝国内で広く使うようにしていました。言葉が同じだと、別々の文化を持つ人たちも協力しやすくなります。
宗教の力も大きく、皇帝が『太陽神インティの子』として神聖視されることで、人々の心が一つにまとまりやすくなっていました。
こうした道路、言葉、宗教、地域ごとの工夫が組み合わさることで、インカ帝国はとても広い土地をひとつにまとめることができたのです。
インカ帝国は、知れば知るほどもっと知りたくなる文明
インカ帝国には、まだ完全に分かっていないことがたくさん残っています。
『キプー』の本当の意味、マチュピチュの役割、どうやって道路を作ったのか、どんな気持ちで暮らしていたのか――その一つ一つが、私たちの好奇心を強く引きつけます。
500年前の人たちが自然と向き合いながら作り上げた文明は、今もなお、多くの研究者や旅行者を魅了し続けています。
最後に
番組の内容と異なる場合があります。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

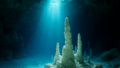

コメント