見て楽しい!食べておいしい!進化するあめ細工と金平糖の世界
2025年5月4日に放送されたNHK総合『有吉のお金発見 突撃!カネオくん』では、目にも美しく、食べてもおいしい日本の伝統菓子「あめ細工」と「金平糖」の世界が紹介されました。日本独自の職人技が詰まったこの分野は、現在国内外から大きな注目を集めています。今回の放送では、そんな伝統の中に息づく職人の努力と、現代のニーズに合わせて進化を遂げる最新のあめ文化がたっぷりと掘り下げられました。
世界が驚く職人技!リアルな動物を5分で作るあめ細工

番組で最初に紹介されたのは、東京・浅草にある外国人観光客に人気の「あめ専門店」です。そこでは、あめ細工歴15年の手塚新理さんが、その卓越した技を披露していました。店内には、リアルな動物のあめ細工がずらりと並び、訪れる人々の目を惹きつけてやみません。中には、人気ゲーム「モンスターハンター」とのコラボ作品もあり、ゲームファンにも強いインパクトを与えていました。
使用される飴の温度はなんと約90℃。この高温の状態で飴を加工しなければならず、冷めてしまうと固まってしまうため、作業は一秒を争うスピード勝負となります。職人はその熱さにも慣れており、素手で飴を扱いながら形を作っていきます。飴を丸めて棒の先に取りつけると、そこからは手早く仕上げるしかありません。
・和バサミ1本で削らずに形を整える
・切り落としや削り直しができない一発勝負
・飴が冷める前に細部まで作り込む技術力が必須
手塚さんは金魚のあめ細工を約5分で完成させていました。ヒレの透明感やうろこの光沢感まで再現されたその作品は、飴とは思えないほどのリアルさで、まるで生きているかのような印象を与えます。さらに、大きな作品になると、パーツごとに分けて制作し、仕上げに熱で接合しながら一体化させる高度な技術も披露されました。
仕上げにはバーナーを使い、表面を軽く炙ることで、まるでガラスのような光沢感を演出します。従来のあめ細工は乳白色が一般的でしたが、手塚さんはこれを一新。空気が入らないよう飴を加工する技術を3年かけて習得し、透明なあめ細工を実現したのです。
・飴の透明度を保つために空気を入れない加工を追求
・素材の成分と温度管理を何度も調整し最適化
・バーナーによってガラスのような質感を表現
また、あめ細工は目で楽しむだけでなく、味も重視されています。最後に食用の色素で丁寧に色づけされ、見た目も華やかに仕上げられていました。番組ではカネオくんのあめ細工も登場し、職人の手によって可愛らしく再現されていました。
このように、日本の伝統技術と現代の創造力が融合したあめ細工は、世界中の人々を魅了する唯一無二のアートです。アメリカ、フランス、アブダビなど海外からも注目され、浅草のお店には連日外国人観光客が押し寄せています。わずか数分の間に完成するその美しさと精密さには、誰もが驚かされることでしょう。職人の長年の努力と経験が凝縮された一瞬の芸術が、今、世界の舞台で脚光を浴びているのです。
エンタメとしても進化!“ネオ組みあめ”の世界

番組の後半で取り上げられたのは、飴を切っても切っても同じ絵柄が現れる「組みあめ」。この伝統的な技術は、明治時代に東京・台東区で生まれた「金太郎あめ」にルーツがあります。当時は子どもの健やかな成長を願って金太郎の顔をあしらった飴が作られ、全国に広がっていきました。
しかし今、この組みあめが“ネオ”として進化を遂げています。東京・丸の内では、製作現場をガラス越しに公開し、工程そのものをエンターテインメントとして楽しめるスタイルが注目されています。飴の製作中は、訪れた人々が目の前で職人の技を見られるだけでなく、その緻密な作業に感嘆の声を漏らします。
・柔らかい飴に色をつけて練り上げる
・空気を含ませながらのばして成形する
・複数のパーツを手作業で組み合わせて1つのデザインにまとめる
・細く伸ばしてカットすれば、8000粒以上の飴が一度に完成
たとえば今回の放送では、番組のマスコットであるカネオくんの顔をかたどった組みあめも職人の手で丁寧に仕上げられていました。作業は高温で飴が固まる前に一気に行うため、短時間で正確に形を整える職人技が光ります。
このような組みあめは、時代とともに用途も広がっていきました。昭和後期には、希望の絵柄でオリジナルあめを作れる注文サービスが始まり、バブル期には特に人気が爆発。特に結婚式の引き出物として、自分たちの顔や名前をあしらった組みあめを配る夫婦が急増し、年間1000件以上の注文が数年続いたといいます。
・オリジナルデザインの組みあめはイベントや贈答品に最適
・企業ロゴや商品キャラクターを入れて販促ツールとして活用
・観光地限定のご当地キャラ入り組みあめも人気上昇中
今では、若者向けにアニメキャラやポップなモチーフを取り入れた組みあめも登場しており、伝統と現代文化の融合が新たな魅力を生んでいます。見て楽しく、もらってうれしく、食べておいしい“ネオ組みあめ”は、まさに日本の菓子文化の進化系。昔ながらの技術を守りながらも、新たなアイデアとデザインで再び脚光を浴びているのです。
職人の努力の結晶「金平糖」誕生の裏側

番組の最後に紹介されたのは、16世紀にポルトガルから伝わった日本の伝統菓子「金平糖」。その美しいトゲトゲの形状と鮮やかな色合いで、長年にわたり親しまれてきたこのお菓子の裏側には、驚くほど手間のかかる工程が隠されています。京都市にある、江戸時代後期創業の金平糖専門店では、1種類の金平糖を仕上げるのに約2週間という長い時間をかけて製造されています。
まず、作業は直径約2メートルもある大きな釜に、金平糖の核となる「イラ粉」と呼ばれるでんぷんを固めた小さな粒を入れるところから始まります。この釜を傾けながら常に回転させ、糖蜜を少しずつ加えていきます。糖蜜が加わると、粒は釜の中をコロコロと転がりながら蜜を吸収し、徐々に大きくなっていきます。
・釜の回転によって金平糖の粒が絶えず動き続ける
・糖蜜が乾燥すると表面に小さな凹凸ができる
・凹凸に次の糖蜜が引っかかり、突起が少しずつ形成される
このようにして金平糖の特徴的なトゲトゲが自然に生まれていきます。とはいえ、その成長はとてもゆっくりで、1日にわずか1ミリ程度しか大きくならないため、毎日釜の温度や回転速度、糖蜜の量を調整しながら、朝から晩まで釜の前を離れず管理し続ける必要があります。
・突起の数は平均で17〜24個程度
・温度、湿度、糖蜜の濃度、釜の速度などが形状に大きく影響
・職人は粒の動きや流れる音を聞き分けながら作業を行う
完成した金平糖は、外はカリッと、中はサクッとした独特の食感が魅力。現在では、定番の砂糖味に加え、イチゴ・パイン・ワイン・チョコなど、バリエーション豊かなフレーバーも登場しています。さらに、ゲーム『信長の野望』にも登場することで話題を呼び、アメリカ・アリゾナからの観光客が「本物を見てみたい」と来日し購入するほど、世界的な注目も集めています。
・ポルトガル語に由来する名前を持つ日本独自の進化菓子
・信長や戦国時代にまつわる逸話も多く、歴史好きにも人気
・長寿や繁栄の象徴とされ、祝い菓子としても重宝されている
金平糖の一粒一粒には、職人の経験と丁寧な手仕事が凝縮されています。見た目のかわいさに反して、製造には時間と技術、根気が必要であり、それゆえに価値があり、大切にされてきたのです。時代が変わっても、変わらぬ手法で作り続けられるこのお菓子は、日本の“甘い伝統”の結晶と言えるでしょう。
まとめ
今回の放送では、見て楽しく、食べておいしい日本の伝統菓子にスポットを当て、手間と技術を惜しまない職人たちの姿と、文化の進化を感じさせる魅力が余すところなく紹介されました。あめ細工も組みあめも金平糖も、それぞれが日本の“技”と“心”を形にした食べられる芸術品です。
観光客だけでなく、私たち日本人も改めてその価値と美しさに目を向けたいと思える内容でした。今後、あめ文化がどのように世界とつながり、未来へ受け継がれていくのか、ますます目が離せません。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

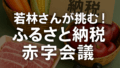
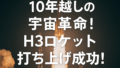
コメント