ひとえに会いたい 東村アキコのキモノ道・秋分
「着物は大好きだけど、結婚式や式典、観劇などの特別な場でどんな柄を選べばいいのかわからない」
「普段着として着てみたいけれど、格を間違えたら恥ずかしいのでは…」
そんな悩みを抱えていませんか。実は、この戸惑いは多くの人が通る道です。私自身も若いころは、着物に触れる機会はあっても「格って何だろう?」「どんなルールがあるのだろう?」と迷い、場違いな装いをしてしまわないか不安に感じたことがありました。
今回放送される『ひとえに会いたい 東村アキコのキモノ道・秋分』は、まさにそうした悩みを解きほぐしてくれる番組です。番組のテーマは「格を知ること」。格を理解することで、着物の世界は一気に広がり、自分の装いに自信が持てるようになります。
Eテレ【ひとえに会いたい】東村アキコが憧れる芸妓さんの着物と京都文化の秘密|2025年6月25日
東村アキコが訪ねる“着物の達人”
今回東村アキコさんが会いに行くのは、時代劇衣裳の第一人者として知られる竹林正人さんです。『独眼竜政宗』『いのち』『光る君へ』など、日本のテレビ史に残る名作で数多くの衣裳を手がけてきました。竹林さんの衣裳づくりの特徴は、単に華やかさや美しさを追求するのではなく、その人物が生きた時代や社会的立場を衣裳で表現することにあります。
例えば、戦国大名の武士であれば質実剛健な生地や落ち着いた色調を用い、姫君であれば豪奢な刺繍や雅な色彩で気品を演出。町人や庶民であれば、素朴で実用的な素材を取り入れるなど、登場人物の役割に即した衣裳を徹底して選んできました。こうした取り組みが、視聴者にとって物語の世界観をよりリアルに感じさせる要因となっています。
格を知ることが着物の第一歩
着物における「格」とは、その着物が持つフォーマル度合いのこと。場面や立場にふさわしい装いかどうかを判断する大切な基準です。たとえば『黒留袖』は既婚女性の最も格式高い礼装として結婚式に着られますし、『訪問着』や『色無地』は準礼装として、華やかでありながら落ち着いた場面にふさわしいとされています。一方で、『紬』や『小紋』などは普段着としての要素が強く、気軽に街歩きやお茶会で楽しむのに向いています。
格を決めるポイントは紋の数や柄の配置、素材の種類など。紋が多いほど格式が高く、裾にだけ柄があるものは格が上がる傾向があります。染めの着物は織りの着物よりも格が高いとされ、光沢のある絹などは特にフォーマルな場にふさわしいとされています。
時代劇においても格は重要です。登場人物の立場や背景を視聴者に直感的に伝えるのが衣裳の役割。竹林さんは「格」を正しく設定することで、歴史のリアリティを観客に届けてきました。
東村アキコのまなざし
東村アキコさんは、着物を単なる衣裳としてではなく、文化や物語をつなぐものとして捉えています。若いころから日常的に着物に親しみ、現在は着物をテーマにした漫画を連載中。番組で竹林正人さんに会うのは、憧れの気持ちだけではなく、自身の創作に生かすためでもあります。
番組では、東村さんが着物愛好家ならではの質問を投げかけ、竹林さんがその裏にある知識や哲学を語ることで、視聴者も自然と着物の奥深い世界に引き込まれていきます。彼女のまなざしは、伝統を受け継ぐ者としての真剣さと、現代に着物を生かしていきたいという柔軟さの両方を兼ね備えています。
押さえておきたい視点
・着物には「格」という絶対的なルールが存在する
・時代劇の衣裳は登場人物の身分や人柄を語る大切な要素
・竹林正人さんは『独眼竜政宗』『いのち』『光る君へ』などを通じて衣裳の表現を磨いてきた
・東村アキコさんは漫画を通じて着物文化を発信し、現代に新しい視点を与えている
こうした背景を理解して視聴すれば、ただ番組を見るだけでなく、衣裳に込められた意味や文化的な奥行きを深く味わえるでしょう。
まとめ
この記事のポイントは以下の3つです。
-
『ひとえに会いたい』では東村アキコさんが竹林正人さんを訪ね、着物の「格」の大切さを学ぶ。
-
竹林正人さんは数々の時代劇で衣裳を通じて人物像や世界観を表現してきた。
-
東村アキコさんのまなざしを通して、視聴者も着物をより身近に感じられる。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


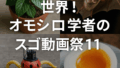
コメント