昭和のぬくもり、街の記憶をたどる旅へ
急ぎ足で過ぎていく毎日。高層ビルの間を抜け、スマホを見つめながら歩く現代の私たちは、いつの間にか「昔ながらの暮らし」や「人と人との温かさ」に、ふと心を寄せるようになりました。そんな時代の空気を映すように、近年じわじわと人気を集めているのが“郷土の博物館”です。
地域の人々の生活道具や古い建物、町並みの模型などを通して、過去の暮らしを体感できるこれらの施設は、観光地というより“心のふるさと”のような存在。今を生きる私たちが、どこかで「自分のルーツを確かめたい」と感じるのは自然なことかもしれません。
10月10日(金)放送予定の『おとな時間研究所 温故知新 郷土の博物館』では、俳優の常盤貴子さんと、博物館マニアの丹治俊樹さんが、昭和の香りを今に残す3つの博物館をめぐります。
新宿の“もうひとつの顔”を知る場所 ― 新宿歴史博物館
高層ビルが立ち並ぶ新宿。最先端の街として知られていますが、その地下に一歩足を踏み入れると、まるで昭和初期の世界へタイムスリップしたような光景が広がります。
新宿歴史博物館は、江戸時代から現代までの新宿の歴史を一望できる施設。特に注目なのが、昭和初期の繁華街を再現した常設展示です。電飾看板がきらめく模型の街並みや、再現された路面電車の車体、当時の文化住宅の部屋の中まで細かく再現されており、「あの頃の新宿」が生き生きと蘇ります。
館内の展示は、単に古い資料を並べるだけでなく、そこに暮らした人々の息づかいや夢を伝える構成。サラリーマンが通勤に使っていた革のカバンや弁当箱、子どもたちが遊んでいた紙風船など、どの展示にも“生活のぬくもり”が宿っています。
また、特別展や企画展では、時代ごとのテーマを掘り下げた展示も開催。例えば「戦後の新宿芸術運動」や「歌舞伎町の誕生」など、都市文化を社会学的に切り取る内容も多く、研究者からも評価されています。
アクセスはJR・東京メトロの四ツ谷駅から徒歩約10分。都心にありながら、静かに“過去と向き合う時間”を過ごせる場所です。
建築そのものが語る物語 ― 岩槻郷土資料館
次に訪れるのは、埼玉県さいたま市岩槻区にある岩槻郷土資料館。ここは、昭和5年に建てられた旧岩槻警察署の建物を活用した資料館で、外観は見事なアール・デコ様式。シンメトリーに整った窓の配置や曲線を取り入れた階段のデザインには、当時の「モダン建築」の美学が息づいています。
建物の中に一歩入ると、当時の取調室や留置場がそのまま残されており、時代の重みを感じさせます。展示室では、岩槻人形の制作過程や、旧城下町として栄えた岩槻の歴史、地元の産業や祭りなど、地域文化が細やかに紹介されています。
この建物は2016年、国の登録有形文化財に指定されました。警察署という公共建築を「文化の拠点」として再生させたことは、地域の人々の誇りでもあります。
館内には地元ボランティアによる解説もあり、訪れた人に岩槻の魅力を語り継ぐ温かい空気が流れています。アクセスは東武アーバンパークライン岩槻駅から徒歩約10分。静かな住宅街の中にあり、地域の“歴史の守り人”のような存在です。
生活の中にある“郷土の原風景” ― 浦安市郷土博物館
そして最後に紹介されるのが、千葉県にある浦安市郷土博物館。この博物館の最大の特徴は、“見て終わり”ではなく、“歩いて感じる”ことができる体験型展示です。
屋外に広がる昭和27年ごろの浦安の町並みは圧巻。魚市場、木造家屋、銭湯、駄菓子屋などが並び、子どもたちが遊ぶ姿が目に浮かぶようです。細部まで丁寧に再現されており、看板の文字や、ちゃぶ台の上に置かれた茶碗、物干し竿に揺れる洗濯物まで、すべてが当時の生活を物語っています。
館内には、浦安の漁業の歴史を伝える展示も充実。かつて海辺の町だった浦安の象徴ともいえる和船や漁具、船大工の道具などが展示され、失われつつある漁師文化を今に伝えています。さらに、希少な魚『アオギス』の標本展示も見どころのひとつ。
また、館内併設のカフェ「すてんぱれ」では、地元食材を使った『あさりめし』などの郷土料理も楽しめます。週末には、屋外展示エリアにある駄菓子屋が営業し、家族連れにも人気です。アクセスは浦安駅からバスで「市役所前」下車徒歩約4分。無料で入館できるのもうれしいポイントです。
“温故知新”の心が未来を照らす
番組タイトル『温故知新』には、「古きをたずねて新しきを知る」という意味があります。
この言葉こそ、郷土博物館が持つ本質を表しています。過去の暮らしや文化を学ぶことは、単に懐かしむためではなく、未来をより良くするためのヒントを見つける行為でもあります。
新宿歴史博物館が伝える「都市の中の人間の営み」、岩槻郷土資料館が示す「建物に刻まれた時代の記憶」、そして浦安市郷土博物館が体現する「生活そのものが文化であるという気づき」。これら3つの場所には、形は違えど共通する“記憶の力”があります。
便利さの裏で失われかけている“地域のぬくもり”を取り戻す――それが、今回の番組が伝えたいメッセージなのかもしれません。
まとめ
この記事のポイントは以下の3つです。
・新宿歴史博物館では、昭和の繁華街と都市文化を再現。人々の暮らしと夢を立体的に感じられる。
・岩槻郷土資料館は、旧警察署を活用した建築美の宝庫。地域の伝統工芸と近代建築の融合が見どころ。
・浦安市郷土博物館は、昭和の町並みを歩いて体感できる体験型施設。漁師町の文化と生活の知恵が息づく。
『おとな時間研究所 温故知新 郷土の博物館』は、過去を懐かしむ番組ではなく、“人の営みの価値”を見直すきっかけをくれる時間です。
出典:NHK公式『おとな時間研究所 温故知新 郷土の博物館』(2025年10月10日放送予定)
https://www.nhk.jp/
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

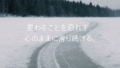
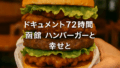
コメント