心のままに進む 高木美帆が見つめる“やり残した夢”とは
世界のトップで戦い続けるアスリートたちの中でも、高木美帆ほど内面の深さを感じさせる存在は多くありません。北海道・幕別町で生まれ、15歳でオリンピックに出場して以来、彼女は日本女子スピードスケート界の象徴として歩み続けてきました。
4大会連続の五輪挑戦――その言葉の響きだけでも、彼女の覚悟と精神力の強さが伝わってきます。
しかし、すでに7つのメダルを手にしながらも、彼女はまだ満足していません。心の奥底に残る“やり残したこと”が、彼女を再び氷の上へと導いているのです。
この記事では、スポーツ心理学の視点から、彼女の挑戦の意味と、長い競技人生を支える「心の整え方」に迫ります。
「どうしてそこまで続けられるの?」と感じたことのある方も、この記事を読むことで、努力を続ける人の心のメカニズムが見えてくるでしょう。
やり残した“たったひとつ”とは
彼女の“やり残したこと”――それはスピードスケート女子1500mの金メダルです。
これまでの五輪で彼女は1000mやチームパシュートで金・銀・銅を獲得し、日本女子最多となる通算7個のメダルを手にしてきました。
しかし、最も思い入れの強い1500mでは、2018年平昌、2022年北京と2大会連続で銀メダル。
頂点にあと一歩届かない現実が、心に静かに残り続けています。
北京五輪後の記者会見で、彼女はこう語りました。
「1500mで思い描いたような滑りをすることができなかった」
その言葉には、結果への悔しさよりも、“納得できる自分の滑り”を見せられなかった葛藤がにじみます。
心理学的に見れば、この“未完の経験”はモチベーションの源でもあります。
達成できなかった過去の経験が、人間の中に「もう一度だけ挑戦したい」という強い動機づけを生み出すのです。
つまり彼女の挑戦は、勝利への執着ではなく、自分自身を完成させたいという内的欲求に突き動かされているといえます。
新たな挑戦を選んだ理由
2022年春、高木美帆は大胆な決断を下しました。
長年所属していたナショナルチーム(NT)を離れ、恩師ヨハン・デビットコーチと共に「team GOLD」を立ち上げたのです。
ナショナルチームはトップ選手の育成体制として整備されており、最新の科学的サポートや設備を受けられる一方で、練習メニューや環境が画一的になりがちです。
彼女はその枠を超え、より自分の感覚に合った練習を求めました。
「もっと自由に、自分の考えで滑りを作っていきたい」
そう語る姿は、まさに“自己決定理論”が示す心理的自立の好例といえます。
さらに彼女は新チームで、異なる国や競技のアスリートたちと交流する機会を増やしました。
その目的は、外部から新しい刺激を受け取り、「自分の滑りを客観的に見る」こと。
これは心理学でいう“メタ認知”の発達にもつながります。
自分を客観視する力は、成長の停滞を打破するうえで極めて重要です。
そして、彼女の挑戦は技術面にも及びます。
新しいスケート靴のブレードを導入し、これまでの感覚を一度リセット。
わずか数ミリ単位の違いが記録に影響する世界で、「新しい自分の滑り」を模索しています。
変化には常に不安が伴います。
それでも高木選手は「まだ完成していない滑りを磨くのが楽しい」と話します。
この“楽しさ”の感覚こそ、心理学的にはフロー体験――集中と幸福が重なる状態。
彼女はまさに、挑戦の中で心が最も生き生きと輝く瞬間を見つけているのです。
挑戦を支える“心の整え方”
高木美帆の強さの本質は、単なる技術や体力ではなく、「心の整え方」にあります。
世界のプレッシャーを受けながらも、彼女が折れずに前を向けるのは、心のセルフマネジメント力が極めて高いからです。
まず、彼女は“不安や焦りを否定しない”タイプのアスリートです。
北京大会では3000mで思うような結果を残せず、自分を責めた時期もありました。
しかし彼女は、その感情を「なかったこと」にせず、素直に言葉にして整理していきます。
「表情が死んでいたけど大丈夫?」と声をかけられた時、彼女はその言葉をきっかけに自分の心を見つめ直しました。
心理学では、感情を言語化する行為がエモーション・レギュレーション(情動調整)と呼ばれ、メンタルを立て直す有効な方法とされています。
次に、「もし調子が合わなくても攻める」という信念。
これは、“結果ではなく過程を支配する意識”とも言えます。
自分でコントロールできない結果ではなく、「どう滑るか」という行動に焦点を置くことで、プレッシャーを軽減しています。
また、彼女はイメージトレーニングを欠かしません。
滑る自分の姿を鮮明に描き、どんな展開でも動揺せずに動けるようにしています。
これは心理学でいう自己効力感を高める行動で、目標達成の確率を飛躍的に上げるとされています。
そして、忘れてはならないのが「自分を許す力」。
完璧主義である彼女だからこそ、うまくいかない自分を受け入れることが課題でした。
北京大会後には「悔しさと喜びの両方が自分にとって大切」と語り、感情を否定せずに受け入れる姿勢を見せました。
これはまさに、セルフ・コンパッション(自己への思いやり)の実践。
強さとは、弱さを認める勇気なのです。
さらに、周囲の支えを受け入れる柔軟さも彼女の大きな武器です。
家族やコーチとの信頼関係、仲間との会話、他者の励まし――それらが彼女の心を安定させる“心理的安全基地”になっています。
孤独な競技だからこそ、「誰かに支えられている」という実感が、挑戦を続ける力に変わっているのです。
まとめ
この記事のポイントは以下の3つです。
・高木美帆の“やり残したこと”は、1500m金メダルと「納得のいく自分の滑り」
・ナショナルチームを離れ、自ら環境を作り直すことで“心の自由”を手にした
・感情を言葉にし、他者と支え合うことで、心を整えながら挑戦を続けている
挑戦とは、結果を求める行為ではなく、「自分を深める旅」。
高木選手の言葉「日々を紡ぐ先に五輪がある」は、努力を積み重ねるすべての人に響くメッセージです。
たとえ金メダルを取れなかったとしても、彼女の挑戦はすでに“自己超越”の形を示しています。
この先、彼女がどんな滑りを見せてくれるのか――その日を楽しみに待ちたいと思います。
(放送後には、番組で描かれたトレーニングの現場や心の揺らぎ、新たなコメントなどを追記予定です)
出典・参考:
GOETHE(ゲーテ)/4years./Number Web/JOC-日本オリンピック委員会
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


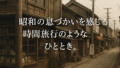
コメント