鳥取のらくだらっきょうと本漬けの秘密に迫る30分
2025年6月19日(日)18:00からNHK Eテレで放送された「小雪と発酵おばあちゃん」では、鳥取砂丘が育てる特産品「らくだらっきょう」と、その魅力を最大限に引き出す発酵による本漬けが紹介されました。小雪さんが現地を訪ね、発酵の知恵と手仕事を受け継ぐ「発酵おばあちゃん」たちと交流しながら、らっきょうの奥深い世界に触れる内容です。見た目の美しさ、発酵による変化、多彩な料理法など、らっきょうの新しい可能性が次々と明らかになりました。
鳥取砂丘で育つ「らくだらっきょう」とは

「らくだらっきょう」は、鳥取砂丘に隣接する福部町や北栄町で100年以上前から栽培されている品種です。らくだのように丸く大きな粒が特徴で、その美しさから「白い宝石」とも呼ばれます。夏は気温60度を超え、冬は雪に覆われるという過酷な砂丘地で育つため、病気や害虫に強く、薬品に頼らない栽培が可能です。
・繊維が細かく、シャキシャキとした独特の歯ごたえ
・栄養分の少ない砂地で育つため、色白で形が美しい
・鳥取県の特産ブランドとして商標登録・GI認証も取得
このような自然環境と農家の技術が合わさって、今では全国的にも高い評価を受けているらっきょうです。
らっきょうの本漬けの作り方(発酵仕込み)

鳥取の伝統的な「らっきょうの本漬け」レシピは、手間を惜しまず発酵の力を活かした味わい深い漬物です。発酵の工程を経ることで、辛味や刺激がやわらぎ、シャキシャキとした食感とまろやかな酸味を楽しめます。以下に材料と手順を詳しくご紹介します。
【材料(作りやすい分量)】
・らっきょう(根と茎を切ったもの)…2kg
・水(塩水用)…1400ml
・塩…300g
<甘酢(2kg分)>
・水…300ml
・砂糖…500g
・酢(酸度4.5%の純米酢推奨)…700ml
・とうがらし…適量
【作り方】
・らっきょうはザルに入れ、流水でやさしく揉み込むように洗います。このとき、薄皮が自然に剥がれ、白くきれいな状態になります。
・洗ったらっきょうはしっかりと水を切っておきます。水分が残っていると発酵が不安定になるため注意します。
・次に、分量の水に塩をしっかり溶かし、塩水を用意します。
・煮沸消毒した保存瓶にらっきょうを詰め、塩水を注ぎ入れてらっきょうがしっかり浸かるようにします。
・このまま常温で約2週間、塩漬け発酵させます。
・最初の5日間は、塩が沈んで偏らないよう、手で軽く混ぜて塩水を循環させます。
・3日目〜4日目ごろから発酵が始まり、泡が表面にブクブクと出始めます。
・1週間ほど経つと泡が落ち着いてきて、表面も静かになり、臭いも弱まります。これが発酵の目安です。
・発酵が終わったら、流水に一昼夜さらして塩抜きを行います。1粒食べてみて塩分を確認し、塩辛い場合はさらに時間を延ばします。
・塩抜き後は、ザルにあげてしっかり水を切り、周囲のやわらかい皮も丁寧に取り除きます。
・鍋にたっぷり湯を沸かし、らっきょうを10秒ほど熱湯に通してから湯切りして冷まします。この工程で食感が引き締まります。
・甘酢を作ります。水に砂糖を加えて鍋で加熱し、ひと煮立ちさせてから冷まします。完全に冷めてから酢を加えるのがポイントです。好みに応じてとうがらしも加えます。
・煮沸消毒した瓶に、冷ましたらっきょうと甘酢を注ぎ入れます。辛味がほしい場合はここでとうがらしも加えます。
・冷暗所で保管し、約1ヶ月漬け込むと食べ頃になります。長く漬けるほど味がなじみ、風味が深まっていきます。
らっきょう本来の風味を生かしながら、発酵の力でまろやかに変化した味わいは、ほかの漬物にはない奥行きがあります。手間はかかりますが、一粒ごとに手仕事のぬくもりを感じられる漬物として、食卓に彩りを添える一品です。
らっきょうのカツの作り方(鳥取の発酵アレンジ料理)
「らっきょうのカツ」は、鳥取の本漬けらっきょうを主役にしたユニークな揚げ物料理です。甘酢と発酵のうま味がしみ込んだらっきょうを、お肉で包んでサクッと揚げることで、シャキッとした食感とジューシーな肉の旨味が同時に楽しめる一品になります。
【材料(つくりやすい分量)】
・らっきょうの本漬け…適量
・豚ロース肉(薄切り)…適量
・豆板醤…適量(※辛さは好みで)
・卵…適量
・パン粉…適量
・小麦粉…適量
【作り方】
・豚ロース肉は、らっきょうの長さに合わせて折りたたむようにして準備します。お肉が大きすぎると巻きにくくなるので、長さを調整するのがポイントです。
・肉の片面に豆板醤を薄く塗ります。辛味が苦手な場合は少量、もしくはチーズに代えても相性が良く、小雪さんは実際にチーズを使ってアレンジしていました。
・らっきょうを1粒、お肉の中央に置いてくるくると巻き、爪楊枝でしっかりとめます。この工程で形が崩れにくくなり、揚げやすくなります。
・巻いた肉に小麦粉、溶き卵、パン粉の順につけて衣をしっかりとつけます。
・170〜180度の油でゆっくりと揚げます。油の温度が高すぎると中まで火が通る前に焦げやすいので、中温を保ちながらじっくり揚げるのがコツです。
・全体がキツネ色にカリッと揚がったら完成です。中かららっきょうの爽やかな酸味とお肉のコクが広がります。
このレシピは、らっきょうを“漬物”としてではなく料理の主役として活用する発想の転換が詰まっています。お弁当のおかずにもぴったりで、冷めても味がしっかり残るので常備菜としてもおすすめです。豆板醤の辛味やチーズのコク、豚肉の旨味が、らっきょうの酸味と合わさって、新感覚の一品に仕上がります。
っきょうのタルタルソースの作り方(鳥取の本漬けアレンジ)
「らっきょうのタルタルソース」は、鳥取の本漬けらっきょうを活かした爽やかな風味の万能ソースです。シャキシャキとした食感と、まろやかな酸味が特徴の本漬けらっきょうを使うことで、定番のタルタルソースが一気に奥深い味わいになります。
【材料(つくりやすい分量)】
・らっきょうの本漬け…適量
・ゆで卵…適量
・マヨネーズ…適量
【作り方】
・らっきょうの本漬けをみじん切りにします。粒が大きい場合は粗みじんにして、食感を残すと歯ごたえも楽しめます。
・ゆで卵も細かくみじん切りにします。白身と黄身が均一になるように丁寧に刻むのがポイントです。
・刻んだらっきょうとゆで卵をボウルに入れ、マヨネーズを加えて全体をよく混ぜます。味見をしながら量を調整し、塩気や酸味が強い場合は少量の砂糖を加えても味がまとまります。
完成したタルタルソースは、フライや焼き魚、蒸し鶏、野菜スティックなどにぴったりです。市販のピクルスの代わりにらっきょうを使うことで、和風のやさしい酸味と自然な甘みが加わり、味に深みが出ます。本漬けらっきょうならではのコクと発酵の旨味が効いており、子どもから大人まで楽しめるアレンジソースになります。
小雪流 トマトとらっきょうのサラダの作り方(鳥取の発酵アレンジ)
「小雪流 トマトとらっきょうのサラダ」は、本漬けらっきょうの爽やかな酸味とミニトマトの甘みが調和した、夏にぴったりのさっぱりサラダです。発酵の力でまろやかになったらっきょうの風味を、フルーツのようなトマトと合わせることで、副菜にも前菜にもなる洗練された一皿が完成します。
【材料(つくりやすい分量)】
・らっきょうの本漬け…適量
・ミニトマト…適量
・はちみつ…適量
・レモン…適量(果汁と皮)
・甘酢(らっきょうを漬けていたもの)…適量
【作り方】
・らっきょうの本漬けをみじん切りにします。粒の大きさによっては粗みじんでも良く、全体に風味が広がるようにします。
・ミニトマトは半分、または4等分にカットして食べやすくします。色の異なるトマトを使うと見た目も鮮やかです。
・ボウルにらっきょうとトマトを入れ、レモンのしぼり汁、はちみつ、らっきょうの甘酢を加えてやさしく和えます。甘さや酸味は味を見ながら好みで調整してください。
・レモンの皮を細かく刻んで仕上げに加えると、香りに深みが出て爽やかさが増します。皮はしぼり終えたものでもOKです。
このサラダは、冷やしておくことでさらに味がなじみ、夏場の前菜や付け合わせとしても重宝します。砂糖や酢を加えなくても、らっきょうの甘酢とレモン、はちみつだけで自然な甘酸っぱさが出るのが特徴です。発酵と生の素材を合わせた、小雪さんならではのナチュラルでヘルシーな一品です。
発酵の知恵と手仕事に触れる
小雪さんは、実際に発酵おばあちゃんたちの作業現場を訪れ、らっきょうの仕込みから漬け込みまでの全工程を体験しました。現場では、すべての作業が手作業で行われ、機械では真似できない細かな技と感覚が大切にされています。
・皮むきや根切りを一粒ずつ丁寧に行うことで、品質が保たれる
・発酵の見極めは、見た目や香り、手の感触で判断
・塩抜きの時間や甘酢の配合も、気温や湿度を見ながら調整する
これらの作業は、数十年かけて身につけた知識と経験が必要であり、まさに人の勘と経験が活きる世界です。また、らっきょうの栽培や収穫も地域ぐるみで協力し合う文化があり、農家の方々の連携も番組で紹介されていました。
まとめ
「小雪と発酵おばあちゃん」は、発酵の力と人の手が織りなす、らっきょうの魅力を深く掘り下げた内容でした。砂丘で育てられる「らくだらっきょう」は、見た目の美しさと食感の良さに加え、発酵によって味に深みが生まれることで、ただの漬物にとどまらない可能性を秘めています。
小雪さんが現地で体験し、発酵の工程や手仕事を間近で学ぶ姿から、食の知恵や文化を次世代に伝える大切さも感じられました。らっきょうはこれからも、主役にも脇役にもなれる万能食材として、さまざまな形で食卓に彩りを添えてくれるでしょう。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


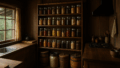
コメント