彫刻家ふたりの友情に学ぶ、人生の歩き方
「長く続く友情ってどうすれば育まれるのだろう?」――そんな問いに答えてくれるような番組が、2025年9月12日に放送されました。NHK総合『時をかけるテレビ』で紹介されたのは、1995年放送のドキュメンタリー「老友へ ~83歳 彫刻家ふたり~」の再放送です。登場するのは、戦後日本を代表する彫刻家、佐藤忠良さんと舟越保武さん。彼らの60年以上にわたる友情と創作の軌跡が描かれました。この記事では番組の流れを追いながら、ふたりの歩んだ人生と、そこから私たちが学べるメッセージをより詳しく紹介します。
美術学校での出会いと「新制作展」の誕生
ふたりの出会いは昭和9年、東京美術学校。若き日の佐藤さんと舟越さんは、下宿を共にして生活を送りながら、互いに刺激し合いました。当時の美術界はアカデミズムが支配的で、型にはまった作品が高く評価されていた時代。二人はそれに反発し、「反アカデミズム」を掲げて新しい団体を立ち上げます。これが、のちに日本美術界を支える存在となる新制作派協会でした。
その後、彼らは毎年の「新制作展」で自作を発表し続けます。作品は互いの最大のライバルであり、同時にお互いを成長させる糧にもなっていきました。やがてふたりはともに高村光太郎賞を受賞し、戦後日本を代表する彫刻家として名を残していきます。舟越さんが「佐藤はいつも左前方30度を歩く男」と評した言葉は、彼が常に先行しながらも、真正面を塞ぐことなく仲間を導く存在だったことを物語っています。
脳梗塞に倒れても彫刻を続けた舟越保武
人生の後半、舟越さんに試練が訪れます。脳梗塞で倒れ、右手の自由を失ったのです。作家生命の危機とも言える出来事でしたが、彼は制作を諦めませんでした。その支えとなったのは、親友・佐藤さんから送り続けられた手紙でした。直接会いに行くのではなく、あえて文字に思いを込めて寄り添った佐藤さんの姿勢は、深い友情の証しと言えるでしょう。
退院後、舟越さんは左手だけで制作に挑みます。通常なら粘土を盛り足して形を作るところを、彼は削り出す方法で作品を仕上げていきました。その苦闘の末に生まれた作品のひとつが「その人」。不自由な体でなお挑み続ける姿勢に、多くの人が心を打たれました。
銀座を歩き、日常から作品を生む
舟越さんは銀座を愛していました。帽子店や喫茶店を巡り、街ゆく人々の顔を眺めながらインスピレーションを得ます。モデルを立てず、日常の人々の姿から造形のヒントを得る――そのスタイルは、彼が「人間」を彫る彫刻家であることを示していました。病の後遺症を抱えながらも銀座を歩き続けた姿は、芸術と共に生きる決意そのものだったのです。
佐藤忠良を支えた友情の記憶
佐藤さんもまた、創作に行き詰まることがありました。長崎を訪れ、舟越さんの代表作「26殉教者記念像」を目にしたとき、その壮大な作品に励まされ、自分の制作を再び進める力を得ました。舟越さんが4年半をかけて完成させたこの像は、命を削るような情熱の結晶であり、佐藤さんにとって大きな支えとなったのです。
さらに忘れられないのは、若き日に佐藤さんが彫刻を続けるかどうか悩んでいたときのこと。夜汽車で札幌へ向かう途中、深夜の盛岡駅で舟越さんが黙って待っていてくれました。言葉を交わさずとも「一緒に歩もう」という意思を確認できた瞬間。その記憶は、佐藤さんの生涯に刻まれた友情の象徴でした。
制作と時間との戦い
晩年、ふたりの作品づくりは時間との戦いでもありました。舟越さんは15分の作業で疲れてしまうこともあり、締切に追われ苛立つ日々を過ごします。一方の佐藤さんも、制作中の作品が損壊し、例年2点出していた出品を1点に減らさざるを得ないトラブルに見舞われました。ともに苦しみながらも、「新制作展」に出品し続けた姿勢は、芸術家としての責任感と互いへの敬意を物語っています。
武田鉄矢が語った「友情のかたち」
スタジオでは武田鉄矢さんがゲストとして登場。舟越さんの言葉「左前方30度を歩く男」について「正面の風景を塞がずに歩く存在」と解釈し、友情の在り方を語りました。また、自身の仲間である西田敏行さんとの関係を例に挙げ、「友達を通じて自分の正体が分かる」と述べました。芸術家の友情と、自身の青春時代の仲間との思い出を重ねる言葉には説得力がありました。
ふたりの作品が今も並ぶ場所
やがて舟越さんは2002年にこの世を去り、佐藤さんも後を追うように亡くなります。しかし、彼らの作品は今も埼玉県川口西公園などに並び立ち、互いに寄り添うかのように人々を見守っています。舟越さんは「同じ世に生まれ、良き道連れになった」と語り、佐藤さんは「性格は違ったが、それが一つのレールになれた」と振り返りました。死後もなお、友情は作品を通じて生き続けているのです。
まとめ ― 私たちが学べること
今回の放送から浮かび上がるのは、芸術の力だけでなく友情の力です。
-
友情は、言葉を超えて相手を支える力になる
-
ライバル関係は、互いを高める原動力になる
-
困難に直面しても「続けること」が人を感動させる
2025年の今、長く続く人間関係を築くことが難しいと感じる人も多いはずです。だからこそ、佐藤さんと舟越さんの物語は私たちに響きます。大切な友人にどう寄り添うか、自分の情熱をどう守り続けるか。その答えのヒントが、ふたりの生き方にありました。
次のお出かけ先として、美術館でふたりの作品に触れてみるのはいかがでしょうか。実物を前にすれば、60年を超える友情と芸術の鼓動を、きっと肌で感じられるはずです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


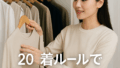
コメント