令和流エイジレスな生き方|年齢を超えて楽しむヒント満載!
「シニアになったら静かに暮らすもの」と思っていませんか?
でも2025年の今、その常識はどんどん変わっています。ぬい活に夢中な俳優の大和田伸也さんや、インスタで2.5万人のフォロワーを持つ65歳の藤原民子さんのように、シニア世代が年齢を忘れて人生を楽しむ姿が広がっています。この記事では、NHK「首都圏情報 ネタドリ!」で紹介された“令和流エイジレスな生き方”をまとめ、あなたの暮らしに取り入れられるヒントを紹介します。
新人類世代が切り開くエイジレスライフ
かつて「新人類世代」と呼ばれた人たちが、今は60代〜70代のシニア層になっています。しかし、その生き方は従来の「高齢者」というイメージとは大きく違います。昔のシニアといえば「落ち着いて静かに暮らす」という印象が強かったのですが、今の世代は自分らしく、積極的に新しいことに挑戦する姿が目立ちます。
たとえば都内で開催されているDJ OSSHYさんの「シルバーディスコ」。ここでは音楽に合わせて体を動かし、笑顔で踊るシニアが大勢集まります。会場はいつも満員で、世代を超えた交流の場にもなっています。年齢に縛られず、純粋に「楽しい!」を追い求める姿は、まさに令和のエイジレスな生き方を象徴しています。
また、65歳の藤原民子さんはSNSを活用してファッションやメイクを発信し、約2.5万人ものフォロワーを抱える人気インスタグラマーです。シニア世代だけでなく、30代から50代の幅広い人たちから支持されており、「年齢を理由におしゃれを諦める必要はない」というメッセージを体現しています。藤原さんの投稿には「自分も挑戦してみたい」「こんな年の重ね方をしたい」といった声が多く寄せられています。
さらに、博報堂生活総合研究所の内濱大輔さんは「新人類世代は若いころから自由に選択する価値観を大事にしてきた。そのため、年齢による嗜好や価値観の差が小さくなってきている」と指摘します。つまり、この世代は若いころから「好きなものを選ぶ」「自分らしく生きる」という意識が強かったため、シニアになった今も自然にその姿勢を保ち続けているのです。
このように、新人類世代のシニアは、ただ年を重ねるのではなく、自分の好きなことを楽しみ、SNSやイベントを通じて社会と積極的につながっています。彼らの姿は、「高齢者」という言葉のイメージを塗り替え、次の世代にも新しい生き方のヒントを与えています。
子ども心を忘れない「キダルト」の台頭
シニアを含む大人たちが、今や日本のおもちゃ市場を力強く支えています。その市場規模は過去最高の約1兆円に達しており、子ども向けという従来のイメージを大きく超えています。背景にあるのは、「子ども心を持ち続ける大人=キダルト」という新しい価値観です。大人になっても純粋に楽しむ気持ちを忘れない人たちが増え、それが市場全体を活性化させています。
その代表例が、60代の長船忠彦さんです。長船さんはお気に入りのぬいぐるみと一緒にカフェを訪れる「ぬい活」に夢中。お気に入りの席でぬいぐるみと並んでコーヒーを飲み、写真を撮ってSNSに投稿するのが日常の楽しみになっています。さらに、毎月1体は新しいぬいぐるみを購入するというこだわりもあり、その姿勢はまるで若い世代のコレクターのようです。
長船さんは「ぬいぐるみは癒やし。『かわいいですね』と声をかけてもらえると、会話のきっかけになる」と語っています。この言葉は、多くの人の共感を呼びました。ぬいぐるみは単なる物ではなく、人と人をつなぐ架け橋になり、世代を超えた交流を生み出す存在にもなっているのです。
このように、「キダルト」という価値観の広がりは、シニア世代に新しい楽しみをもたらすだけでなく、社会全体のつながり方や日常の過ごし方に変化を与えています。
医学が裏付ける若返り現象
ニッセイ基礎研究所の前田展弘さんによれば、現代のシニアは医学的にも「若返り」の傾向が見られるそうです。具体的には、75〜79歳の歩行速度が10年前と比べて速くなっており、体力的にはおよそ10歳分も若返っていると評価されています。年齢を重ねてもなお活発に動ける人が増えているのは、日常的な運動習慣や医療の進歩、健康意識の高まりが背景にあると考えられます。
こうした変化を受けて、日本老年学会は「高齢者の定義を従来の65歳以上から75歳以上へ見直すべき」と提言しています。実際の生活感覚としても、70代前半の人を「高齢者」と呼ぶことに違和感を覚える場面が増えており、社会全体で新しい基準が求められているのです。
さらに、デジタル分野でも大きな変化が進んでいます。YouTubeやInstagramの利用率はこの数年で急増し、特にInstagramは過去5年間で約2.5倍に伸びています。シニア世代が日常的にSNSを使いこなし、情報発信や趣味の共有、仲間との交流に活用している姿はもはや珍しくありません。動画を楽しんだり、自ら発信したりすることが、暮らしの一部として自然に定着しつつあるのです。
このように、体力面でも精神面でも、そしてデジタルスキルの面でも、シニア像は大きく変わりつつあります。従来の「年をとったら静かに過ごす」という枠組みを超え、自分らしく積極的に社会と関わる姿が新しいスタンダードになっています。
SNSとアバターが広げる人とのつながり
都内で開かれたシニアSNSのたこ焼きパーティーには、50〜70代の男女10人が集まりました。全員が初対面でしたが、同じ交流サイトを通じてつながったことですぐに打ち解け、会話が弾みました。こうしたイベントは特別なものではなく、会員数40万人以上を誇るシニア向けSNSでは、年間およそ2万回ものイベントが各地で開催されています。世代を超えて「初めまして」から始まる新しいつながりが日常的に生まれているのです。
しかし一方で、現実には孤独を感じるシニアも少なくありません。内閣府の調査によると、日本の高齢者の3人に1人が「親しい友人がいない」と回答しています。特に男性にその傾向が強く、約4割が友人関係の希薄さを訴えています。背景には、長年会社勤めをしてきた男性が定年を迎えた後、職場以外の人間関係を築くことが難しくなり、社会とのつながりが途切れてしまうという現実があります。俳優の大和田伸也さんも「男性は会社以外の場に出るのに勇気がいる」と共感を示していました。
そこで注目されるのが、東京大学の秋山弘子先生が提唱する**「貢献寿命」**という考え方です。これは「誰かに感謝され、役立つ関わりを持ち続ける期間」を意味します。単に長生きするのではなく、人との関わりを持ち、誰かの役に立つことで自分自身の存在価値を感じながら生きることが、人生の豊かさにつながるのです。
こうした新しい考え方は、シニア世代に「孤独を避け、仲間を見つけ、社会に貢献しながら生きる」ための大切な指針となっています。
デジタルで広がる学びと挑戦
67歳の女性は、若いころから絵を描くことが好きでした。最近では大学生と一緒に、タブレットを使ったデジタル絵画に挑戦しています。紙と鉛筆ではなく、ペン型デバイスで描く新しい体験に最初は戸惑いもありましたが、大学生から操作を学ぶことで新しい世界が広がりました。「自分にもまだできることがある」という発見が、大きな喜びにつながっています。
また、70代の夫婦は孫と一緒にレジャースポットを訪れる計画を立て、不安を感じていました。そこで若い世代に「どう楽しめばいいのか」を相談し、実際にアドバイスをもらって安心して出かけられたそうです。こうした経験は、孫との距離を縮めるだけでなく、自分たちの行動範囲を広げるきっかけにもなりました。
これらの活動を支えているのが、AgeWellJapanという団体です。シニアと若い世代をつなぎ、学び合いや交流の場を提供しています。世代の違いを越えて一緒に挑戦することで、互いの強みを活かしながら新しい価値を生み出しています。
番組に出演した前田展弘さんは「自分にとって居心地のいい人や場所を見つけることが大切」と指摘しました。安心できるつながりがあることで、挑戦への一歩も踏み出しやすくなるからです。さらに、俳優の大和田伸也さんも「好奇心を持って新しいことに挑戦する」ことの重要性を語りました。年齢を重ねても「やってみたい」と思った気持ちを素直に行動に移すことが、人生を豊かにする秘訣といえるでしょう。
まとめ|あなたのエイジレスな一歩を
今回の放送から見えてきたポイントは以下の通りです。
-
シニア像は大きく変化し、「高齢者=受け身」ではなく「挑戦者」へ
-
SNSやアバターで世代を超えた交流が広がっている
-
医学的にもシニアは10歳若返っている
-
ぬい活・シルバーディスコ・キダルトなど、新しい趣味が心の支えに
あなたも自分に合った「エイジレスな生き方」を探してみませんか?
興味のあることに一歩踏み出すだけで、日常はぐっと楽しく、豊かになります。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

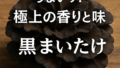
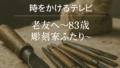
コメント