こころ整う片づけ習慣で暮らしを変える
2025年9月12日(金)20:00〜放送予定「おとな時間研究所」
部屋が散らかると「なんとなく気持ちが落ち着かない」と感じた経験はありませんか?NHK「おとな時間研究所」では、寺本あや子さんをはじめとする達人たちが「片づけが心を整える理由」と、その実践術を紹介します。本記事では放送前に、番組の見どころや片づけの心理的効果を整理し、日常に活かせるヒントをまとめました。
寺本あや子さんの片づけ術
人気ブロガーの寺本あや子さんは、中古マンションをリフォームし、限られた空間を最大限に生かす暮らしを実践しています。その工夫は、単なる整理整頓にとどまらず、「心地よい暮らし方のデザイン」にまで踏み込んでいるのが特徴です。
死角を活用した収納
ご主人がため込んだ大量のCDは、普通ならリビングの棚や収納ボックスに並べてしまい、どうしても生活感が出てしまうもの。寺本さんはここに着目し、玄関から見えない壁裏に専用の棚を造作しました。
これにより、訪問者からも自分自身の目からも視界に入らず、部屋全体の印象がすっきりします。ポイントは「隠す」ことではなく、日常動線の外に移すことで余計な刺激を減らす工夫だといえます。
生活感を隠す工夫
キッチンは家の中でも生活感が出やすい場所です。特にごみ箱や掃除用品などは、どれだけきれいに置いても“片づいていない印象”を与えてしまいがち。
寺本さんはリフォームの際に仕切り壁を設け、ごみ箱をその裏に配置しました。調理や片付けの際にはすぐ手が届く位置にありながら、リビングからは見えません。つまり「便利さ」と「美しさ」を両立させた収納です。この工夫により、キッチンが常に整然とした雰囲気を保てるようになりました。
持ち物の定量化
さらに寺本さんの暮らし方で大きな特徴が、持ち物の数をあらかじめ決めていることです。
たとえば洋服は「20着まで」というルールを設定。季節ごとの入れ替えも含めて20着以内に収め、迷いなく管理できるようにしています。このルールを守ることで、クローゼットは常に余裕があり、服を選ぶ時間も短縮。結果として心にも空間にも“ゆとり”が生まれるのです。
見せない収納+モノを減らすルール化の効果
こうした工夫の積み重ねにより、寺本さんの住まいは単なる「片づいた部屋」ではなく、視覚的ノイズを排除した“心が落ち着く空間”になっています。
部屋に入った瞬間に余計な物が目に入らないため、リラックスしやすく、また集中したいときにも邪魔が入りません。さらに、数を減らすことで「どれを使うか迷うストレス」も解消。片づけ自体が「心のメンテナンス」になっているのです。
実践のヒント
-
収納は「目に入らない場所」を優先して確保する
-
ごみ箱や生活用品など“見せない方がよい物”は壁や家具の裏へ
-
洋服や持ち物は「上限数」を決め、増えたら減らすサイクルをつくる
-
“迷ったら手放す”ルールで、モノの滞留を防ぐ
家族で取り組む片づけの事例
今回の番組では、寺本あや子さんの片づけ術に加え、他の家庭が実際に取り組んでいる事例も取り上げられます。どれも「モノを減らす」ことにとどまらず、家族の協力や暮らし方そのものを変えていく力を持っています。
ゼロ・ウェイストな暮らし
ある家庭では、「ゴミを減らす」ことを家族全員で意識的に実践しています。
-
生ごみは家庭用のコンポストで堆肥化し、ベランダや庭で育てる植物に再利用。ゴミが資源に変わる循環を子どもも体験。
-
買い物ではできるだけリユース容器や量り売りを利用し、プラスチック包装や使い捨て製品を避ける。
-
キッチンペーパーの代わりに布巾を繰り返し使うなど、「小さな置き換え」を積み重ねる。
こうした取り組みは最初こそ面倒に思えても、習慣化すると自然に暮らしに溶け込みます。家族で「今日はゴミが少なかったね」と話し合えること自体が、生活の価値観を共有する時間になっています。
実家の片づけ
もう一つ注目されるのが、実家の片づけに取り組む家族です。
-
長年積み重なった思い出の品や大量の書類、家具などをどう整理するかは、多くの家庭に共通する課題。
-
番組では「ただ捨てる」のではなく、写真を撮って記録を残す/家族で思い出話をしながら仕分けるといった方法が紹介されます。
-
親世代と子世代で一緒に取り組むことで、過去を振り返りながら次世代へと住まいを引き継ぐ「家族の節目の時間」にもなっているのです。
単なる片づけ作業ではなく、親子のコミュニケーションを深めるきっかけとして大きな意味を持つのが実家片づけの魅力です。
子どもも参加できる片づけ
片づけを大人だけの仕事にせず、子どもも自分の担当を持てる工夫をしている家庭も紹介されます。
-
おもちゃの片づけは「箱」や「引き出し」にラベルをつけ、戻す場所を明確化。「電車」「ブロック」「ぬいぐるみ」など子どもでも一目でわかる表示。
-
ゴミ箱をリビングの端に設置して、子どもが自分で紙くずを捨てられる仕組みをつくる。
-
「5分片づけタイム」を家族みんなで設け、遊び感覚で一緒に片づける。
こうすることで、子どもは「片づけは面倒な作業」ではなく、「遊びや日常の一部」として自然に身につけることができます。さらに、親も「言わなくても片づけてくれる」という安心感を得られ、家族の雰囲気も和やかになります。
片づけの効果を支える理由
片づけをすると「部屋がすっきりする」だけでなく、心まで軽くなるのはなぜでしょうか。心理学・脳科学・環境心理学の研究から、その裏付けが少しずつ明らかになっています。
ストレス軽減
散らかった部屋には、目に入るだけで余計な情報があふれています。例えば、机の上に本や書類が山積みになっていると、「あれもしなきゃ、これも片づけなきゃ」と無意識に脳が処理を続けるため、常にタスクを抱えている状態になります。
逆に、整った部屋では視覚的な刺激が減り、脳が余計なエネルギーを使わずに済むため、自然とリラックス状態に入りやすいことが報告されています。これは「視覚的ノイズが減ることで副交感神経が優位になる」生理的効果とも関係しています。
集中力の向上
物が多すぎる空間では、必要なものを探すだけで時間と注意力が奪われます。アメリカの研究では、散らかった環境にいると作業効率が40%以上低下する可能性があるというデータもあります。
片づいた空間では、必要なものがすぐに見つかり「探すストレス」が消えるため、目の前の作業に集中できます。特に仕事や勉強に取り組むときに、整頓された机の効果を感じる人は多いでしょう。
自己肯定感の向上
片づけを終えた後の「部屋がきれいになった!」という達成感は、心理学でいう自己効力感(self-efficacy)を高めます。これは「自分にもできた」という自信につながり、次の行動へのモチベーションを生み出します。
逆に散らかった部屋は、「自分は片づけもできない」という無力感や罪悪感を無意識に植えつけることがあり、心の重荷となってしまいます。小さな片づけの成功体験を積み重ねることは、自己肯定感を支える大切な要素なのです。
健康面の効果
片づいた空間は心だけでなく体の健康にも影響します。
-
整理整頓された寝室は、眠る前のリラックスを促し、睡眠の質を改善する。
-
ごちゃごちゃした部屋では、コルチゾール(ストレスホルモン)が慢性的に高まり、疲れやすさや気分の落ち込みにつながる。
-
掃除や片づけ自体が体を動かす軽い運動となり、セロトニンなど気分を安定させる神経伝達物質の分泌を促す。
つまり片づけは、ストレスを抑えるだけでなく、心身のバランスを整えるセルフケアの一種とも言えるのです。
習慣化による安心感
片づけを「特別なイベント」と考えるのではなく、日常の小さな習慣にするとさらに効果が高まります。
例えば「帰宅したら必ずバッグを同じ場所に置く」「使ったら5秒以内に戻す」などのルールを決めることで、常に整った状態が“当たり前”になるのです。これにより、片づけるための意志力を消耗せず、心も安定します。
習慣化された環境は、「もう散らかる心配がない」という安心感を生み、精神的な余裕を与えてくれます。
放送の見どころ
-
寺本あや子さんの実践例:リフォームと収納の工夫
-
ゴミを減らす家族の挑戦:ゼロ・ウェイストな日常
-
実家の片づけに取り組む家族:世代を超える心の整理
-
司会:常盤貴子さん、杉浦友紀さんの軽快なトークで片づけの本質を掘り下げ
まとめ
片づけは「部屋を整えること」以上に、心の状態や家族の関係を整える大切な習慣です。
-
空間が整えば集中力が増す
-
習慣化でストレスが減る
-
家族と一緒に進めることで絆が深まる
9月12日の「おとな時間研究所」を観れば、すぐに真似できるヒントが必ず見つかります。番組視聴後には、自宅の一角から片づけを始めてみてはいかがでしょうか。
📺 放送情報:
NHK Eテレ「おとな時間研究所 こころ整う部屋片づけ」
2025年9月12日(金)20:00〜20:45
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

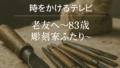
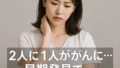
コメント