がんは“運”だけじゃない?命を守る最新トリセツ
「自分はまだ大丈夫」「面倒だからまた今度」──そんな気持ちでがん検診を後回しにしていませんか?日本人の死因第1位であるがんは、2人に1人がかかる病気です。しかし、早期発見すれば90%以上が治るとも言われています。この記事では、2024年10月23日に放送されたNHK「あしたが変わるトリセツショー」『がん対策SP』をもとに、がんの原因研究や検診率を上げる最新の取り組みをわかりやすく解説します。読めば「今すぐ検診に行こう」と思えるはずです。
【あしたが変わるトリセツショー】新「がん対策」のトリセツ!命を守る切り札SP 第2弾
がんはなぜ起こるのか?京都大学の研究から見えた真実

番組では、京都大学医学部の藤田恭之教授が登場しました。藤田教授は研究仲間から「細胞オタク」と呼ばれるほど、細胞の働きや仕組みに情熱を注いでいる専門家です。長年にわたり、がんがどのようにして発生するのか、そのメカニズムを追い続けています。
がんの原因を一言で表すと、「細胞分裂のコピーミス」です。人の体の中では、毎日何十億もの細胞が新しく生まれています。その過程で、ごくわずかな確率でランダムなエラーが発生し、本来なら正常に働くはずの細胞が異常な状態になることがあります。この偶然のエラーこそが、がんの「運」の側面といえるのです。
しかし、がんの発生は運だけではありません。喫煙や食生活、さらには生活習慣や環境といった要因も大きく関わっています。例えば、タバコの煙に含まれる有害物質や、偏った食事による栄養の乱れは、細胞にダメージを与え、コピーミスが積み重なるリスクを高めてしまいます。つまり、「運」と「生活習慣」が重なり合うことで、がんになる確率が一気に高まるのです。
さらに藤田教授は、世界で初めて「ちょう悪細胞」が周囲の細胞から追い出される瞬間を映像として記録することに成功しました。この発見は、がん細胞がどのように広がるのか、また体がどう抵抗しようとするのかを明らかにする重要な一歩となっています。最前線の研究成果は、がんの早期発見や治療法の開発に大きな期待を与えています。
デーモン閣下の体験談が伝える早期発見の大切さ

出演者のデーモン閣下は、自身ががんを早期に発見して治療した経験を率直に語りました。普段から強烈なキャラクターで知られる閣下ですが、このときは一人の人間としての体験を真剣に伝え、スタジオの空気を引き締めました。
閣下は現在、広島県のがん検診啓発特使として活動しています。実際に医師から「がんが見つかりました」と告げられたとき、多くの人ならショックを受けて落ち込むはずです。ところが閣下は「むしろラッキーだと思った」と語りました。それは、がんがまだ小さく、早い段階で見つかったからこそ治療が可能だったという意味です。
もし発見が遅れていたら、命に関わる深刻な事態になっていたかもしれません。このリアルな体験談は、単なる医療の知識以上に強い説得力を持ち、視聴者に深く響きました。「検診に行くことで命が助かる可能性がある」という事実を、デーモン閣下の言葉が改めて実感させてくれたのです。
日本人はなぜ検診を受けないのか?

番組で紹介された調査では、がん検診を一度も受けたことがない男女20人に対して専門家から説明が行われました。しかし、その後実際に検診を受けに行ったのは、たった3人だけという結果でした。
多くの人が行かなかった理由は、「自分は大丈夫だろう」という根拠のない楽観や、「手続きがめんどう」という気持ちでした。頭では大切だと分かっていても、つい先延ばしにしてしまうのが人間の心理です。
こうした心理的な壁を乗り越えるためには、単に正しい知識を伝えるだけでは不十分です。大切なのは、人が自然に「行ってみようかな」と思えるような、行動を後押しする仕組みを整えることです。例えば、検診の案内がタイミングよく届いたり、手続きが簡単にできるようになることで、一歩を踏み出しやすくなります。
ナッジ理論を活用!行動科学で検診率をアップ

ここで紹介されたのが、ナッジ理論です。これはノーベル経済学賞を受賞したリチャード・セイラー博士が提唱した考え方で、人々が気づかないうちに自然と良い選択をできるように導く仕組みを意味します。強制ではなく、あくまで「ちょっと背中を押す」ような工夫が特徴です。
番組に登場した行動科学の専門家・溝田友里さんは、この理論をがん検診に応用しました。彼女が作成したのは、思わず「受けてみようかな」と感じさせる特別な案内状です。参考にしたのは、思わず注文してしまう通販番組の仕組みでした。ちょうどテレビでがん検診の重要性を知った直後に、自分のもとへ自治体から案内が届けば、その流れで行動に移しやすくなります。
この取り組みには、すでに全国280の自治体が参加しています。検診率の向上につながると期待されており、「知っている」から「行動する」へと人々を導く新しい方法として注目されています。
地域ごとの工夫と広がるプロジェクト
番組では、静岡県富士市や福岡県太宰府市、さらに人口の少ない青森県西目屋村といった自治体の事例も取り上げられました。大都市だけでなく、小さな地域までそれぞれの工夫を凝らして取り組んでいる点が、とても印象的でした。
特に目を引いたのは、QRコードを活用した予約システムです。検診の案内にQRコードが印刷されていて、スマホで読み取るだけで予約ページにアクセスできます。これなら、わざわざ電話をかけたり、窓口に行ったりする必要がなく、空いた時間にすぐ手続きが可能です。
このように、自治体ごとに地域の実情に合わせた工夫を取り入れながらも、「行動を後押しする仕組み」が全国的に広がっていることが、現代的で頼もしい取り組みだと感じられました。
この記事のポイントまとめ
・がんは「運」と「生活習慣」が重なって発生する
・早期発見すれば治る確率は90%以上
・日本では「自分は大丈夫」という意識から検診率が低い
・ナッジ理論を活用した行動科学的アプローチが効果的
・280自治体が参加するプロジェクトで全国的に拡大中
次のステップ:あなたができること
がん検診は「行くか行かないか」で未来が大きく変わります。この記事を読んだ今が行動のチャンスです。お住まいの自治体のホームページを確認し、検診の予約ページを開いてみましょう。
もし迷っているなら「今日だけでも調べてみる」と決めるのも大きな一歩です。
2025年現在、日本のがん対策は行動科学を取り入れ、より身近で受けやすい仕組みに進化しています。あなた自身、そして大切な人のために、一度立ち止まって行動してみませんか?
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

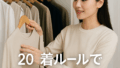

コメント