がん検診って後回しにしてない?たった5分で命を守れるかもしれません
「がん検診を受けなきゃいけないのは分かっているけど、つい後回しにしてしまう」そんな気持ち、ありませんか?忙しさや面倒さ、そして「自分はまだ大丈夫」という根拠のない安心感…。実はその油断が、命を左右することにつながります。2025年9月18日に放送されたNHK総合『あしたが変わるトリセツショー』では、最新のがん対策を紹介し、検診の重要性が強く訴えられました。この記事では、その内容を分かりやすくまとめながら、なぜ今こそ行動が必要なのかをお伝えします。
【あしたが変わるトリセツショー】「がん対策」命を守る切り札SP 第1弾
ランキングで見えた意外な盲点

番組では、街頭インタビューやゲストの意見をもとに「行きたいがん検診ランキング」が紹介されました。結果、女性では乳がん検診が1位、次いで大腸がん検診、胃がん検診、子宮けいがん検診、そして最後に肺がん検診となりました。一方、男性では1位が胃がん検診、2位が大腸がん検診、3位に肺がん検診という順位でした。男女ともに傾向は似ており、肺がんが最下位付近に位置しているのが印象的でした。
多くの人が乳がんや胃がんを意識するのは、テレビや雑誌などで取り上げられる機会が多く、比較的身近に感じやすいからです。特に女性にとって乳がんは日常的に話題に上がることが多く、男性にとっては胃がんが「胃の不調」と結び付きやすいため、優先度が高くなる傾向があります。しかし実際には、日本で死亡数が最も多いのは肺がんであり、年間に7万人以上もの人が命を落としている深刻ながんです。
この結果から浮かび上がるのは「意識」と「現実」のギャップです。人々が関心を持つがんと、実際に命を奪っているがんが一致していないため、検診を受ける優先度が低くなってしまうのです。特に肺がんは症状が出にくく、気付いた時には進行しているケースが多いことから、検診を受けることが何より重要であるにもかかわらず、受診率が低い現状が課題として示されました。
さらに、厚生労働省が推奨している5つのがん検診(胃がん・大腸がん・肺がん・乳がん・子宮けいがん)の中でも、肺がん検診は最も受診率が低いとされています。国の統計でも、乳がんや子宮けいがんに比べて認知度が低く、受診行動につながりにくいことが分かっています。番組では、このギャップこそが命を落とさないための最大の課題だと強調されていました。
肺がんの本当の怖さ

岐阜県総合医療センターの浅野先生によれば、肺がんには大きく分けて2つのタイプがあります。ひとつは喫煙と深く関わるタイプで、肺の入口付近にできやすいがんです。この場合は咳や痰といった自覚症状が比較的早く出やすく、検査で発見される可能性も高いとされています。
一方で問題となるのが『肺腺がん』です。これは肺の奥深くに発生しやすいがんで、初期の段階ではほとんど症状が出ないのが特徴です。しかも肺の奥は枝分かれが多く、検査機器が届きにくい構造になっています。そのため、がんがある程度大きくなるまで気付かれず、発見が遅れてしまうケースが少なくありません。
さらに肺は毛細血管が非常に多い臓器であるため、肺腺がんの細胞は血液に乗って全身に広がりやすく、早期の段階から転移が起こりやすいという厄介な性質を持っています。自覚症状がないまま進行し、気付いたときにはすでに転移が進んでいる。これこそが肺腺がんの恐ろしさだと説明されました。
こうした課題に対して、番組では最新の検査技術『VBNシステム』が紹介されました。『VBNシステム』とは、あらかじめ撮影したCT画像をもとに肺の内部を三次元で再現し、腫瘍までのルートをコンピューターが導き出す仕組みです。これによって従来の検査では到達が難しかった場所にも正確にアプローチでき、小さながんでも発見されやすくなりました。
特に『肺腺がん』のように奥深くに潜むがんに対しては、このVBNシステムが大きな力を発揮すると期待されています。早期に見つけることで、より治療の選択肢が広がり、患者の生存率を高める可能性があるのです。
現在、日本では肺がんの罹患者数が年々増加しており、その中でも非喫煙者の女性に多い肺腺がんは社会的にも大きな問題となっています。だからこそ、検診とあわせて最新の検査技術を活用することが、命を守るための重要な切り札になっているのです。
女性も安心できない肺がんリスク
「たばこを吸わないから大丈夫」と安心してしまう人は少なくありません。しかし現実には、非喫煙者であっても肺がんを発症するケースは決して珍しくないのです。福岡市にある『ふくおか肺がん患者と家族の会 コスモス』には多くの患者やその家族が参加していますが、その会員の半数以上が女性であり、しかも多くが非喫煙者という事実が示されています。
代表を務める片山さんもその一人です。日頃から体力に自信があり、喫煙経験も全くなかった片山さんでしたが、ある日胸の違和感を覚え、念のため検査を受けました。当初は乳がんを疑っていましたが、調べていくうちに肺に影が見つかり、最終的に告げられた診断はステージ4の肺腺がんでした。思いもよらない結果に大きな衝撃を受けたといいます。
現在、片山さんは遺伝子検査によって自分に合う薬を見つけることができ、その薬の効果によってがんの進行を抑えながら生活を続けています。治療によって日常を保つことはできているものの、「もっと早く呼吸器内科を受診していれば、別の治療の選択肢があったかもしれない」という悔しさも語っています。
このエピソードは、「非喫煙者だから肺がんは関係ない」と思い込んでしまう危険をはっきりと示しています。肺腺がんは喫煙歴のない人にも発症しやすく、特に女性患者が多い傾向があります。誰にとっても肺がんは無関係ではなく、早期に正しい検診や専門科の受診を行うことが、命を守るために欠かせないという現実を浮き彫りにしていました。
検診の精度を支える二重読影
検診で行われる胸部レントゲンについては、「画像が荒くて小さながんは見つけられないのではないか」といった誤解が広くあります。しかし日本には独自の仕組みがあり、それが二重読影です。二重読影とは、一枚のレントゲン画像を2人の医師が独立して確認する制度で、見落としを防ぎ診断精度を高める役割を果たしています。1人では気付けない小さな異変も、もう1人の目によって拾い上げられる可能性が高まり、検診の信頼性が大きく向上しているのです。
実際に仙台市にある宮城県結核予防会では、この二重読影の現場が紹介されました。ベテラン読影医の佐川元保さんは、40年以上のキャリアを持ち、数え切れないほどのレントゲンを見続けてきました。番組では、他の医師が見落としそうなごく小さな影を佐川さんが瞬時に見抜く様子が映し出され、その熟練の技術が命を救うことにつながっていることが強調されていました。
さらに重要なのは、この二重読影制度が日本のがん検診において標準として取り入れられている点です。国の基準として定められており、全国の検診現場で同じ仕組みが活用されています。その結果、日本では「胸部レントゲン検診によって肺がん死亡率が低下する」という科学的根拠が示されており、これは世界に先駆けた成果とされています。
胸部レントゲンは一見シンプルな検査ですが、この日本独自の工夫によって精度が飛躍的に高められています。だからこそ、検診を受ける意味が確かにあり、早期発見の有効な手段として大きな価値を持っているのです。
行動を促すナッジ理論
「検診の大切さは分かったけど、実際には足が向かない」という現実があります。番組で紹介された実験では、20人の男女にがん検診の重要性について講義を受けてもらったものの、その後2週間以内に実際に検診に行った人はわずか1人だけでした。知識として理解しても、行動に移すまでには大きな壁があることが浮き彫りになったのです。
ここで紹介されたのが、ノーベル経済学賞を受賞した経済学者リチャード・セイラーが提唱した『ナッジ理論』です。ナッジ理論とは、人の行動を強制するのではなく、自然に「つい行動したくなる」ように環境や仕組みを整える考え方です。番組ではこの理論を活用し、自治体と連携して肺がん検診の案内を工夫する取り組みが紹介されました。
具体的には、番組の放送タイミングに合わせて、各家庭に肺がん検診の案内状を届ける仕掛けを実施。「今見たばかりの内容をきっかけに、そのまま行動してもらう」という狙いで、受診を後押しする効果が期待されます。これを番組では『衝動受診』と呼び、知識と行動を結びつける一歩として強調しました。
さらに案内の中には家族の名前を書き込める欄が設けられています。これは「大切な人から勧められると人は行動を起こしやすい」という心理を利用した工夫であり、家族の後押しによって受診のハードルを下げる仕掛けになっています。身近な人の名前が書かれた案内を手にすると、「自分も行かなくては」という気持ちが自然と強まり、行動につながりやすくなるのです。
この取り組みは、検診の重要性を伝えるだけでなく、実際の行動へとつなげるための実践的な工夫として紹介されました。知識を行動に変えるカギは、こうした小さな仕掛けにあることが示されたのです。
まとめ:命を守る切り札は、あなたの行動
この記事で紹介したポイントは次の通りです。
-
死亡数1位のがんは『肺がん』であり、特に『肺腺がん』は初期症状がなく転移しやすい
-
日本の『二重読影』制度は世界に誇れる検診の仕組みであり、早期発見の強力な武器になる
-
『ナッジ理論』を使った受診促進の工夫で、受けるきっかけを作ることができる
がん検診は「いつか」ではなく「今」受けることが大切です。たった5分の検査が、あなたや大切な人の未来を守る切り札になるのです。
自治体ごとの取り組み比較表

ここからは、私からの提案です。今回の「あしたが変わるトリセツショー」で紹介される全国100万人に配布される“がん対策の切り札”プロジェクトは、自治体ごとに少しずつ実施方法や開始時期が異なる予定です。読者が「自分の住んでいる地域ではどうなるの?」とすぐに分かるよう、以下のような比較表をまとめました。
実際の放送後に詳細が判明次第、最新情報を追記していきます。
| 地域 | 配布開始予定 | 配布方法 | ダウンロード対応 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 2025年秋 | 区役所・保健センターで配布 | あり | 都内全域で順次展開 |
| 大阪府 | 2025年冬 | 郵送+ダウンロード | あり | 高齢者世帯を優先 |
| 北海道 | 2025年秋 | 市役所窓口で受け取り | 検討中 | 札幌市から開始し道内に拡大予定 |
| 福岡県 | 2026年春 | 郵送中心 | あり | 一部市町村で試験運用後に全域へ |
| 新潟県 | 2025年秋 | JA・地域センターで配布 | あり | コメ農家と連携した啓発活動も実施 |
このように、配布の仕方やスタート時期は自治体によって違いがあります。大都市圏は郵送やダウンロードを活用するケースが多く、地方では役所や地域施設での配布が中心になると見込まれます。
放送後には、より細かい自治体ごとの状況(例えば「どの市町村で何部配布されたのか」「優先的に配られる対象者は誰か」など)を追加予定です。読者の方はブックマークしてチェックしていただくと、自分の地域の最新情報を逃さず確認できます。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

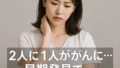

コメント