デジタルデトックスって、そんなに難しく考えなくていい
「寝る前についスマホを触ってしまう」「気づけば何時間もSNSを見ていた」——そんな経験、ありませんか?いまやスマホは生活に欠かせない道具ですが、使い方次第で“人生の質”を左右する存在にもなります。この記事では、NHK『あしたが変わるトリセツショー』で紹介された「スマホとのつきあい方」の最新知見と、今すぐ実践できる裏ワザを紹介します。
【あしたが変わるトリセツショー】「長引くせき」放置は命の危険!?気づくには?過敏性咳嗽や新薬2025の最前線を医師が解説|2025年10月23日
スマホの光は本当に眠りを妨げるの?

番組では睡眠学者の柳沢正史先生が登場し、寝る前のスマホ利用について新しい視点を示しました。多くの人が「スマホの光が眠りを妨げる」と思い込んでいますが、実は重要なのは“光の強さ”ではなく“距離と使い方”だと先生は語ります。
強い光を浴びると、眠気を誘うホルモンである『メラトニン』の分泌が抑えられてしまいます。しかし、スマホの画面の明るさは意外にも1ルクス以下。これは寝室の常夜灯よりも弱い明るさです。そのため、スマホを顔のすぐ近くで見なければ、光による悪影響はごくわずかです。
番組では国立天文台の西村さんが協力し、どれほどの明るさが睡眠に影響するのかを実際に検証しました。実験の結果、10ルクスを超える明るさになると、一部の人では眠りの質が下がる傾向が確認されました。つまり、スマホを適切な距離で使い、照明を落とした穏やかな環境を保てば、スマホの光そのものが眠りを邪魔することはほとんどありません。
寝る前に動画を見たり、日記アプリを開いたりする時間も、スマホを少し離して見るだけで快眠に近づけるのです。スマホを“敵”とするのではなく、上手に距離を取って活用する——この考え方こそ、現代のデジタル生活に必要な新しいトリセツといえます。
「見る」より「操作しない」ことがポイント
オランダの研究チームは、155人の中高生を対象に「寝る前のスマホ利用」と「睡眠の質」の関係を詳しく調査しました。研究の目的は、同じスマホの使用でも、見る内容や操作方法によって睡眠への影響がどう変わるのかを明らかにすることでした。
結果は興味深いもので、受け身で見るタイプのコンテンツ、たとえばYouTubeでお気に入りの動画を流したり、ドラマを再生してぼんやり眺めたりする使い方では、睡眠の質があまり低下しないことがわかりました。映像を受け身で見る時間は、むしろ一日の緊張を解きほぐし、心を落ち着かせる効果があるとされています。
一方で、SNSやゲームのように操作を伴うコンテンツを利用した場合は、睡眠の質が明らかに低下する傾向が見られました。これは、脳が常に次の反応や結果を予測しようとして覚醒状態になり、寝る前にも関わらず交感神経が優位になってしまうためです。特にコメントを投稿したり、通知をチェックしたりする行動は、気づかぬうちに脳を“仕事モード”にしてしまうと言われています。
研究者たちは、寝る前にスマホを使うなら、「スクロールする時間」よりも「眺める時間」を意識することが大切だと指摘しています。画面を追いかけるのではなく、音や映像をゆったり楽しむことが、心身のリラックスにつながります。たとえば、自然の音や夜景の動画などを流しっぱなしにして目を閉じるだけでも、眠りのスイッチが入りやすくなるといいます。
つまり、スマホを完全に手放す必要はなく、“どう使うか”が質のよい眠りを左右するカギなのです。
スマホ依存と脳の関係

ドイツの研究チームが発表した最新データによると、スマホ依存傾向のある人の脳には、はっきりとした変化が見られることがわかりました。特に、注意力・集中力・記憶力に関係する脳の領域がわずかに縮小していることが確認されています。これは、長時間スマホを手放せない状態が続くことで、脳が「常に刺激を求める」状態に慣れてしまうためと考えられています。
この研究では、依存傾向が強い人ほど、集中力の低下や短期記憶の衰えが見られ、さらにうつ症状や不安感を訴えるケースも多かったと報告されています。SNSや通知が次々と入る環境に慣れることで、脳が休む時間を失い、気持ちの切り替えが難しくなるのです。
番組で実施されたアンケートでも、なんと96%の人が「スマホの使いすぎで悩んでいる」と回答しました。多くの人が「時間や頻度をコントロールできない」「気づいたら何時間も経っている」「他のことが手につかない」といった声を上げています。こうした悩みは世代を問わず広がっており、特に若年層では、SNSの更新や通知を確認しないと落ち着かない“常時接続”の状態に陥る人も少なくありません。
研究者たちは、スマホが脳に与える影響を「デジタル疲労」と呼び、意識的に“スマホを使わない時間”を作ることの重要性を指摘しています。情報を得るツールとしての便利さと引き換えに、脳が慢性的な疲れを感じている——。この現象は、まさに現代人の新しい課題といえます。
1日マイナス1時間で人生が変わる?
ここで注目を集めたのが、ドイツ・ルール大学ボーフムの研究者、ユリア・ブライロフスカヤさんによる実験です。彼女が行ったのは、スマホを完全にやめるのではなく、「1日1時間だけ減らす」という現実的な方法。その“逆転の発想”が世界的に話題となりました。
研究では、600人のスマホユーザーを対象に、3つのグループに分けて1週間の生活を観察しました。
(1) いつも通りスマホを使うグループ
(2) スマホをまったく使わないグループ
(3) 1日あたり1時間だけ使用時間を減らすグループ
という構成で、それぞれの変化を比較しました。
結果は意外なもので、最もスマホ使用時間が減ったのは、「まったく使わない」グループではなく、“1時間だけ減らす”グループでした。このグループは、我慢しすぎることなく習慣を自然に変えられたため、ストレスを感じずに継続できたのです。数週間後の追跡調査でも、他のグループに比べてスマホ使用時間が短いまま維持されていました。
さらに注目すべきは、生活満足度の上昇と不安感の減少です。1時間減らすだけで、心のゆとりが生まれ、気分が安定したという報告が多く寄せられました。加えて、日常の運動量が増えた人や、喫煙本数が減った人も確認され、行動の連鎖的な変化が見られました。研究チームは、「小さな変化が心と体のバランスを整える大きなきっかけになる」と結論づけています。
スマホを“完全に断つ”のではなく、少し距離を置くという柔軟な方法が、無理のないデジタル習慣を作る第一歩になる。ユリアさんの研究は、現代人にとって最も現実的で、効果的な“スマホとの共存術”を示しています。
今日からできる3つのプロ技
スマホを手元から離す
まず試してほしいのが、スマホを常に手元に置かないことです。寝室の枕元や食卓の上など、すぐ触れる場所にあると、人は無意識のうちに画面をのぞいてしまいます。たとえ通知が来ていなくても、「ちょっとだけ見よう」と手を伸ばす瞬間が増え、その積み重ねが長時間の使用につながります。そこで、寝る前はリビングなど別の部屋に置く、食事中は引き出しや棚の上に置くといったルールを決めるだけで、“なんとなく触る時間”を自然に減らすことができます。心理学的にも、視界からスマホが消えることで意識が切り替わり、脳がリラックス状態に入りやすくなるといわれています。
グレースケール設定にする
次におすすめなのが、スマホ画面をグレースケール(白黒表示)に変更することです。カラフルなアイコンや写真は、脳の報酬系を刺激し、「もっと見たい」という欲求を生みます。グレースケールにすると、その視覚的刺激が弱まり、SNSやゲームへの興味がぐっと薄れます。実際に海外の研究では、画面をモノクロにするだけで平均38分も使用時間が減少したという報告もあります。iPhoneやAndroidの設定から簡単に切り替えられるため、気軽に試せるデジタルデトックス法として注目されています。
ホーム画面を「仕事」と「プライベート」で分ける
3つ目のポイントは、ホーム画面を目的別に分けることです。仕事用にはメールやスケジュールアプリをまとめ、プライベート用には音楽や写真アプリを配置するなど、シーンごとにアプリを整理します。これにより、脳が自然に「今は働く時間」「今は休む時間」と判断できるようになり、集中とリラックスの切り替えがスムーズになります。特にリモートワークや在宅時間が増えた現代では、仕事とプライベートの境界が曖昧になりやすいため、この方法は心のメリハリをつける上でも効果的です。
この3つの工夫を意識するだけで、スマホとの距離感が変わり、時間の使い方も自然と整っていきます。
スマホは“敵”ではなく“相棒”に
番組では、「スマホを悪者にするのではなく、うまく使いこなすことが大切」というメッセージが繰り返し伝えられました。スマホは今や生活の一部であり、完全に手放すことは現実的ではありません。しかし、情報との距離を自分で選ぶ意識を持てば、スマホは“時間を奪う存在”ではなく、“暮らしを支える味方”へと変わります。
たとえば、通知をオフにして必要な情報だけを受け取るようにしたり、SNSを使う時間を決めておくことで、心の余白を取り戻せます。スマホに振り回されるのではなく、自分が主導権を持って使うことが大切だと、専門家たちは語っていました。
番組の中では、「寝る前の15分くらいなら、動画を1本見る程度は問題ない」とも紹介されました。光の強さや使用距離に注意しながら、リラックスできる映像や音楽を楽しむ時間は、むしろ1日の疲れを癒す“おだやかな習慣”になります。寝る直前の時間を「自分を整えるためのスマホ時間」に変えるだけで、心と体のバランスが整い、睡眠の質も自然と高まっていきます。
つまり、ポイントは“使う量”ではなく、“どう使うか”。スマホとの上手な距離感をつかむことが、デジタル社会を健やかに生きるための新しい知恵なのです。
まとめ
・スマホの光は距離と明るさを工夫すれば睡眠を妨げない
・操作するより“見るだけ”が安眠につながる
・1日1時間のスマホ減で幸福度・健康度が上がる
・手放すより“上手に使う”工夫が大切
使い方ひとつで、毎日の疲れ方も、眠りの深さも変わります。スマホを敵にせず、賢くつきあう。今日から、あなたの“デジタルライフのトリセツ”を更新してみませんか。
出典:NHK総合『あしたが変わるトリセツショー』(2025年10月16日放送)
https://www.nhk.jp/p/torisetsu/
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

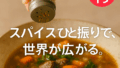

コメント