認知症と自分らしさを守る方法とは
2025年6月19日放送の「あしたが変わるトリセツショー」では、「認知症」がテーマとして取り上げられました。番組では、認知症へのイメージを見直し、本人の気持ちに寄り添った支援や、認知症があっても前向きに生きるための備えについて、実例を交えて紹介されました。座談会や体験レポート、最新研究まで、多角的に構成された内容をふまえ、認知症との向き合い方を学べる放送となりました。
【あしたが変わるトリセツショー】転倒予防&体力改善SP!足の握力強化&フレイル対策エクササイズ|2025年3月13日放送
認知症のイメージと実際のギャップ

番組の冒頭では、認知症に対する社会のイメージが強く、本人が支援や治療につながりにくい現実が紹介されました。多くの人が「認知症=すべてができなくなる」と思い込んでしまい、家族や本人自身も不安や孤立を感じやすくなることが指摘されました。これによって、医療機関への受診が遅れたり、本人が自信を失い、外出や人付き合いを避けるようになることもあります。
番組では、こうした状況を変えるために、認知症当事者による座談会が開かれました。実際に認知症とともに暮らしている人たちが集まり、一人ひとりの症状や感じ方が異なることを語り合いました。番組で紹介された内容からは、次のような現実が伝わってきました。
-
症状の現れ方は人によって違い、「すべてがわからなくなるわけではない」
-
暮らしの中で「できること」も多く、日常生活を自分で続けている人も多い
-
周囲の理解があれば、安心して地域で暮らし続けることができる
この座談会を通じて、視聴者は「認知症だから何もできない」という一方的なイメージを持たず、本人の声を聴くことが理解の第一歩であると実感できるような構成になっていました。また、参加者たちの落ち着いた様子や前向きな発言も印象的で、「できること」に目を向けることの大切さが自然に伝えられていました。
こうした番組の内容は、これまでの「認知症=終わり」といった固定観念をゆるやかに解きほぐし、支援が届きやすい環境づくりや意識の変化につながるヒントを与えてくれました。
症状は脳のどこに影響があるかで違う

番組では、認知症の症状が人によって異なる理由として、脳のどの部分にダメージがあるかによって現れる症状が変わることが説明されました。脳の中では、神経細胞同士が情報をやりとりすることで、記憶や感情、判断などが成り立っています。しかし、この神経細胞が傷つくことで、情報の伝達がスムーズに行われなくなり、さまざまな生活の困りごとが出てくるのです。
症状の具体例として、以下のような部位別の変化が紹介されました。
-
海馬に障害がある場合:新しいことを覚えるのが難しくなり、物忘れが目立つようになる
-
後頭葉が傷つく場合:見えていないものが見えると感じる幻視の症状が出やすくなる
-
前頭葉が損傷されると:注意力が続かない、感情の起伏が激しくなるなど、行動や気分の変化が現れる
このように、脳のダメージを受けた場所によって出てくる問題は違い、認知症とひとことで言っても一律ではないことが強調されました。また、ダメージを受けていない部分の機能は残っているため、全体の能力が一度に失われるわけではないという点も重要です。
番組では、視聴者に対して「一人ひとりの状態に目を向けて理解すること」が支援の出発点になると伝えていました。脳のどの部分に変化が起きているのかを知ることが、本人の生活をサポートするヒントになるという内容でした。専門的な説明をわかりやすく紹介しながら、現実的な接し方の大切さが伝えられていました。
体験ゴーグルで「認知症の世界」を知る
番組では、認知症のある人が見ている世界を体感できる特別なゴーグルが紹介されました。タレントの島崎和歌子さんが実際にこのゴーグルを装着し、認知症の視覚的な特徴を再現した疑似体験を行いました。
ゴーグルを通して再現されたのは、以下のような視覚の変化です。
-
視野が極端に狭く感じられる
-
色の違い(コントラスト)が識別しづらくなる
-
物との距離感がつかみにくくなる
こうした変化により、日常生活の中で人や物の位置を正確に把握するのが難しくなることや、歩行中につまずきやすくなるなどのリスクがあることが実感されました。島崎さんも、思っていた以上に不便さを感じた様子で、足元が不安定になったり、テーブルの端がどこにあるかがつかみにくかったりする様子が映されました。
視覚の情報は、私たちが生活するうえでとても重要です。番組では、視覚の変化によって不安や誤解が生まれやすくなる現実をわかりやすく伝えていました。特に「物が見えていない」「見えにくい」という状態が、周囲には伝わりにくいため、理解や配慮が足りないまま接してしまうケースも少なくないという点も示されました。
このゴーグル体験は、認知症のある人にとっての「日常の大変さ」を視覚的に知るきっかけとして、多くの視聴者に深い印象を与えた内容でした。見え方の変化を知ることは、声かけやサポートの仕方を見直す第一歩になるというメッセージも伝わっていました。
認知症基本法と本人の意思を尊重する社会づくり

番組では、2024年に施行された認知症基本法について取り上げられました。この法律は、「認知症があっても、本人の意思を大切にしながら自分らしく暮らせる社会」をつくることを目的としています。これまでのように、支援や介護が“管理”を中心に行われがちだった状況から、本人主体の生活を守る方向へと考え方を切り替えていく流れが始まっています。
番組内では、実際に認知症とともに暮らす人々の声が紹介されました。
-
「まだできることがあると感じている」
-
「やりたいことをあきらめたくない」
-
「自分の暮らし方を自分で選びたい」
こうした発言は、これまでの「支えられるだけの存在」という認識を大きく変えるものであり、社会全体がその思いをどう受け止めるかが問われていると番組は伝えていました。
また、認知症の進行度に関わらず、本人の希望を尊重することが支援の出発点であるという視点も示され、たとえ不安や失敗があったとしても、「その人の選択を否定しない」「できる工夫を一緒に考える」ことの大切さが強調されました。
このように、認知症基本法の理念は、単なる福祉制度の整備にとどまらず、地域社会や家族、職場など、あらゆる場面での接し方を変えるための土台として紹介されました。番組では、制度を生かすためには一人ひとりの理解と行動が不可欠であり、まずは「認知症があってもできることはたくさんある」という視点に立つことが、社会づくりの第一歩であると伝えていました。
相談できる場所を知っておくことの大切さ

番組では、認知症かもしれないと感じたときに早めに相談できる場所を知っておくことが重要であると伝えていました。症状が出ても「まだ大丈夫」と思い込んでしまったり、「どこに相談していいかわからない」という理由で受診が遅れることが少なくありません。しかし、早い段階で正しく対応することで、本人や家族の不安を軽くし、生活の質を保つことができます。
相談先として紹介されたのは以下のような機関です。
-
地域包括支援センター:各市区町村に設置されており、高齢者やその家族の相談窓口。認知症の心配があるときも、まずここに相談することができます。
-
認知症疾患医療センター:専門的な診断や医療的支援が受けられる施設で、認知症と診断された後のケアについても相談できます。
-
若年性認知症コールセンター:働き盛りの世代で発症する若年性認知症に特化した相談窓口。電話での対応も行っています。
さらに、具体的な地域の例として、長野県上田市の地域包括支援センターや、東京都渋谷区笹幡にある支援センターが紹介され、実際に相談に訪れた人たちが受けている支援の様子も映されました。これにより、支援の内容が現実のものとして伝わりやすくなっていました。
番組では、「ひとりで悩まないこと」が繰り返し強調されており、地域の支援機関を頼ることが前向きな一歩であることが丁寧に説明されていました。認知症への理解が広がる中で、こうした支援機関の存在を知っておくことが、本人にも家族にも大きな支えになるというメッセージが込められていました。
仲間とつながる「ピアサポート」の取り組み
番組では、認知症のある人同士が悩みや思いを共有する「ピアサポート」という活動が注目されていることが紹介されました。特に大分市では、認知症の当事者が集まり、自分の体験や不安、困りごとなどを語り合える場が作られており、その取り組みが実際に進んでいる様子が放送されました。
認知症と診断された直後は、誰もが強いショックを受け、将来への不安に押しつぶされそうになることがあります。そのようなときに、同じ立場にいる仲間と出会い、「自分だけじゃない」と感じられることが大きな力になります。参加者の多くが、最初は戸惑いながらも、徐々に気持ちを話せるようになり、笑顔を取り戻していく様子が描かれていました。
-
「同じ経験をしている人だからこそ分かり合える」
-
「ただ聞いてくれる存在がいるだけで心が軽くなる」
-
「不安を口に出せる場所があることが希望につながる」
こうした関係性は、医療や介護の専門職との関わりとはまた違う支え方として大切であり、本人の気持ちを尊重しながら安心できる環境づくりにつながっています。
さらに、うつ症状についても言及され、認知症と診断された後に気持ちが落ち込みやすくなることが珍しくないと説明されました。うつ症状は、認知症の発症や進行を早めるリスクにもなるため、早い段階から人とつながることが大切であると強調されていました。
番組では、こうしたピアサポートの場が全国でも広がりつつあり、本人主体の支援のあり方としてこれからさらに期待されていると伝えていました。支え合いの中で生まれる前向きな気持ちが、日々の生活に活力を与えているという事例は、多くの人にとって希望となる内容でした。
自分らしく生きるための「わたしのトリセツ」シート
番組では、認知症になっても自分らしく暮らすための工夫のひとつとして、「わたしのトリセツ」シートが紹介されました。これは、自分のことを周囲に伝えるためのシートで、本人の好みや生活習慣、趣味などを簡単なチェック形式でまとめられるツールです。
「わたしのトリセツ」シートの内容はとてもシンプルで、以下のような項目に○をつけて記入していきます。
-
日常でしていること(例:毎朝ラジオ体操をする、コーヒーはブラックで飲む)
-
好きなこと・していて楽しいこと(例:編み物が好き、犬の世話が好き)
-
してみたいこと・これからも続けたいこと(例:散歩に行きたい、家事を手伝いたい)
このシートをもとに、家族や介護スタッフはその人の「らしさ」を大切にした接し方ができるようになります。例えば、「朝に新聞を読むのが習慣」という記録があれば、入所先でも同じ時間に新聞を手渡すことができ、日常の流れが保たれ、安心感につながります。
番組では、この取り組みを広げている日本作業療法士協会の活動も紹介されました。認知症になっても、「これが好き」「これが落ち着く」「これは避けたい」といった個人の価値観や生活リズムを伝えることはとても大切です。本人の意思や習慣を記録に残すことで、支援する側も迷わず、心のこもった対応がしやすくなります。
また、「わたしのトリセツ」シートは、本人自身の気持ちの整理にも役立ちます。「できること」「したいこと」を改めて見直すことで、前向きな気持ちや自信を保つ手がかりにもなると番組は伝えていました。
このようなツールが活用されることで、認知症があっても一人ひとりの「その人らしい暮らし」を守る社会へと近づいていくことが期待されています。
認知症リスクを減らす可能性のある研究も紹介
番組では、認知症の予防やリスク低下につながる最新の研究についても紹介されました。注目されたのは、名古屋市と国立環境研究所による調査研究で、犬と暮らしている高齢者は、犬を飼っていない高齢者に比べて、認知症の発症リスクが約40%低いという結果が示されたというものです。
この研究では、日常生活の中での運動量や社会とのつながり、精神的な充足感などが影響していると考えられています。犬を飼うことで、毎日の散歩が習慣になるほか、犬を通じたご近所づきあいや地域との交流が増えることもあり、生活にリズムと刺激が生まれやすくなるためです。
また、番組では単にペットを飼うということだけでなく、高齢の保護犬を引き取りたい高齢者と結びつける地域の取り組みにも焦点が当てられていました。これは、行き場のない犬と、暮らしに安心や目的を求める人とをつなぐ新しい試みとして注目されています。
-
毎日犬と散歩をすることで自然と身体を動かす時間が増える
-
犬との関わりが「話しかける」「触れ合う」などの行動を促し、気持ちも穏やかになる
-
飼い主同士の交流や地域とのつながりが自然と生まれ、孤立の予防にもつながる
こうした活動は、ペットを通じた健康づくりという新しい形として評価されており、認知症予防だけでなく、日常生活を前向きに楽しむきっかけにもなっています。研究結果と地域の取り組みが両輪となって、高齢者が安心して暮らせる社会づくりに役立てられていることが、今回の番組からよく伝わってきました。
まとめ
今回の放送では、「認知症=すべてを失う」といった古いイメージを見直し、「認知症があっても自分らしく暮らす」という新しい視点を広める内容が多数紹介されました。症状は人それぞれであり、適切なサポートやつながりがあることで、多くの人が生き生きと暮らすことができます。これからの社会に求められるのは、認知症の理解を深め、本人の意思や暮らしを尊重する仕組みをつくることです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


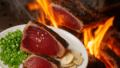
コメント